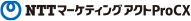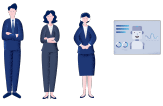コンタクトセンター
コールセンターの運用費用や相場は?内製と外注の違いと費用を抑える方法
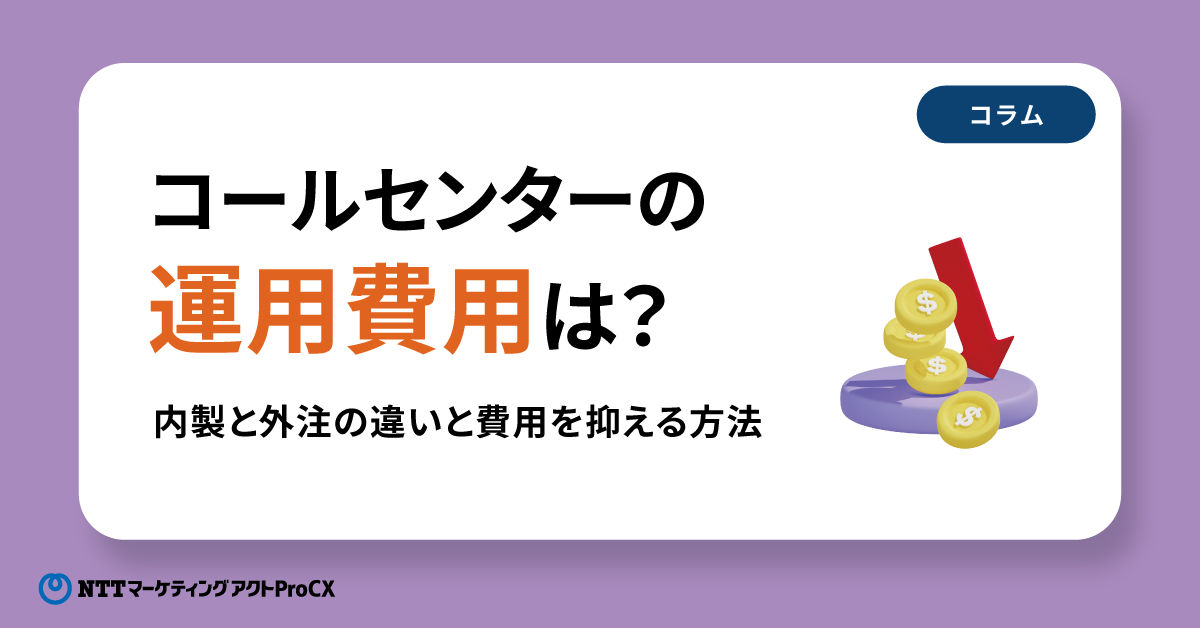
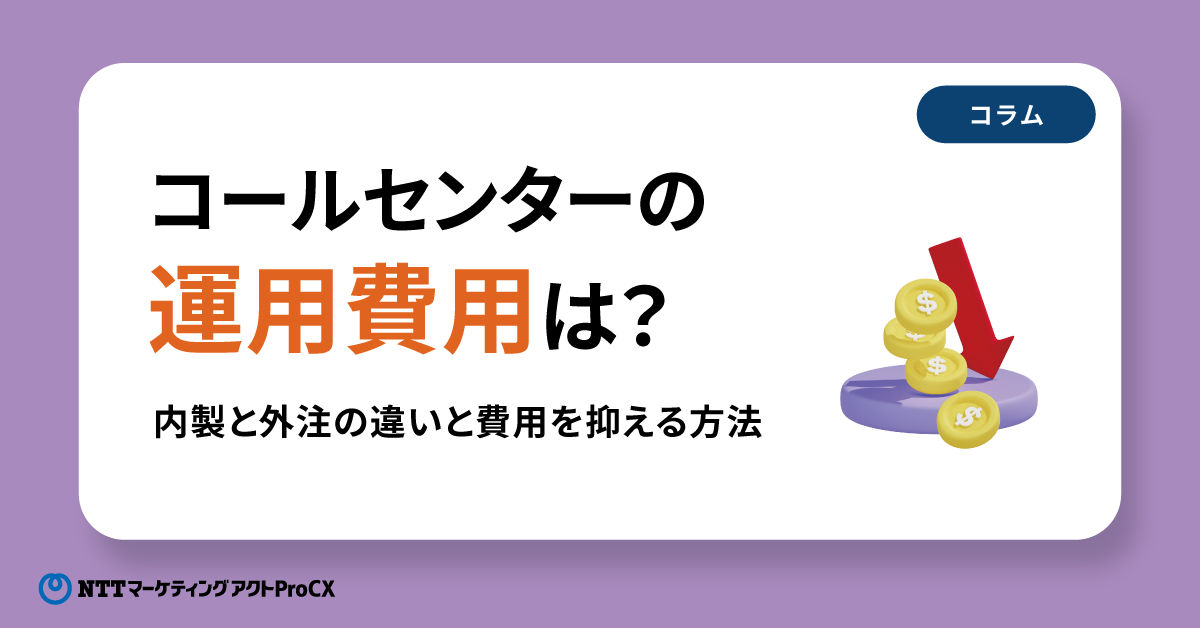

コールセンターの運営には、自社内で管理する内製と専門業者に依頼する外注の2つの方法があり、それぞれの形態で費用や運用の効率・管理の自由度などに違いがあります。
コールセンターは企業とお客様を繋ぐ大切な窓口。だからこそ、自社のニーズに合った選択が求められます。そこでこの記事では、内製と外注の特徴や費用相場、さらには外注費用を抑えるための実践的な方法について詳しく解説します。
コールセンターの運営形態とは?

コールセンターの運営形態は、大きく2つに分けられます。ひとつは自社内にセンターを立ち上げる内製、もうひとつは運営を外部に委託するアウトソーシングです。それぞれについて見ていきましょう。
自社で内製する
自社でコールセンターを運営する場合、システムの導入からオペレーターの採用や教育・日常的な運用管理まで、すべてを自社で対応します。
このメリットとしては、コールセンターを自社でしっかり監督・管理できること、またシステムに不具合や運用のしにくさが現れた際にカスタマイズしやすいこと、自社との連携が取りやすいためスムーズな運用ができることなどが挙げられます。
反対にデメリットとしては、コールセンター運営の知識や経験がない場合、準備や運用に多くの時間と労力が必要になることや、初期費用が高額になりがちなことなどが挙げられます。
運営を外注する
一方、コールセンター運営を外部に委託するアウトソーシングの場合、オペレーターのみを外注に任せる・もしくはシステムも管理者もオペレーターも全て丸ごと任せるといった方法があります。
このメリットとしては、システムや人員リソースの準備が必要ないため、迅速にコールセンターを立ち上げられる点、専門的なノウハウや経験豊富なオペレーターを活用できる点です。また、自社で設立する場合に比べて初期費用を抑えられるケースもあります。デメリットとしては、外注業者の選定には慎重さが求められるほか、長期的にはランニングコストがかかることが避けられません。
運営形態別に解説!コールセンターの運営費用はどのくらい?

コールセンターの運営費用について、内製と外注それぞれのケースを見てみましょう。
自社で内製する場合の費用相場
自社でコールセンターを内製する場合、コールセンターシステムの導入やオペレーターの採用・教育といった費用がかかります。これら初期費用の相場は約20万円から300万円程度で、オフィスを一から準備する場合はさらに賃貸料や備品の購入費用なども必要になります。なお、この相場に開きがあるのは、コールセンターの規模感によって費用は大きく変わるからです。
また、ランニングコストとして、システムの運用費・人件費・ライセンス料・インフラ維持費などもかかってきます。システムの運用費の目安は年間で50万円から150万円、人件費はオペレーター1人当たり時給1,200円から3,000円、ライセンス料は月額で約4万円が一般的な目安です。こちらもコールセンターの規模によって費用は大きく変わります。場合によってはさらに多額の予算が必要になることもあるでしょう。
外注する場合の費用相場
外部の専門業者に運営を委託する場合、小規模なコールセンターの場合、初期費用は1万円から2万円程度で収まることもあります。中には初期費用は無料という業者も。コールセンターを迅速に立ち上げることができるだけでなく、初期コストを抑えられる点が外注の大きなメリットと言えるでしょう。コストやスピードを重視する場合には、外注が適している場合が多いのではないでしょうか。
ただし、大規模なコールセンターでネットワークや設備の準備までを依頼する場合は、100万円以上の初期費用がかかる場合もあるので注意しましょう。
ランニングコストについては、多くのアウトソーシング業者が月額固定費型もしくは従量課金型の方式をとっています。月額固定費型の場合は、1ヶ月につき10万円から30万円程度が相場です。従量課金型の場合は、1件のコールあたり500円から1,000円程度が一般的です。
コールセンターの料金体系
コールセンターを外注する際の料金体系は、主に「月額固定型」「従量課金型」「成果報酬型」の3つに分けられます。それぞれに一長一短があり、どのプランが最適かは、お客さまのコール数や業務内容、そしてビジネスの目的によって異なります。 まずは、それぞれの特徴を一覧表で比較してみましょう。
| 月額固定型 | 従量課金型 | 成果報酬型 | |
|---|---|---|---|
| 費用の仕組み | 契約した対応件数や席数に基づく月々の固定料金 | 対応したコール件数や時間に基づく変動料金 | 獲得したアポイントや契約などの成果に基づく変動料金 |
| メリット | ・予算が安定し管理しやすい ・コール数が多いと割安になる |
・コール数が少ない場合に無駄がない ・利用した分だけの支払いで済む |
・成果が出なければ費用が発生しない ・費用対効果が明確 |
| デメリット | ・コール数が少ないと割高になる ・超過分は割高な追加料金が発生 |
・コール数が急増すると高額になる ・予算が予測しにくい |
・1件あたりの単価が高い ・成果が多いと総額が高くなる場合も |
| 主な対象業務 | インバウンド業務全般(カスタマーサポート、受注受付など) | コール数が少ない・変動が大きい業務(夜間休日対応、あふれ呼対応など) | アウトバウンド業務(テレアポ、営業代行など) |
月額固定型
毎月定額で、決められたコール数まで対応するプランです。 予算が立てやすいメリットがありますが、コール数が少ない月は割高に、超過した月は割高な追加料金が発生する可能性があります。
従量課金型
対応した件数や時間に応じて費用が発生するプランです。 コール数が少ない事業者にとっては無駄がなく効率的ですが、繁忙期や突発的な問い合わせ増で費用が想定を上回るリスクがあります。
成果報酬型
アポイント獲得や契約成立といった「成果」に応じて報酬を支払うプランです。 主にアウトバウンド業務で採用されます。成果が出なければ費用は発生しませんが、1件あたりの単価が高めに設定されています。
コールセンターの外注費はどう決まる?

コールセンターの外注費用の内訳は?
前項で外注費用の相場を説明しましたが、費用の内訳は以下の要因によって生まれることがほとんどです。
- 対応件数
- 対応時間
- 対応範囲
- 追加費用
それぞれについて詳しく解説します。
対応件数
月額固定制でも従量課金制でも、1ヶ月あたりの対応件数が増えるほど、料金の設定は高くなります。対応件数が多ければ、それだけオペレーターの人数が必要になるからです。
対応時間
コールセンターが対応する時間も料金に関係します。例えば、土日祝日や夜間帯も対応してもらう場合、平日の昼間よりも料金設定は高くなるケースがほとんどです。
対応範囲
コールセンターが対応する範囲によっても料金は変わります。例えば、簡単な取り次ぎ業務だけを扱う場合に比べて、商品サービスの問い合わせやトラブルシューティングなどを行ってもらう方が料金は高くなります。この理由は、委託先のオペレーターに自社商品サービスに関する専門知識をつけてもらい、独自のトークマニュアルなどを整備・教育する必要があるからです。
また、インバウンド業務よりもアウトバウンド業務の方が費用は高くなる傾向があります。これは、相手の話を聞くインバウンド業務よりも、自ら電話をかけて商品サービスの提案や営業を行うアウトバウンド業務の方が難易度は高く、より専門的なトークスキルが求められるからです。
追加費用
このほか、追加費用がかかることもあります。例えば、月額固定制で契約しているケースで、あらかじめ決められているコール数を超えた場合には、追加費用がかかります。同様に、定められている対応時間や対応範囲を超えた場合にも、追加料金がかかるのが一般的です。
コールセンターの外注費用を抑えるためのポイントは?

コールセンターの外注費用を抑えるためには、以下のポイントを押さえると良いでしょう。
対応件数・時間・範囲を明確にする
まずは、対応件数や時間、範囲を明確に設定しましょう。これらが曖昧なままでは、後から追加料金や割増が発生しやすくなり、結果的に費用が膨らんでしまいがちです。
自社のコールセンターでどのような業務を行うのかを考えて、月々あたりどのくらいのコール数が見込まれるのか、お客様からの電話は何曜日の何時くらいが多いのか、どの程度の範囲までコールセンターで対応するのかなど、あらかじめ綿密なシミュレーションを行って必要なサービス内容を詳細に見積もることで、無駄なコストを防ぐことができます。
外注に使える予算を決める
外注に充てられる予算を事前に決めておくことも大事です。対応件数や時間、範囲を踏まえたシミュレーションを実施し、それをもとに外注費用としてどのくらいの金額を捻出できるのかを具体的に算出しましょう。この段階で予算を確定し、その範囲内で依頼することで、運用後に「当初の計画よりもコストがかさんでしまった」という事態を防げます。
対応件数を減らすための施策を行う
対応件数自体を減らすための対策も検討してきたいところです。対応件数が減れば、その分コストも削減されます。例えば、インバウンド対応の場合は、FAQやWebサイトのコンテンツを充実させ、お客様自身が問題を解決できる仕組みを作り、コールセンターに電話をしなくても済む環境を整えると良いでしょう。
複数の業者を比較検討する
業者選びの際には、最初から一社だけに絞り込むのではなく、複数の業者から見積もりを取って比較することが大事です。どの業者が最もコストパフォーマンスに優れているかは、実際に見積もりを取ってみなければわかりません。自社の予算や求めるサービス内容を明確にしたうえで複数の候補を比較することで、もっとも費用対効果の高い業者を選ぶことができるでしょう。
インバウンドの方がアウトバウンドより費用が安い
インバウンド業務は、業務では、正確な情報伝達能力や丁寧な顧客対応が求められますが、顧客の側から働きかけがあるため、比較的会話が進みやすく、オペレーションの難易度もアウトバウンドに比べると低めです。そのため、費用も相対的に抑えられる傾向にあります。
一方、アウトバウンド業務はインバウンド業務と比較して、より高度なスキルと戦略、そしてオペレーターへの手厚いサポートが必要となるため、それに伴い料金も高く設定されています。
まとめ
今回ご紹介したように、コールセンターの内製と外注にはそれぞれ独自の強みと課題があります。内製は自由度が高く柔軟な運用が可能ですが、初期費用や運営負担が大きくなる傾向があります。一方、外注は迅速な立ち上げと専門的なノウハウの活用が可能な反面、ランニングコストが膨らむ可能性があることや業者選びが非常に重要だという点に注意しましょう。
費用を抑えるためには、対応件数・時間・範囲を明確化した上で、予算を設定したり、問い合わせ削減策を検討したり、複数の業者から見積もりをとって比較検討したりすることが大事です。自社の状況に合った最適な運営形態を選び、コストパフォーマンスの良いコールセンター運営を実現しましょう。

ProCX編集部
NTTマーケティングアクトProCX