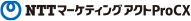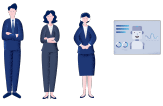コンタクトセンター
コールセンターの「応答率」とは?低下する原因と改善ポイントや平均値・計算方法を解説!
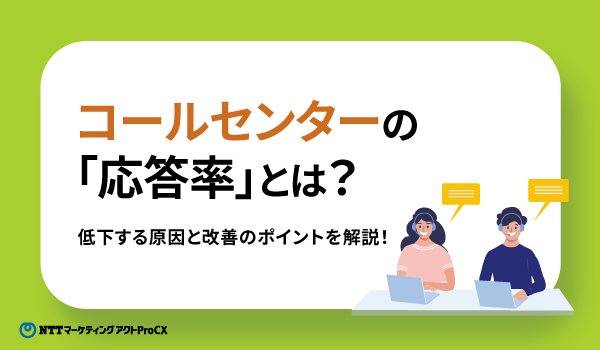
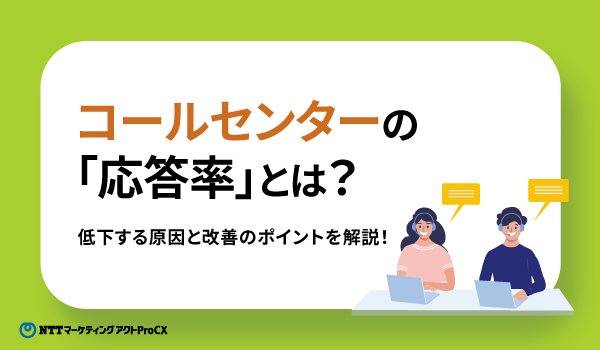

「コールセンターの応答率が下がってしまい、顧客からのクレームが増えている…」そんな悩みを抱えていませんか? 応答率は、顧客の印象を大きく左右し、企業の信頼にも関わる重要な指標のひとつです。しかし、なぜ応答率が低下するのでしょうか? そして、どのように改善すればよいのでしょうか?この記事では、応答率の基礎知識から計算方法・低下の原因・具体的な改善策などを詳しく解説します。
INDEX
- コールセンターの応答率とは?役割と計算方法
- コールセンターで応答率が低下する原因は?
- オペレーターの人数が不足している
- 1件あたりの対応時間(AHT)が長すぎる
- 入電数が急激に増加した
- オペレーターのスキルにバラつきがある
- 問い合わせ内容が複雑化している
- 事務処理などのバックエンドに時間がかかっている
- コールセンターの応答率を改善する方法は?
- オペレーターの数を増やす
- オペレーターの教育や研修を充実させる
- トークスクリプトを修正する
- FAQシステムの導入を検討する
- チャットボットの導入を検討する
- コールセンターのアウトソーシング
- 業務フローの可視化・再設計
- 自己解決を促す導線(IVRなど)を整備
- コールセンターシステムの刷新・統合
- 応答率の改善のポイント
- 応答率に関するKPI管理の方法
- 応答率がもたらす影響と改善の他への効果
- まとめ
コールセンターの応答率とは?役割と計算方法

応答率とは?
コールセンターの応答率とは、コールセンターにかかってきた電話(着信数)のうち、実際にオペレーターが対応できた件数の割合を示す指標です。
顧客満足度と直結するKPIである
応答率は顧客満足度に直結する重要なKPI(重要業績評価指標)であり、低い場合は早急な改善が求められます。なぜなら、コールセンターの応答率とは、入電数に対するオペレーターの対応数の割合を指し、コールセンターの「つながりやすさ」を示す重要な指標であるためです。応答率が低いと、顧客は電話がつながりにくく、待たされる時間が長くなるため、不満が蓄積され、結果として顧客満足度の低下やサービスからの離脱につながるリスクがあります。また、ネガティブな顧客体験はSNSなどで瞬時に拡散され、企業のブランドイメージを大きく損なう可能性もはらんでいます。一方、応答率が高いコールセンターは、顧客が迅速に問題を解決できるため、顧客満足度やブランドへの信頼感を高めることができます。
応答率の適正値とは?
一般的に、コールセンターでは応答率90%以上を目指すことが望ましいとされています。とはいえ、問い合わせが集中する時間帯(ピークタイム)では、一時的に90%を下回ることもあるでしょう。その場合でも、一日の平均応答率が90%以上であれば、顧客のニーズに適切に対応できていると考えられます。
反対に応答率が低下すると、以下のような問題が生じる可能性があります。
・80%以下になっている場合 電話がつながりにくい時間帯が発生し、顧客が何度もかけ直す必要が出てきます。
・50%未満になっている場合 多くの顧客が電話をかけてもつながらない状態が続き、企業のイメージが悪化する恐れがあります。
90%が理想的水準
コールセンターの応答率の目標値は90%程度が理想とされており、多くのコールセンターがこの値を掲げています。この目標値は、顧客がほとんど待つストレスを感じることなく、顧客満足度の向上も期待できる状態と考えられています。 しかし、応答率を90%に維持することは容易ではなく、オペレーターの増員や教育、コールセンターシステムの導入など、継続的な取り組みが不可欠です。また、応答率だけを強制すると応対品質が低下するリスクもあるため、応対品質を含めた複数の指標を組み合わせ、センター全体の状況を正しく把握することが重要です。 応答率が90%に満たない場合でも、80%以上であれば許容範囲とされていますが、これ以上低下するようであれば、何らかの問題が発生している可能性が高いです。そのような場合は、対応件数や顧客満足度への影響を避けるためにも、早急な見直しと改善が求められます。
応答率はどうやって計算する?
応答率は、以下の計算式で求めることができます。
応答率=対応件数÷着信件数×100
例えば、100件の電話がかかってきて、そのうち90件に対応できた場合の応答率は、「90件÷100件×100」で90%となります。
放棄率との関係
応答率だけでなく、顧客がオペレーターにつながる前に電話を切ってしまった件数を示す放棄呼数(放棄呼率)や、平均通話時間などの他の指標も合わせて分析することで、より詳細なパフォーマンス評価が可能となります。特に、放棄呼率の平均は8.6%程度とされており、サービス品質向上や業務改善にとって重要なKPIです。これらの指標を定期的に測定・分析することで、顧客満足度の向上と業務効率化につなげることができるでしょう。
コールセンターの応答率以外の指標は?
コールセンターの生産性や効率を上げるためには、応答率だけでなく以下の指標も参考にしましょう。
CPH
CPHは「1時間あたりにオペレーターが対応できるコール数」を示す指標で、「CPH = 対応したコール件数 ÷ 稼働時間」で算出します。例えば、1人のオペレーターが8時間勤務し、その間に80件の電話対応を行った場合、「80 ÷ 8 = 10」となり、1時間あたり10件の対応を行ったことになります。この数値が高いほど、効率よく業務が行われていると判断できます。
ATT(Average Talk Time)
ATTは「1件の電話にかかる平均通話時間」を示す指標です。通話時間が長すぎると、1時間あたりの対応件数が減少し、業務効率が低下します。一方で、短すぎると十分な対応ができていない可能性があります。ATTは業務効率を測る一つの指標ではありますが、単にこれだけを見て判断するのではなく、他の指標と共に総合的に見ることが大事です。
ACW(After Call Work)
ACWは「通話終了後に必要な事務作業の時間」を指します。オペレーターは通話が終わった後、顧客情報の記録や必要な手続きを行う時間が必要です。この時間が長すぎると、次の電話を受けるまでの間隔が空いてしまい、業務効率が下がる原因となります。ACWを最適化するためには、事務作業のフローを見直したり、作業をしやすくするためのシステムを導入したりすることが大切です。
AHT(Average Handling Time)
AHTは「1件の対応にかかる総時間」を指し、「AHT = 通話時間(ATT)+ 後処理時間(ACW)」で算出します。 AHTの管理を適切に行うことで、オペレーターの負担を軽減し、全体の業務効率を向上させることができます。
稼働率
稼働率は、オペレーターが勤務時間のうち、どれだけの時間を実際の電話対応に費やしているかを示す指標で、「稼働率 =(通話対応時間 + 対応後作業時間 + その他業務)÷(勤務時間 - 離席時間)」で算出します。この数値を分析することで、オペレーターの適切な配置や業務負担の調整を行うことができます。
もっと詳しく知りたい方は、こちらの記事もあわせてお読みください。
コールセンターで応答率が低下する原因は?

コールセンターの応答率が低下する原因として、以下が考えられます。
オペレーターの人数が不足している
コールセンターでは、オペレーターの数が十分でなければ、かかってきた電話をすべて受けることができません。特に、予測を上回る入電数があった場合、対応が追いつかず応答率が低下します。例えば、新商品の発売やサービスの障害発生時には、一時的に問い合わせが殺到して対応が追いつかなくなり、応答率が低下することがあります。
1件あたりの対応時間(AHT)が長すぎる
AHT(Average Handling Time)とは、1件の電話対応にかかる平均時間のことです。AHTが長くなると、オペレーターが1時間に対応できる件数が減少し、結果的に応答率も低下してしまいます。AHTが長くなる原因としては、「顧客対応の際に不要な会話が多い」「必要な情報を探すのに時間がかかっている」「システムの操作に手間取っている」などがあります。
入電数が急激に増加した
テレビCMの放映直後やSNSで話題になった直後、あるいはトラブル発生時には、通常の予測を大きく超える入電が発生することがあります。例えば、通販サイトのセール期間中や金融機関のシステム障害時には、顧客からの問い合わせが殺到し、オペレーターのキャパシティを超えてしまいます。このような場合、通常の体制では対応しきれず、応答率が大幅に低下する可能性があります。
オペレーターのスキルにバラつきがある
人員が十分にもかかわらず応答率が低い場合、その原因としてオペレーターのスキル不足が挙げられます。特に経験の浅い新人オペレーターは、対応時間の長期化を招きやすく、その結果全体の対応可能件数を減らしてしまうため、応答率の低下につながります。 この課題を解決するためには、まずオペレーター全体のスキル不足なのか、特定のオペレーターに課題があるのかを明確にすることが重要です。多くのオペレーターに共通の課題がある場合は集合研修やトレーニングを、特定のオペレーターの場合はOJTやロールプレイングを強化し、個別の応対スキルを向上させます。また、新人オペレーターが入電数のピーク時に集中しないよう、適切なシフト管理も応答率維持に不可欠です。
問い合わせ内容が複雑化している
問い合わせ内容の複雑化は、オペレーターが対応に要する時間を長期化させ、結果的に応答率を下げる大きな要因となります。例えば、新商品やサービス、システムに関する専門的な質問が増えたり、複数の問題が絡み合った複雑なケースが増えると、オペレーターはより多くの時間を使って情報を調べたり、適切な解決策を導き出す必要があります。これにより、1件あたりの通話時間が伸び、次に電話をかけてきた顧客を待たせてしまうことになります。この問題に対応するためには、ナレッジベースの拡充や、継続的な研修によるオペレーターのスキルアップ、専門チームへのエスカレーション体制の構築などが重要となります。
事務処理などのバックエンドに時間がかかっている
事務処理などのバックエンド業務に時間がかかることも、応答率を下げる要因となります。顧客との通話が終了した後も、オペレーターは通話内容の入力、関連部署への情報共有、後続の対応手配など、さまざまな事務作業を行う必要があります。これらの業務が効率的に行えない場合、次の電話に対応できるまでの時間が長くなり、結果として応答率が低下します。例えば、システム操作が複雑であったり、複数のシステムに情報を入力する必要があったりする場合、バックエンド処理に要する時間が増加します。この問題を解決するためには、業務プロセスの見直しや、システムの統合、事務処理を自動化するツールの導入などが有効です。
コールセンターの応答率を改善する方法は?

コールセンターの応答率を90%以上に保つためには、以下の改善策を検討してみてください。
オペレーターの数を増やす
最も基本的な解決策は、必要に応じてオペレーターを増員することです。特に、繁忙期やキャンペーン期間中は、一時的に契約社員やアルバイトなどを雇用して増員するのが有効です。人が増えれば自ずと対応件数も増えるので、応答率を向上させることができます。
オペレーターの教育や研修を充実させる
AHTの改善には、オペレーターのスキルアップが不可欠です。オペレーターが顧客対応に慣れていないと、1件あたりの対応時間が長くなり、応答率が低下する原因になるからです。研修を充実させ、一人ひとりのスキルアップに注力しましょう。例えば、実際の顧客対応を想定したロールプレイングやシステム操作のトレーニング・タイピングスピード向上のための研修などが効果的です。
トークスクリプトを修正する
トークスクリプトとは、オペレーターが顧客対応を行う際のガイドラインとなる台本のようなものです。トークスクリプトは、特に新人オペレーターにとっては必要不可欠と言えます。適切なトークスクリプトが用意されていれば、迷わずに対応でき、会話がスムーズに進みます。
また、トークスクリプトを定期的に見直し、不要な部分を削ることで、AHTの短縮につながります。結果として、より多くの電話を受けられるようになり、応答率の向上が期待できます。
FAQシステムの導入を検討する
オペレーターが問い合わせ対応に時間を要する理由の一つに、適切な回答を探すのに手間取ることがあげられます。そのため、社内のFAQシステムを充実させ、必要な情報をすぐに検索できる環境を整えることが重要です。FAQシステムを導入すれば、オペレーターが適切な情報をすばやく提供できるようになり、対応時間の短縮と応答率の向上につながるでしょう。
チャットボットの導入を検討する
最近では、企業の公式サイトやECサイトにチャットボットを導入するケースが増えています。チャットボットは、顧客からの問い合わせに自動で回答する仕組みで、簡単な質問であれば、オペレーターを介さずに解決できます。例えば、商品の在庫確認や営業時間の問い合わせなど比較的シンプルな内容であれば、チャットボットで対応することで入電数を減らし、コールセンターの負担を軽減することができます。
コールセンターのアウトソーシング
自社だけで対応するのが難しい場合は、外部のコールセンターに業務を委託する(アウトソーシング)のも選択肢の一つです。応答率やCPHなどさまざまな指標を改善でき、顧客満足度の向上も期待できます。常時ではなくても繁忙期のみ一時的に、もしくはコールセンター業務の全てではなく一部だけ、アウトソーシングを利用するのもおすすめです。
業務フローの可視化・再設計
業務効率に課題がある場合は、業務フローの見直しが有効です。オペレーター向けのFAQやトークスクリプトを改善し、マニュアル化を徹底することで、電話対応時間を短縮できます。また、コールセンターの受付時間を延長して入電を分散させることも、応答率の向上に繋がります。現状の業務内容やフローを客観的に評価し、非効率な部分を改善することが重要です。
有人・無人対応の役割分担を見直す
顧客から頻繁に寄せられる質問は、WebサイトにFAQとして公開し、顧客自身による自己解決を促すことが効果的です。これによりコールセンターへの入電数が抑制され、応答率の向上とオペレーターの負担軽減が期待できます。FAQをWebサイトの見やすい位置に配置し、専門用語を避けるなどの工夫をすることで、より多くの顧客が自己解決できるようになります。
自己解決を促す導線(IVRなど)を整備
IVR(自動音声応答)やビジュアルIVRを導入し、自動化できる業務を任せることで、オペレーターの負担を軽減できます。IVRは着信先の振り分けなどを通じて電話応対を効率化するシステムで、オペレーターの負担を減らすだけでなく、自動音声によって受注の取りこぼしを防ぐメリットもあります。また、新人オペレーターのストレスを軽減することで、離職率の低下も期待できます。
コールセンターシステムの刷新・統合
コールセンターシステムを導入・刷新することで、応答率に関する課題を解決できます。例えば、CTIシステムはコンピュータと電話を連携させるシステムで、入電時に顧客情報をPCに表示させるポップアップ機能や、オペレーターに電話を均等に割り振るACD(着信呼自動分配)機能などを備えています。これらの機能を活用することで、応対がスムーズになり、顧客満足度の向上にも繋がります。
応答率の改善のポイント
応答率を効果的に改善するためには、単一の施策だけでなく、多角的なアプローチが求められます。ナレッジの整備、KPIの可視化、そして外部リソースの活用が重要なポイントとなります。
ナレッジベースの整備と活用
ナレッジの整備と活用は、オペレーターの対応効率を上げる上で非常に重要です。オペレーターが対応に困りSV(スーパーバイザー)に助けを求めた際、その解決策がナレッジとして蓄積されないと、同じ問題が繰り返されてしまいます。解決策をその日のうちにナレッジとして追加・共有し、検索しやすくする体制を整えることで、オペレーターは自己解決能力を高め、対応時間を短縮することができます。
KPIの可視化とモニタリング体制の強化
応答率を改善するには、まず現状を正確に把握することが不可欠です。応答率をはじめとする各種KPIを時間帯別・曜日別など、細かな単位で計測・分析することで、具体的な課題が見えてきます。例えば、特定の時間帯に応答率が著しく低下していることが分かれば、その時間帯の人員配置を見直すなどの具体的な対策を講じることができます。データを可視化し、継続的にモニタリングする体制の強化が改善の第一歩です。
代行サービス(BPO)の活用
社内のリソースだけで応答率の改善が難しい場合、コールセンター業務を外部の専門業者に委託するBPO(ビジネス・プロセス・アウトソーシング)の活用が有効です。特に人手不足は応答率低下の大きな原因であり、アウトソーシングによってリソース不足を補うことができます。専門業者は豊富な運営ノウハウを持っているため、自社で運営するよりもサービス品質の向上が期待でき、結果的に応答率改善と顧客満足度向上に繋がります。
応答率に関するKPI管理の方法
応答率をKPIとして効果的に管理するには、正確な測定方法を確立し、他の指標とのバランスを考慮しながら、自社の状況に合った現実的な目標を設定することが重要です。
応答率の正確な測定方法
応答率は、オペレーターが応答した件数を総入電件数で割り、100を掛けることで算出されます。
【応答率の算出方法】 応答率(%)=応答件数÷入電件数×100
入電数は時間帯によって大きく変動するため、30分や1時間といった短い単位で計測することが理想的です。また、オペレーターに着信する前に切断された「途中放棄呼」を入電数に含めるかどうかの基準をあらかじめ決めておかないと、正確な評価ができなくなるため注意が必要です。
他の指標(CPH・稼働率・AHT等)との比較分析
応答率だけを重視すると、応対品質の低下を招くリスクがあります。そのため、CPH(1時間あたりの処理件数)やAHT(平均処理時間)、オペレーターの稼働率など、他の関連指標と合わせて総合的に分析することが不可欠です。例えば、応答率が高くてもAHTが極端に短い場合は、必要な案内を省略している可能性があります。複数の指標を比較分析することで、センターの健全な状態を多角的に評価できます。
適切な応答率目標の立て方
多くのコールセンターでは応答率90%を理想的な目標としていますが、この数値を達成するために単純にオペレーターを増員すると、人件費が過剰になる可能性があります。自社の事業内容や顧客の期待値を考慮し、費用対効果のバランスが取れた目標を設定することが重要です。応答率が80%台でも安定したサービスを提供できている場合もあれば、それ以上が求められる場合もあります。時間帯ごとのデータ分析に基づき、現実的かつ最適な目標値を設定しましょう。
応答率がもたらす影響と改善の他への効果
応答率の改善は、コールセンターの「つながりやすさ」という直接的な指標の向上だけでなく、顧客満足度や売上、さらには従業員の定着率といった企業経営全体にプラスの効果をもたらします。
顧客満足度(CS)向上
応答率の改善は、顧客満足度(CS)の向上に直結します。電話がすぐにつながり、待たされるストレスがないことは、顧客にとってポジティブな体験となります。問題が迅速に解決されることで、企業やサービスに対する信頼感が高まり、長期的な顧客ロイヤルティの醸成にも繋がります。逆に、応答率が低い状態が続くと、ネガティブな評判が広がり、ブランドイメージを損なう可能性もあります。
新規受注率の改善
応答率の改善は、機会損失を防ぎ、売上向上に貢献します。IVR(自動音声応答)などを活用して入電を効率的に処理することで、繁忙時間帯でも受注の取りこぼしを防ぐことができます。電話がつながらないことが原因で競合他社に流れてしまう顧客を減らし、潜在的な売上を確保することに繋がります。特に、注文受付などを担うコールセンターにとって、応答率の維持・向上は売上を左右する重要な要素です。
離職率の低下
応答率の改善施策は、オペレーターの働きやすさにも繋がり、離職率の低下に貢献します。例えば、IVRの導入によって簡単な問い合わせが自動化されると、新人オペレーターが感じる業務への心理的負担やストレスが軽減されます。また、適切な人員配置や効率的な業務フローは、オペレーター一人ひとりにかかる過度な負荷を減らします。働きやすい環境が整備されることで、従業員の定着率が高まり、採用や教育にかかるコストの削減も期待できます。
まとめ
コールセンターの応答率は、顧客満足度を維持し、企業の信頼を守るために欠かせない指標です。今回の解説したように、応答率が低下する原因には、オペレーター不足や対応時間の長さ・急激な入電数の増加などがありますが、適切な対策を講じることで応答率の改善は十分可能です。
オペレーターの増員や教育の充実・トークスクリプトやFAQシステムの見直し・チャットボットの導入など、状況に応じた対策を組み合わせて最適な運営を目指しましょう。応答率の向上は、顧客満足度だけでなく、オペレーターの負担軽減や業務効率の向上にもつながります。ぜひ今回の記事の内容を役立ててくださいね。

ProCX編集部
NTTマーケティングアクトProCX