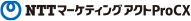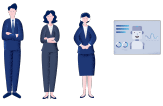コンタクトセンター
コールセンターのATTとは?通話時間が長くなってしまう原因と短縮のポイントを解説!
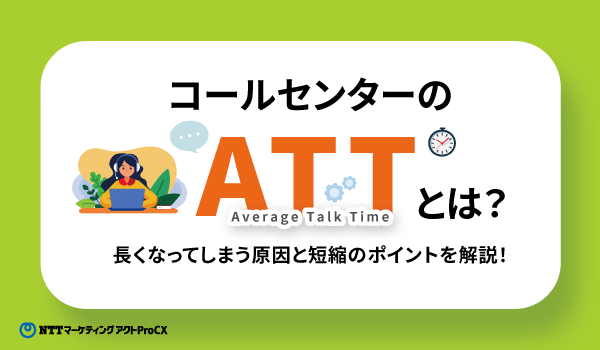
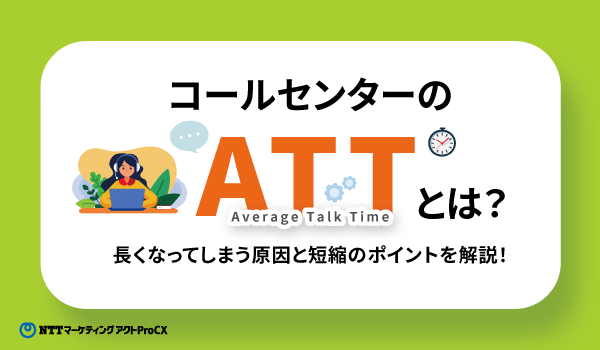

日々多くの問い合わせが寄せられるコールセンターでは、効率的に対応を進めて業務の生産性を上げることが重要なテーマになります。その際に指標となるのが、「AHT」「ATT」「ACW」といった指標です。この記事では、「AHT」「ATT」「ACW」の具体的な意味を解説するとともに、コールセンターの運営を効率化し、生産性を高めるために実施すべき取り組みについてご紹介します。
コールセンターのATTとは?生産性に関わる3つの指標

コールセンターの3つの指標「ATT・AHT・ACW」とは?
ATTとは?
ATTとは、Average Talk Timeの略です。オペレーターとお客様の通話の平均時間を意味します。1日にたくさんの入電があるコールセンターにおいては、生産性アップのためにはATTはできるだけ短い方が良いとされています。しかし、実際の現場では問い合わせの内容やお客様によって対応時間は左右するため、安易に短縮だけを目指すのが良いとは言えません。また、オペレーター個人の力量ではATTの短縮は難しいため、全体の管理体制としてマネジメントしていくことが大切です。
AHTとは?
AHTとは、Average Handling Timeの略です。通話時間・保留時間・後処理時間の平均処理時間を意味します。一般的にAHTはできるだけ短い方が良いとされていますが、AHTを短くすることだけに注力しすぎると、問い合わせをしてきたお客様に冷たい印象や事務的な印象を与えたり、ミスやクレームに繋がったりすることも。そのため、単にAHTを短くしようとするのではなく適切に管理することが大切です。
ACWとは?
ACWとは、After Call Workの略です。お客様との通話後に、オペレーターが応対記録の入力やお客様からの問い合わせ内容・依頼内容をまとめる処理などにかかる平均時間を意味します。ACWの短縮化も生産性アップに大きく関わります。しかし、オペレーター個人の努力ややる気だけで短縮化ができるわけではないので、入力項目を整理・簡略化したり自動入力を導入したり、コールセンター全体として改善に当たっていく必要があります。
コールセンターにおけるATTの重要性
前項で説明したように、ATT(Average Talk Time)は、オペレーターが1件の通話で顧客とやりとりする時間の平均を示す指標です。この時間を短縮できれば、同じ時間内で対応できる顧客の数を増やすことが可能になります。たとえば、1件あたりの通話時間が平均15分から10分に短縮されると、その分多くの問い合わせに対応できるようになります。特に、問い合わせが集中するコールセンターでは、生産性を高めるためにATTの短縮を目指す取り組みが重要です。
顧客満足度・コスト・生産性に与える影響
ATTは単なる「時間」の指標ではなく、コールセンターの健全性を測る上で重要な3つの要素、「顧客満足度」「コスト」「生産性」に直接的な影響を与えます。
- 顧客満足度への影響:顧客は自身の問題が迅速に解決されることを望んでいます。ATTが適切に管理され、スムーズな対話で問題が解決すれば満足度は向上しますが、不必要に長引けば顧客のストレスとなり、満足度の低下に直結します。
- コストへの影響:コールセンターの運営コストの大部分は人件費です。ATTが1分短縮されるだけでも、センター全体で対応できるコール数は大幅に増加します。これは、同じ人員でより多くの業務をこなせることを意味し、コスト効率の向上に繋がります。
- 生産性への影響:ATTは生産性を測る最も直接的な指標の一つです。ATTが短縮されれば、オペレーター一人ひとりの対応件数が増加し、センター全体の生産性が向上します。これにより、電話が繋がらない「あふれ呼」の発生を抑制する効果も期待できます。
ATTの計算方法は?
ATTは、オペレーターが対応した全通話の合計時間を対応したコール数で割れば算出できます。具体的な式としては以下になります。
- 平均通話時間(ATT)=総通話時間÷総コール数
ATTを計算したい場合は、こちらの式を参考にしてみてください。
コールセンターのATTが長くなってしまう原因は?

効率と丁寧さを両立できていない
商品やサービスに関する知識が乏しいお客様や高齢の方への対応は、どうしても通話時間が長くなりがちです。こうしたケースでは、無理に通話時間を短縮しようと話を切り上げたり対応を急いだりすると、説明不足によりクレームにつながったり、顧客満足度を下げてしまうリスクがあります。オペレーターには、効率的かつ丁寧に会話を進める技術が求められます。
トークスクリプトが不十分
トークスクリプトが十分に用意されていない場合、オペレーターはその場で対応を考えながら話を進める必要があり、通話時間が長くなりがちです。問い合わせが多い内容については、具体的な対応手順や標準的な回答が記載されたスクリプトを用意しておくと、効率よく案内できるようになるでしょう。
トークのフローが整備されていない
適切な対応フローが整備されていない場合、オペレーターはどのように問題を解決するべきか迷ってしまうでしょう。例えば、「お客様をどの部署に繋ぐべきか」「質問に対してどの資料を参照すればよいか」といったフローが明確でない場合、対応が長時間化しがちです。また、FAQやオンラインのチャットボットなどを活用すればお客様自身で解決できる内容の場合も、フローが不十分だと対応を引き延ばしてしまうケースもあるでしょう。適切なフローを構築し、それをオペレーター全員に徹底することが必要です。
オペレータースキル不足
オペレーターのスキルが十分でないことも、通話時間が長くなってしまう要因です。例えば、顧客からの質問に対して的確に答えられなかったり、話の要点を整理できなかったりする場合、説明が冗長になりがちです。また、会話をリードする能力が不足していると、顧客が本題に入る前に話が逸れてしまい、無駄な時間が生じることがあります。これらの問題を解消するには、オペレーターに対して定期的な研修やトレーニングを実施するのが効果的です。
コールセンターのATTを改善する方法は?

通話内容を分析する
まずは、オペレーターごとの通話内容を詳細に調査・分析し、どの部分に問題があるのかを明確化しましょう。それぞれのオペレーターが抱える課題を把握することで、適切な改善策を考えられるようになります。
オペレーターごとのATTの目標数値を設定する
上記の分析データをもとに、各オペレーターに適したATTの目標値を設定しましょう。ここで大事なのは、一人ひとりの現状を踏まえた現実的な目標を設定することです。具体的な改善の指針があれば、生産性向上へのモチベーションを高めることができるはずです。
トークスクリプトやフローを整備する
トークスクリプトや対応フローを整えることで、オペレーターが迷うことなくスムーズに案内を進められるようになります。また、オペレーターのスキルに依存せず、誰でも一定の質で対応できる体制を実現できるでしょう。
対応チャート・マニュアルの活用
トークスクリプトを補完するものとして、視覚的に分かりやすい対応チャート(フローチャート)や、検索性に優れた電子マニュアルの活用が有効です。 問い合わせ内容が複数のパターンに分岐する場合でも、フローチャートがあればオペレーターは次に何をヒアリングし、どの情報を提供すべきかを瞬時に判断できます。また、キーワード検索が可能なマニュアルを整備することで、複雑な仕様や例外的な対応に関する情報を探す時間を大幅に短縮し、ATTの削減に貢献します。
音声ガイダンスを導入する
音声ガイダンスを導入することも検討しましょう。例えば、「商品に関するお問い合わせは1、予約のキャンセルは2」といったものです。オペレーターに接続される前に問い合わせ内容を分類・整理しておくことで、お客様も一から説明する必要もなくなるため、無駄な時間が削減され通話の効率が上がります。
チャットボットを導入する
チャットボットは、AIと自然言語処理を用いて顧客の質問に自動応答できるシステムのこと。チャットボットを活用することで、顧客対応の一部を機械に任せられるので、電話対応件数や通話時間の削減が期待できます。
FAQを充実させる
FAQを充実させて、お客様がコールセンターに問い合わせなくても自分で問題を解決できるようにしましょう。問い合わせをする前にFAQを参照できるようにすれば、問い合わせ件数を大幅に減らすことが可能です。また、FAQとチャットボットを組み合わせるのも非常に有効です。
システムの導入・改善サービス・アウトソーシングもATT改善に有効!

システムの導入
音声ガイダンスやチャットボット・FAQといった自動化システムを導入することで、ATTの短縮に大きな効果が期待できます。これらのツールにより、通話内容の事前処理やお客様の自己解決を促進することができるので、オペレーターの負担軽減にもつながります。また、これらのシステムはデータ分析機能も充実しているため、オペレーターの教育やパフォーマンス向上にも役立ちます。
クラウドPBXやCRMの連携による効率化
最新のコールセンターシステム、特にクラウドPBX(電話交換機)とCRM(顧客関係管理システム)の連携は、ATT改善に大きな効果をもたらします。 着信と同時に、発信者の電話番号からCRM内の顧客情報(過去の購入履歴や問い合わせ履歴など)をオペレーターのPC画面に自動表示させる「ポップアップ機能」が代表例です。これにより、オペレーターは「どのようなお客様か」を瞬時に把握でき、本人確認や状況説明の時間を省略して、すぐに本題に入ることができます。
対応品質の改善サービス
コールセンターの対応品質を評価・分析するためのモニタリングやミステリーコールサービスを利用するのもおすすめです。実際の対応状況を把握できるようになるため、問題点が明確化され、その改善に向けた具体的な対策を講じやすくなるでしょう。特に自社でコールセンターを運営している場合、これらのサービスは非常に効果的です。
応答率や稼働率の見直し
外部の品質改善サービスなどを活用する際は、ATTという単一の指標だけでなく、応答率(電話の繋がりやすさ)や稼働率(オペレーターが顧客対応にどれだけ時間を使っているか)といった関連指標と合わせて見直すことが重要です。 例えば、ATTの短縮のみを追求した結果、解決しきれないまま通話を終えてしまい、顧客が再度電話をかけてくる「再入電」が増加しては本末転倒です。専門家の視点を取り入れることで、各指標のバランスを取りながら、コールセンター全体のパフォーマンスを最適化するアプローチが可能になります。
コールセンターのアウトソーシング
コールセンター業務を外部に委託することも検討してみてはいかがでしょうか。外部委託により、専門的なシステムや優れたオペレーターの採用が可能になるので、ATTの大幅な改善が期待できます。また、コスト削減や効率化も期待できるので、業務全体の生産性を高めることができるでしょう。
コールセンターのアウトソーシングについて詳しく知りたい方は、こちらの記事を合わせてお読みください
生産性に関わるその他の指標とATTとの関係
ATTは単独で存在する指標ではありません。他の主要なKPIと密接に関連しており、それらの関係性を理解することが、コールセンター運営の質を高める鍵となります。
応答率(Answer Rate)とは
応答率とは、コールセンターにかかってきた電話(着信数)のうち、オペレーターが対応できた電話の割合を示す指標です。ATTが長引くと、一人ひとりのオペレーターが次の電話に出るまでの時間も長くなるため、結果として応答率は低下します。応答率の低下は、顧客が電話を諦めてしまう「放棄呼」の増加に直結し、機会損失や顧客満足度の低下を招きます。
稼働率(Occupancy Rate)とは
稼働率とは、オペレーターがログインしている時間のうち、顧客対応(通話、後処理、待機時間)に費やしている時間の割合を示す指標です。一般的に80~85%が適正値とされます。ATTが不必要に長い状態が続くと、オペレーターは常に顧客対応に追われることになり、稼働率が過度に高まります。これはオペレーターの疲弊やバーンアウトに繋がり、応対品質の低下や離職率の増加といったリスクを高めます。
休憩時間管理とモニタリングの重要性
高い品質を維持するためには、オペレーターが適切な休憩を取ることが不可欠です。しかし、ATTが長く、常に対応に追われている状況では、オペレーターは休憩を取りづらくなります。管理者(スーパーバイザー)は、各オペレーターのATTやその他の指標を定期的にモニタリングし、負荷が高くなりすぎていないかを確認し、適切に休憩を促すなどのケアを行うことが重要です。健全な労働環境が、結果的に安定したATTと高い応対品質を支えます。
よくある質問
Q. ATTとAHTの違いは?
A. ATT(Average Talk Time)は「平均通話時間」、つまり純粋にお客さまと会話している時間のみを指します。一方、AHT(Average Handling Time)は「平均処理時間」を意味し、ATTに加えて、通話後の対応記録入力などのACW(After Call Work / 平均後処理時間)を含んだ、1コールあたりの総作業時間(ATT + ACW = AHT)を指します。
Q. ATTは短ければ短いほどいいの?
A. 一概にそうとは言えません。無理にATTを短縮しようとすると、説明不足による再入電の増加や、顧客に「話を急かされている」という不満を与えてしまい、かえって顧客満足度を低下させるリスクがあります。目標とすべきは、単なる「最短」ではなく、顧客の問題を確実に解決し、かつ無駄のない会話で構成された「最適」なATTです。
Q. 業界平均はどれくらい?
A. 業界や業務内容によって大きく異なるため、一概に「平均は〇分」と言うことは困難です。例えば、商品の受注受付のような定型的な業務ではATTは短くなる傾向にありますが、専門的な知識が必要なテクニカルサポートでは長くなるのが一般的です。他社の数値を追うよりも、まずは自社の過去のデータを基準に目標を設定し、継続的な改善を通じて自社にとっての最適なATTを見つけていくアプローチが重要です。
まとめ
今回は、コールセンターの「ATT」について解説しました。ATTは、オペレーターとお客様の平均通話時間を示し、生産性向上の大切な指標ですが、単純に短縮を目指すだけではなく、顧客満足度や対応品質を損なわないための工夫が求められます。 コールセンターの運営は日々の積み重ねが大切です。小さな改善を積み重ねていくことで、ATTを適切に管理しつつ、より効率的で高品質な対応を実現できるでしょう。ぜひ今回の記事を参考に、自社の課題に合った取り組みを検討してみてくださいね。

ProCX編集部
NTTマーケティングアクトProCX