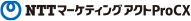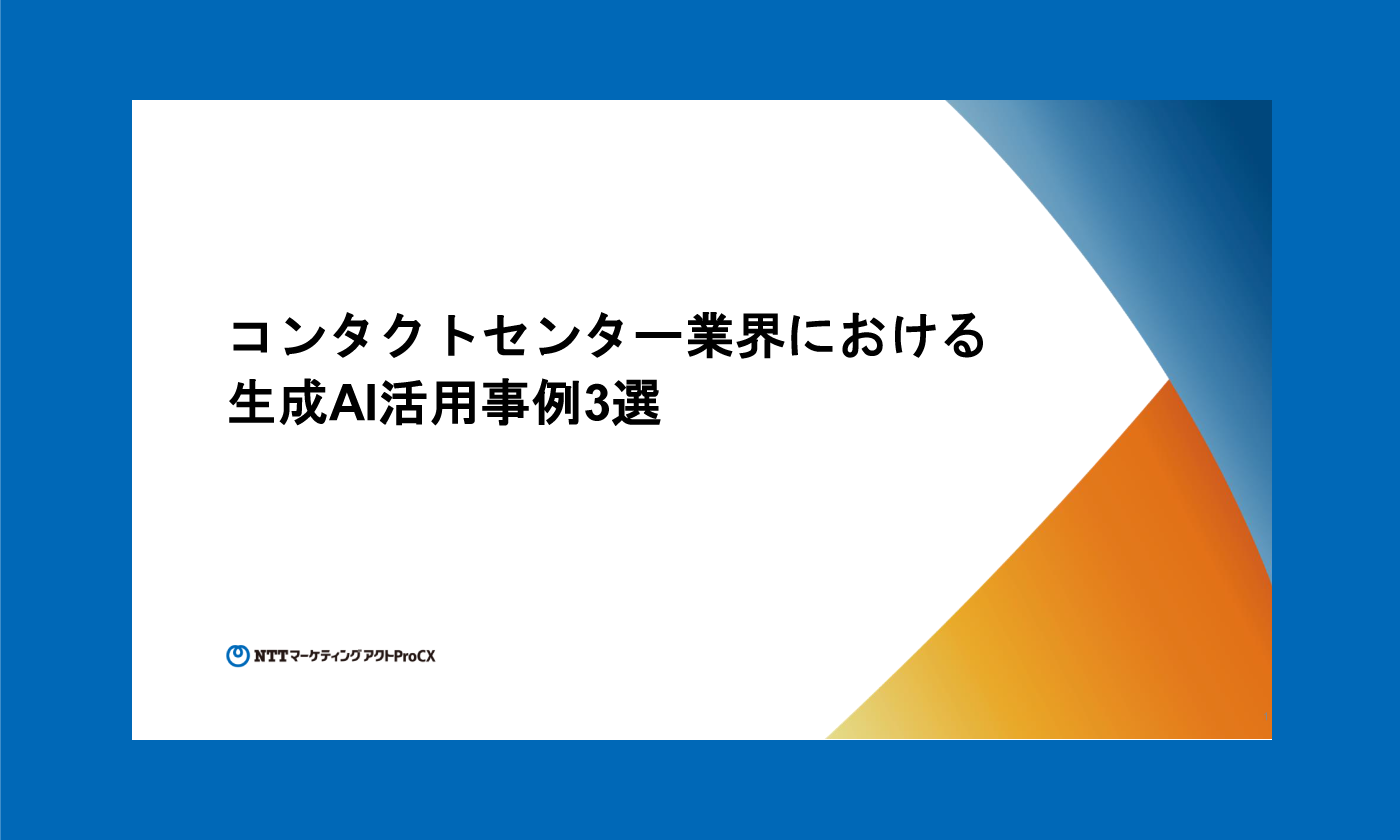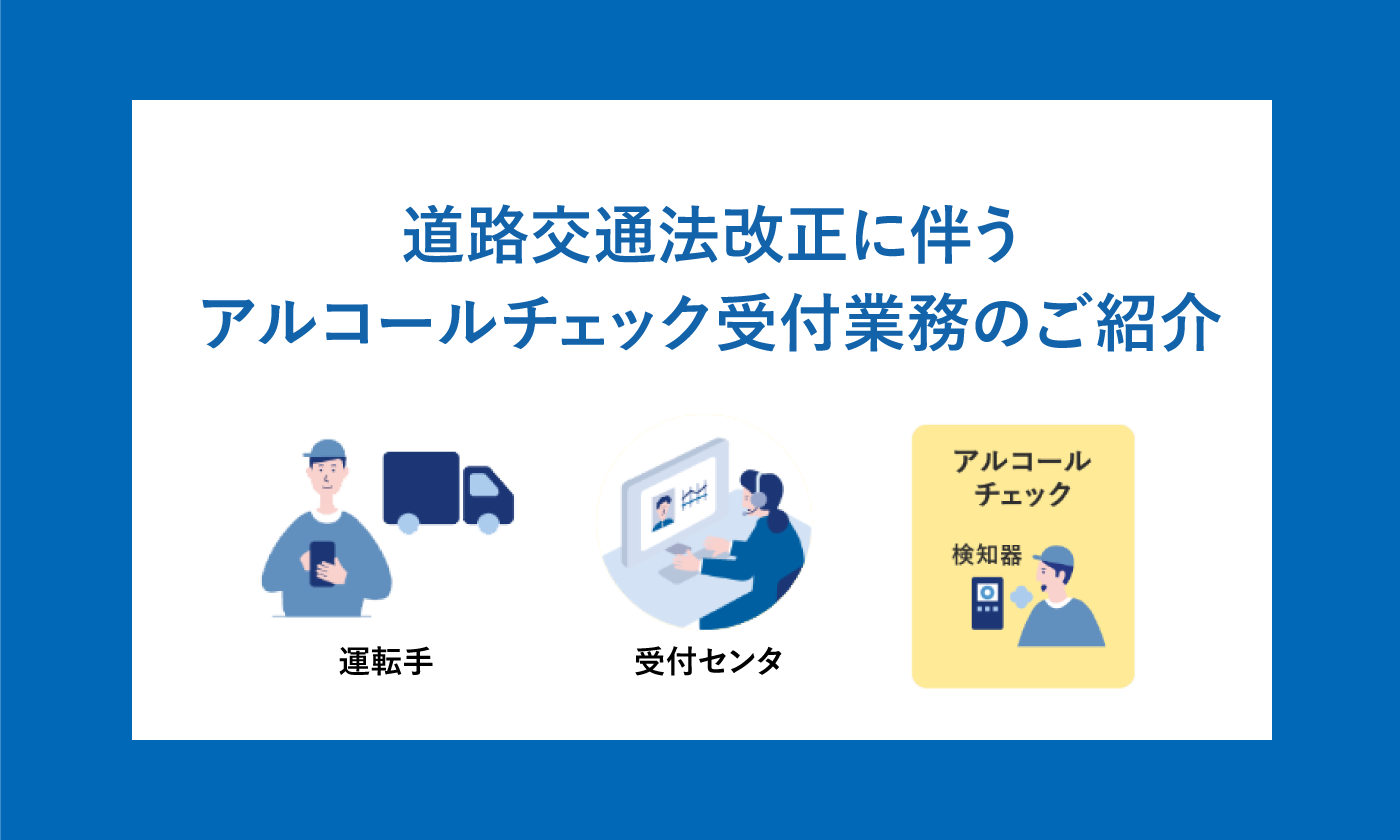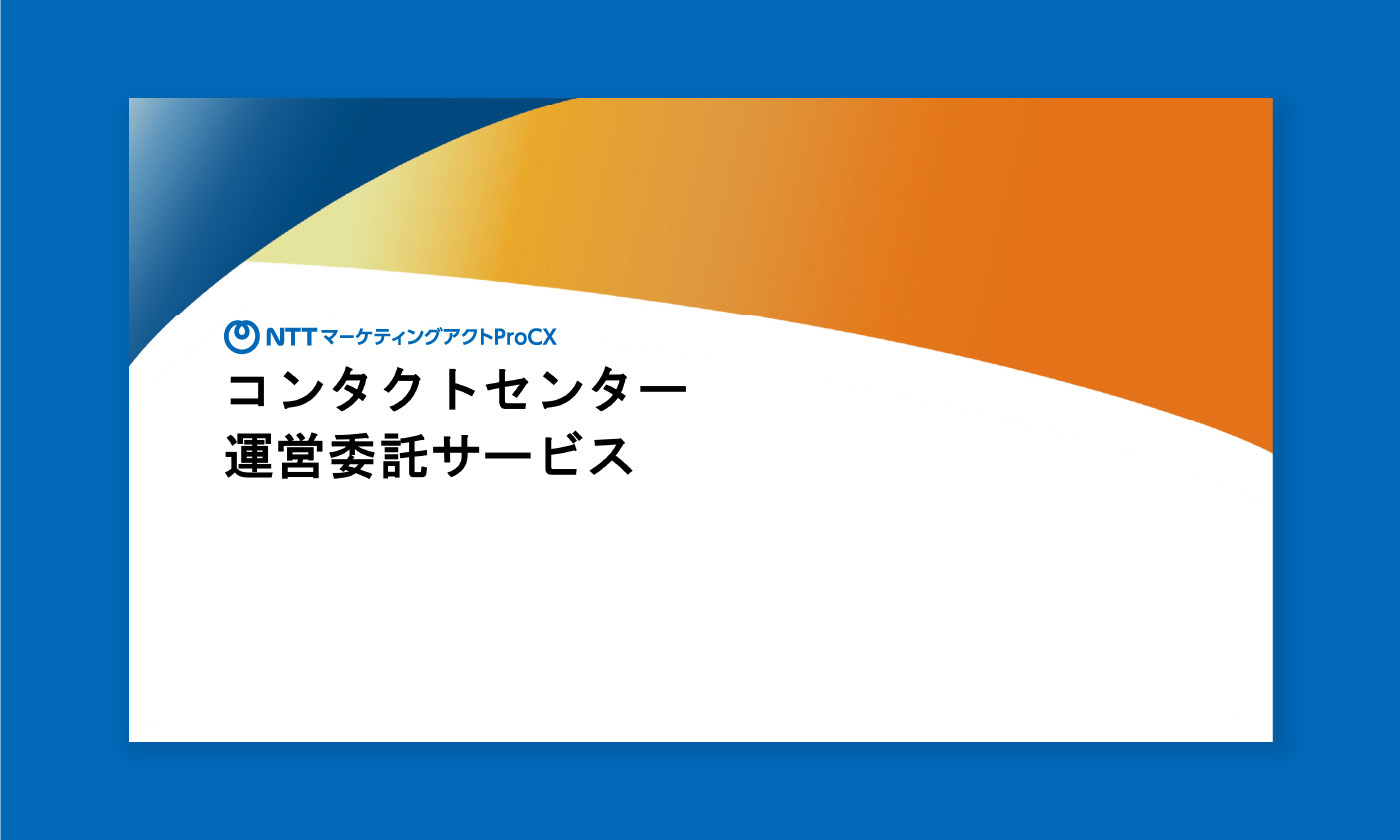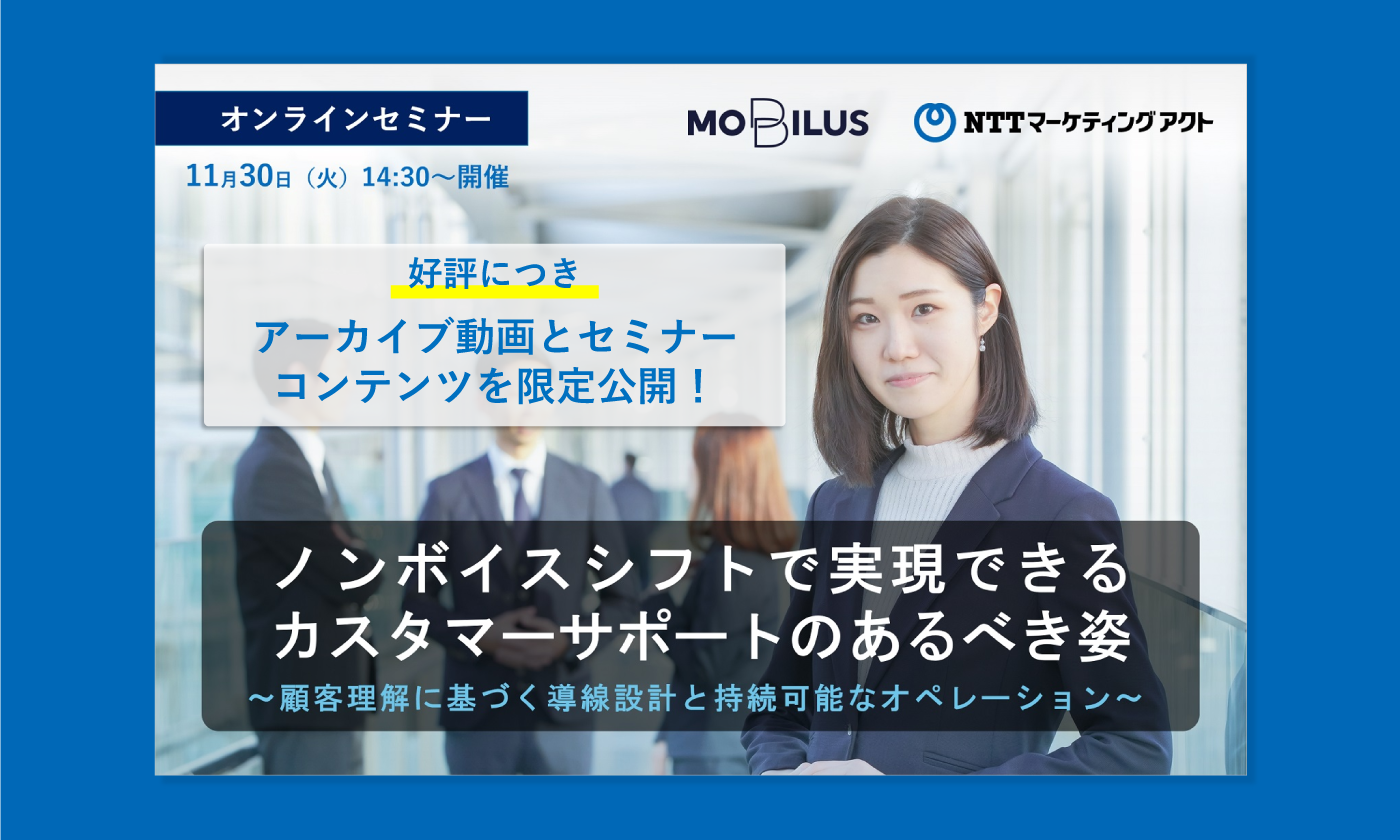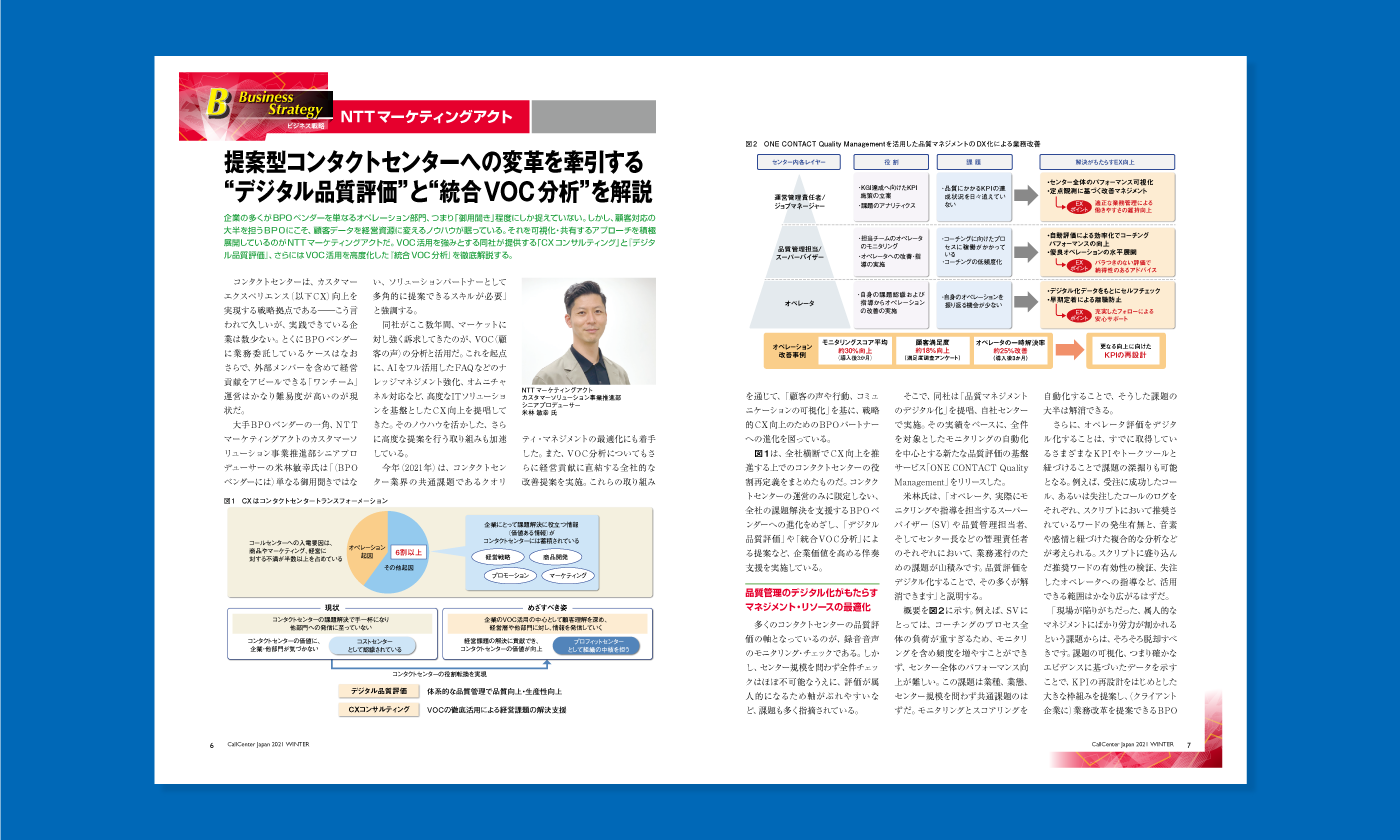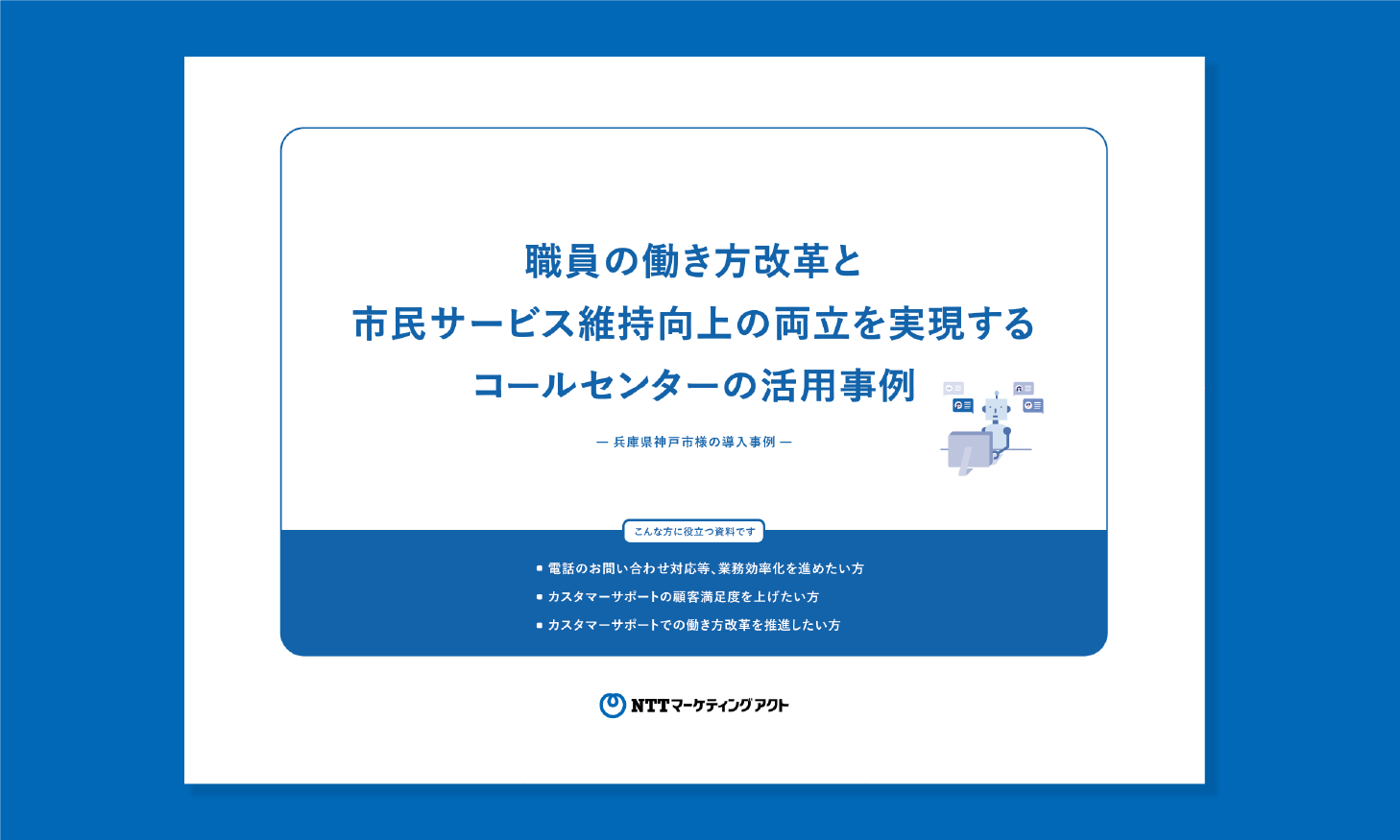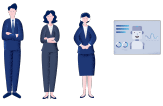コンタクトセンター
コールセンター効率化のポイントとは?よくある課題と改善策を解説
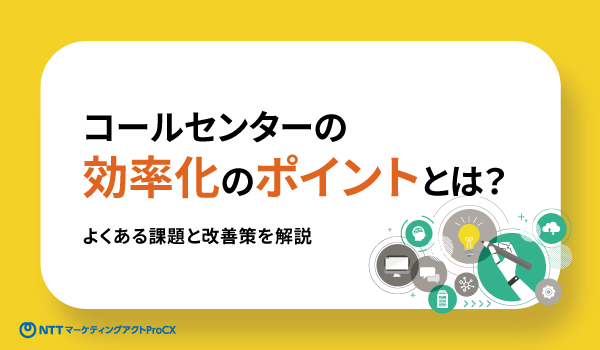
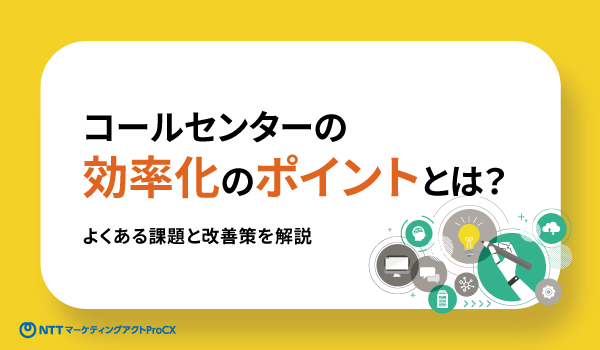

日々大量の電話対応を行うコールセンターでは、さまざまなトラブルが発生します。
システムの構造、オペレーターの対応、情報の入力作業やアウトプットの仕方など、どこかで問題が発生すると、業務が遅延して顧客満足度が低下してしまうほか、業務負担によるオペレーターの離職などにつながる恐れもあります。
そこで今回は、コールセンターでよくある課題と改善策の一部を簡単にご紹介します。
コールセンター業務でよくある課題は?

コールセンターの現場では、業種やサービス内容に関係なく、共通する運営課題が多く見られます。ここでは、現場のパフォーマンスや顧客満足度に直結する代表的な課題を詳しく解説します。
繁忙期の問い合わせ増加に追いつけない
キャンペーンや年末年始、新商品発売などの繁忙期には、通常の数倍の問い合わせが集中することがあります。このようなタイミングで、人員を増やす準備が間に合わない場合、電話がつながりにくくなったり、メールやチャットの対応が遅れたりして、顧客の不満が高まりやすくなります。
また、対応履歴やナレッジが十分に蓄積されていない場合、オペレーターは毎回ゼロから調査・確認を行う必要があり、結果として対応に時間がかかってしまいます。この遅延がさらに問い合わせ件数を積み重ね、悪循環を引き起こします。
オペレーター不足・配置の最適化ができていない
慢性的な人手不足や、オペレーターの離職率が高い現場では、人員計画が常に綱渡りになっているケースもあります。特に、業務量の波に対して適切な人数配置ができていないと、忙しい時間帯に対応しきれず、応答率や対応品質が低下します。
さらに、シフトの調整が手作業や表計算ソフトで行われている場合、急な欠員への対応が難しく、穴埋めの調整が現場に負荷をかけます。また、複数業務を1人でこなせる体制が整備されていない場合、業務の偏りが発生し、一部のオペレーターに負荷が集中することもあります。
対応フローや業務分担が曖昧
誰が何を担当するのかが明確でない場合、対応のたびに業務の押し付け合いや「これは自分の仕事ではない」といった認識のずれが生じやすくなります。その結果、顧客対応に遅れが出たり、対応の質が下がったりすることがあります。
また、エスカレーション(対応を上位者に引き継ぐ)基準が曖昧な場合、オペレーターの判断が属人的になり、ある人はすぐに引き継ぐが、別の人は最後まで抱え込んでしまうなど、対応方針にばらつきが出ます。こうした不統一はチーム全体の効率と品質に悪影響を与える要因です。
後処理や記録が手間になっている
電話やチャットでの応対が終わった後には、内容の記録やシステムへの入力作業が必要になりますが、この「後処理」に時間がかかることも大きな負担となります。特に、応対内容を詳しく残す必要がある業務では、後処理の時間が長引くことで次の問い合わせへの対応が遅れるケースもあります。
また、入力内容にばらつきがあったり、記録ミスが発生したりすることで、情報の正確性や信頼性に課題が生じます。記録ルールやフォーマットが統一されていないと、同じ情報でも記録方法が担当者によって異なるため、後から内容を確認しにくくなり、業務の引き継ぎや分析にも支障をきたします。
コールセンター業務を効率化するメリットは?

コールセンター業務の効率化は、単なる業務のスピードアップにとどまらず、顧客対応の質やスタッフの働きやすさ、さらには経営的なコスト削減にも大きく貢献します。ここでは、業務効率化によって得られる主なメリットを3つの視点から詳しく解説します。
対応スピードが上がり、顧客満足度が向上
業務を効率化することで、顧客からの問い合わせに迅速に対応できる体制が整い、待ち時間を大幅に削減することが可能になります。長時間の保留やメール返信の遅延といった「待たされるストレス」が軽減されることで、顧客の不満が減り、企業に対する信頼感が高まります。
また、対応履歴の共有やナレッジの活用がスムーズに行えるようになれば、オペレーターが過去のやり取りをすぐに把握できるため、質問に対する回答精度も上がり、問い合わせが一度で解決する「一次解決率」も向上します。
これは顧客の再問い合わせを減らし、企業と顧客の双方にとって効率的で満足度の高い対応につながります。
オペレーターの負担軽減・離職率の低下
業務効率が上がれば、オペレーターにかかる負担が軽減され、特に繁忙期などのストレスフルな環境下でも安定して業務に取り組めるようになります。例えば、FAQテンプレートの活用や問い合わせ対応の一元管理ツールの導入によって、複雑な手作業や確認作業を減らせるため、精神的・物理的な負担が和らぎます。
また、業務の進捗や成果を数値化して可視化することで、自身の仕事への達成感ややりがいを実感しやすくなり、モチベーションの維持にもつながります。こうした取り組みは職場全体の定着率を高め、慢性的な人手不足や高い離職率の改善にも良い影響を与えるでしょう。
運用コスト・教育コストの削減
業務の標準化や自動化が進めば、新人オペレーターの教育期間を短縮できるだけでなく、業務の質も均一化されやすくなります。例えば、マニュアルやトークスクリプトが整備されていれば、経験の浅いスタッフでもスムーズに対応できるようになります。
加えて、問い合わせ対応の自動化(例:IVRやチャットボットの活用)や、効率的なシフト配置により、業務時間外の残業や不必要な人員配置が削減され、人件費の圧縮が可能になります。さらに、効率化によってクレームやトラブルの発生件数が減れば、再対応にかかる時間や人的リソースも抑えられ、全体としての運用コストを下げることができます。
コールセンターの効率化に必要な施策は?

コールセンターの業務効率を高めるためには、ツールの導入だけでなく、情報整理・人材育成・対応チャネルの最適化など、さまざまな側面からのアプローチが求められます。
ここでは、業務全体の生産性向上に直結する施策の一部をご紹介します。
FAQ・ナレッジベースを構築・整備する
顧客からの問い合わせには一定の傾向があり、特に多い内容についてはFAQ(よくある質問)やナレッジベースとして整理することで、対応時間の短縮が可能になります。トークスクリプトや対応テンプレートを事前に整えておけば、誰でも同じ基準で対応できるため、品質の均一化にもつながります。
また、情報を検索しやすいフォーマットで共有することで、オペレーターが必要な情報にすばやくアクセスでき、回答までの時間を大幅に短縮できます。FAQの更新は定期的に行い、現場の声を反映させることで、常に実用性の高いナレッジを維持できます。
IVR・スキルルーティングの導入
IVR(自動音声応答)を活用することで、電話を受けた段階で問い合わせ内容を振り分け、最適な部署や担当者へ自動的に転送できます。たとえば「製品の使い方については1を、請求に関する問い合わせは2を」といった案内があることで、顧客は自分の要件に合ったオペレーターにすぐに繋がります。
さらに、スキルルーティングを導入することで、顧客の問い合わせ内容に応じた専門スキルを持つオペレーターに自動で振り分けることができ、一次対応での解決率が向上します。結果として、対応の品質が安定し、二次対応やエスカレーション件数の減少にもつながります。
WFM(ワークフォースマネジメント)システムを活用
WFMとは、業務量と人員配置を最適化するための管理手法です。コール数の予測や時間帯別の問い合わせ傾向を分析することで、過不足のないシフト編成が可能になります。これにより、オペレーターの稼働率や待機時間のバランスを改善でき、業務効率とコスト削減の両立が実現します。
また、急な欠員やイレギュラー対応にも柔軟に対応できるため、業務継続性の確保にも寄与します。繁忙期やキャンペーン時期など、需要の変動にも素早く対応できるのがWFM導入の大きな利点です。
音声認識・自動要約ツールの活用
近年ではAIを活用した音声認識ツールが進化し、通話内容をリアルタイムでテキスト化することが可能になっています。これにより、通話終了後の手入力作業が不要になり、オペレーターの後処理時間を大幅に削減できます。
さらに、自動要約機能を組み合わせれば、通話の要点だけを抽出して記録できるため、管理者や後続対応者への引き継ぎもスムーズになります。正確な記録により、トラブル対応時の証拠資料としても活用可能です。
チャットボット・自己解決チャネルの拡充
電話対応が混み合う時間帯や休日にも顧客の疑問に対応するために、チャットボットの導入やFAQページの拡充は非常に効果的です。事前に登録した質問と回答により、よくある問い合わせには即時で対応でき、オペレーターの負担も軽減されます。
さらに、顧客自身がマイページなどで注文履歴や契約情報を確認できる自己解決型の仕組みを提供することで、問い合わせ自体を減らすことも可能になります。結果として、オペレーターはより付加価値の高い対応に集中できるようになります。
マニュアル・教育体制の見直し
現場の実態に即したマニュアル整備は、業務効率と対応品質の安定に欠かせません。トーク例や注意点を盛り込んだ分かりやすいマニュアルがあれば、新人オペレーターでも自信を持って対応に臨めます。
また、ロールプレイやOJT(実地研修)を取り入れることで、実践的なスキルの定着が図れます。教育が属人化しないように、指導内容や研修プログラムもマニュアル化し、誰が教えても同じ品質で育成できる体制を構築することが重要です。
このように、コールセンター効率化の方法にはさまざまな方法があります。ここで、それぞれの具体的な方法まで紹介することはできませんが、「自社の課題への対策にマッチする」と感じるものを改めて調べて、試してみるとよいでしょう。
コールセンターの効率化の進め方と注意点

コールセンターの業務効率化は、生産性の向上やコスト削減、従業員の働きやすさ向上など、さまざまなメリットがある一方で、進め方を誤ると現場に混乱を招いたり、サービス品質が低下したりするリスクもあります。ここでは、効率化を成功させるための進め方と最低限注意すべきポイントをご紹介します。
いきなり多施策を同時展開しない
効率化を進めるうえで最も避けたいのが、複数の施策や新しいツールを一斉に導入してしまうことです。現場のオペレーターにとっては、急激な変化が業務負荷やストレスの増加につながり、かえって混乱を招くおそれがあります。
そのため、まずはひとつの施策を小さく導入し、一定期間の検証と現場からのフィードバックを得たうえで、段階的に展開していくことが望まれます。また、施策ごとに「なぜそれを行うのか」「何を目指すのか」という目的と優先順位を明確にし、関係者全体で共有しておくことも、着実な定着を促すポイントです。
効率化によって品質が落ちないように注意
効率化に注力するあまり、対応の「速さ」ばかりが重視されると、オペレーターが流れ作業のように応対してしまい、結果として顧客との信頼関係を損なうことにもつながります。
たとえば、定型文に頼りすぎて個別対応が不十分になったり、確認不足によるミスが増えたりするリスクがあります。そのため、効率化と同時に、品質の維持・向上にも目を向ける必要があります。定期的な顧客満足度調査や対応品質のモニタリングを行い、サービスの「質」が維持されているかどうかをチェックしましょう。
また、KPI(応答率・処理時間など)だけでなく、現場での実感や顧客からの声といった定性的な評価もあわせて分析することで、バランスの取れたマネジメントが可能になります。
効果検証と改善サイクルを定着させる
効率化施策は、導入して終わりではありません。実施した後に「本当に効果が出ているのか」「現場で活用されているのか」を検証し、改善していくプロセスが不可欠です。これを怠ると、施策が形骸化したり、効果のないまま運用が続けられたりしてしまう可能性があります。
そのため、KPIや業務データの定期的なチェックに加えて、現場の声を吸い上げるヒアリングやアンケートも重要です。そして、得られた結果をもとにPDCAサイクルを回すことを習慣化し、効率化の取り組み自体を「継続的な改善活動」として位置づける必要があります。
また、レビューや改善を「仕組み」として定例化し、担当者やリーダーに役割を明確に持たせることで、「導入して終わり」の状態を防げます。
現在はコールセンターの効率化に適したさまざまなツールと、それに合った運用方法があり、着実に実施することで高い確率で効果がされます。
ただ、無理に複数の施策に取り組んだり、品質よりも効率化を優先させたりしすぎると、かえって逆効果になることも。解決したい課題を明確にして、スモールスタートで効果検証を行いながら効率化を進めるようにしましょう。
まとめ
コールセンターの業務は、多岐にわたる顧客対応を正確かつ迅速に行う必要があり、常に効率性と品質の両立が求められます。しかし現場では、繁忙期の対応遅延や人員配置の最適化不足、オペレーターへの過度な負担など、さまざまな課題が発生しやすいのも事実です。
こうした課題を解決するには、今回ご紹介したようなツールを導入し、効率化の施策を実施することが大切です。
ただ、社内リソースなどの問題で、効率化に時間を割けないというケースもあるでしょう。その場合は、アウトソーシングやBPOサービスの活用も有効です。専門性を持つ外部パートナーと連携することで、品質を保ちながら業務を効率化し、より戦略的な運営体制を実現できます。
業務効率化は、単なるコスト削減ではなく、顧客満足度や従業員の働きやすさ、組織全体の成長にもつながる重要な取り組みです。自社の課題を正しく見極め、継続的な改善を目指していきましょう。

ProCX編集部
NTTマーケティングアクトProCX