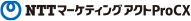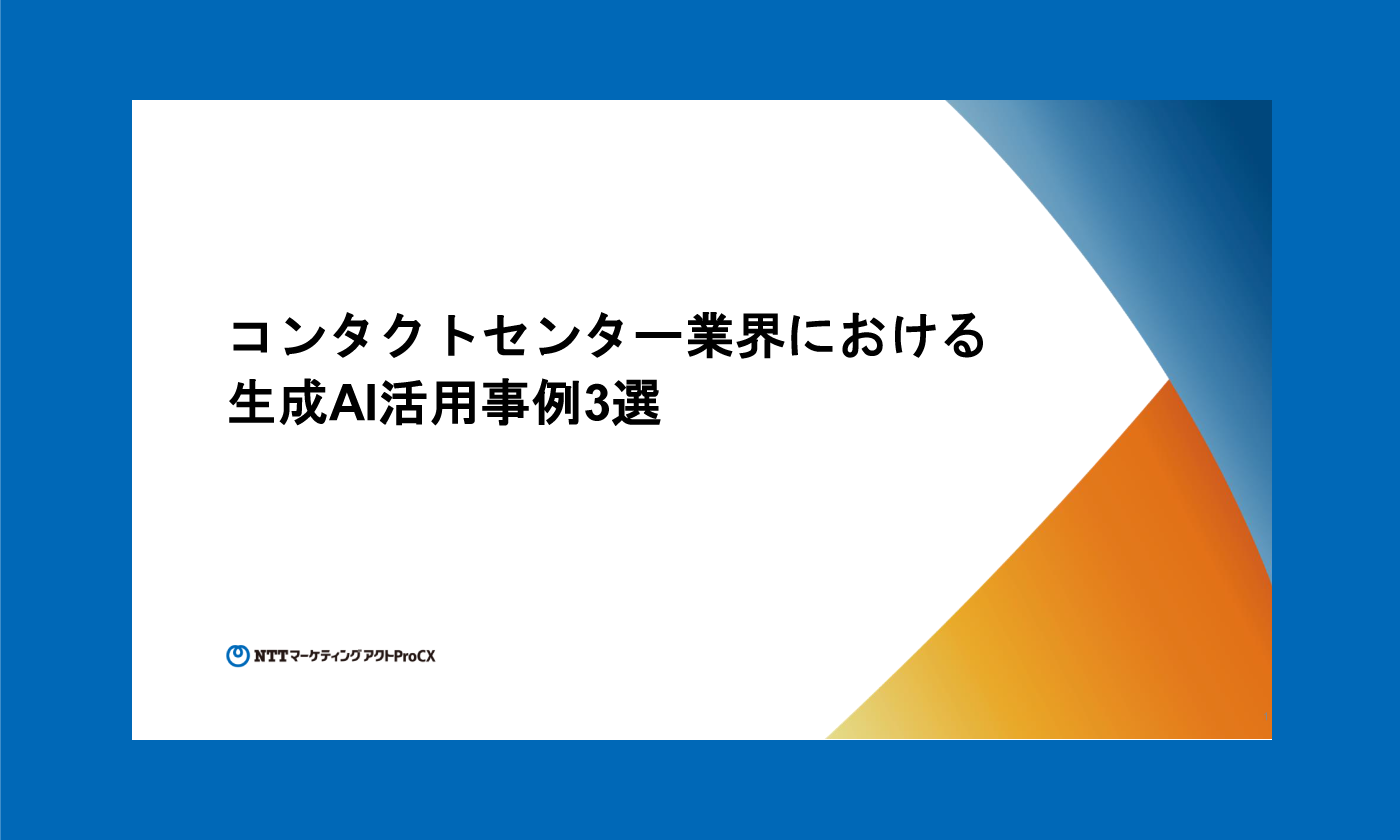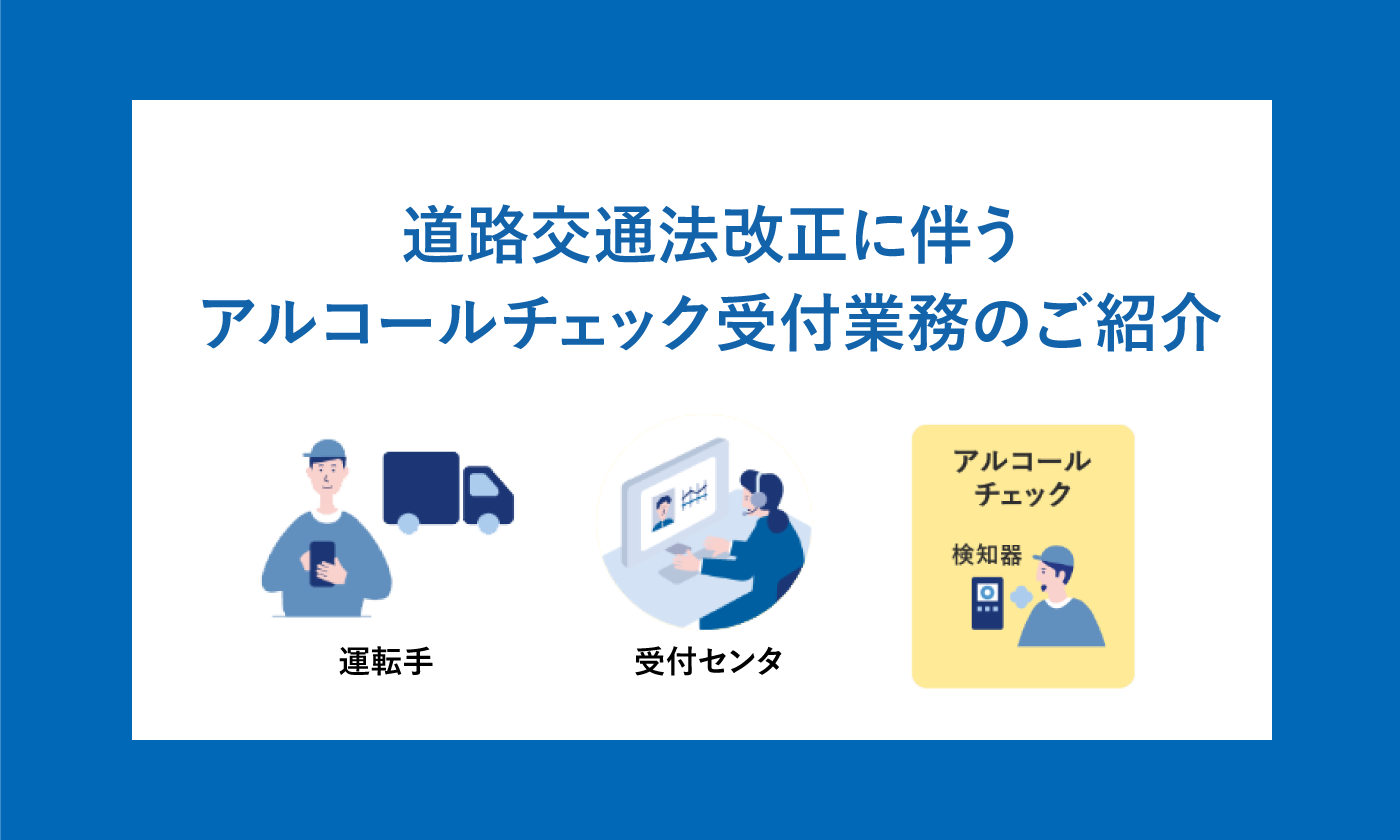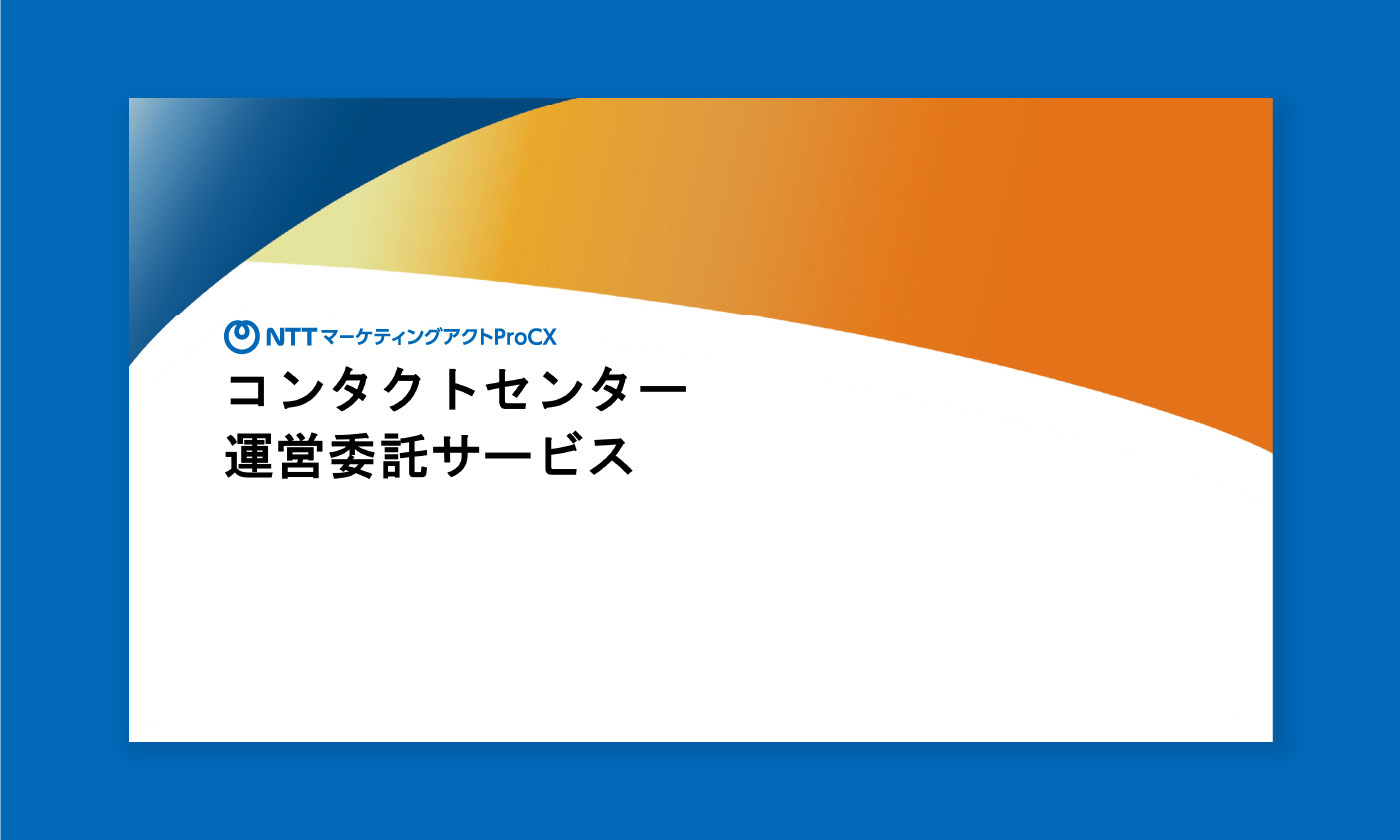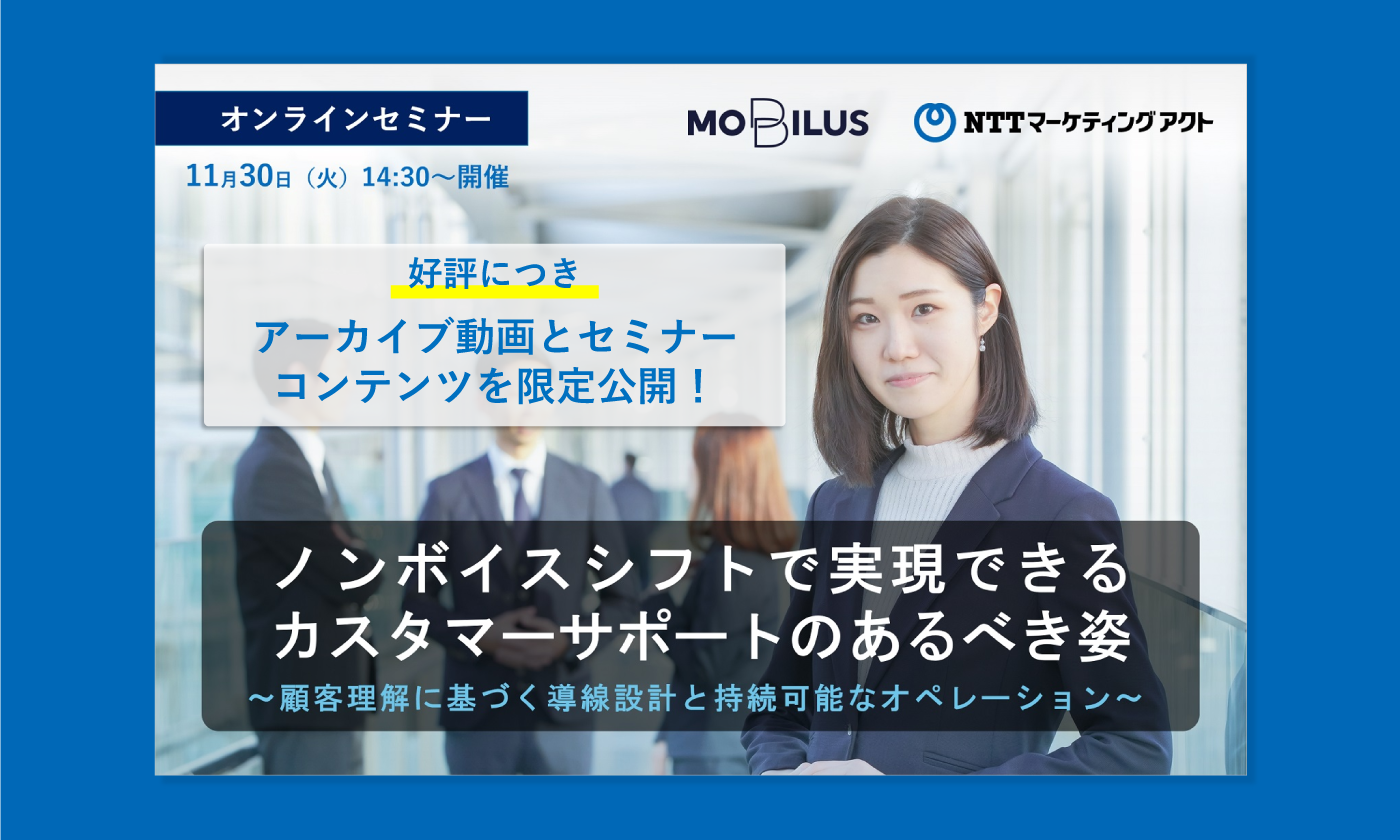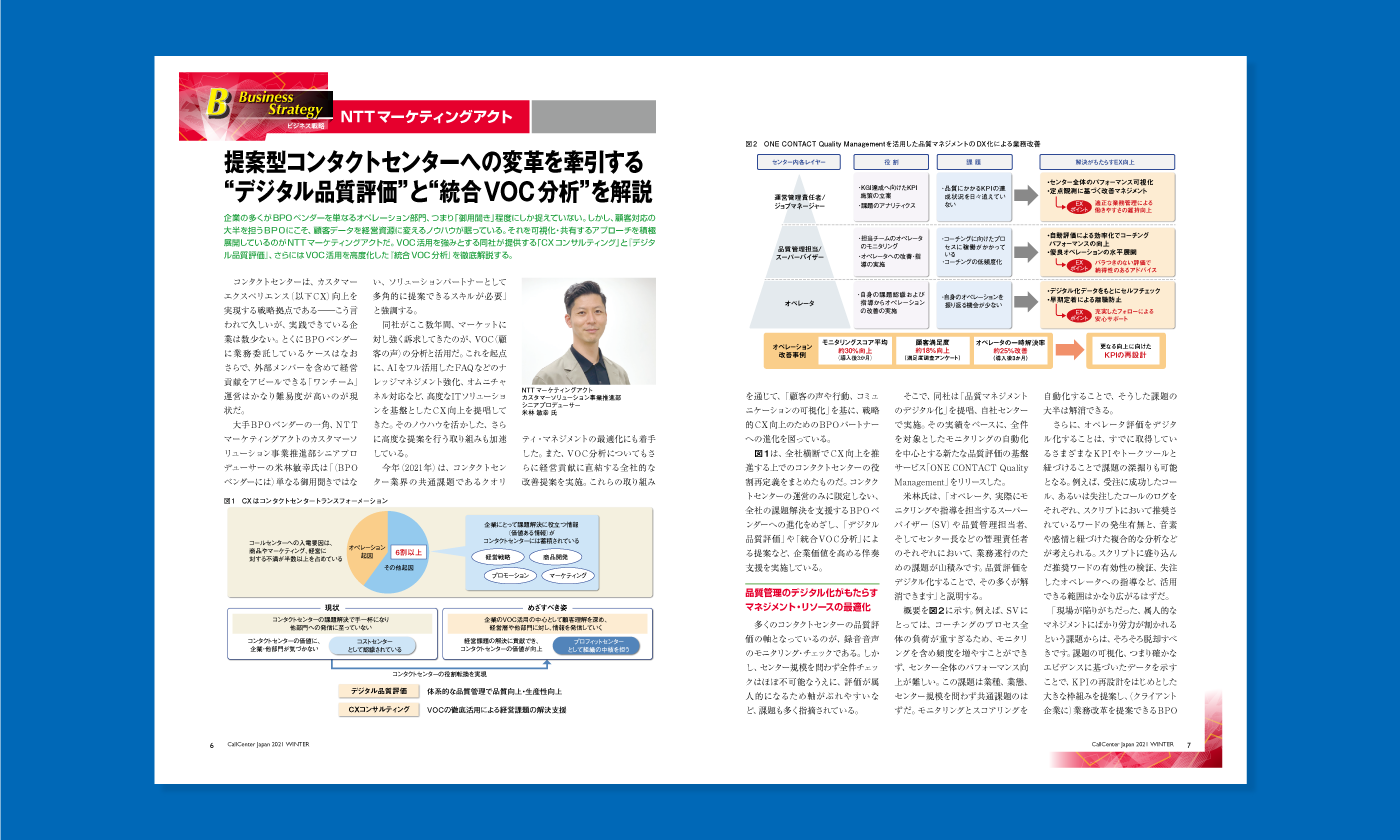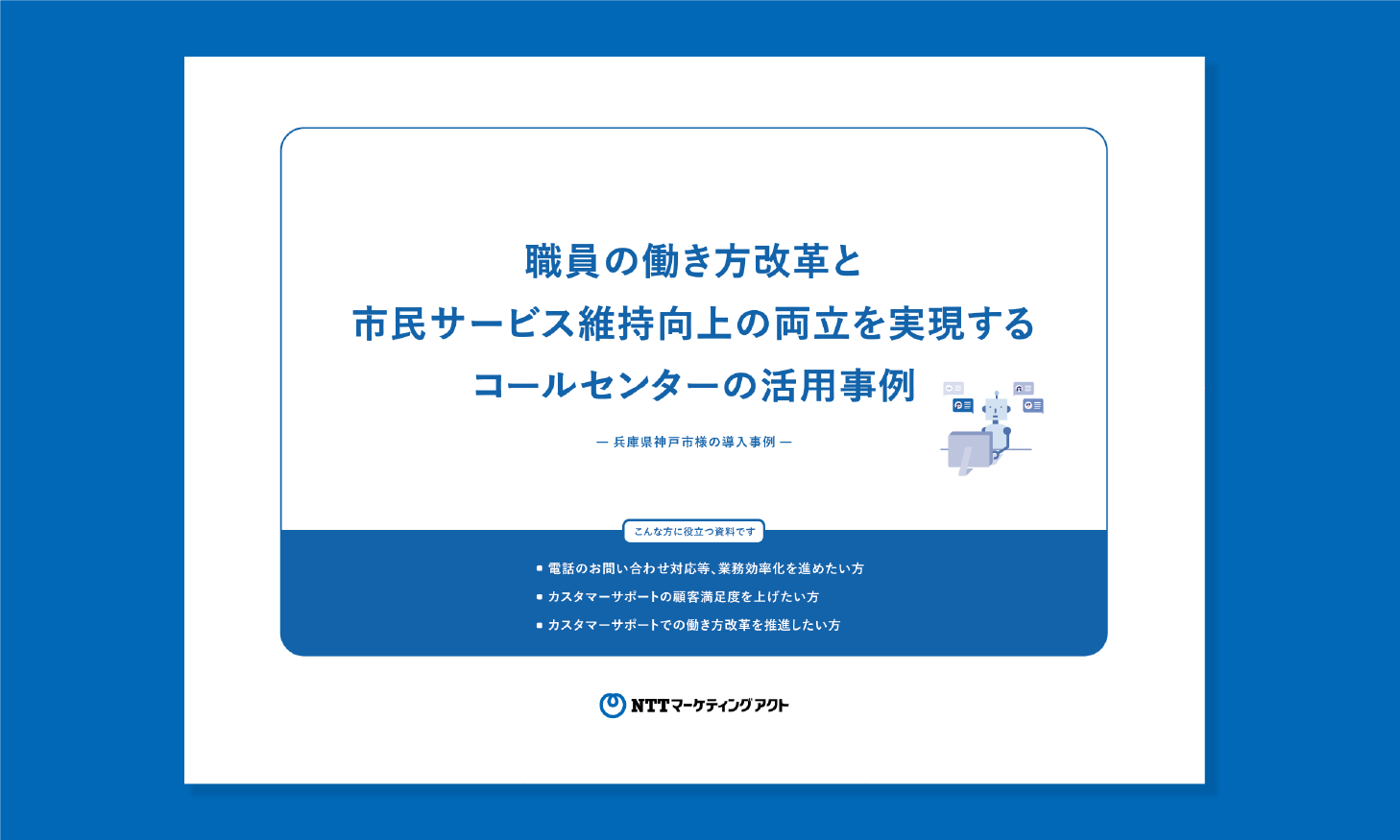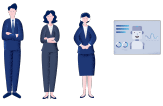コンタクトセンター
コールセンターのPBXとは?主な機能と選び方のポイントを解説!
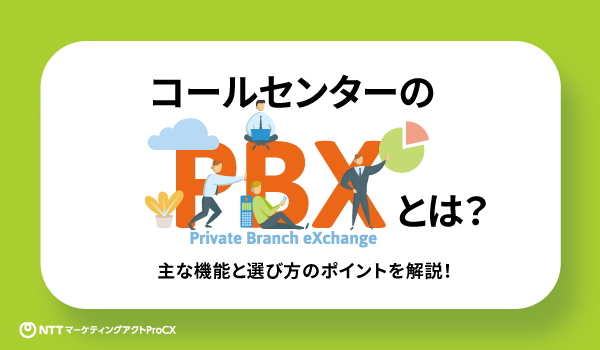
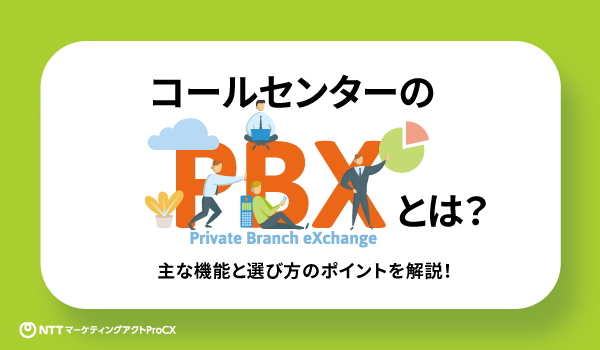

コールセンターでは、複数のオペレーターが同時に電話応対を行い、顧客とのスムーズなコミュニケーションを維持する必要があります。
その中核を支えるのが「PBX(Private Branch eXchange)」です。PBXは社内電話網を管理し、外線と内線を効率的に制御するシステムで、近年はクラウド型の普及が進んでいます。
この記事では、PBXの基本機能や種類、選び方のポイントをくわしく解説します。
PBXの基礎!コールセンターでPBXが担う役割

まずは、コールセンターにおけるPBXの役割など、基本情報についてご紹介します。
PBXの役割は?
PBXは社内の内線・外線通話を統合的に管理し、転送・保留・代表着信などの機能を制御するシステムです。
電話業務を円滑に行うために不可欠で、同時の着信や発信を行っても、混雑や呼損を防ぎながらスムーズに通話を可能にします。
また、CTIやCRM、ACD、IVRなど他システムとの連携基盤となり、顧客情報表示や自動音声応答などの高度なサービス提供を支える役割もあります。
PBXの種類は?
PBXには大きく分けて「オンプレミス型」と「クラウド型」があります。
オンプレミス型
自社内に機器を設置し、細かなカスタマイズが可能です。 一方で初期投資や保守費用の負担が大きく、災害対策(BCP)を行うには追加投資が必要となります。 拠点を増やしたり在宅勤務に対応したりする場合は、構成が複雑化しやすい点が課題です。
クラウド型
クラウド型は、インターネット回線を通じて利用するため、拠点や在宅環境を問わず利用できるPBXです。小規模からスタートしても段階的に拡張でき、機能追加やアップデートも自動で行われるため、BCP(事業継続計画)にも強みがあります。 料金は月額課金+通話料の形が一般的で、ネットワーク品質に依存する点には注意が必要ですが、柔軟性・コスト面から、近年はクラウド型PBXが主流になっています。
PBXが不可欠な業務シーンとは?
コールセンター業務では、PBXが次のような場面で活用されます。
- 代表番号への着信を自動的に適切なオペレーターへ振り分け、対応漏れを防ぐ
- オペレーター間での内線転送を円滑に行い、顧客対応を途切れさせない
- 緊急時には通話ログの管理や音声録音を活用し、対応履歴の証跡を残す
- AHT(平均処理時間)やFCR(一次解決率)の改善など、業務品質向上の基盤を築く
PBXはコールセンターの電話運営を支える中枢システムです。自社の規模や運営形態、将来的な拡張計画を踏まえ、最適なPBXを選定することが、安定した顧客対応と生産性向上のカギとなります。
PBXの主な機能と導入のメリット

次に、PBXの主な機能と導入の具体的なメリットについてご紹介します。
PBXの主な機能
PBXは、企業の電話環境を統合的に管理する多機能システムです。その機能は大きく「基本機能」と「コールセンター業務に特化した機能」に分けられます。
基本機能一覧
PBXの基本的な機能は、日常の電話応対を安定的に支える基盤です。適切に活用することで、コールセンター運営の効率と顧客満足度が大きく向上します。
・内線・外線制御 PBXは社内の内線と外部への外線を統合的に管理します。代表番号から着信した電話を自動で最適なオペレーターへ振り分けたり、社内の内線同士をつないだりすることが可能です。これにより、顧客は最初の問い合わせで適切な担当者につながりやすくなり、対応スピードが向上します。大規模センターでは数百回線を同時制御するケースもあり、PBXが安定した通話品質を保つ鍵となります。
・保留・転送 顧客対応中に別部署への確認が必要な場合、保留機能は欠かせません。音楽やガイダンスを流して待機時間の不安を和らげることもできます。転送機能では、一次受付から専門部署へのスムーズな引き継ぎが可能です。これにより顧客は同じ説明を何度も繰り返す必要がなく、顧客満足度が高まります。
・発着信履歴管理 すべての着信・発信を自動で記録することで、対応漏れや折り返し忘れを防ぎます。履歴データは応答率や通話件数の分析にも活用でき、繁忙時間帯の特定や人員配置計画に役立ちます。レポートを定期出力すれば、経営層への報告資料としても有用です。
・通話録音 トラブル防止の証跡としてだけでなく、オペレーター教育の教材としても重要です。録音データを分析すれば、クレーム対応の改善点やトークスクリプトの最適化が可能です。金融や医療など規制の厳しい業界では、コンプライアンス遵守の証拠として録音が必須となる場合があります。
・通話ログ管理 通話時間・相手先・担当オペレーターなどを詳細にログ化し、後から検索・抽出して活用できます。特定顧客の問い合わせ履歴を確認したり、AHT(平均処理時間)を算出したりする際に役立ちます。ログをBIツールと連携させれば、経営判断につながる分析も容易です。
・通話モニタリング スーパーバイザーがリアルタイムで応対状況を確認し、必要に応じて即座に助言や介入できます。顧客が不満を感じる前にフォローできるため、顧客満足度を守る重要な仕組みです。新人研修ではモニタリングを通じた即時フィードバックが成長を加速させます。
コールセンター業務に特化した機能
基本機能に加え、コールセンター専用に最適化された機能を活用することで、大量の問い合わせを効率的かつ高品質に処理できます。
・ACD(着信自動分配) 着信をスキルや待ち時間に応じて最適なオペレーターへ自動振り分けします。顧客は最短時間で適切な担当者につながり、一次解決率(FCR)の向上が期待できます。繁忙時でも公平に通話を割り振ることで、オペレーターの負荷を均等化し、離職防止にもつながります。
・IVR(音声ガイダンス分岐) 「1番は商品の注文、2番はサポート」といった音声メニューで顧客を自動誘導します。自己解決できる問い合わせはオペレーターを介さず完結させることができ、結果として対応時間の短縮とコスト削減に貢献します。営業時間外の受付や多言語対応にも柔軟に利用できます。
・CRM連携 顧客管理システムと連動することで、着信と同時に顧客情報や過去の応対履歴を画面に表示できます。オペレーターは名前を呼びかけながら対応でき、パーソナライズされた応対で顧客満足度を高められます。購買履歴やサポート履歴を即参照できる点も大きな利点です。
・スクリプト表示 顧客対応中に会話の流れや案内文をオペレーター画面に自動表示します。経験の浅いスタッフでも均一な応対ができ、ミスや言い回しのばらつきを減らします。キャンペーン告知や新サービス案内など、リアルタイム更新にも対応可能です。
・オペレーター評価 通話内容や顧客アンケートをもとに、応対品質を定量的に評価・記録します。評価結果は人事評価や教育計画に活用でき、成績上位者の対応ノウハウを全体研修に反映させることで、チーム全体のスキル底上げにつながります。
・CTI連携による顧客情報ポップアップ 着信と同時に顧客名、過去の問い合わせ履歴、購入商品などが自動的にポップアップ表示されます。オペレーターは通話開始直後から顧客の状況を把握でき、ヒアリングの時間を短縮しながらスムーズに対応できます。結果としてAHT(平均処理時間)の削減にも効果的です。
これらの機能を総合的に活用することで、コールセンターは単なる電話受付ではなく、顧客体験を向上させる戦略的拠点へと進化します。PBX導入時には、自社の規模・業務内容・将来計画を踏まえ、必要な機能を優先度別に整理して選定することが成功のポイントです。
PBX導入のメリット
PBXを導入することで、以下のような業務改善とコスト最適化が期待できます。
業務効率化
PBXを導入することで、代表番号着信や部署間の転送を自動化し、対応漏れや手戻りを防止します。 ACDやIVRと連携すれば、着信処理が効率化され、待ち時間の短縮につながります。 また、CTI・CRMと連携することで、オペレーターは1画面で顧客情報を参照しながら対応でき、作業の重複を減らせます。
応対品質の平準化
クラウドPBXやCTIに搭載されている、リアルタイムモニタリング機能を活用することで、通話中のオペレーターにスーパーバイザーが直接指導でき、顧客への不適切な対応を防げます。 また、録音やログを活用して通話内容を定期的に評価し、フィードバックや研修に役立てることで、オペレーターの教育を効率化できるほか、トークスクリプトなどを準備することで応対品質の均一化を実現できます。
コストの最適化
クラウドPBXなら初期費用を抑えつつ、拠点の増減や在宅勤務にも柔軟に対応でき、拡張時の追加投資が少なく済みます。また、自社にエンジニアなどの専門家が在籍している場合は、オンプレミス型もコスト最適化に役立つ可能性があります。自社管理のため長期的な安定運用が可能で、通話量の多い大規模センターではランニングコストを抑えられるケースもあるでしょう。このように、PBXを導入することで、コールセンター運営のコストを最適化することができます。
PBXは、基本的な通話管理から高度なコールセンター機能まで幅広くサポートする中核システムです。業務効率化・品質向上・コスト最適化を同時に実現するためには、自社の規模や運用体制、既存システムとの連携を考慮して最適なPBX(クラウド型・オンプレミス型)を選ぶことが重要です。
PBX導入のステップと選定ポイントは?

PBXはコールセンター運営の中枢システムであり、導入には入念な準備と比較検討が欠かせません。ここでは、導入までの具体的なステップと、成功させるための選定ポイントを詳しく解説します。
1. 現状業務の棚卸しと要件整理
まずは自社の電話業務を正確に把握し、導入要件を明確にします。応対件数・通話数・オペレーター人数・拠点数など、現在の運営状況を数値で洗い出します。
CTIやCRMとの連携が必要かどうか、在宅勤務や拠点間接続への対応が必要かを整理し、システム要件として明文化します。
この段階での棚卸しが不十分だと、後の機能選定や費用見積もりが曖昧になり、導入後の使い勝手に影響する可能性があります。
2. PBX方式の選定
次に、自社に最適なPBX方式を決定します。 クラウド型は、初期費用を抑えつつ拠点や在宅勤務に柔軟対応でき、アップデートも自動化されます。
オンプレミス型は、自社設備で運用するためカスタマイズ性が高く、長期運用での安定性に優れます。ハイブリッド型は、オンプレミスを活かしつつ一部クラウドを利用する方法で、段階的な移行に向いています。
選定時には、BCP(事業継続計画)対応、セキュリティ要件、将来の拡張性も考慮しましょう。災害時の通話維持や、オペレーター増員への対応力を事前に検討することが重要です。
3. ベンダー選定と相見積もりの取得
クラウド型かオンプレミス型かを決定したら、複数のベンダーを比較検討します。この際にチェックすべきは、搭載されている機能、API連携の可否、既存設備の流用可否などです。
もし可能であれば、トライアル導入を実施し、操作性やネットワークへの影響、通話品質を実際にチェックしましょう。複数のベンダーから相見積もりを取り、機能・コスト・導入スケジュールを比較することで、自社にとって最適な製品を選ぶことができます。
サポート体制についてもチェックする
システム導入後は運用フェーズが長期にわたるため、ベンダーのサポート体制は非常に重要です。
ベンダーの信頼性やカスタマーサポートの品質を確認し、トラブル発生時に迅速に対応できるかを見極めましょう。サポートが不十分だと、操作方法がわからないときや障害発生時に業務が滞り、効率が大きく低下する恐れがあります。
可能であれば、24時間365日サポートを受けられるか、問い合わせへの初動時間や復旧対応の基準も事前に確認しましょう。
PBX選定時によくある疑問と注意点

PBXを導入・リプレースする際は、機能やコストだけでなく運用面での不安や疑問を解消しておくことが重要です。ここでは、特に相談が多い3つのポイントを詳しく解説します。
クラウドPBXは音声品質が不安?
クラウドPBXはインターネット回線を利用するため、「音声が途切れたり遅延したりしないか」と心配される方も少なくありません。しかし最近では、音声品質の高いクラウドPBXモデルが多数登場しており、従来の固定電話とほぼ変わらないクリアな音質を提供できるサービスが増えています。
さらに、ネットワーク帯域の確保やQoS(Quality of Service)設定を適切に行うことで、回線混雑時でも安定した通話品質を維持できます。 選定時には、ベンダーが提供する音声コーデックや回線冗長化オプション、推奨回線速度なども確認すると安心です。
通話録音・ログ保存のセキュリティは?
通話録音やログは顧客の個人情報を含むため、セキュリティ対策が最重要ポイントです。以下のようなセキュリティ機能が搭載されているかどうかをチェックしましょう。
・暗号化保存 録音データをAESなどの強固な暗号化方式で保存する仕組みがあるか確認します。
・アクセス権管理 管理者や特定ユーザーのみが録音データにアクセスできるよう、権限設定機能が備わっているかをチェックします。
・改ざん防止 ログの書き換えや不正削除を防ぐ監査証跡機能やハッシュ化も重要です。
金融や医療など高いコンプライアンスが求められる業界では、これらが正式な要件として求められるケースもあります。
既存の電話機やPBX資産は活かせる?
「現在使っている電話機やPBX設備をそのまま利用できるか」という質問もよく聞かれます。
SIP対応機器(IP電話に対応した規格を持つ機器)であれば、クラウドPBXへの移行後も再利用できる場合があります。 ただし、機器のファームウェアバージョンやプロトコル対応状況によっては追加設定や変換アダプターが必要になることがあります。
移行前には、ベンダーに既存資産の互換性を確認し、再利用可能な機器と買い替えが必要な機器をリスト化しておくと、余計なコストを防げます。
PBX選定時は、音声品質、セキュリティ、既存資産の活用可否といった実務的な不安を事前に解消しておくことが成功の鍵です。クラウドPBXでも適切なネットワーク設計やセキュリティ機能を備えた製品を選べば、品質と安全性を両立できます。既存設備の再利用も検討しながら、自社の要件に最適なPBXを選定しましょう。
まとめ
コールセンターの運営を効率化し、顧客満足度を高めるには、PBXの活用が必要不可欠です。ただし、PBXにはさまざまな種類があり、どのタイプが自社に合っているのかどうかわからないとお悩みの方も多いでしょう。
自社の業務形態によっても必要な機能は異なるほか、解決したい課題や求める成果によっても選ぶべき製品は異なります。「何を選べばよいかわからない……」とお悩みの方は、ぜひ今回ご紹介した内容を参考にしてみてください。
また、PBX導入のコストが割けないといった場合は、アウトソーシング・BPOを活用するのも有効です。コールセンター業務のノウハウを持った業者に電話業務を任せることで、コールセンターを外部に任せることができます。PBXの導入と合わせて、アウトソーシング・BPOの有効活用も検討してみてください。

ProCX編集部
NTTマーケティングアクトProCX