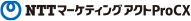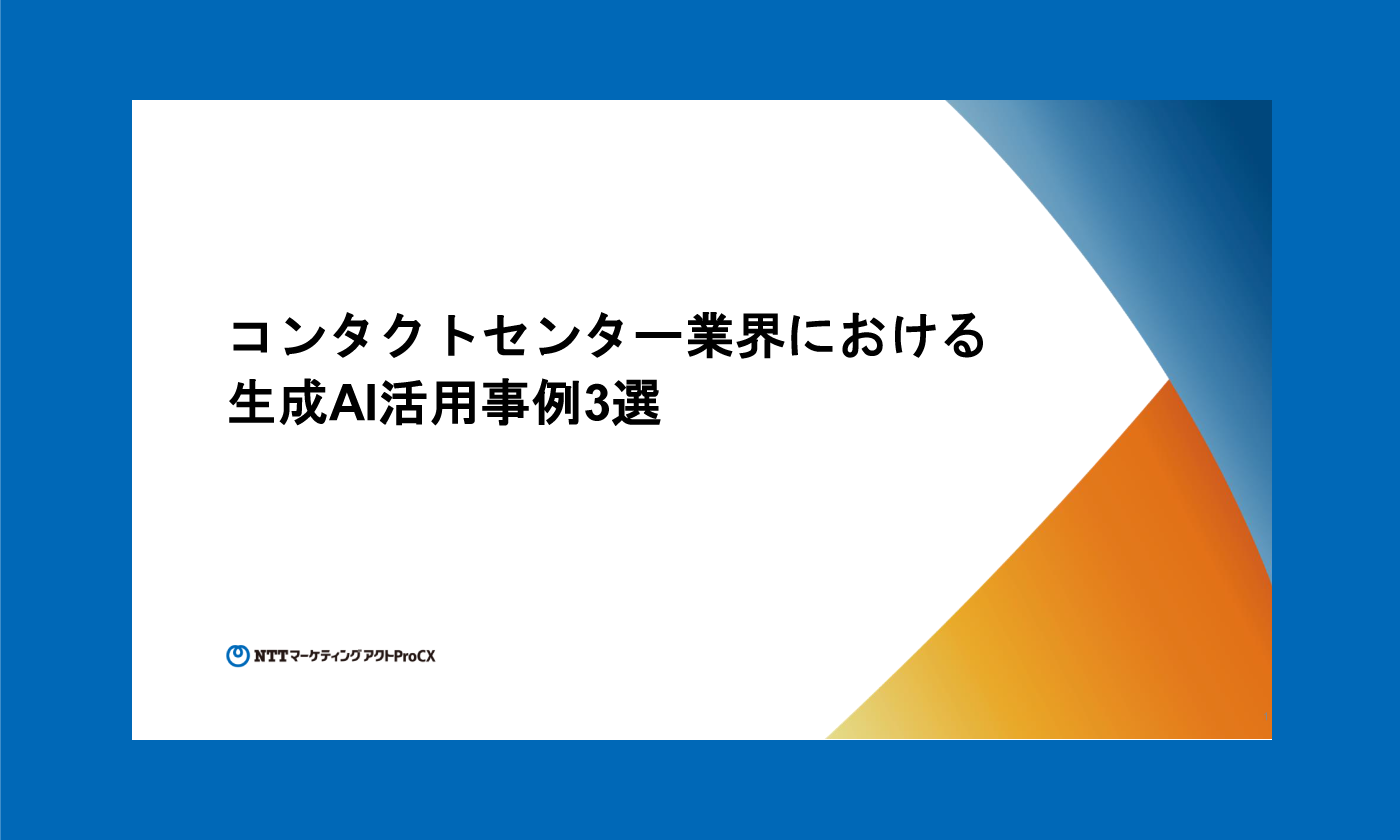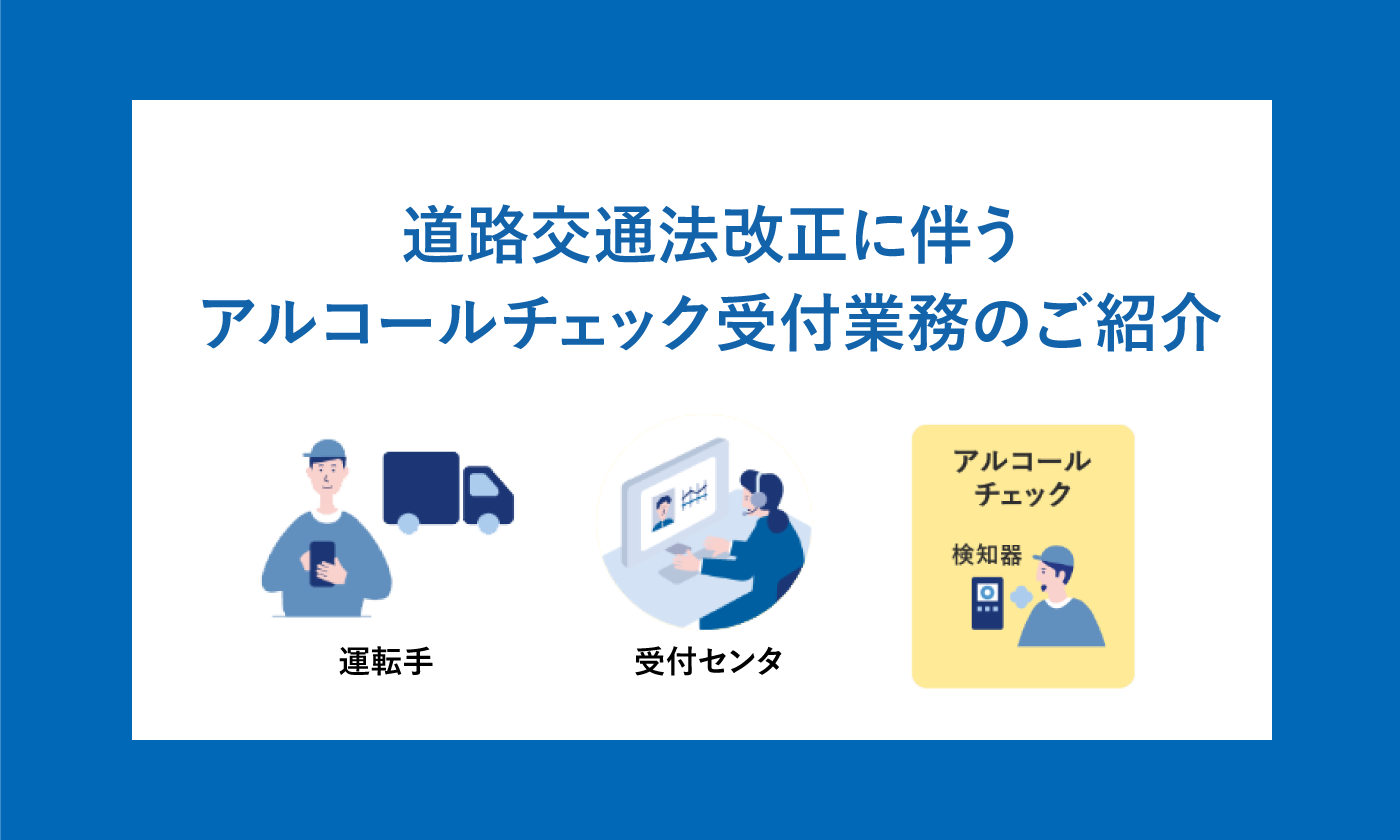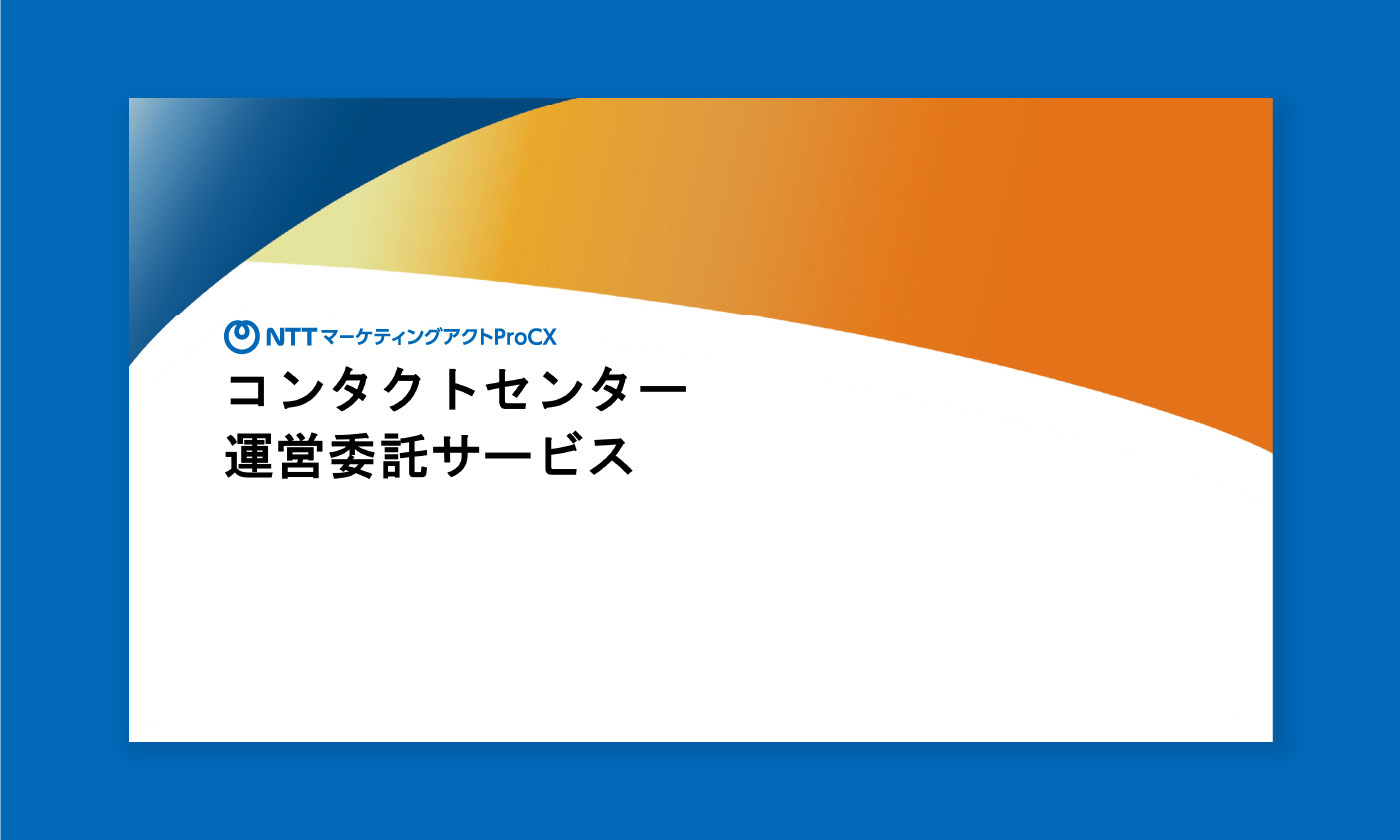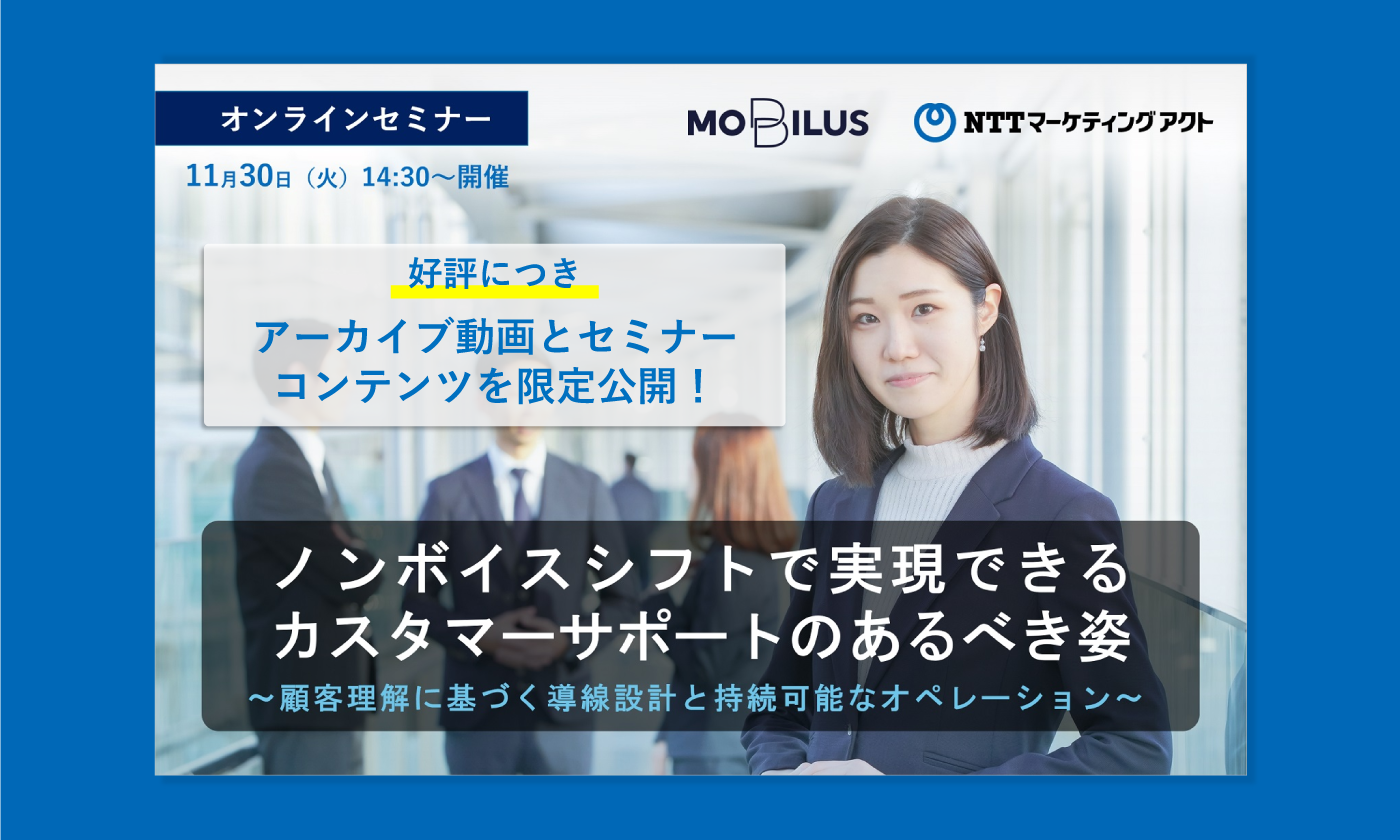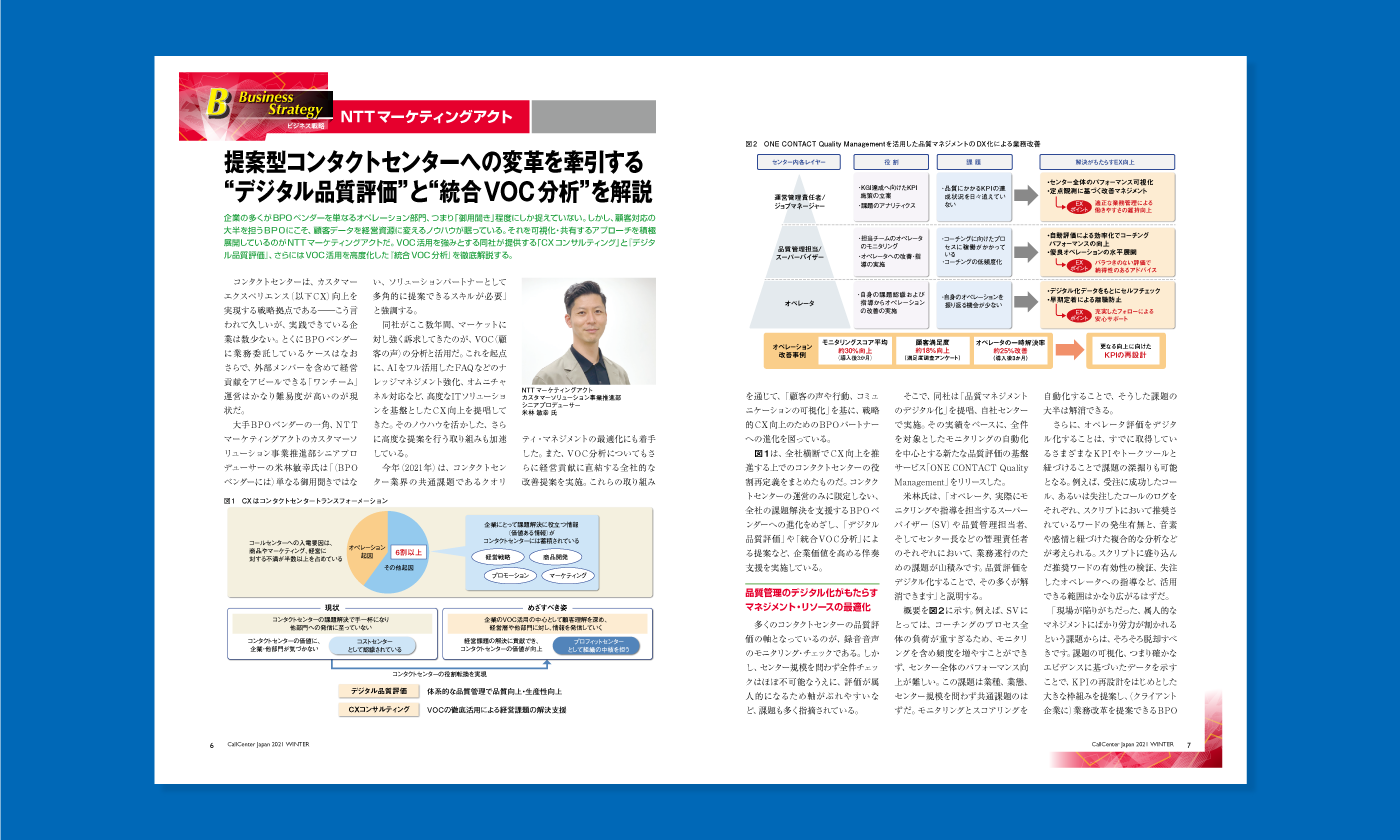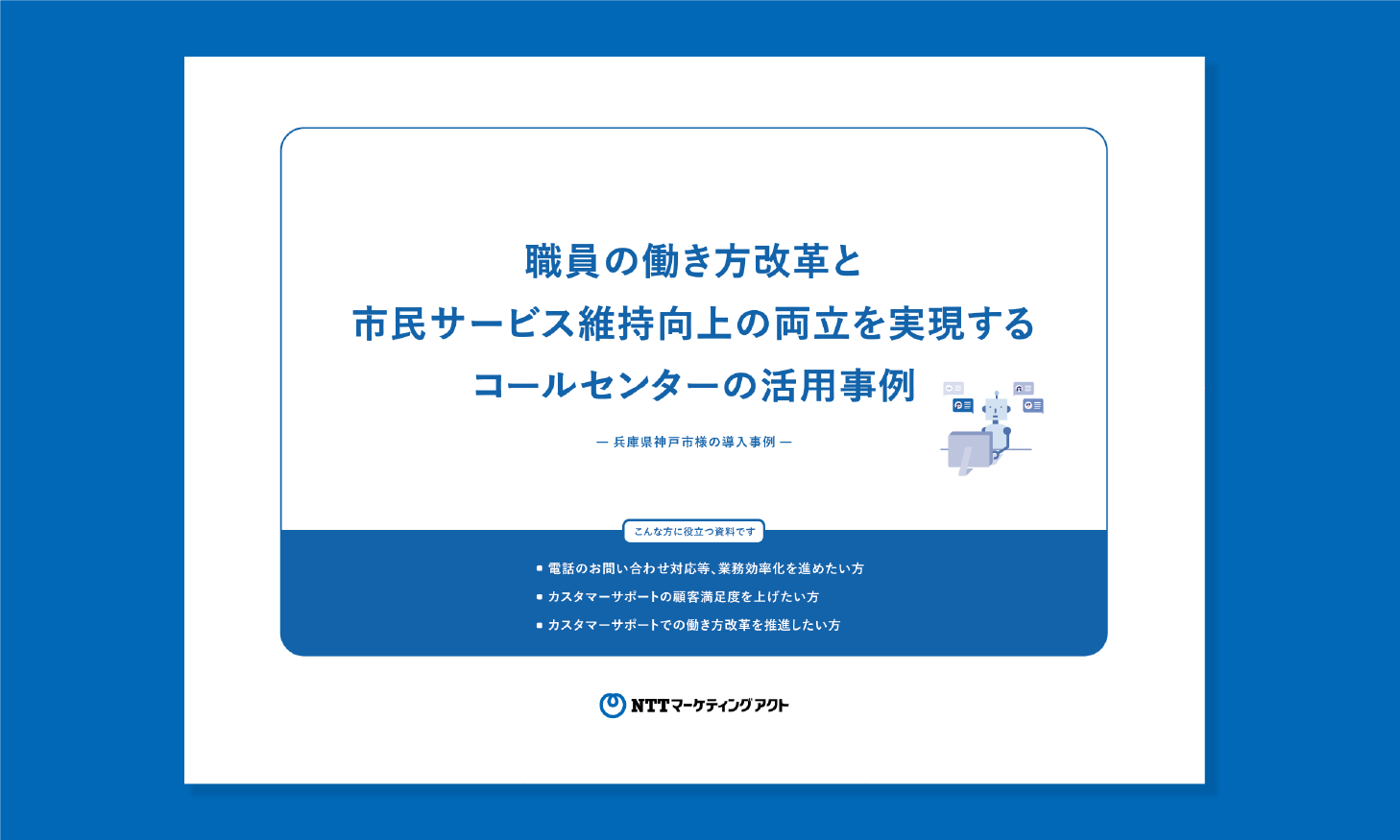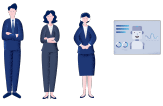コンタクトセンター
コールセンターの通話録音とは? 目的・注意点・活用方法まで徹底解説
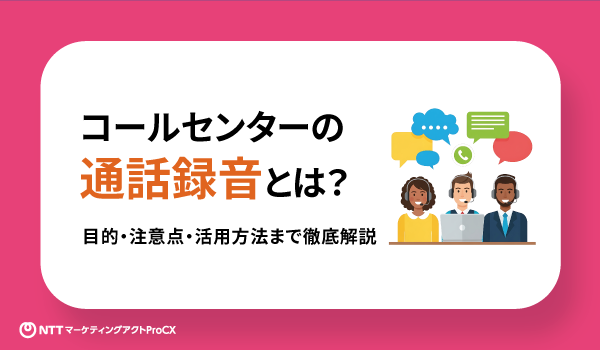
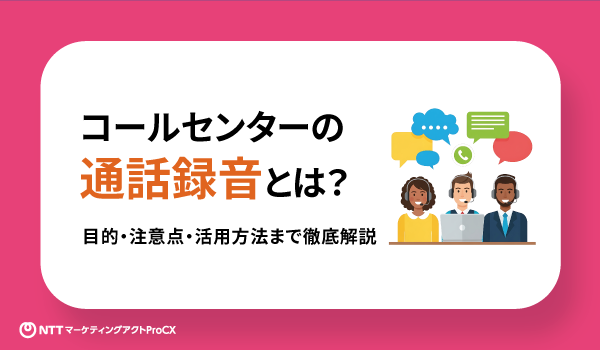

コールセンターで対応する通話内容を録音し、オペレーターへのフィードバックや教育、顧客とのトラブル予防に活かしたいと考えている方も多いでしょう。
そこで今回は、コールセンターで録音を行う目的や注意点のほか、活用方法についてご紹介します。自社のコールセンターで通話録音を行いたいと検討されている方はぜひチェックしてみてください。
コールセンターの通話録音は法的に問題ない?

コールセンターにおける通話録音は、業務効率の向上や顧客対応の品質向上など、さまざまな目的で活用されています。一方で、録音は顧客との通話内容という「個人情報」に該当するケースもあり、取り扱いや運用には一定の法的配慮が求められます。ここでは、録音の目的と法的な留意点について解説します。
コールセンターで通話を録音する目的
コールセンターで通話内容を録音する目的は以下の3点です。
【通話録音の主な目的】 ・顧客との会話内容を記録することで、言った言わないのトラブルや誤解を防ぐ ・実際の応対事例をもとに、良い対応・悪い対応を学ぶ教材として活用する ・応対内容を定期的に確認することで、法令遵守やサービス品質の向上につながる
このような目的で多くのコールセンターでは通話内容を録音しています。
コールセンターの通話録音の法的な問題は?
コールセンターの通話録音の法的な問題の有無について解説します。
通話録音は原則として違法ではないが、事前告知が推奨される
基本的に、業務目的の録音は合法とされるケースがほとんどです。顧客との業務連絡や契約確認の一環として録音する場合、正当な理由があると判断されます。
ただ、トラブルを防ぐためにも、通話の冒頭で録音について明示するとよいでしょう。また、社内ルールとして録音の目的・方法・保存期間などを明文化しておくとよいでしょう。
個人情報保護法を遵守し、録音データの取り扱いには十分注意が必要
注意が必要なのは、録音データの取り扱いです。録音データは個人情報として取り扱われるので、データの保持期間を定め、必要のない情報は速やかに破棄する体制が求められます。
録音データは漏洩リスクの高い情報資産なので、権限管理やシステム面でのセキュリティ対策を徹底しましょう。
顧客から開示を求められた場合、法的義務はないが適切に対応することが望ましい
顧客から録音データの確認を求められるケースに備え、社内体制を整えておくと安心です。
この際、開示によって他の個人情報が漏れないよう、編集処理や確認フローを整えましょう。また、顧客対応フローをあらかじめ決めておけば、対応者によるバラつきを防げます。
法令や業界ガイドラインを常にチェックしておく
業務上の通話録音は基本的に合法とされていますが、通話録音が関連する法律は多岐にわたるため、定期的な法令確認が必要です。
一般社団法人日本コールセンター協会などが出すガイドラインをチェックしましょう。また、法改正や指針の更新に応じて、自社の運用マニュアルも見直しを行うことが重要です。
コールセンターの通話録音をするメリット・デメリット

コールセンターで行われる通話内容を録音することには、メリットだけでなくデメリットもあります。録音の導入を検討する上で、メリット・デメリットを踏まえて、自社に合った導入方法を検討することが大切です。ここでは、コールセンターで通話録音をするメリット・デメリットについてくわしくご紹介します。
録音のメリットは?
録音のメリットとしては以下があります。
クレームや聞き間違いを防ぎ、顧客満足度を維持できる
コールセンターにおいて、通話内容を録音しておくことで、顧客とのやり取りに誤解が生じた場合でも、録音をもとに正確な内容を確認できます。これにより、トラブルの早期解決が可能となり、顧客の信頼を維持することにつながります。また、対応履歴の再確認によって、二重対応や伝達ミスといった業務上のロスも防止できます。
応対の質を可視化し、評価や改善につなげられる
録音された通話内容は、オペレーターの応対スキルを評価する材料としても活用されます。管理者は実際のやり取りをもとに具体的なフィードバックを行えるため、客観的な評価が可能になります。さらに、改善点を明確にできるため、継続的な教育・指導によるスキル向上が期待できます。
過去データの分析により、顧客対応の改善策が見えてくる
蓄積された録音データを分析することで、顧客から寄せられる問い合わせの傾向や、よく使われるトークフレーズなどを把握できます。この情報はマニュアル改善やトークスクリプトの見直し、さらには商品開発やサービス改善のヒントとしても役立ち、業務全体の質を底上げするきっかけになります。
録音のデメリットは?
録音にはデメリットもあります。以下のようなポイントに注意しましょう。
顧客が「録音されている」ことで心理的な抵抗を持つことがある
通話が録音されていることを知った顧客の中には、監視されているような印象を受けて不快感を抱く人もいます。
特にクレーム対応のようなデリケートな場面では、顧客の緊張感が高まり、スムーズな会話の妨げになることもあります。そうした誤解を避けるためにも、録音の目的や使用範囲を事前に明確に伝えておくことが重要です。
データ保存や管理にコストや手間がかかる
録音データを保存するには、サーバーやクラウドストレージの容量確保が必要となり、費用も発生します。また、保存期間の管理や不要データの削除といった運用上の手間も無視できません。
加えて、情報漏洩を防ぐためのセキュリティ対策も不可欠であり、適切なアクセス制限や暗号化などの対策には追加コストがかかる場合もあります。
オペレーターが過度に緊張し、パフォーマンスが下がる可能性も
録音されているという意識が、オペレーターに精神的なプレッシャーを与えてしまうことがあります。とくに新人や慣れていないオペレーターにとっては、緊張から本来のパフォーマンスを発揮できなくなるリスクがあります。
こうした状況を防ぐには、録音の目的や使い方を事前に共有し、納得感を持って業務に臨めるようにすることが大切です。
このように、コールセンターで通話録音を行うにはメリット・デメリットがあります。導入を検討しているタイミングでは、ついついメリットに目が活きがちですが、デメリットや注意点を理解しておかないと、後々のトラブルにつながる可能性も。通話録音の導入を検討する際は、デメリット・注意点を踏まえて、よりよい導入・運用が行えるように意識しましょう。
コールセンターの録音データの活用方法は?

コールセンターでは、日々蓄積される録音データを単なる記録として残すだけでなく、さまざまな業務改善や顧客対応の向上に活用しています。
特に近年では、AIを活用した分析や教育目的での再利用など、その役割はますます広がっています。ここでは、具体的な活用事例を紹介します。
金融機関などでの通話記録の義務対応に活用されている
一部の業界、特に金融業界においては、法令に基づき通話内容の録音が義務付けられているケースがあります。
たとえば、証券会社や保険会社では、商品説明や契約手続きの過程での誤解や不正を防止する目的で、録音の実施と定期的な確認が求められています。録音データは、万一の際に第三者機関による調査や監査にも利用される重要な証拠となります。
クレーム処理時に事実確認として再生し、誤解やトラブルを防止
クレーム対応の現場では、「言った・言わない」といった認識のズレが大きな問題に発展することがあります。そうした場面で、録音された通話内容を再生することで、当時のやり取りを客観的に確認できます。
これにより、事実に基づいた冷静な対応が可能となり、顧客との信頼関係を維持することができます。また、オペレーターの正当性を証明する材料としても活用され、スタッフの保護にもつながります。
顧客対応の改善やCS向上のための音声解析に利用
近年では、AI技術の発展により、録音データを自動で分析し、顧客対応の質を可視化する取り組みも進んでいます。
感情の起伏や会話の流れを解析し、どのようなトークが好印象を与えているか、逆に不満につながっているかといった傾向を把握することができます。
また、頻出するキーワードやフレーズを分析することで、トークスクリプトの見直しやマニュアルの改善にもつながります。これらの活用により、継続的なCS(顧客満足)向上を目指す企業が増えています。
コールセンターの録音機能の選び方

コールセンターに録音機能を導入する際は、業務内容や運用環境、セキュリティ要件に応じて最適なタイプや機能を選ぶことが重要です。
録音システムにはいくつかの種類があり、それぞれに特長や向き不向きがあります。以下に代表的な選定ポイントを解説します。
クラウド型/オンプレミス型/後付け録音デバイスなどの種類がある
録音システムを搭載したCTI(Computer Telephony Integration)は、大きく分けてクラウド型、オンプレミス型、後付けの録音デバイスの3タイプがあります。
クラウド型は、インターネット経由で利用するため初期費用が抑えられ、導入スピードも速いのが特長です。
一方、オンプレミス型は自社サーバーで運用するため、情報管理の自由度が高く、セキュリティ面でも安心感があります。録音の必要が限定的な場合は、後付けの録音機器を使って手軽に対応することも可能です。
CTI連携やCRM連携など他システムとの連携性もチェック
録音機能を選ぶ際は、単体の機能だけでなく、他のシステムとスムーズに連携できるかどうかも重要なポイントです。
たとえば、CTIと連携することで、通話中に顧客情報が画面に表示され、履歴と紐づいた録音データの確認が簡単になります。
また、CRMと連携することで、過去の対応履歴をもとにパーソナライズされた対応がしやすくなります。API対応の有無も含め、将来的な拡張性を考慮して選びましょう。
なお、最近では録音機能が標準搭載されたCTIツールも増えており、CTI導入時に録音機能の有無を確認することも重要です。
必要な録音機能(全通話録音/トリガー録音など)を明確にして選定する
録音機能にはさまざまなタイプがあり、業務に合った機能を明確にしておくことが失敗しない選定のポイントとなります。一般的に多くのコールセンターで利用されているのが「全通話録音」です。
これは、すべての通話を自動で録音する方式で、トラブル時のエビデンス確保や品質管理に適しています。
一方で、「トリガー録音」は、特定の条件を満たしたときのみ録音を開始する機能で、通話の一部だけを記録したい場合に便利です。業務の性質や通話の重要度に応じて、必要な録音方法を見極めましょう。
録音機能の導入を成功させるポイント

コールセンターにおいて録音機能を導入する際には、単にシステムを導入するだけでなく、運用目的や体制、スタッフへの説明など、事前の準備と継続的な活用を意識することが大切です。ここでは、導入をスムーズに進め、効果的に運用するためのポイントを解説します。
録音の目的を明確にし、社内ルールを整備してから運用開始する
録音機能を活用する上でまず重要なのは、「何のために録音するのか」という目的を明確にすることです。
教育や品質管理、トラブル対応、法的証拠の保全など、目的によって運用ルールや保存期間、アクセス権限も変わってきます。
そのため、目的ごとに運用方針を定め、全社員にルールを共有しておくことが必要です。また、導入前にカスタマーサポート部門や情報システム部門など、関係部署と十分に調整を行っておくことで、導入後の混乱を防ぐことができます。
オペレーターにも録音の目的やメリットを説明し、不安を払拭する
録音機能の導入時に見落とされがちなのが、現場オペレーターの心理的負担です。
「録音される=監視されている」と感じてしまうスタッフもいるため、録音の目的があくまで応対品質の向上やトラブル防止、教育支援にあることをしっかりと説明する必要があります。
具体的な活用事例や、録音によって守られる側面(例:クレーム時の証拠保全)も共有し、不安を和らげるとよいでしょう。疑問や懸念に対しては、マネジメント層が丁寧に対応し、納得感を持ってもらうことが大切です。
定期的に録音内容をレビューし、応対改善に役立てる
録音機能を活用する上で重要なのは、録音した内容を「活用」することです。定期的に通話内容をレビューし、応対品質の確認や改善点の洗い出しに役立てましょう。
たとえば、ランダムに録音データをピックアップして管理者がチェックし、良い例・改善が必要な例をチームで共有することで、現場のスキル向上につながります。
また、KPI(例:顧客満足度や対応スピード)と録音レビューの結果を関連づけて分析することで、より具体的な改善施策を打ち出すことができます。
録音機能の導入をはじめ、コールセンターで新しい試みを行う際には、このようなポイントに注意することが大切です。通話録音の導入効果を高めるためにも、これらの3つを意識しましょう。
まとめ
コールセンターの通話録音は、クレーム対応や教育、品質管理などに役立つ重要な機能です。法的には原則問題ないものの、事前告知や個人情報保護への配慮を行い、録音のガイドラインや開示依頼を受けた際のフローを整えましょう。
また録音機能は、クラウド型・オンプレミス型など録音方法は用途に応じて選び、CTIやCRMとの連携も意識する必要があります。最近では、録音機能を搭載したCTIシステムを導入するのが一般的になっているため、録音機能だけでなくCTIの導入も検討してみてください。
なお、最新の録音機能を含めたシステムを保有している会社にアウトソーシングするという方法もあります。自社での導入が難しい場合は、このような方法も検討してみてください。

ProCX編集部
NTTマーケティングアクトProCX