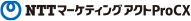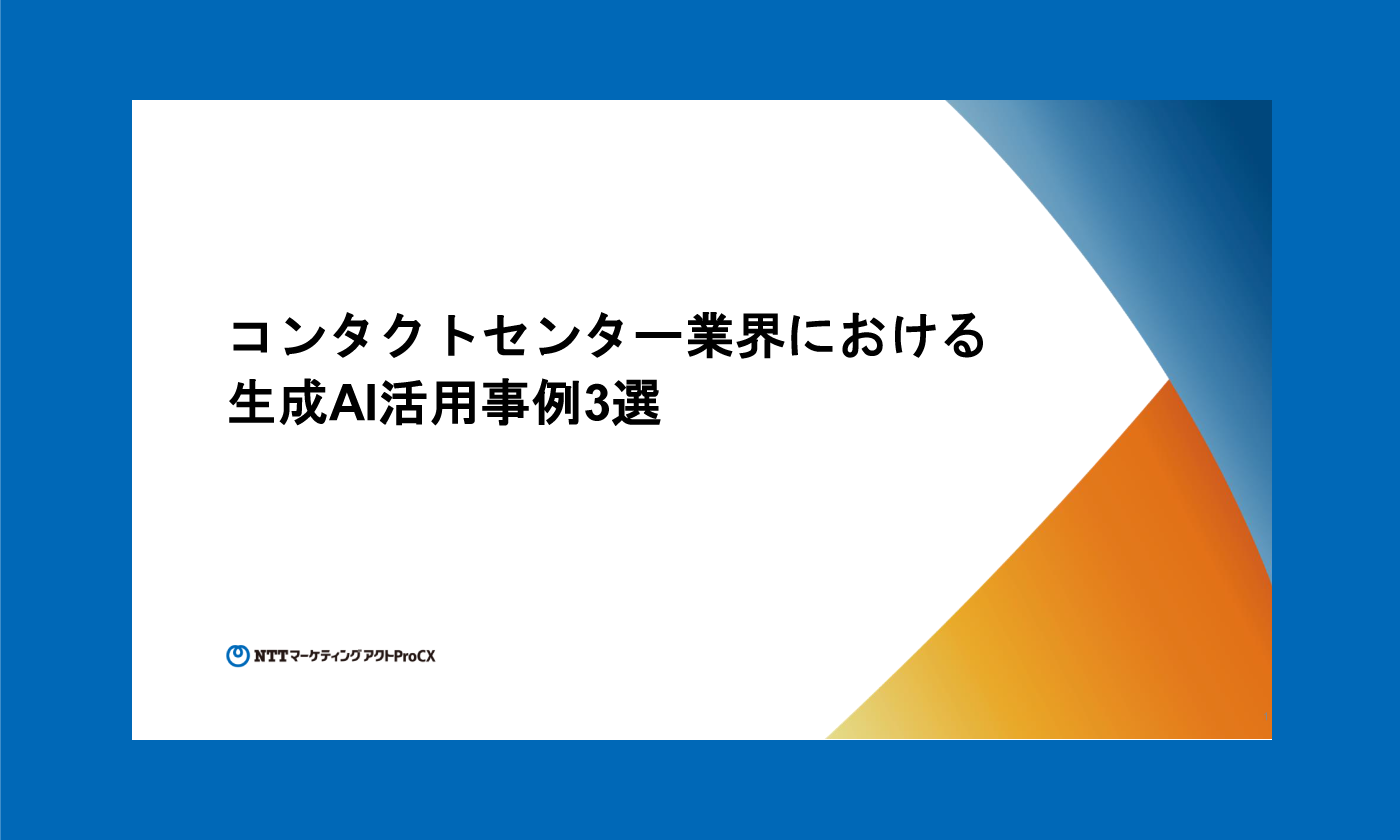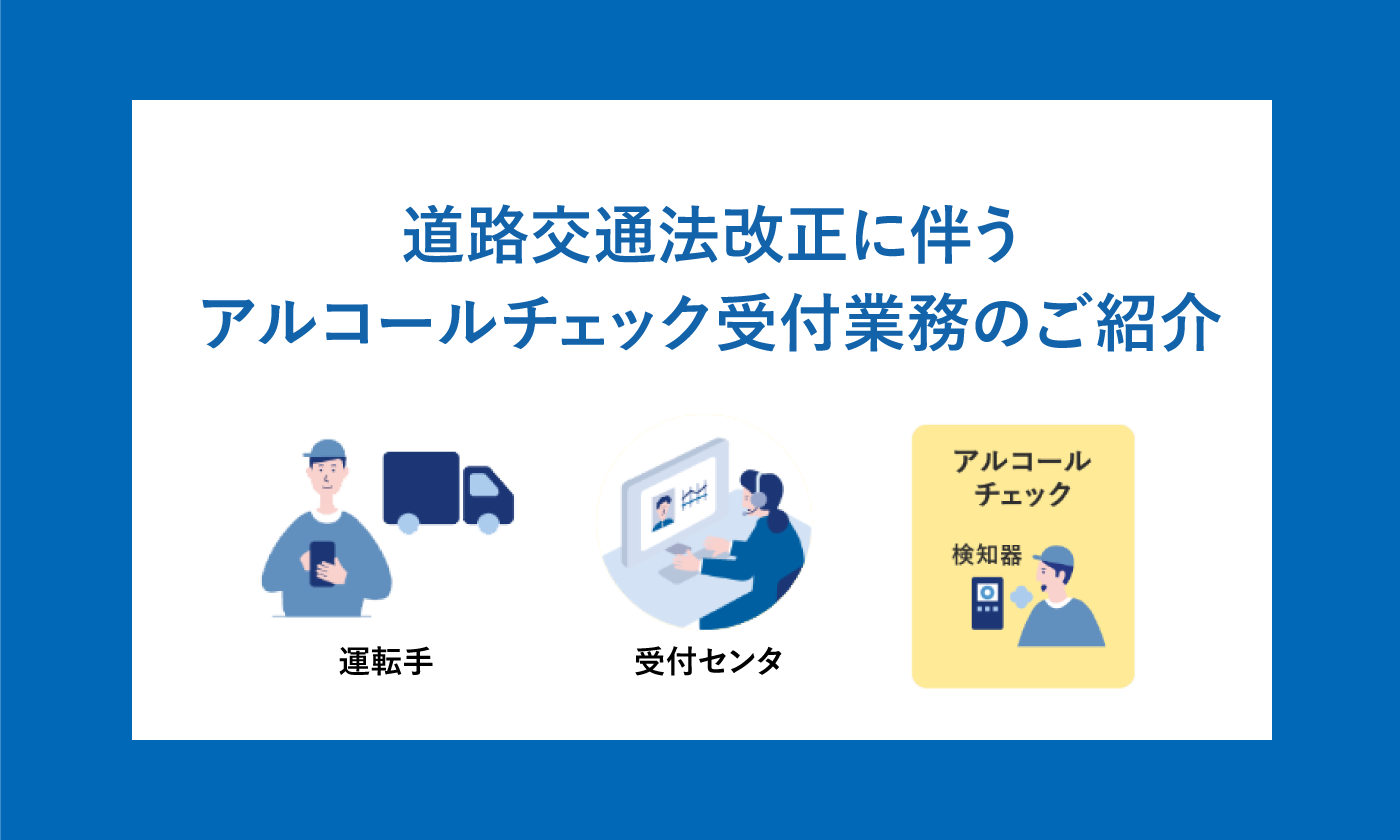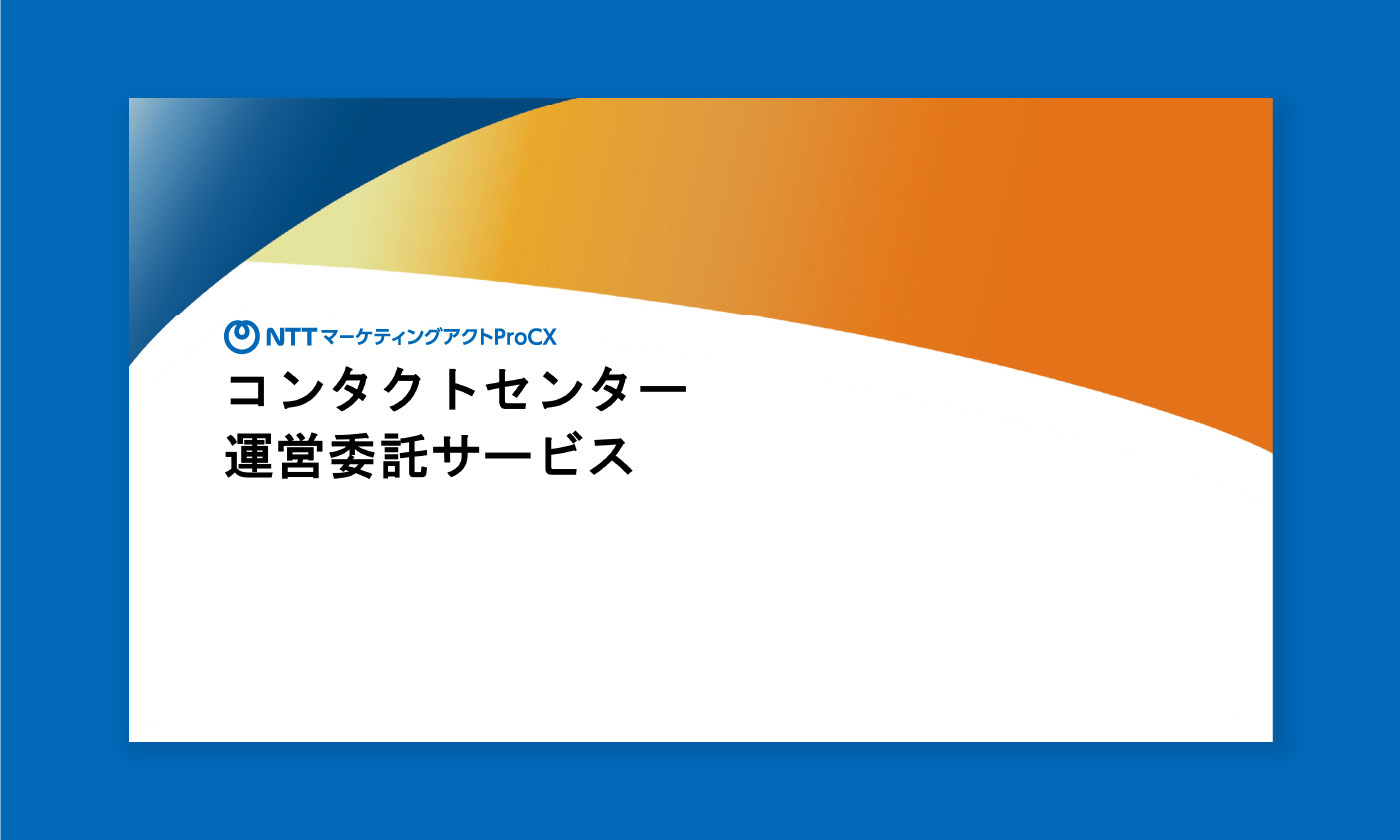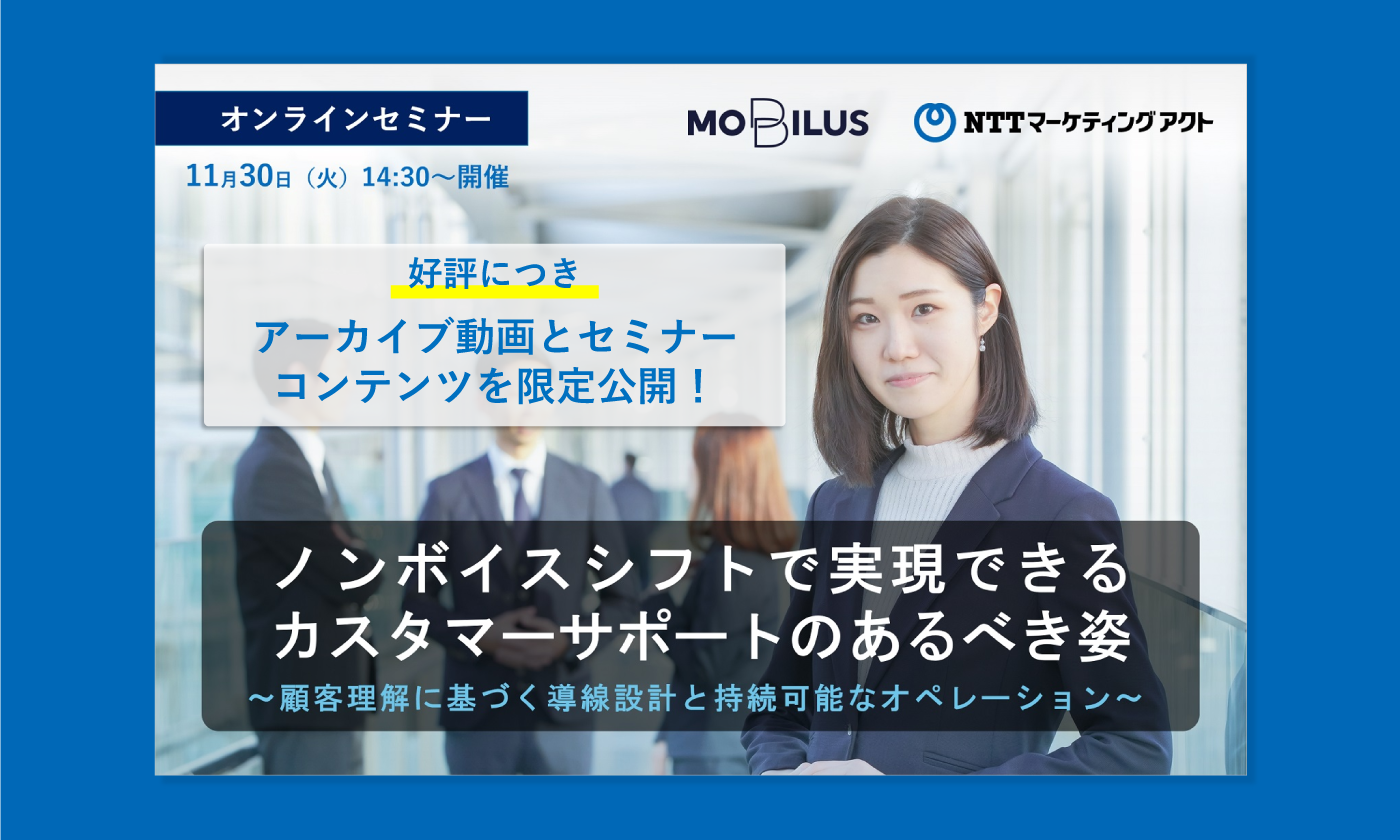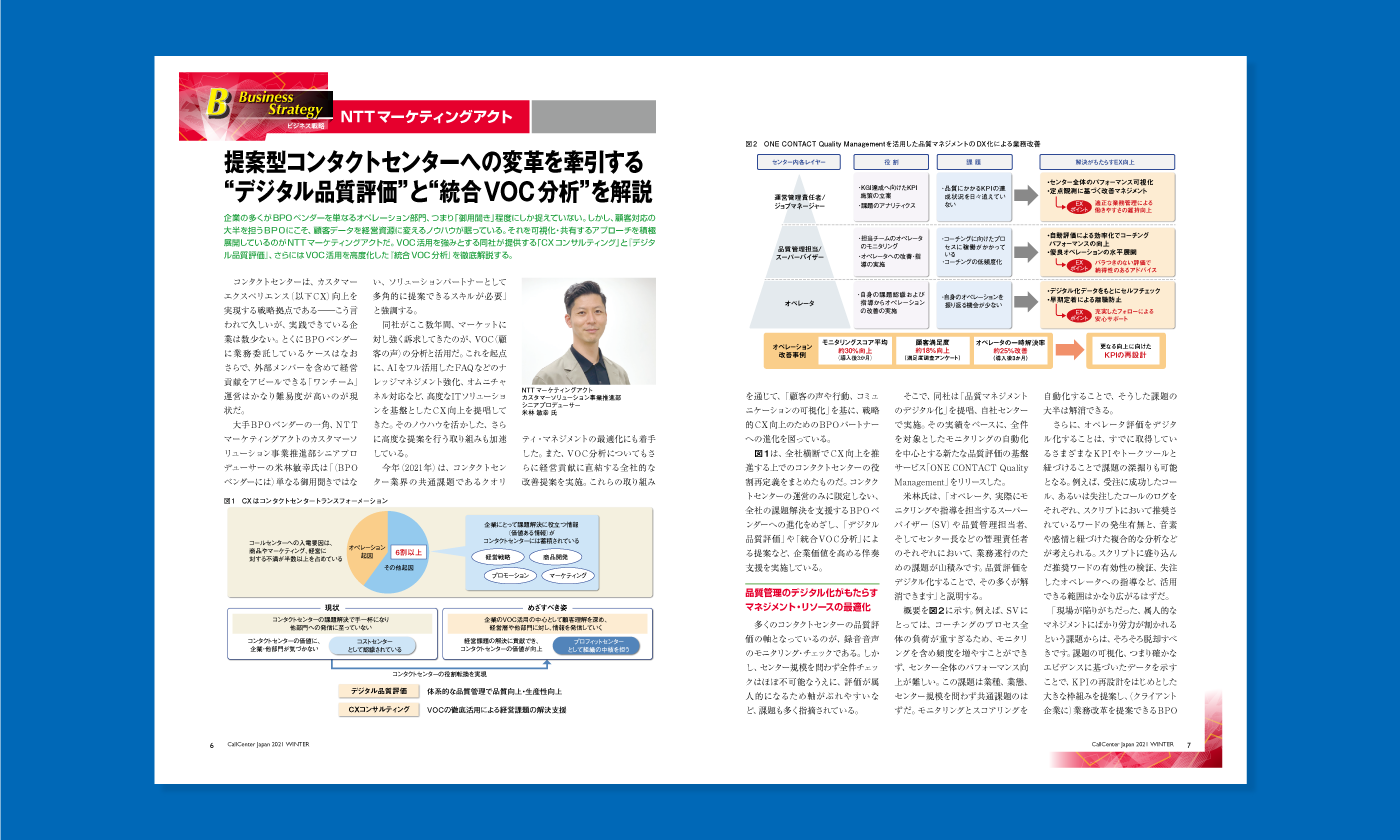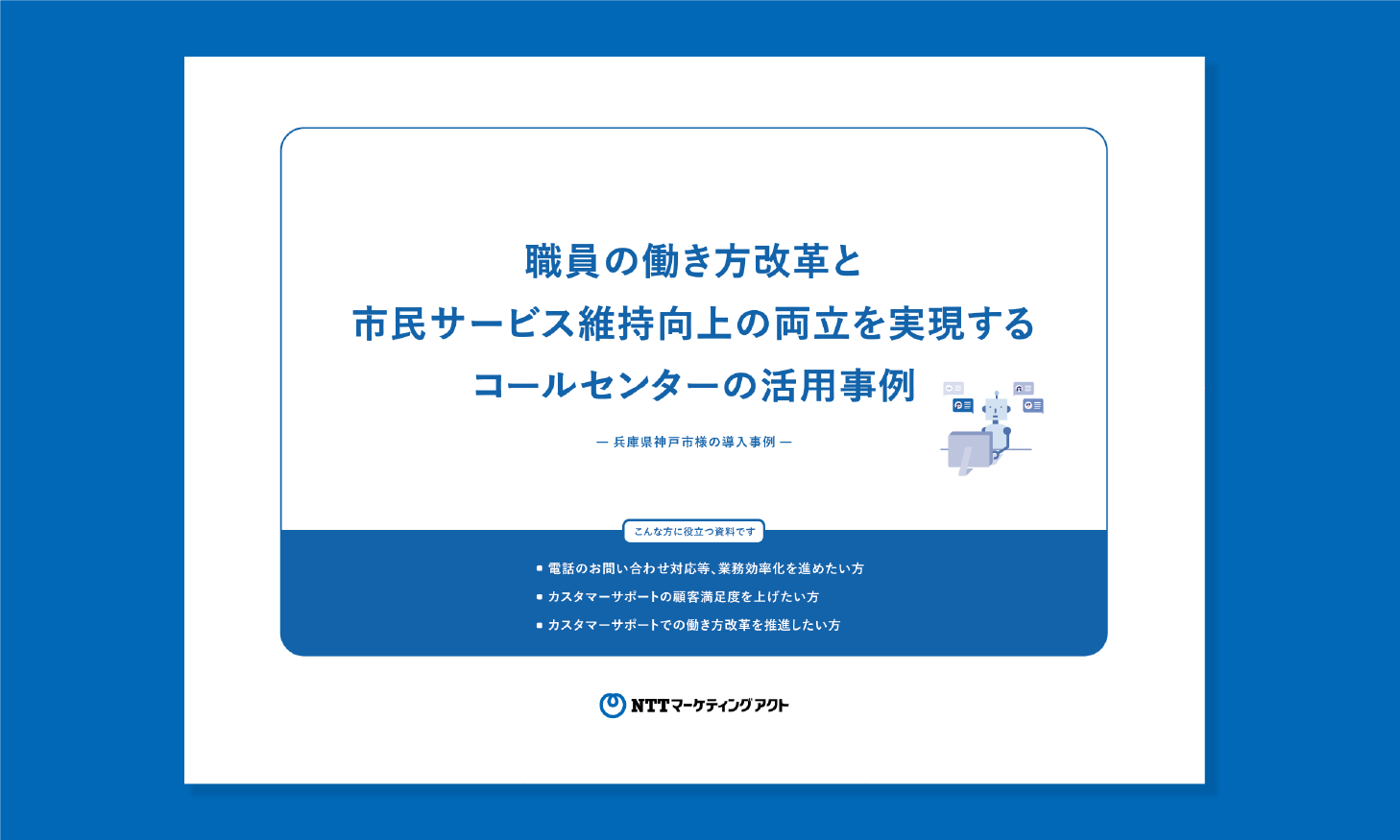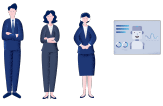コンタクトセンター
テレマーケティングとコールセンターの違いは?使い分けのポイントも解説
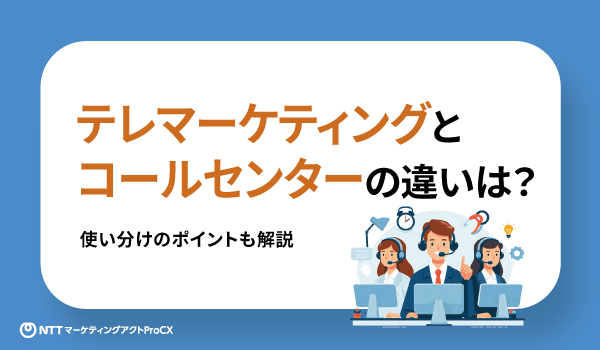
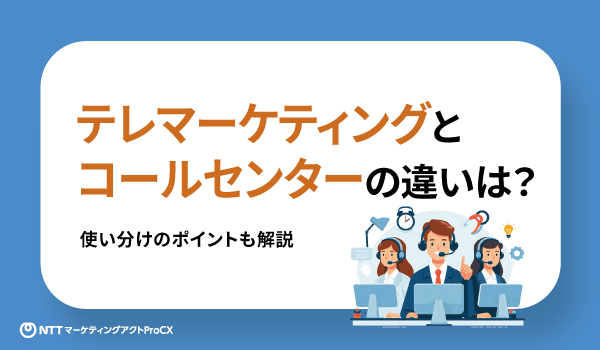

「テレマーケティングとコールセンターの違いや関係性がわからない……」などとお悩みの方もいるかもしれません。そこで今回は、テレマーケティングとコールセンターの違いや、これらの概念を使い分ける際のポイントについてご紹介します。
テレマーケティングとコールセンターの違いは?

電話を使った顧客対応や営業活動にはさまざまな用語がありますが、「テレマーケティング」と「コールセンター」も混同されやすい言葉のひとつです。ここでは、それぞれの意味や特徴、違いについて解説します。
テレマーケティングとは?
テレマーケティングとは、電話を通じて商品やサービスの購入を促したり、顧客との関係を深めたりするマーケティング活動の一種です。
直接的に「この商品は今がお得です」といった案内をするだけでなく、過去に購入した顧客に対して「その後いかがですか?」と近況を尋ねたり、「ご購入ありがとうございました」とお礼を伝えたりと、顧客との継続的な関係づくりも含まれます。
電話をかける側が主導となる「アウトバウンド型」の業務であり、販売促進、見込み顧客の育成、顧客満足度の向上などを目的としています。
コールセンターとは?
コールセンターとは、電話を通じて顧客対応を一括して行う企業の専用窓口や部署を指します。
顧客からの電話を受けて対応する「インバウンド業務」が中心(※アウトバウンド業務を行うコールセンターもある)であり、商品の使い方に関する質問、注文、契約内容の確認、クレーム対応など、顧客のニーズに応えることを目的とした業務を行います。
そのため、コールセンターは業務のことでなく、業務を集中的に行うための部署や拠点を指す言葉と理解するとよいでしょう。
テレマーケティングとコールセンターの違い
両者の主な違いは、「活動内容」なのか「場所・組織」なのかという点にあります。
テレマーケティングは、電話を通じて行う一連のマーケティング活動全般を意味し、営業、顧客対応、アンケート調査など幅広い業務を含みます。
一方のコールセンターは、顧客の問い合わせに対応するための専用の施設や体制を指し、マーケティング活動自体を指す言葉ではありません。
つまり、「テレマーケティング=活動」、「コールセンター=部署・拠点」と理解しておくとよいでしょう。
テレマーケティングとテレアポの違い
テレマーケティングと混同されやすい言葉として「テレアポ」も挙げられますが、テレアポは顧客との商談の約束を電話で取り付けることに特化した営業手法です。
テレアポは、顧客と会う約束(訪問・オンライン面談など)を電話で取得するのが主な目的です。
一方のテレマーケティングは、テレアポも含むより広いマーケティング活動全体を指します。
たとえば、資料送付の案内、アンケート調査、購入後フォロー、顧客満足度のヒアリングなどもすべてテレマーケティングに含まれます。
そのため、テレマーケティングはテレアポよりも広い業務を指す言葉と理解することができるでしょう。
このように、テレマーケティングとコールセンター、そしてテレアポには明確な違いがあります。目的や機能を正しく理解しておくことで、適切な体制づくりや人材配置にもつながります。
テレマーケティングとコールセンターはどんなときに使い分ける?

テレマーケティングとコールセンターは、似た文脈で使われることが多いものの、その性質や役割は異なります。
特に、外部に業務を委託する場合や業務の目的に応じた判断では、適切な使い分けが重要です。以下に具体的な使い分け方をご紹介します。
外部委託を行うときの使い分け
テレマーケティングとコールセンターは、それぞれ「業務内容」と「部署・拠点」という別のジャンルに属する概念です。そのため、外部委託の際には次のような視点で使い分けることが大切です。
テレマーケティングは、マーケティング活動そのものを指すため、委託しても「業務の一部を外注する」という感覚に近く、企業側で企画や戦略を引き続き管理するケースが多く見られます。
一方、コールセンターは企業内の部署・拠点として存在するものなので、これを外部委託するということは、「社内の1部門をまるごとアウトソーシングする」というイメージに近くなります。そのため、委託範囲や責任範囲が大きくなる傾向にあります。
例えば、自社製品に関する問い合わせ対応業務全般を外部に委託したい場合は「コールセンター」が該当しますが、特定の商材に関してアポ獲得や顧客フォロー業務を任せたい場合は「テレマーケティング」という言葉が適しています。
このように、「部門を委託したいのか、業務単位で委託したいのか」という視点で使い分けると判断しやすくなります。
業務の目的別の使い分け
それぞれの業務目的やシーンによって、テレマーケティング・コールセンター・テレアポは使い分けられます。主な活用シーンとしては以下があります。
【テレマーケティングを活用するシーン】
- 新商品やサービスを既存顧客へ紹介したいとき
- 休眠顧客へアプローチして関係を再構築したいとき
- 購入後フォローや満足度調査を行いたいとき
- 顧客のニーズを把握してマーケティングデータを収集したいとき
テレマーケティングは、営業的な意味合いだけでなく、顧客との関係維持や信頼構築などにも活用されます。
【コールセンターを活用するシーン】
- クレームやトラブル対応の受付窓口を設けたいとき
- 資料請求や注文受付を一括して対応したいとき
コールセンターは、顧客からの連絡を受けて対応する業務(インバウンド)に特化しており、企業の信頼性を左右する重要な役割を担います。
【テレアポを活用するシーン】
- 新規顧客への商談機会を獲得したいとき
- 訪問営業やオンライン面談のアポイントを取得したいとき
- 展示会などで集めたリードにアプローチしたいとき
テレアポは、営業活動の入口を作る業務として、主にアウトバウンド型のマーケティングで活躍します。 短期間のキャンペーンなどでも成果を出しやすいため、施策の立ち上げ初期や新規開拓に適しています。
このように、テレマーケティング・コールセンター・テレアポは、それぞれ活用目的や外部委託の考え方が異なります。導入の目的や業務内容に合わせて、最適な形で使い分けることが成果につながる第一歩となります。
テレマーケティングやコールセンターを外部委託するときのポイント

テレマーケティングやコールセンター業務を外部に委託することで、自社の人的・時間的リソースを有効活用できる一方で、委託先の選定を誤ると成果が出なかったり、顧客満足度を損ねてしまったりする可能性もあります。ここでは、外部委託先を選ぶ際に確認しておきたいポイントをご紹介します。
業界に精通している企業か
まず重要なのは、自社の業界や商品・サービスに対する理解度です。
テレマーケティングでは、顧客との会話の中で自然なトークや適切な提案が求められるため、業界知識があるかどうかは大きな差となります。
すでに同業他社での実績や経験がある企業は、業界特有の言い回しや顧客のニーズを把握しており、スムーズな対応が期待できます。
業界特化型の委託先を選ぶことで、短期間で成果を上げやすくなるでしょう。
外部委託の実績
次に確認したいのが、外部委託としての実績や事例の豊富さです。
委託したい業務(例:BtoBのアポ獲得、ECサイトの顧客対応など)と同じような案件でどのような成果を出してきたのか、過去の実績を事前にヒアリングしておきましょう。
特に、自社の目的に近い成功事例がある企業であれば、導入後も期待に沿った運用が可能になります。
オペレーターの質
電話業務は、人が直接対応する業務のため、オペレーターの質が成果に直結します。
どんなに優れたシステムを導入していても、オペレーターのスキルや態度が不適切であれば、顧客満足度や信頼性を損なうリスクもあります。
委託先を選ぶ際には、オペレーターの研修制度やスキル評価体制についても確認しましょう。
特に、コミュニケーション力やヒアリング力、臨機応変な対応力が求められる業務では、経験豊富な人材を多く抱えている業者が安心です。
対応範囲が広い業者を選ぶ
最初からすべての業務を外注するのではなく、段階的に委託範囲を広げたいという企業も少なくありません。そんなときに重要なのが、対応範囲が柔軟な業者を選ぶことです。
- テレマーケティングのみを小規模で依頼し、効果を見ながら徐々に拡大したい
- 将来的にはカスタマーサポートやコールセンター機能まで一括で任せたい
などのニーズに対応できる業者であれば、スモールスタートからのスムーズな移行が可能です。柔軟性とスケーラビリティに優れた業者かどうかを見極めましょう。
これらのポイントをもとに、自社の目的や予算、将来的な展望に合った委託先を選定することが、外部委託の成功のカギとなります。
まとめ
テレマーケティングとコールセンターはどちらも電話業務に関連する用語ですが、その意味や役割は大きく異なります。テレマーケティングはマーケティング活動そのものを指し、コールセンターはその業務を実行するための部署や拠点を指す概念です。
ただ、外部委託を検討する場合には、委託範囲(業務単位か部門単位か)や目的に応じた適切な委託先の選定が重要です。
テレマーケティングやコールセンター業務の外部委託を検討している方は、業界理解や実績、オペレーターの質、対応範囲の柔軟性などを確認し、自社に最適なパートナーを選びましょう。

ProCX編集部
NTTマーケティングアクトProCX