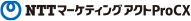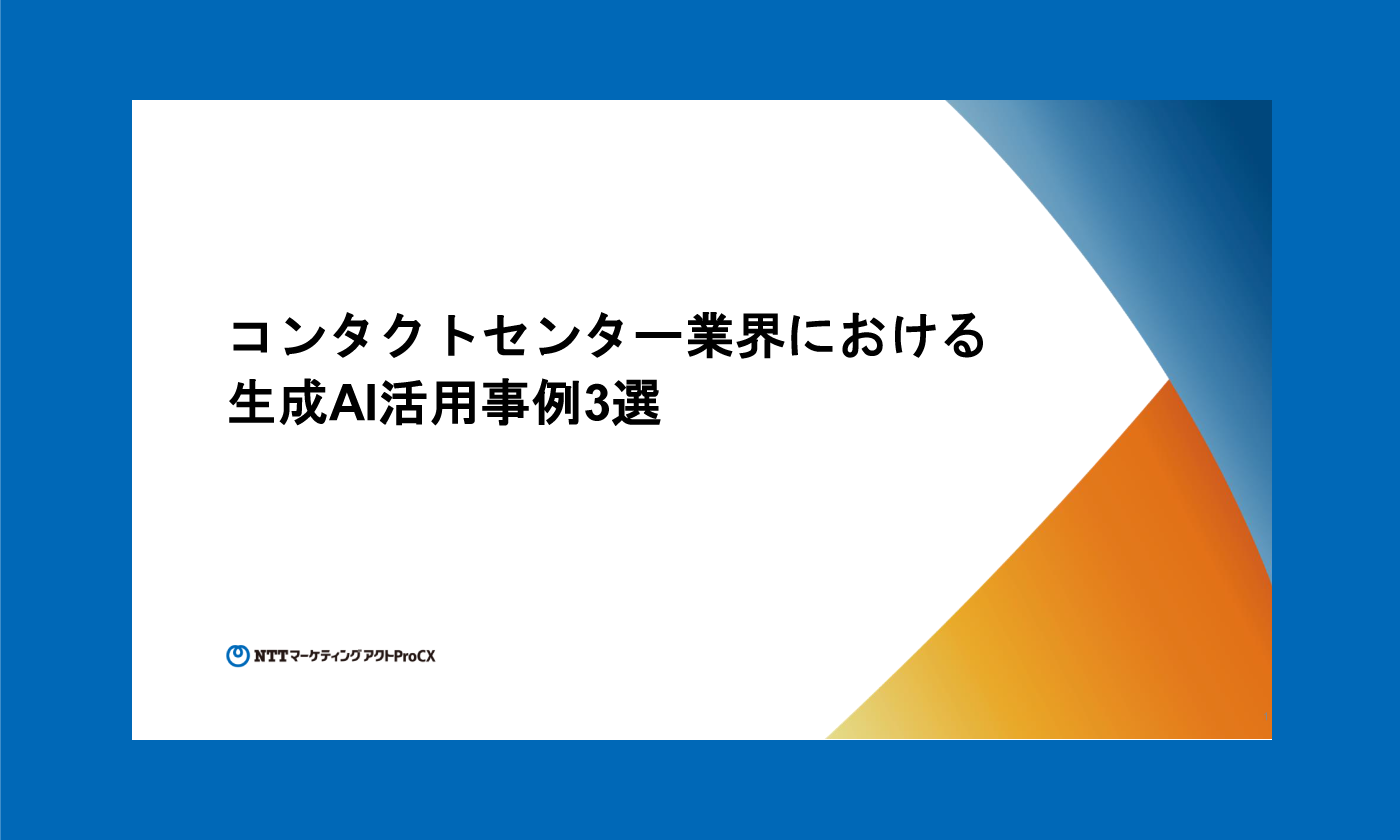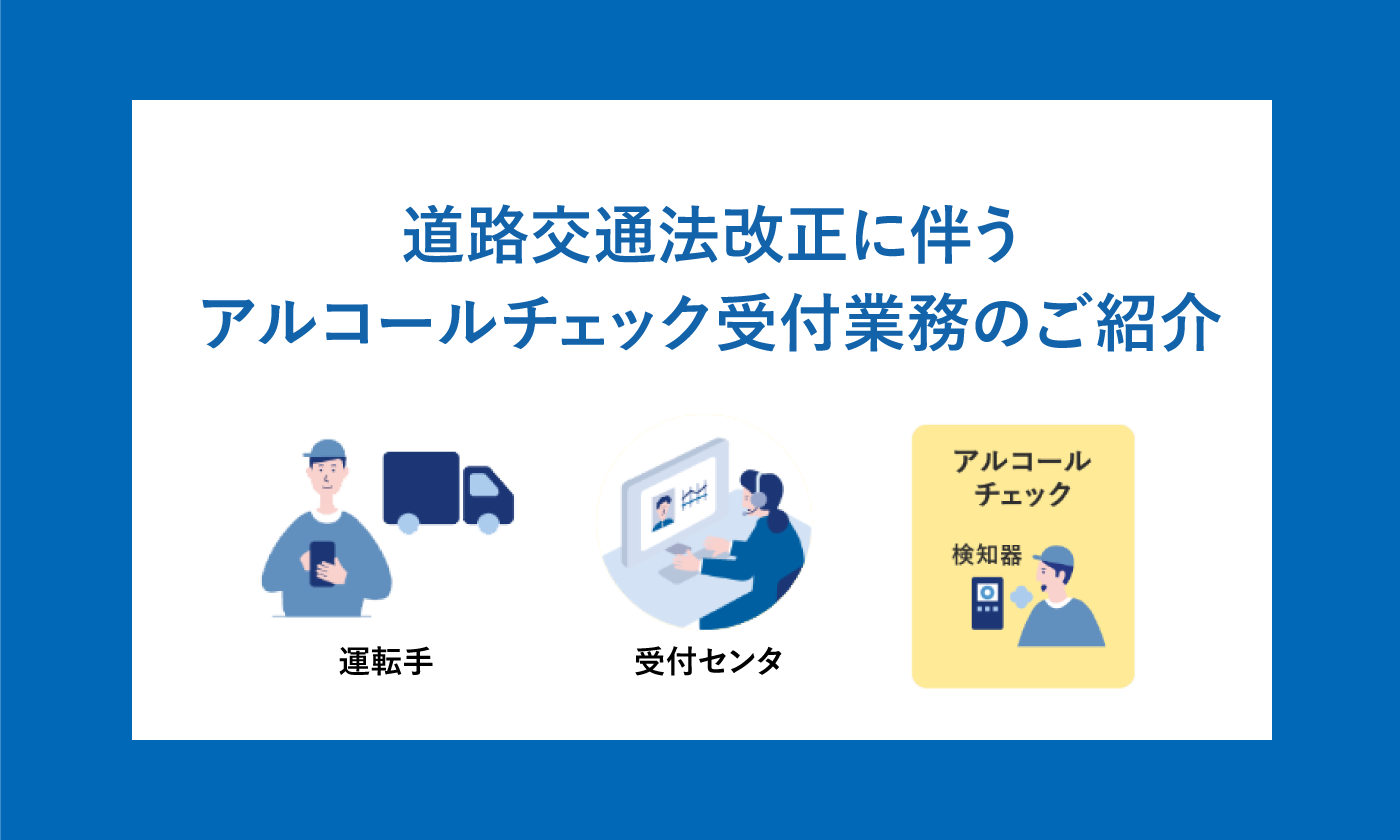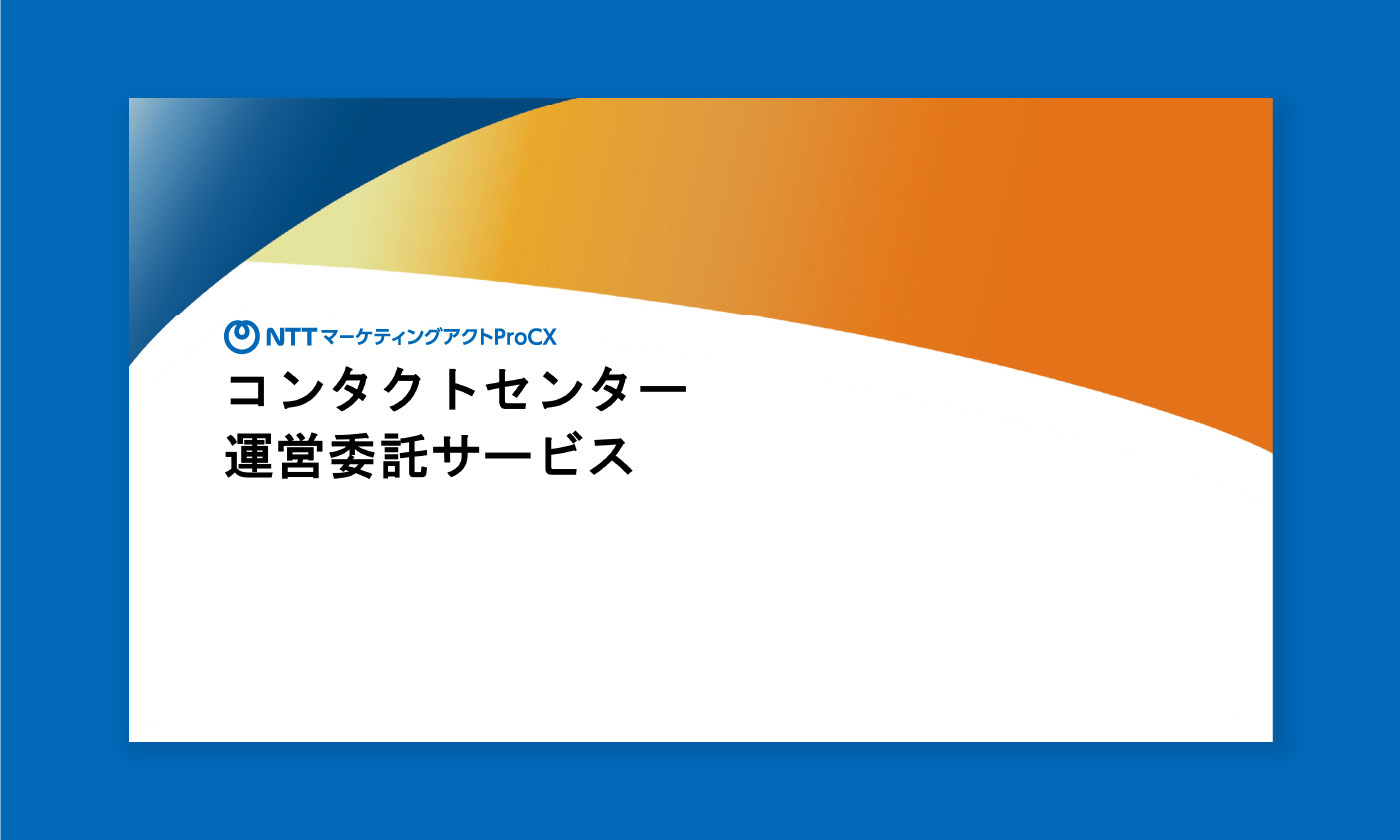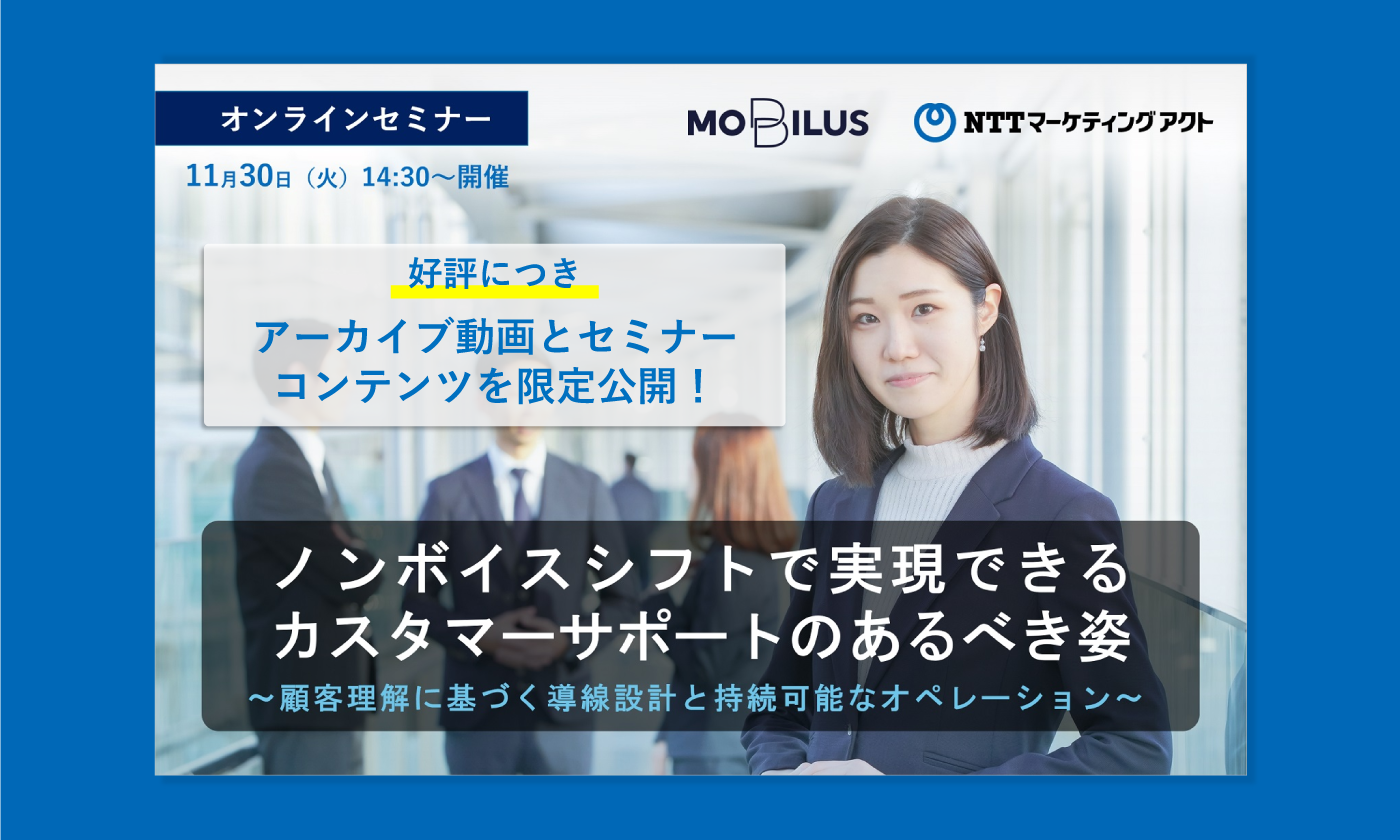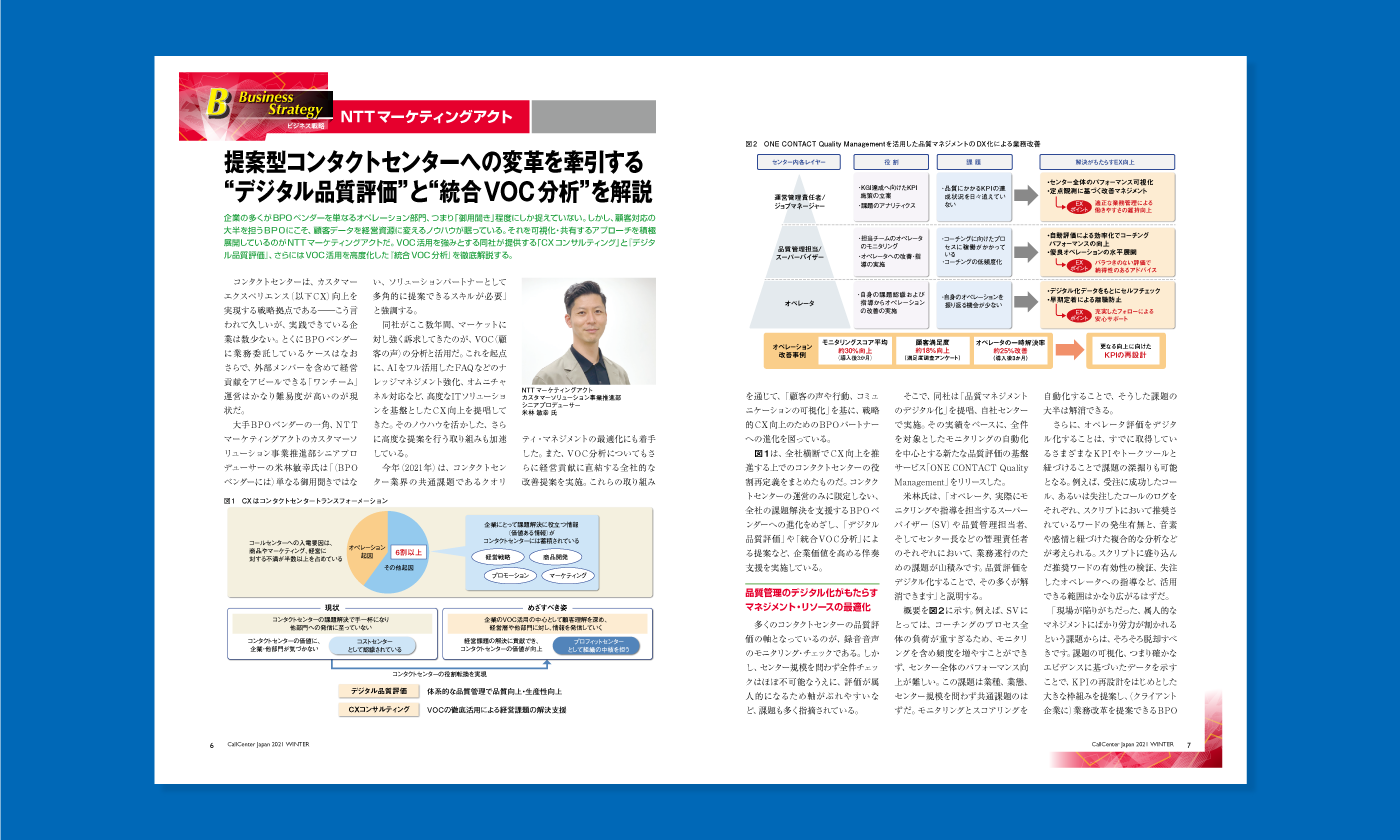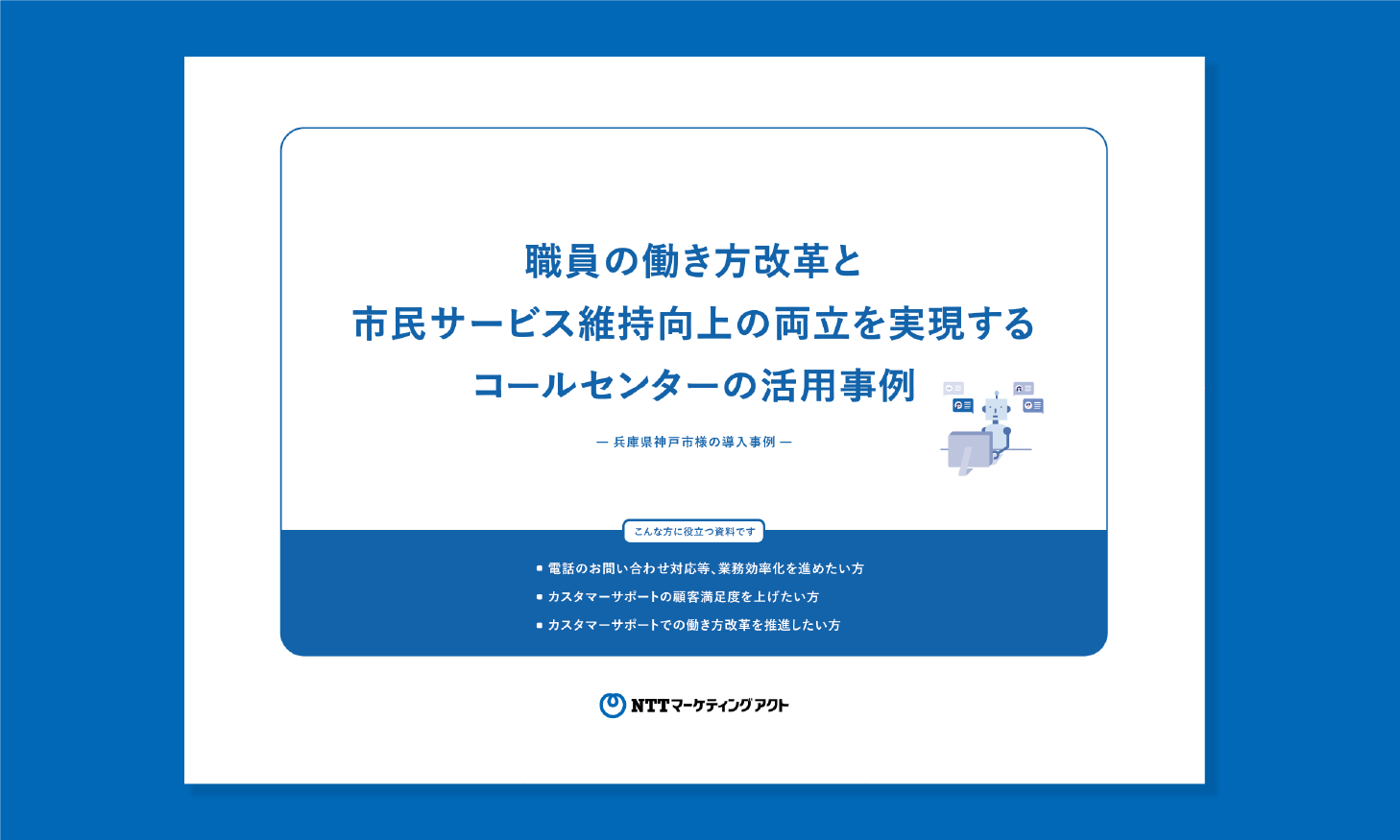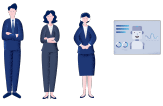コンタクトセンター
コールセンターのCSR・TSRとは?役割・業務内容・違いをわかりやすく解説



コールセンターでは「CSR」や「TSR」といった職種名をよく耳にします。どちらも顧客対応を担う重要なポジションですが、担当する業務の目的や対応範囲には違いがあります。この記事では、まず「CSR」の意味と役割について詳しく解説します。これからコールセンターで働きたい方や、組織のサポート体制を見直したい方は、ぜひ参考にしてください。
CSRとは?言葉の意味と役割

CSRとは?
CSRとは「Customer Service Representative(カスタマーサービス担当者)」の略称で、顧客からの問い合わせに対応する職種を指します。主に電話やメール、チャットなどを通じて、製品やサービスに関する質問やトラブルを解決し、顧客満足度の向上を図る役割です。
日本語では「カスタマーサービス担当者」や「カスタマーサポートスタッフ」と訳され、企業と顧客をつなぐ“第一線”としての役割を果たします。顧客の声を直接受け取る立場であるため、単なる問い合わせ対応にとどまらず、顧客の体験価値(CX)を高める存在でもあります。CSRの応対品質は、企業イメージやリピート率にも直結するため、「コールセンターの顔」といえるでしょう。
CSRの主な役割
CSRの業務は多岐にわたりますが、大きく分けると以下の4つの役割に整理できます。
1. 顧客からの問い合わせ対応
CSRは、電話・メール・チャットなど複数のチャネルを通じて、顧客からの問い合わせや要望に対応します。質問の内容は「商品が動かない」「契約内容を確認したい」など多岐にわたり、スピーディーかつ丁寧な対応が求められます。顧客の立場に立ち、わかりやすく説明するスキルが重要です。
2. 商品・サービスの案内およびトラブル対応
問い合わせに応じて、製品の使い方やサービス内容を案内するほか、トラブルや不具合の際には原因を確認し、解決策を提示します。ときには専門部署との連携も必要になるため、社内コミュニケーション能力も欠かせません。CSRの的確な案内が、顧客の不安解消と信頼醸成につながります。
3. 対応履歴の記録と改善提案
顧客とのやり取りをCRM(顧客管理システム)などに正確に記録することもCSRの重要な仕事です。対応内容をデータ化することで、顧客の傾向や課題を可視化し、商品開発やサービス改善のヒントとして活用できます。こうした情報は企業のナレッジ蓄積にも貢献します。
4. 顧客と企業の「橋渡し役」
CSRは単なる「対応者」ではなく、企業と顧客の関係性をつなぐ存在です。顧客の声を的確に汲み取り、現場にフィードバックすることで、サービスの品質向上やブランド価値の向上をサポートします。顧客からの感謝の言葉が届くことも多く、やりがいを感じやすい職種といえるでしょう。
このようにCSRは、顧客の課題解決を中心に据えた「サポート業務の要」です。次の章では、もう一方の職種である「TSR」について解説し、CSRとの違いを明確にしていきます。
CSRとTSRの違いとは?

TSR(Telephone Sales Representative)は、電話を通じて商品やサービスの提案・販売を行う「電話営業(テレアポ)」担当者を指します。CSRが「顧客対応・サポート(インバウンド中心)」の職種であるのに対し、TSRは「顧客への提案・販売(アウトバウンド中心)」を担う点が大きな違いです。
つまり、CSRは「顧客からの問い合わせに対応する受け身の業務」、TSRは「企業側から顧客にアプローチする攻めの業務」といえます。しかし、両者とも“顧客との接点を通じて企業価値を高める”という目的は共通しており、コールセンターにおける重要な役割を分担しています。以下の表は、CSRとTSRの主な違いをまとめたものです。
| CSR | TSR | |
|---|---|---|
| 主な業務内容 | 顧客からの問い合わせ・サポート対応 | 商品・サービスの提案・販売活動 |
| 対応スタイル | 受動的(インバウンド中心) | 能動的(アウトバウンド中心) |
| 目的 | 顧客満足度・信頼関係の向上 | 売上・契約数の拡大 |
| 主なスキル | 傾聴力・問題解決力・共感力 | 提案力・営業トーク・交渉力 |
| 成果指標 | 顧客満足度(CS)、応対品質 | 架電件数、成約率、売上高 |
| 対象顧客 | 既存顧客・利用者 | 新規顧客・見込み顧客 |
| 評価軸 | 顧客体験(CX)向上 | 売上成果・契約実績 |
コールセンターにおけるCSRの業務内容

CSRの仕事は「顧客の声を受け止め、問題を解決する」ことに軸を置いています。単に問い合わせに対応するだけでなく、顧客の感情や要望を正確に把握し、最適な解決策を提示することが求められます。コールセンターにおけるCSR業務は大きく「インバウンド(受電)」と「アウトバウンド(発信)」の2種類に分けられます。
インバウンド業務(受電対応)
CSRの中心的な業務が、このインバウンド対応です。顧客からの問い合わせや相談、クレーム対応などに対応し、円滑なコミュニケーションを通じて問題を解決します。主な内容は以下の通りです。
- 顧客からの問い合わせ・相談・クレーム対応を行う。
- 商品説明や操作案内、トラブルシューティングなど、顧客が求める情報を的確に提供する。
- FAQやマニュアル、ナレッジベースを活用し、迅速かつ正確に回答する。
- 応対品質を一定に保ち、顧客満足度(CS)を継続的に高める。
この業務では「傾聴力」と「共感力」が特に重視されます。顧客の言葉の裏にある不満や不安を汲み取り、安心感を与えることが、信頼構築の第一歩となります。
アウトバウンド業務(発信対応)
CSRが行うアウトバウンド業務は、販売を目的とするTSR型とは異なり、既存顧客との関係性維持を目的としています。主にフォローアップや調査、改善提案などを通じて顧客満足度を高める活動を行います。
- 既存顧客へのフォローコールや、契約更新・満足度調査などを行う。
- クレーム対応後のフォローアップや、改善提案のための連絡を実施する。
- 顧客が抱える小さな課題を早期に把握し、サポート体制を整える。
- 顧客との継続的な関係性を築き、解約防止やリピート促進につなげる。
このように、CSRは「問題が起こったときに対応する存在」から「顧客との関係を育てる存在」へと進化しつつあります。
企業にとってCSRが重要な理由は?

CSRは、企業の「顔」として顧客と最前線で接する存在です。顧客が企業に抱く印象の多くは、このCSRによる応対品質に左右されます。そのため、CSRは単なるサポート業務にとどまらず、企業ブランドや信頼性を支える重要な役割を担っています。
CSRが重要な理由
CSRが重要な理由としては以下があります。
・企業ブランドを支えるフロントライン
CSRは、顧客と直接やり取りを行う最前線の担当者です。丁寧で迅速な対応ができるCSRがいることで、「信頼できる企業」「対応がしっかりしている」というポジティブな印象を顧客に与え、ブランド価値を高めます。
・応対品質が企業イメージを左右する
顧客にとって、商品やサービスに関する最初の接点がCSRであることも多く、その対応が企業全体の印象を決定づけます。クレーム対応ひとつでも、適切な言葉遣いや対応姿勢によって「誠実な企業」として信頼を得られるケースも少なくありません。
・顧客の声を最も近くで聞く存在
CSRは顧客の意見・不満・要望をリアルタイムで受け取る立場にあり、その情報は商品開発やサービス改善に直結します。現場で得た“生の声”を社内にフィードバックすることで、企業全体の顧客体験(CX)向上に貢献します。
・多チャネル化による役割の拡大
近年は、電話対応に加え、メール・チャット・SNSなど多様なチャネルで顧客が企業と接点を持つようになりました。それに伴い、CSRには「マルチチャネル対応力」や「情報統合管理スキル」などが求められるようになり、役割はますます広範になっています。
CSRがもたらす企業への主な効果
CSRの存在は、企業の顧客基盤を強化し、売上やブランド価値の向上に大きく寄与します。主な効果は以下の通りです。
・顧客満足度(CS)の向上
丁寧で迅速な対応を行うことで、顧客満足度が向上し、ポジティブな口コミや紹介を生み出します。
・顧客ロイヤルティの強化
一度の良質な対応が信頼を生み、長期的な関係維持につながります。リピート購入率や契約継続率の向上にも直結します。
・クレーム発生率の低下
初期対応で顧客の不満を的確に解消できれば、クレームの再発や炎上を防止できます。トラブルの早期解決は、コスト削減にも効果的です。
・リピート購入・解約防止への貢献
顧客が安心してサービスを利用できる環境を作ることで、解約防止や再購入の促進につながります。
・顧客データを活かしたサービス改善
問い合わせ内容や対応履歴のデータを分析することで、製品改善やFAQ更新、対応フローの見直しといった業務改善に役立てられます。
日本とアメリカで異なるCSRの立ち位置

CSRの役割は、国や企業文化によっても捉え方が異なります。特に日本とアメリカでは、CSRに求められる価値観や目的に違いが見られます。
・日本:問い合わせ対応中心の「サポート業務」
日本では、CSRは主に「カスタマーサポート=問い合わせ対応担当」としての位置づけが強く、問題が発生した際の“対応者”という役割が中心です。顧客からの質問に正確に答え、トラブルを未然に防ぐ「守りのサポート」が重視されています。
・アメリカ:顧客成功(Customer Success)の一部
一方でアメリカでは、CSRは単なるサポート担当者ではなく、「Customer Success(顧客成功)」の一翼を担う存在とされています。単に問題を解決するだけでなく、顧客の満足度を継続的に高め、エンゲージメントを強化する「攻めのサポート」が期待されています。
近年の日本企業でも、CSRの役割は「顧客対応のプロ」から「顧客体験(CX)の創出者」へと進化しています。AIチャットやCRM連携ツールを活用し、顧客の課題を先読みして対応するなど、より戦略的な顧客対応が求められています。CSRは今後、「問い合わせを受ける人」から「顧客と共に価値を創る人」へと変化していくでしょう。
まとめ
コールセンターにおけるCSRは、顧客からの問い合わせ対応や問題解決を通じて、企業の信頼を支える重要な存在です。TSRが販売促進を目的とした“攻めの営業”を担うのに対し、CSRは“顧客との信頼構築”を目的とした“守りのサポート”を行います。
顧客対応の質は企業の印象を大きく左右し、満足度やロイヤルティ、リピート率の向上にも直結します。近年では、電話だけでなくチャットやSNSなど多様なチャネルで顧客と接する機会が増え、CSRの役割は「対応者」から「顧客体験(CX)の創出者」へと進化しています。
今後のコールセンター運営では、単なる応対スキルだけでなく、データ活用や顧客理解力を備えた“戦略的CSR”の存在が、企業の競争力を左右する鍵となるでしょう。

ProCX編集部
NTTマーケティングアクトProCX