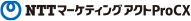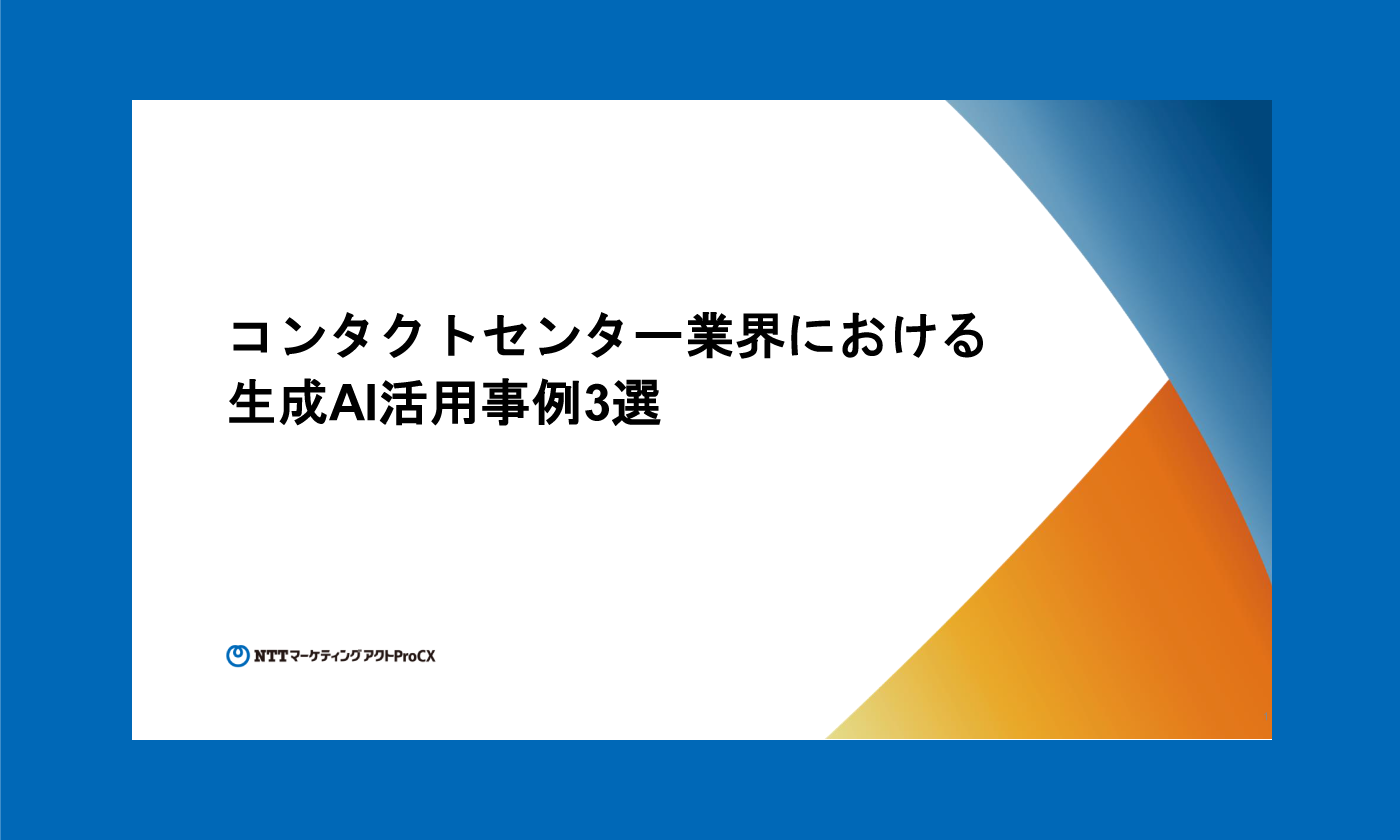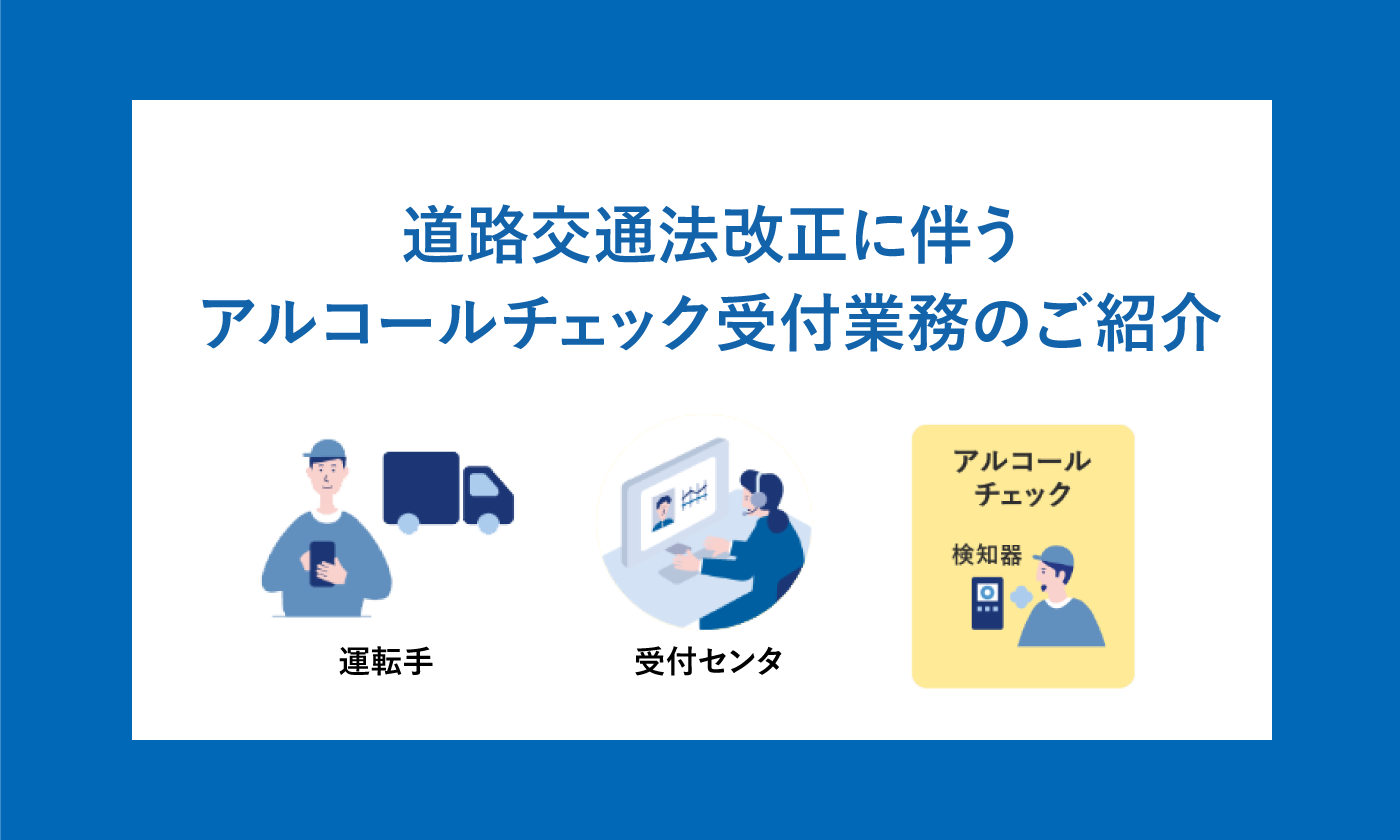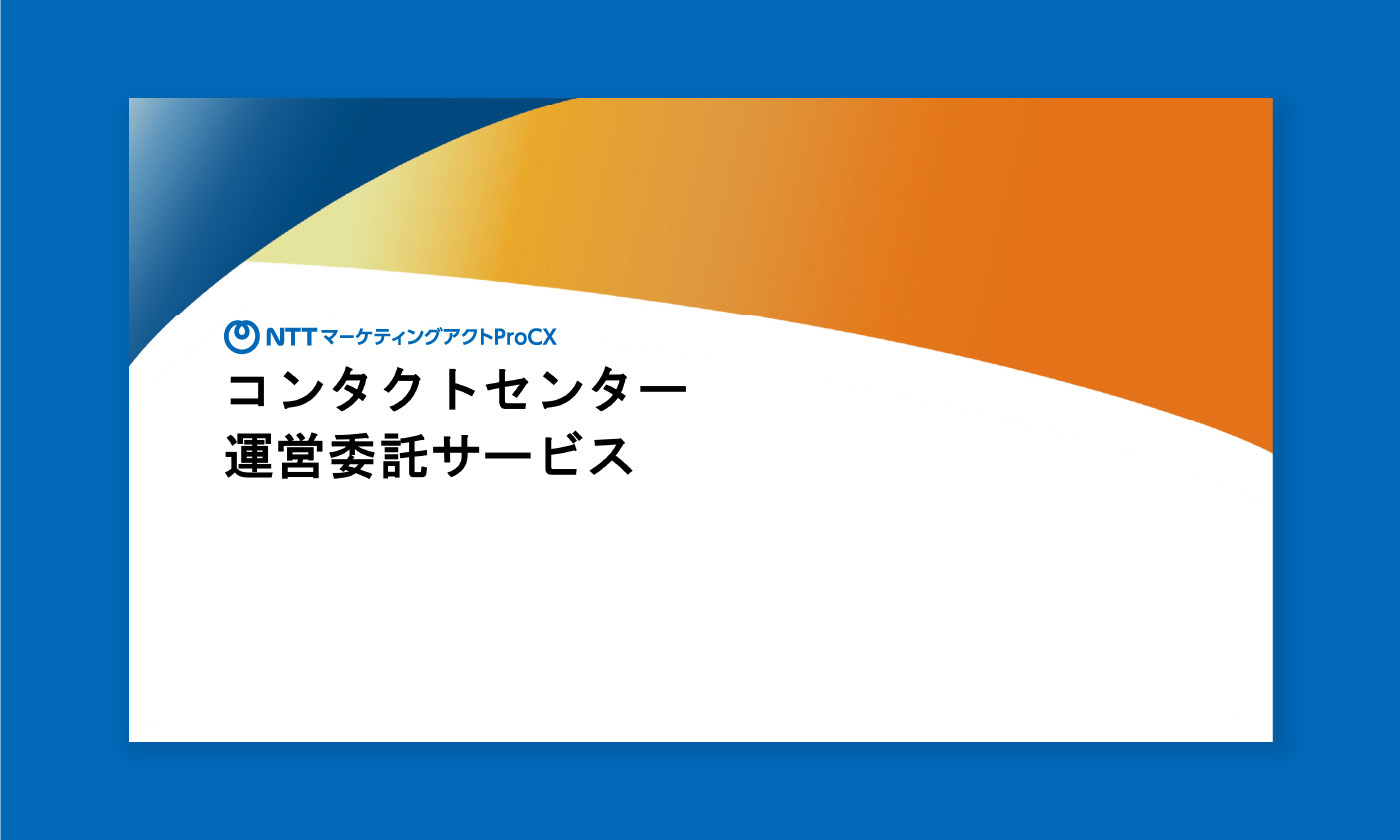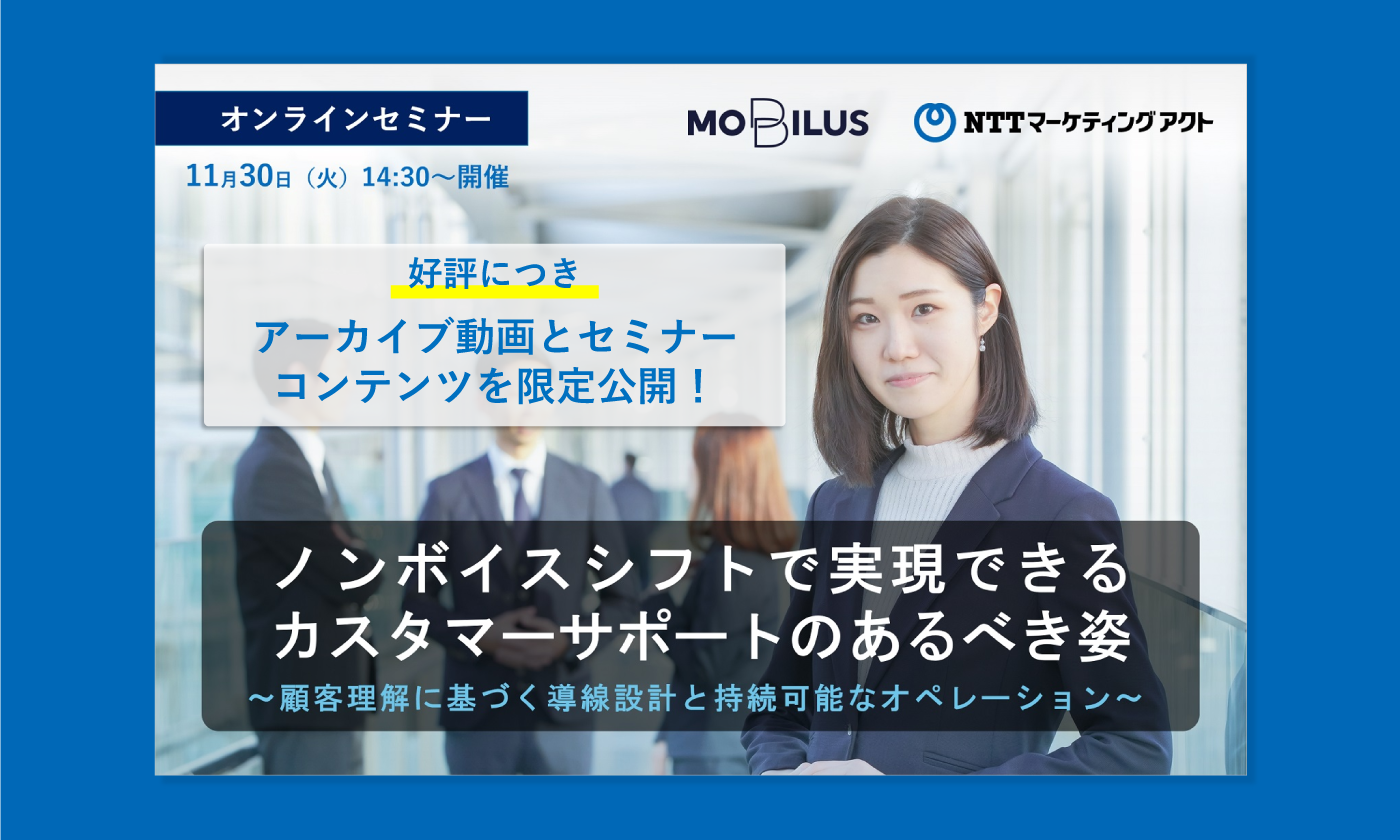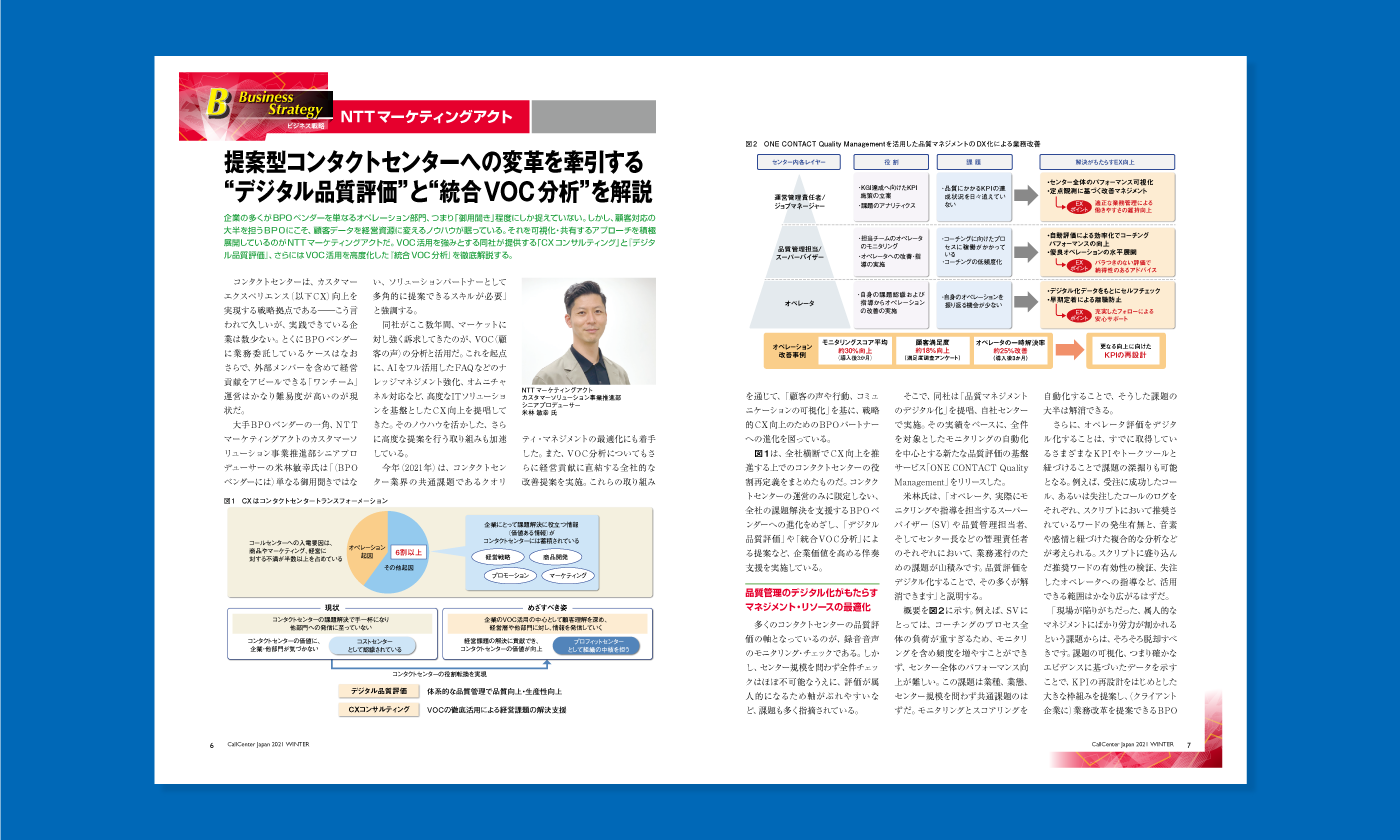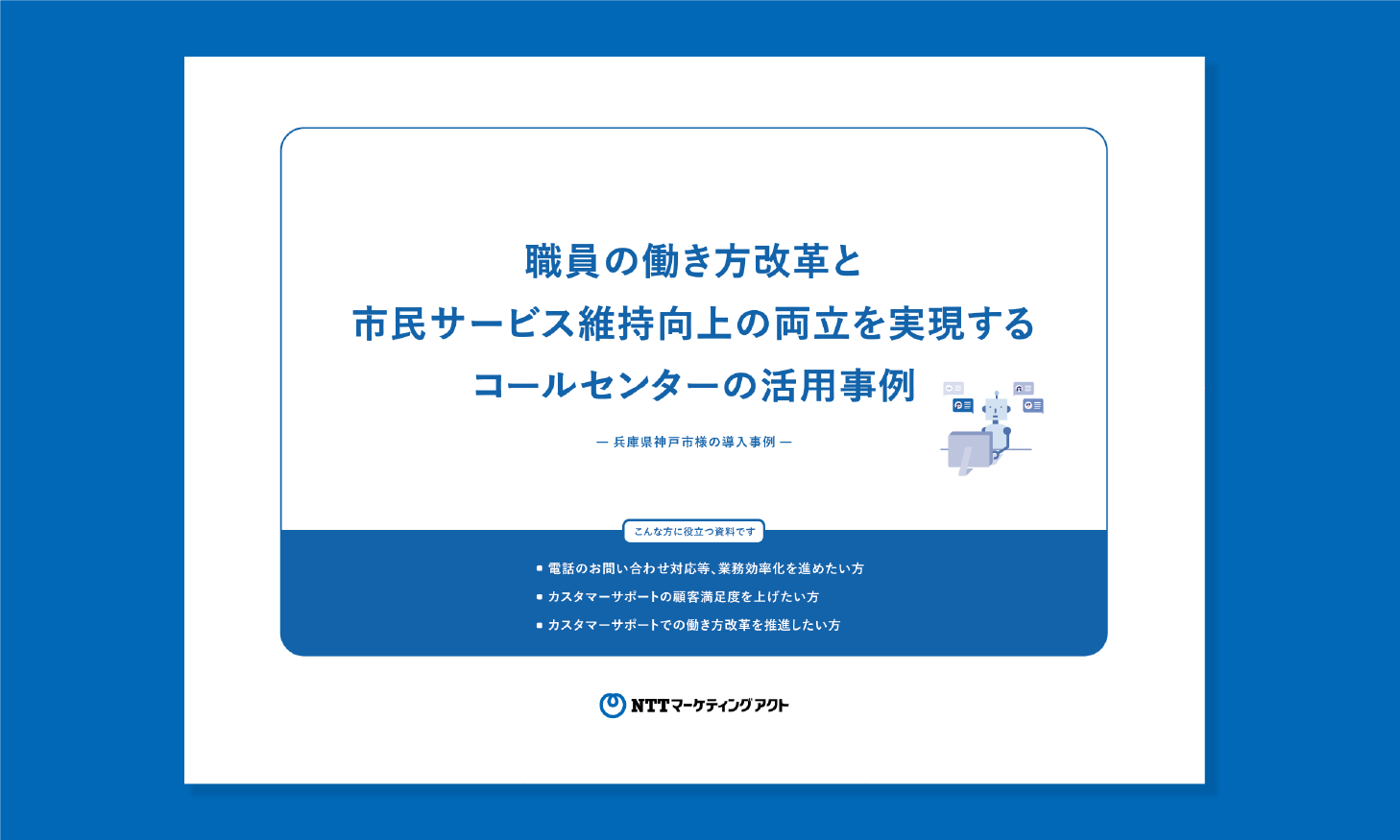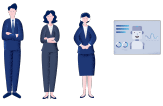コンタクトセンター
コールセンターの業務フロー・コールフローとは?ポイントを解説
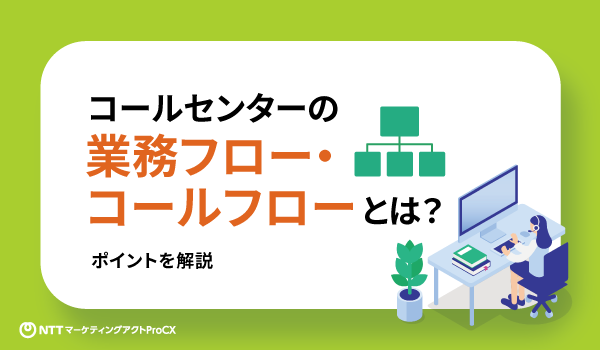
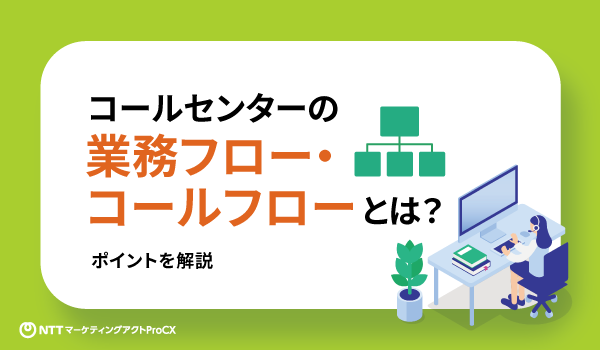

コールセンターの運営においては、「業務フロー」と「コールフロー」を明確に設計することが欠かせません。 業務フローは、オペレーターが行う一連の業務手順を整理したもので、効率的な対応や教育体制の整備に直結します。
一方、コールフローは電話応対における“システム上の流れ”を示すもので、顧客が目的の窓口にスムーズにたどり着けるよう設計されます。
この記事では、コールセンターにおける業務フローの具体例や、コールフローの設計ポイント・注意点をわかりやすく解説します。新人教育や運用改善に役立てたい方はぜひ参考にしてください。
コールセンター業務フローの具体例

コールセンターの業務フローは、「顧客からの入電」から「対応後の後処理」までの一連のプロセスを体系的に示したものです。業務フローを明確にすることで、オペレーター間の対応品質が均一化し、属人化を防ぐ効果もあります。
入電から後処理までの流れ(インバウンド)
一般的なインバウンド業務(受電対応)は、以下のような流れで行われます。
1.顧客からの入電 顧客が問い合わせや要望、トラブル報告のために電話をかけてくる。
2.IVR(自動音声応答)による振り分け 顧客が音声ガイダンスに従って番号を選択し、問い合わせ内容に応じた部署へ自動振り分け。
3.ACDで担当オペレーターへ着信 IVRを経由した着信をACD(着信呼自動分配装置)が最適なオペレーターに自動で接続。
4.オペレーターによる対応・CRMへの記録 顧客の要望や問い合わせ内容をヒアリングし、CRMシステムに対応内容を記録。必要に応じて社内共有や二次対応を実施。
5.フォローアップ・後処理 対応終了後、フォローコールや報告書作成、クレーム対応記録などを行う。対応データを分析し、サービス改善にも活用する。
この流れを標準化することで、センター全体での応対品質の均一化とオペレーション効率の最大化が実現します。
外部システムと連携する業務フロー
コールセンターの業務フローは、CTIやCRMなど外部システムとの連携によって高度化しています。代表的な連携フローは以下の通りです。
【連携フローの例】 ・CTIとCRMを連携し、着信時に顧客情報を自動ポップアップ。過去の対応履歴を参照しながらスムーズに対応できる。 ・FAQシステムやチャットボットと接続し、オペレーターの回答精度を向上。知識共有の効率化にもつながる。 ・対応履歴をもとにレポート作成やVOC(Voice of Customer)分析までを一連の流れで実施し、改善活動に活用する。
このように、業務フローとシステムを統合することで、現場の負担を軽減しつつ、より高品質な顧客対応を実現できます。
新人研修に活用できる業務フロー
業務フローは、新人教育やマニュアル整備にも非常に有効です。入電対応から後処理までの流れを図示し、ケースごとの対応例をまとめることで、教育の効率化と品質維持が図れます。
業務全体の流れを把握することで、対応手順の理解が深まり、ミスの予防にも効果があります。また、実際のコール内容を用いたロールプレイ研修にも応用できます。
コールフローとは?メリット・注意点

コールフローとは、顧客からの電話がどのような経路でオペレーターに到達するかを示す設計図のようなものです。主にIVRやACDなど、電話システム上の制御ルートを定義し、顧客を最適な担当へ導くために用いられます。
コールフローの概要
コールフローとは、顧客対応の流れを「視覚的に」整理したシナリオ図のことです。IVR(自動音声応答)やACDなど、システム連携による電話制御のルートを設計します。適切なコールフローを設計することで、顧客が迷わず目的の担当にたどり着けるようになります。
コールフローに関わる制御システム
コールフロー設計では、複数のシステムが連携して機能します。主な構成要素は以下の通りです。
・CTI 電話とPCを統合する技術・システム。顧客情報の自動ポップアップなどを実現。
・CRM 顧客情報を一元管理し、履歴や属性をもとに対応を最適化する仕組み。
・IVR 顧客が番号を選択し、希望する部署や内容に応じて自動的に振り分ける機能。
・ACD 待機中のオペレーターに着信を自動分配し、応答率を最適化する仕組み。
これらのシステムが連携することで、顧客と企業双方にとって効率的な通話環境が構築されます。
メリット
コールフローを適切に設計することで、以下のようなメリットが得られます。
【コールフロー設計のメリット】 ・顧客がスムーズに目的の担当者へたどり着ける。 ・不要な転送や待ち時間を減らし、オペレーターの負荷を軽減。 ・応対内容が標準化され、業務の効率化・品質向上を両立できる。 ・IVRの自動応答により、営業時間外対応や簡易案内にも対応可能。
注意点
一方で、設計次第では顧客の利便性を損ねるリスクもあります。コールフロー設計時は以下の点に注意が必要です。
【コールフロー設計の注意点】 ・分岐が多すぎると、顧客が迷って離脱する可能性が高まる。 ・音声ガイダンスが長すぎると、顧客体験(CX)の悪化につながる。 ・複数窓口を兼任するオペレーターが混乱しないよう、ルート設計を明確にする。 ・定期的に通話ログや顧客アンケートを分析し、フローを改善していく。
コールフロー設計・作成のステップ

コールフローの設計は、「顧客が迷わず、オペレーターが混乱しない流れを作ること」が基本です。適切に設計されたフローは、顧客満足度(CS)の向上と、コールセンター全体の業務効率化の両立につながります。以下では、コールフローを構築する際の7つのステップを順に解説します。
1. 利用する電話番号と用途を整理
まずは、運用中または新規で使用する電話番号の目的と役割を明確にすることから始めます。窓口の目的が曖昧なままだと、顧客がどの番号に電話をかければよいか迷い、結果として応対負荷が増加します。 番号の用途の「サポート窓口(製品の使い方・トラブル対応)」「クレーム窓口(苦情・改善要望の受付)「キャンペーン窓口(応募・申込み専用ライン)」「法人・個人など顧客属性別の受付番号」など、「誰に」「何を」案内するための番号かを整理することが、全体設計の出発点となります。
2. 窓口設計を行う
続いて、顧客の利便性やオペレーターのスキルに基づいて、窓口の設計を行います。目的は、最短ルートで最適な担当者へ接続することです。
顧客の利便性をふまえて、できるだけ少ないステップで目的の部署に到達できる設計にすること、オペレーターの商品知識や対応スキルに応じて担当範囲を設定することといった点に注意しましょう。
窓口設計を明確にすることで、IVR・ACD設定時のルート設計がスムーズになります。
3. 対応・作業を洗い出す
電話応対に関わる作業をすべて可視化します。ここでは「電話を取ること」だけでなく、周辺業務(入力・報告・引き継ぎなど)も含めてリストアップすることが重要です。電話応対に関わる作業をすべて可視化します。
ここでは「電話を取ること」だけでなく、周辺業務(入力・報告・引き継ぎなど)も含めてリストアップすることが重要です。この工程で抜け漏れなく作業を把握しておくことで、フロー作成後の手戻りを防止できます。
4. 登場人物(担当者・部署)を整理
コールフローには、複数の担当者や部署が関わります。誰がどの段階を担当するのかを明確にすることで、責任の所在が明確になり、連携ミスを防止できます。
オペレーター(一次対応)・SV(品質管理・エスカレーション対応)・他部門(経理・物流・技術サポート・営業など)といったように整理を行いましょう。これにより、エスカレーションルートや対応分担が整理され、オペレーターが迷うことなく対応できる体制が整います。
5. 作業を時系列に並べ、フロー化する
ここまで整理した業務内容を時系列で並べ、流れを可視化します。「顧客接点 → 応対 → 入力 → 確認 → 報告 → 完了」といった流れを整理することで、全体像を誰でも理解しやすくなります。
フロー化により、業務手順の標準化・属人化防止を実現できるほか、研修や業務引き継ぎ用の資料としても活用できます。また、プロセス全体を俯瞰できるため、ボトルネックの発見にも役立つ。
6. コールフロー図を作成する
整理した情報をもとに、実際のコールフロー図(シナリオ図)を作成します。IVRの分岐設定やACDの分配ルール、担当者の対応ステップ、後処理までをひとつの図にまとめましょう。フロー図は、新人教育やシステム設計時の仕様書としても活用できます。
7. 運用しながら改善する
コールフローは、一度作って終わりではありません。実運用データに基づいて継続的に改善することが重要です。現場の声とデータ分析を組み合わせてPDCAサイクルを回すことで、顧客体験(CX)の最適化とセンター運営の効率化を同時に実現できます。
コールフロー設計時のポイントと基本ルール

コールフローは、顧客満足度を左右する重要な設計要素です。IVRやACDの設定によっては、顧客が目的の部署にたどり着けず、ストレスを感じてしまうこともあります。ここでは、顧客視点とオペレーター視点の両面から考慮した設計ポイントと、作成時の基本ルールを紹介します。
コールフロー設計のポイント
コールフロー設計のポイントとしては以下があります。
・階層や選択肢を少なくして、シンプルなルートにする IVRでの選択肢が多すぎると、顧客が混乱して離脱しやすくなります。理想は3階層以内、選択肢は1階層あたり3〜4件程度に抑えるのが基本です。
・音声案内(セリフ)は短く・明確に 長い案内や専門用語の多用はNGです。顧客が一度で理解できる、簡潔で具体的なフレーズを心がけましょう。例:「ご契約に関するお問い合わせは1を、操作方法については2を押してください。」
・「その他の問い合わせ」項目を設けることで離脱防止 選択肢に該当しない問い合わせを受け付ける窓口を設けることで、行き止まりを防ぎます。顧客が「どこに進めばいいかわからない」と感じる状況を減らすことが大切です。
・入電呼量・対応時間のバランスを考慮する 特定の部署や時間帯に呼が集中すると、対応遅延や放棄呼が発生します。コール分配データを分析し、呼量ピークに合わせたルーティングや人員配置を行いましょう。
・複数窓口兼任オペレーターが混乱しないよう設計する 1人のオペレーターが複数業務を担当する場合、着信経路や対応内容を明確に区別できる設計が必要です。CTI画面に窓口名をポップアップ表示するなどの工夫も効果的です。
業務フロー・コールフロー作成の基本ルール
コールフローや業務フローを設計する際は、誰が見ても理解できる“シンプルかつ体系的な構成”を意識します。フローチャートを作成する場合は、以下の基本ルールを押さえましょう。
・開始点と終了点を明示し、範囲を明確にする どの時点で業務が始まり、どの時点で完了するのかを明示します。フローの範囲が曖昧だと、担当間で責任が不明確になり、対応ミスの原因となります。
・分岐点や例外対応もフロー内に含める 想定外のケース(転送不可・クレーム発生など)もあらかじめフローに組み込みます。分岐条件を明示しておくことで、誰でも適切な対応を判断できるようになります。
・図形・記号を統一して視覚的にわかりやすくする 「楕円=開始・終了」「長方形=作業」「ひし形=判断」「矢印=流れ」など、記号の意味を統一して使用します。統一ルールがあると、チーム内での共有がスムーズになります。
・シンプルで誰でも理解できる設計にする 新人や他部署の担当者が見ても理解できるレベルの明快さを意識しましょう。複雑すぎる設計は、運用フェーズで混乱を招くリスクがあります。
まとめ
コールフロー設計のポイントは、「顧客が迷わず、オペレーターが混乱しない仕組み」を作ることです。シンプルな分岐設計・明確な音声案内・適切な呼分配設定を行うことで、顧客体験(CX)と運用効率の両方を高められます。
また、IVR・ACD・CTI・CRMなど複数のシステムを組み合わせて運用する場合は、設計段階から現場とシステム担当者が連携することが重要です。
自社でフロー設計や改善が難しい場合は、コールセンター運営に精通したアウトソーシング(BPO)事業者の支援を活用するのも効果的です。専門的な知見を取り入れることで、顧客満足度向上・応答率改善・コスト最適化を同時に実現できるでしょう。

ProCX編集部
NTTマーケティングアクトProCX