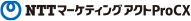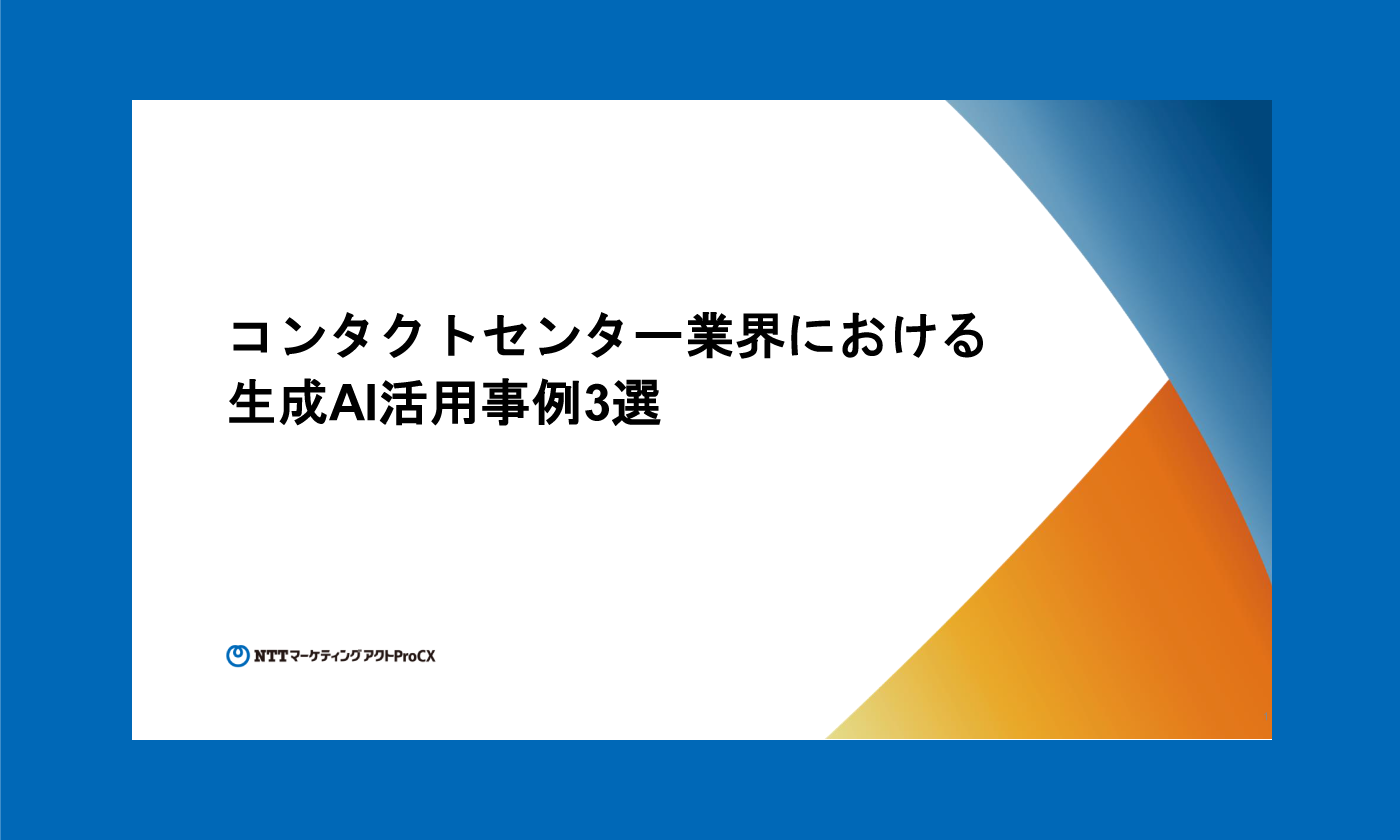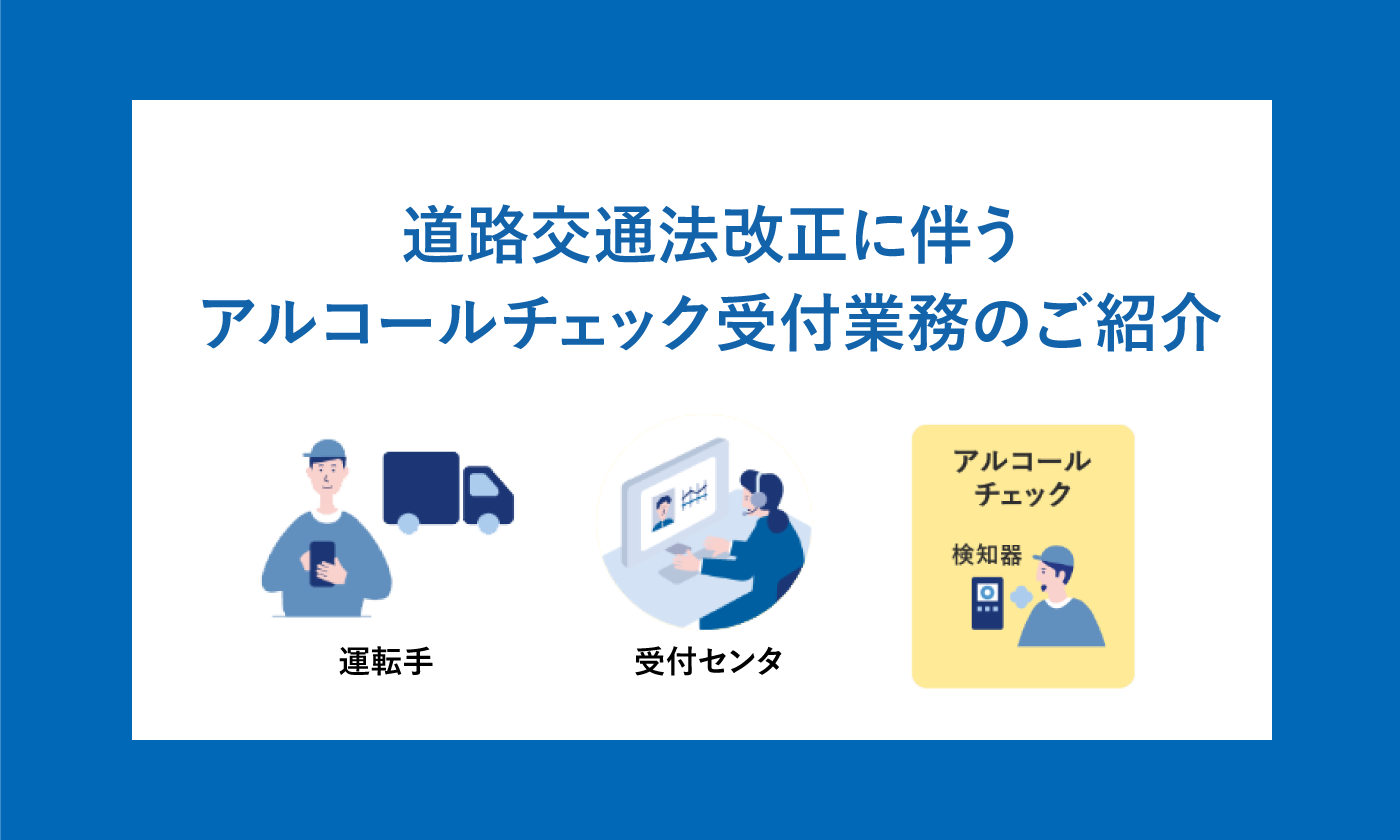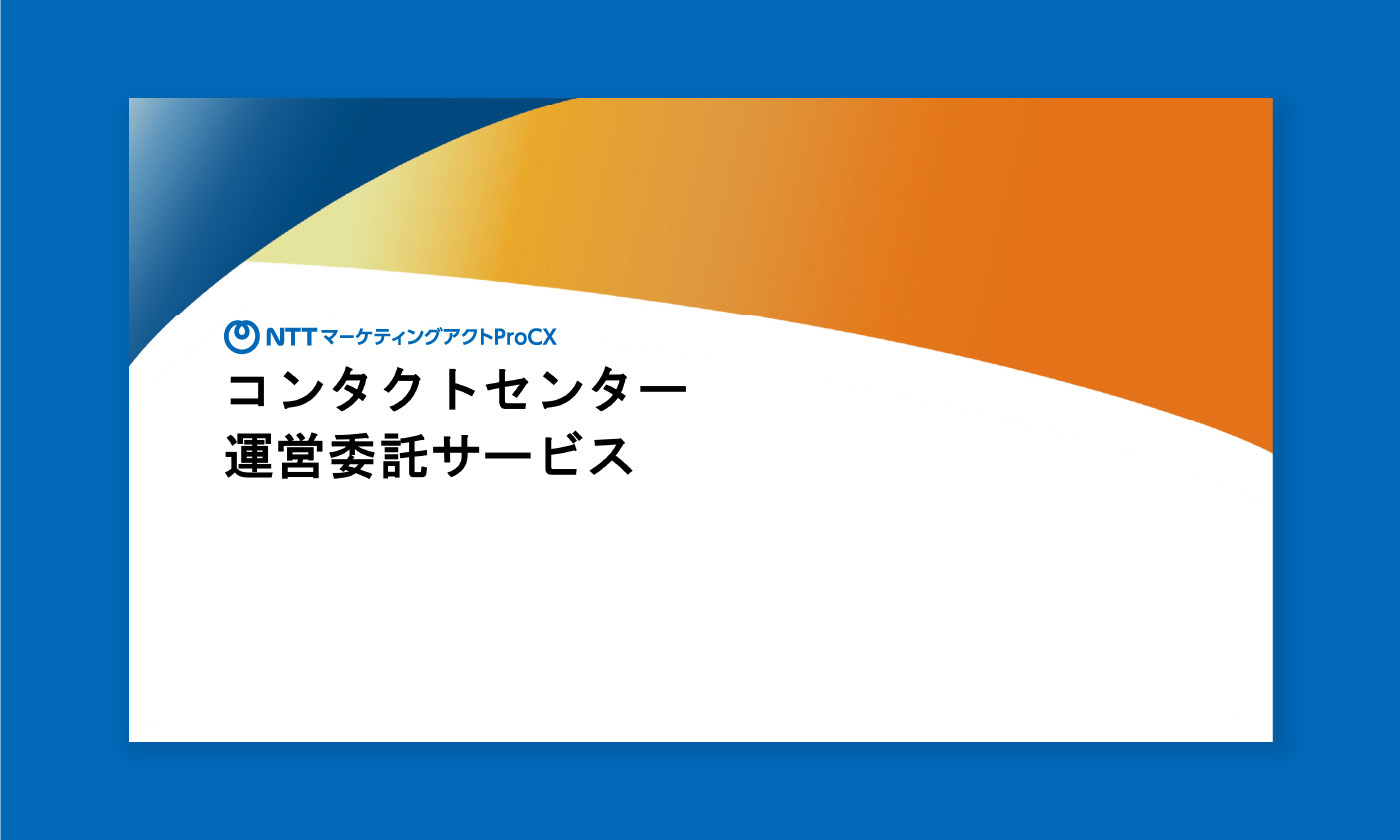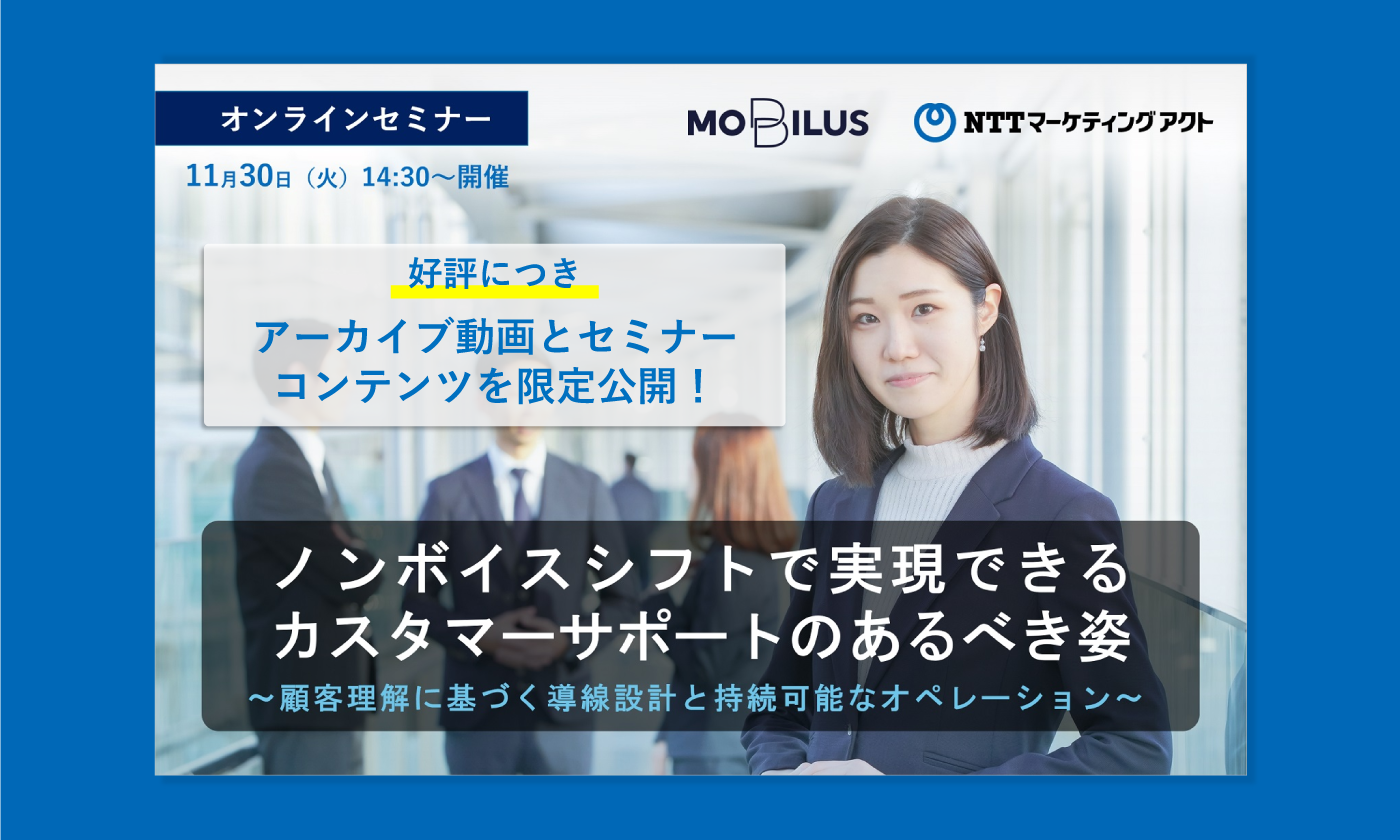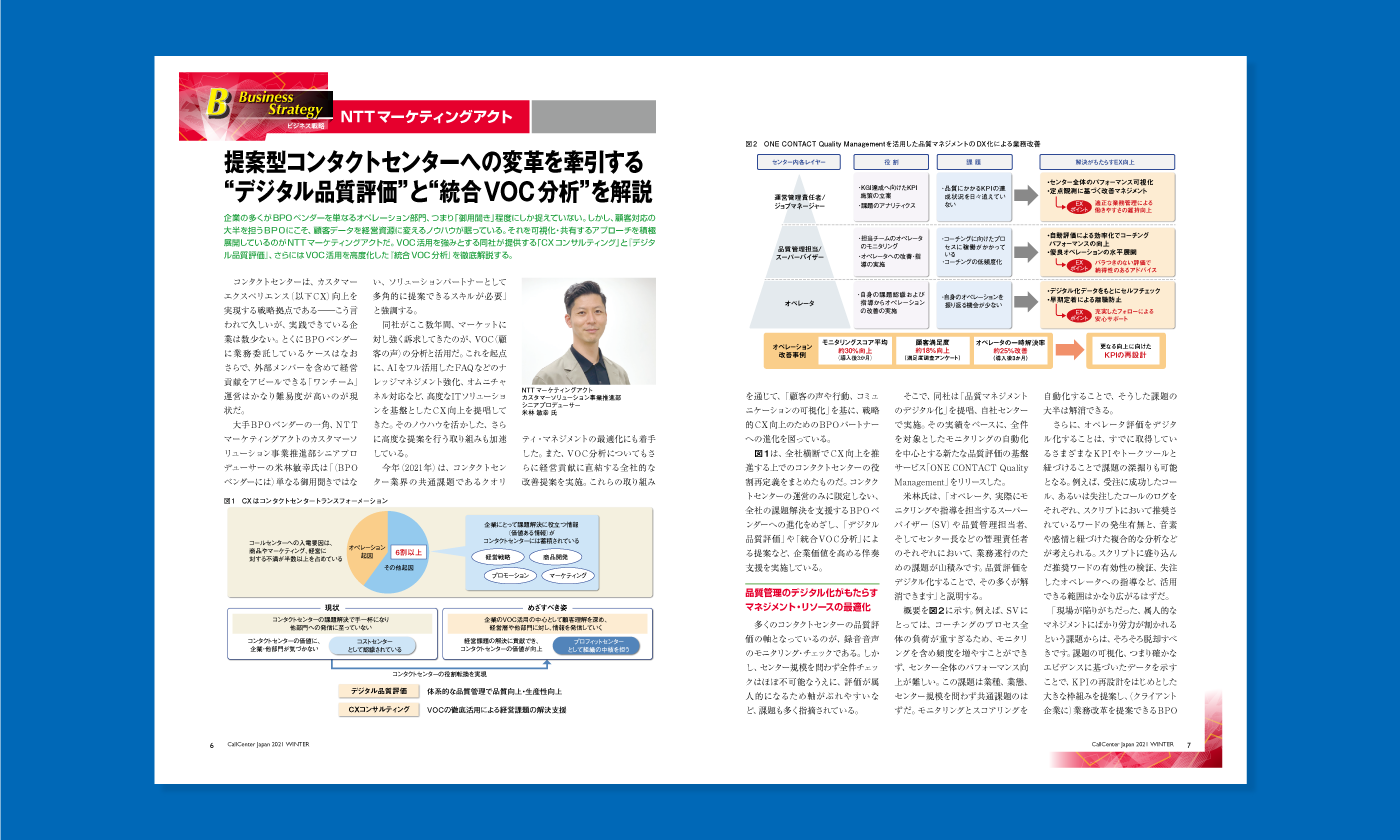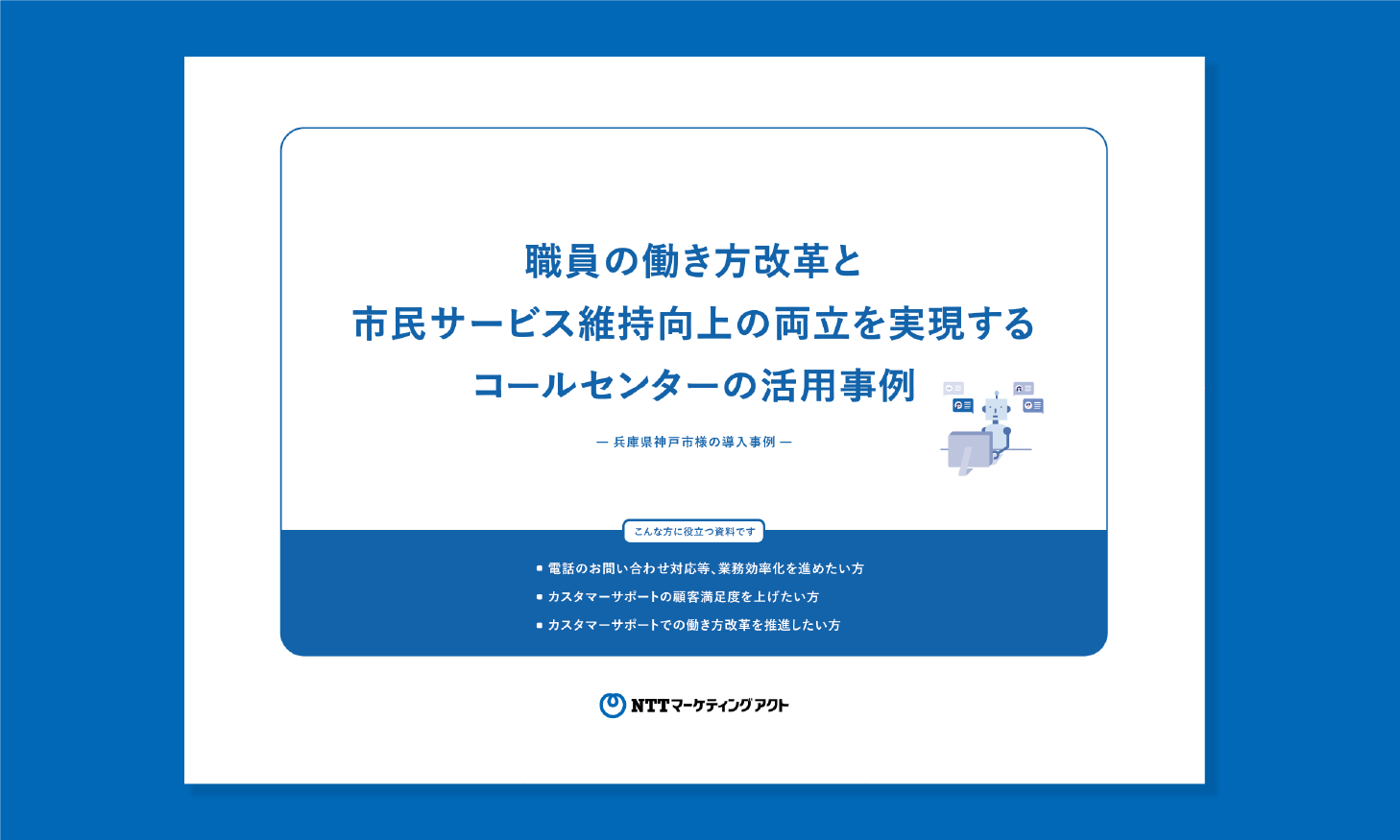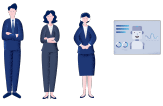コンタクトセンター
コールセンターのKPIとは?重要指標や改善のポイントを解説
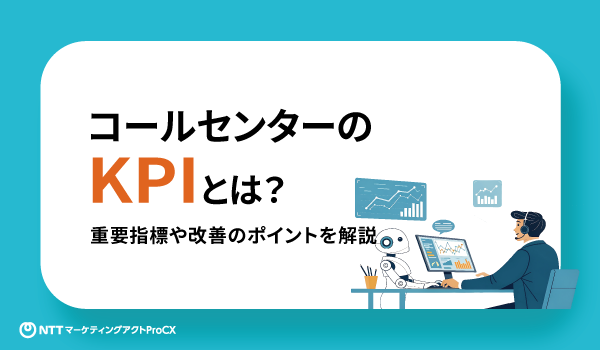
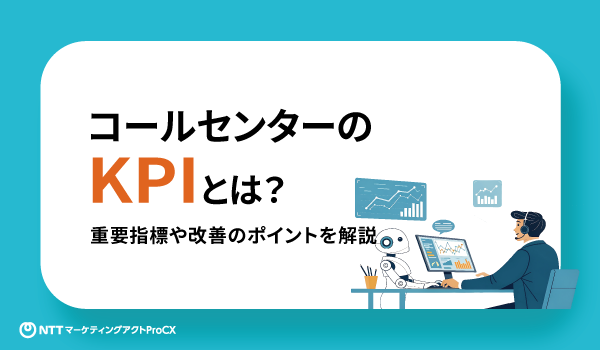

コールセンターでは、日々多くの顧客対応が行われており、その成果を正確に把握するためには定量的な評価指標(KPI)の設定と運用が欠かせません。KPIを適切に管理することで、業務品質や生産性を客観的に評価できるだけでなく、課題の発見・改善サイクルのスピードも大きく向上します。 この記事では、コールセンターにおけるKPIの基本的な考え方や、設定の目的、マネジメントにおける重要性についてわかりやすく解説します。KPIの運用に課題を感じている方や、センター改善の指針を明確にしたい方はぜひ参考にしてください。
コールセンターにおけるKPIとは

コールセンターにおけるKPIにはさまざまな種類があります。コールセンターにおけるKPIの定義や管理の重要性について紹介します。
KPIの定義
KPI(Key Performance Indicator:重要業績評価指標)とは、コールセンターの業務成果を定量的に測るための指標のことです。日々の対応件数や応答率、顧客満足度(CS)などの数値を追うことで、センター運営の現状を「見える化」できます。
KPI(Key Performance Indicator)とは、重要業績評価指標の略称で、業務のパフォーマンスを可視化し、改善の方向性を明確にするための指標です。コールセンター業務の「成果を定量的に測る」ための数値であり、属人的な判断に頼らず、誰でも同じ基準で業務品質を評価するためにあります。
KPIは「中間目標」として位置づけられ、最終的なKGI(例:売上拡大、顧客満足度向上、コスト削減など)を達成するための道筋を数値化します。たとえば、KGI=顧客満足度(CS)を90%以上にするという目標を設定した場合、そのためのKPIとして「一次解決率(FCR)」「応答率」「平均対応時間(AHT)」などが活用されます。
KPIを管理する重要性
コールセンターでは、KPIを管理することで現場の状態を可視化し、定量的なマネジメントを実現できます。感覚的な判断ではなく、データに基づいた改善を行うことで、顧客体験(CX)と従業員体験(EX)の両立が可能になります。
・業務品質・生産性を可視化できる KPIを設定・追跡する最大の目的は、「現場の状態を見える化すること」です。たとえば、対応件数・応答率・放棄呼率・平均処理時間(AHT)などをモニタリングすることで、コールセンターの稼働状況を定量的に把握できます。
・応答率が低下している場合:オペレーター不足やシフト設計の問題が明らかになる。 ・放棄呼率が高い場合:IVR設計や待ち時間管理の見直しが必要。 ・AHT(平均処理時間)が長い場合:トークスクリプトの煩雑さやナレッジ共有不足が原因。
このように、数値をもとに「どの部分を優先的に改善すべきか」を判断でき、感覚ではなく事実に基づく意思決定が可能になります。また、KPIをグラフやダッシュボードで可視化することで、オペレーターやSV自身が課題を自発的に把握し、改善意識を高める効果もあります。
・課題の早期発見・改善に役立つ KPIを継続的に記録・分析することで、問題の兆候を早期に察知できます。たとえば、前月比で「応答率が5%低下」「放棄呼率が2倍に増加」といった変化をいち早く把握できれば、顧客満足度が下がる前に対応策を講じられます。
・呼量の増減トレンド分析:季節要因やキャンペーン施策による入電増加を予測し、事前に人員を再配置。 ・オペレーター別のAHT比較:処理時間が長い担当者を特定し、OJTやマニュアル改善でスキルの底上げを図る。 ・FCR(一次解決率)の変動分析:一度の対応で完結していないケースを抽出し、ナレッジ整備やFAQ改修を実施。
このように、KPIの推移を分析することで、原因を“勘”ではなくデータから特定できるようになります。結果として、問題対応のスピードと正確性が大幅に向上し、センター全体の安定稼働につながります。
・顧客体験(CX)と従業員体験(EX)の両立を図れる KPIの管理は「顧客の満足度(CX)」と「オペレーターの働きやすさ(EX)」の両方を最適化するためのツールです。応答率や放棄呼率などの外的指標だけでなく、稼働率・占有率・離職率などの内的指標を併せてモニタリングすることで、負荷と成果のバランスを保てます。
稼働率が高すぎる(90%超など)場合は、オペレーターが休む間もなく対応している可能性があり、疲弊・離職のリスクが高まります。一方、稼働率が低すぎると顧客の待ち時間が増加し、サービスレベルが低下します。
適正なKPIバランスを維持することで、「働きやすさ」と「顧客満足度」双方の最大化が可能になります。 たとえば、ACDやスキルベースルーティングの調整により、スキルや対応力に応じて負荷を均等化する仕組みも整えられます。結果として、現場の安定稼働と顧客体験の質向上が両立できるのです。
・データに基づいたマネジメントが可能になる KPIのもう一つの大きな役割は、データに基づく意思決定を可能にすることです。SV(スーパーバイザー)やマネージャーは、KPIを定期的にモニタリング・共有することで、感覚ではなく「数値的根拠」をもとに判断できます。
また、KPIを定例ミーティングなどで共有することにより、現場のメンバーが数値目標を共通認識として持ち、「データを起点にしたチーム運営」が可能になります。最終的には、組織全体が「データドリブン型マネジメント」へと進化し、持続的な改善サイクルを生み出せます。
コールセンターのKPIの4分類とは?

コールセンターにおけるKPIの4つの分類と、それぞれの概要について紹介します。
コールセンターのKPIの4分類とは?
コールセンターにおけるKPIは、大きく分けて 「応対品質」「生産性」「顧客満足」「マネジメント(人材管理)」 の4つのカテゴリに整理できます。それぞれの指標をバランスよく追うことで、センター全体の運営状況を多角的に把握し、的確な改善施策につなげることができます。以下では、各分類の代表的な指標とその意味、算出方法・目安を詳しく解説します。
1. 応対品質に関するKPI
顧客からの電話に対して、どれだけ迅速・正確に対応できているかを測る指標群です。「つながりやすさ」や「対応力」は顧客満足度に直結するため、センター運営の基礎指標として最も重視されます。
2. 生産性・効率性に関するKPI
オペレーターがどれだけ効率的に業務をこなしているかを示す指標です。処理スピードや稼働バランスを可視化し、人的リソースの最適化やコスト削減の基礎データとして活用されます。
3. 顧客満足に関するKPI
顧客が「このセンターに相談して良かった」と感じる度合いを定量化した指標です。 サービス体験(CX)の質を数値で測定し、改善効果を追跡するのに用いられます。
4. マネジメント・人材管理に関するKPI
オペレーターの稼働安定性や組織状態を示す指標です。人材の定着や勤務環境の健全性を把握することで、センター運営の持続性を高めることができます。
これら4分類のKPIを総合的に管理することで、「品質」「効率」「顧客満足」「人材安定」のバランスを維持しながら、センターの最適運営と持続的な成長を実現できます。
KPIを設定・運用する際のポイント

KPIを効果的に活用するためには、「目的に沿った設定」と「継続的な改善サイクル」が欠かせません。単に数値を追うだけではなく、「なぜこの指標を追うのか」「どう改善に活かすのか」を明確にすることが重要です。以下の5つのポイントを押さえておくと、より実践的なKPIマネジメントが可能になります。
目的を明確にする
KPIは「KGI(Key Goal Indicator:最終目標)」に紐づけて設定する必要があります。目的と手段が一致していないと、数値を追うこと自体が目的化してしまいます。
【例】 ・顧客満足度の向上 → FCR(一次解決率)/NPS(顧客推奨度) ・業務効率化 → AHT(平均処理時間)/稼働率 ・売上拡大 → 成約率/アップセル率/CPH(コール・パー・アワー)
目的を軸にKPIを設計することで、センター全体の方向性が統一されます。
優先順位をつける
KPIは多く設定しすぎると、現場が混乱して本質的な改善が難しくなります。目的に沿って重点指標を3〜5個程度に絞り込み、優先順位を明確化しましょう。特に、応答率・AHT・CS・FCRなどはセンターの主要指標としてバランスよく選定するのが一般的です。
数値の目安を設定する
自社の業種・チャネル(電話/メール/チャットなど)に合わせて適正値を定義します。一般的な目安の適正値は以下です。
【各指標の適正値の目安】 - 応答率:90%以上 - 放棄呼率:5%以下 - AHT(平均処理時間):300〜360秒以内 - FCR(一次解決率):70〜80%以上 - CS(顧客満足度):80%以上
明確な数値基準を設けることで、改善目標が具体化します。
定期的に振り返る
KPIは設定して終わりではなく、「運用・分析・改善」を繰り返す仕組みが重要です。月次や四半期ごとに振り返りを行い、傾向を分析します。「数値の上がった要因」「下がった原因」「今後の改善策」を明確にしてPDCAを回すことで、継続的な成長を実現できます。
ツールを活用する
CRM・CTI・音声認識・BIツールを組み合わせることで、KPIの自動収集・可視化が可能になります。リアルタイムでダッシュボード化し、SVやマネージャーが即座に判断できる環境を整備しましょう。データの見える化は、チーム全体の意識改革にもつながります。
KPI設定・運用で生じやすい課題と対策は?

KPI運用の目的は「データをもとに改善を促すこと」ですが、実際の現場では数値管理が目的化したり、データを活かしきれなかったりするケースが多く見られます。ここでは、コールセンターで発生しやすい4つの課題とその対策を紹介します。
KPIが目的とずれている
数値達成を重視しすぎるあまり、本来の目的(顧客満足度の向上など)から乖離してしまうケースがあります。たとえば、AHT(平均処理時間)を短縮することに注力しすぎて応対品質が下がるなどが典型例です。対策として、KGI(最終目標)を再確認し、KPIを「目的達成のための手段」として再定義する必要があります。
KPIが多すぎて混乱
数値管理の対象が多すぎると、SVやオペレーターの負担が増加し、現場が疲弊します。対策として、3〜5個の重点KPIに絞り込み、現場との合意形成を行うことが重要です。不要な指標を整理し、「今どのKPIを改善すべきか」を全員が理解できる体制をつくりましょう。
データの精度が低い
CTIやCRMとの連携不足、手入力による誤差などにより、データの信頼性が低下するケースがあります。この場合、BIツールや音声認識システムを導入して自動集計化し、人的ミスを減らすのが有効です。また、「データを取るだけ」で終わらず、定例会で数値をもとに議論・改善策立案を行う体制を整えましょう。
KPIを活用できていない
KPIを報告資料としてまとめるだけで、改善アクションにつながっていないケースも多く見られます。データは「報告して終わり」ではなく、「分析・改善・検証」までを一連の流れに組み込むことが重要です。
【具体例】 1. 定例ミーティングでKPI数値を共有 2. 数値の変動要因を分析 3. 改善施策を決定・実行 4. 次回のKPIで効果を検証
このようなPDCAをチーム全体で定着させることで、KPIが“生きた指標”として機能するようになります。
まとめ
コールセンターにおけるKPIは、業務品質・生産性・顧客満足度をバランス良く可視化するための重要なツールです。 設定段階ではKGIとの紐づけと指標の優先順位を明確にし、運用段階では定期的な分析と改善アクションを継続することが鍵となります。
また、KPIの可視化やデータ分析に時間やリソースを割けない場合は、コールセンター運営やデータマネジメントを専門とするBPO(業務委託)サービスの活用も有効です。
専門的な知見を取り入れることで、より精度の高いKPI設計・運用が可能となり、顧客満足度と業務効率の両立を実現できます。

ProCX編集部
NTTマーケティングアクトProCX