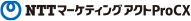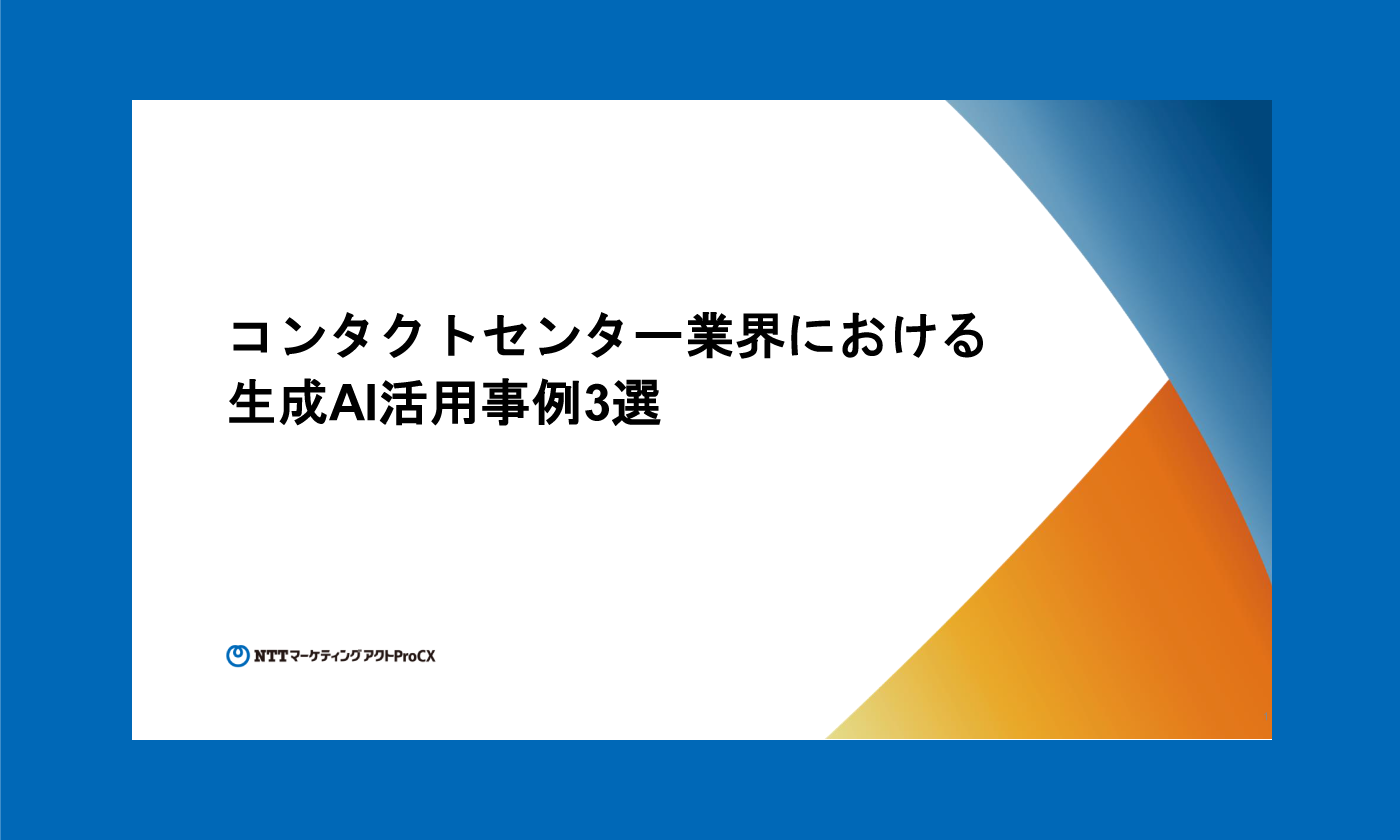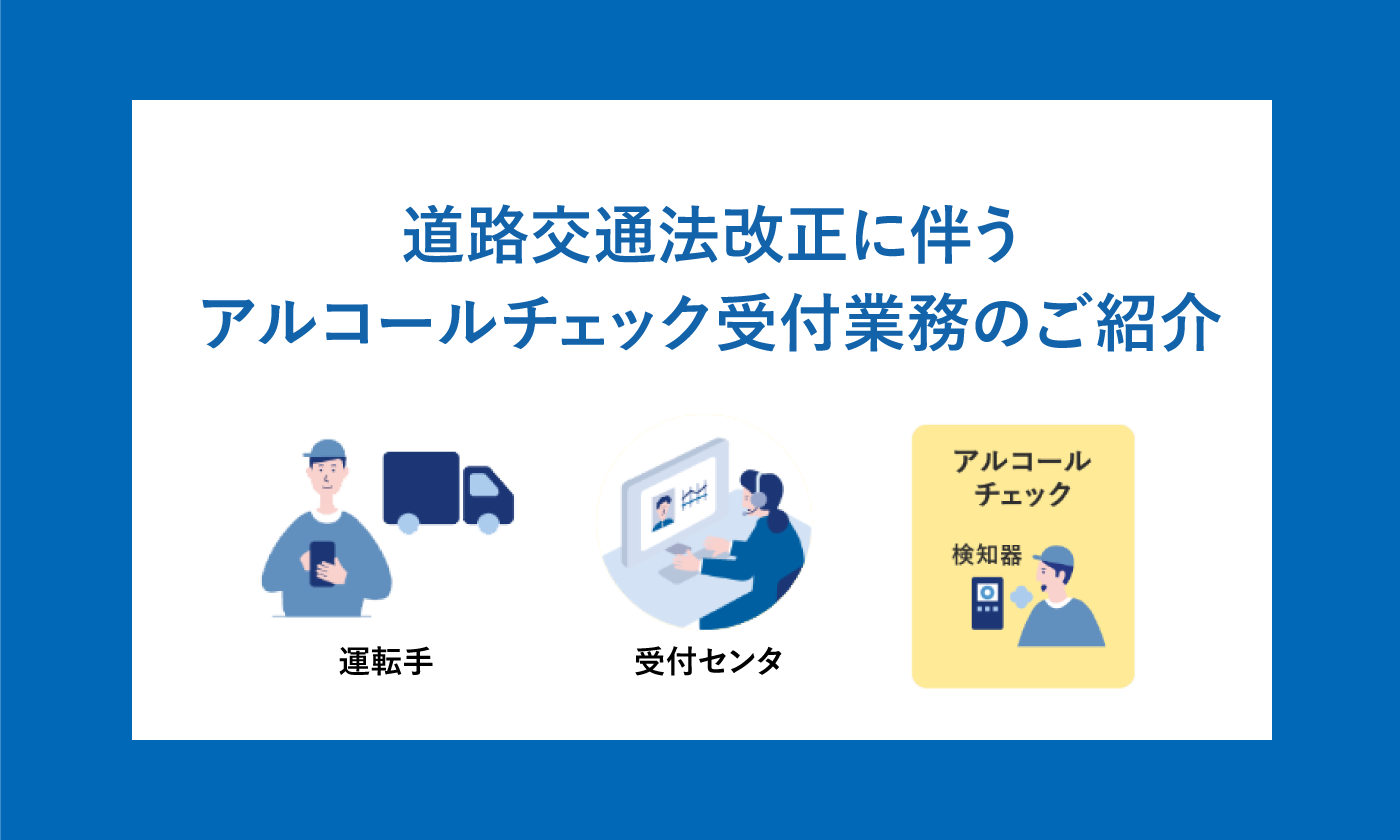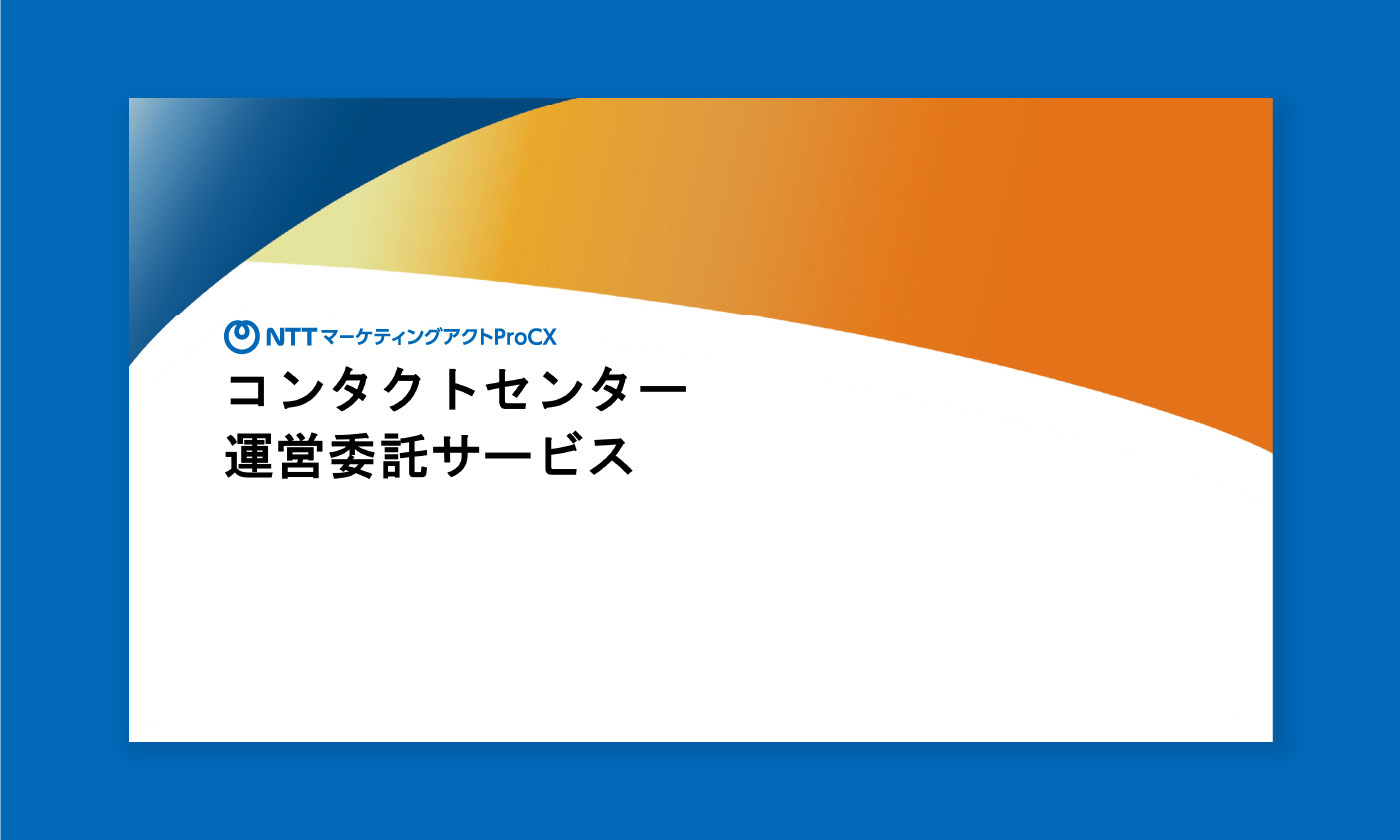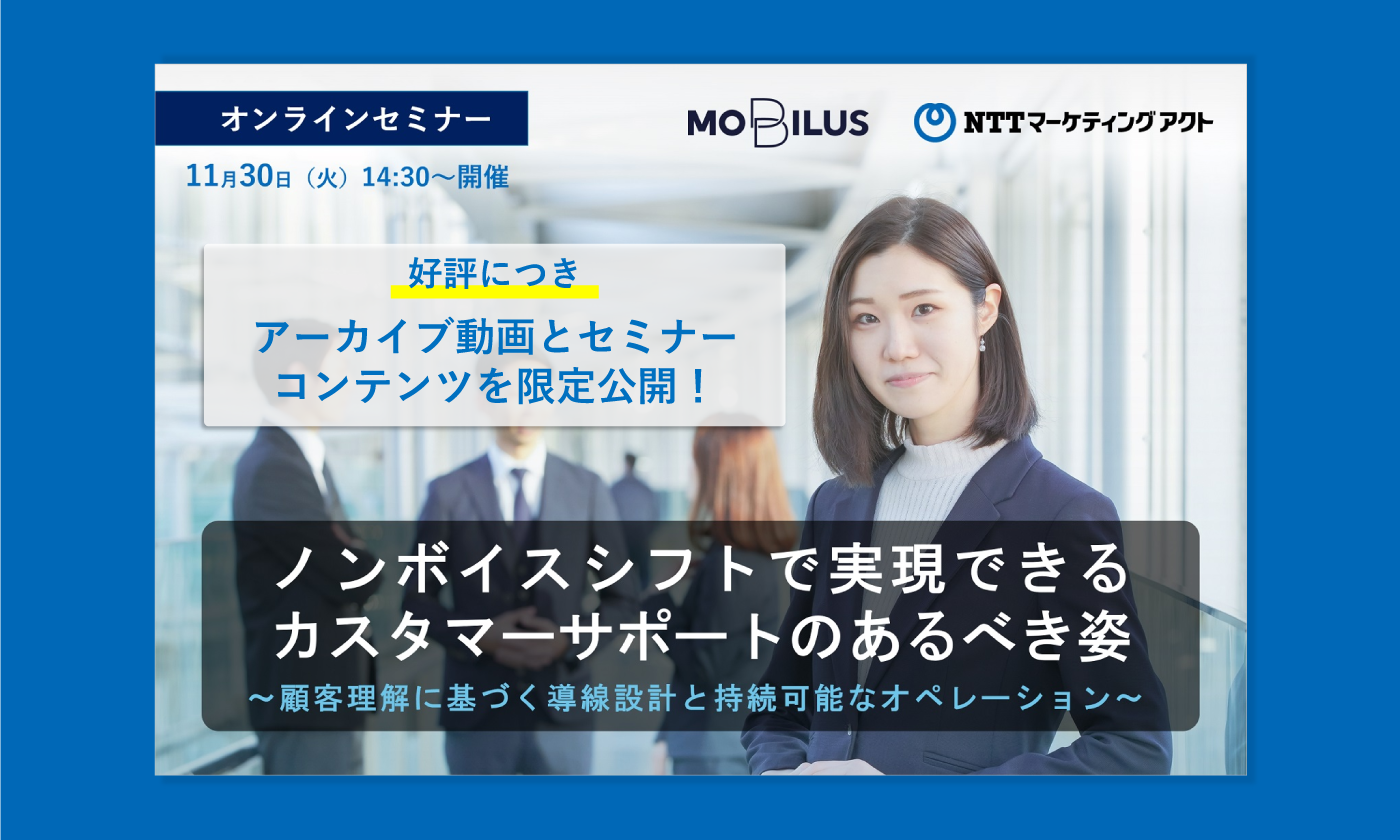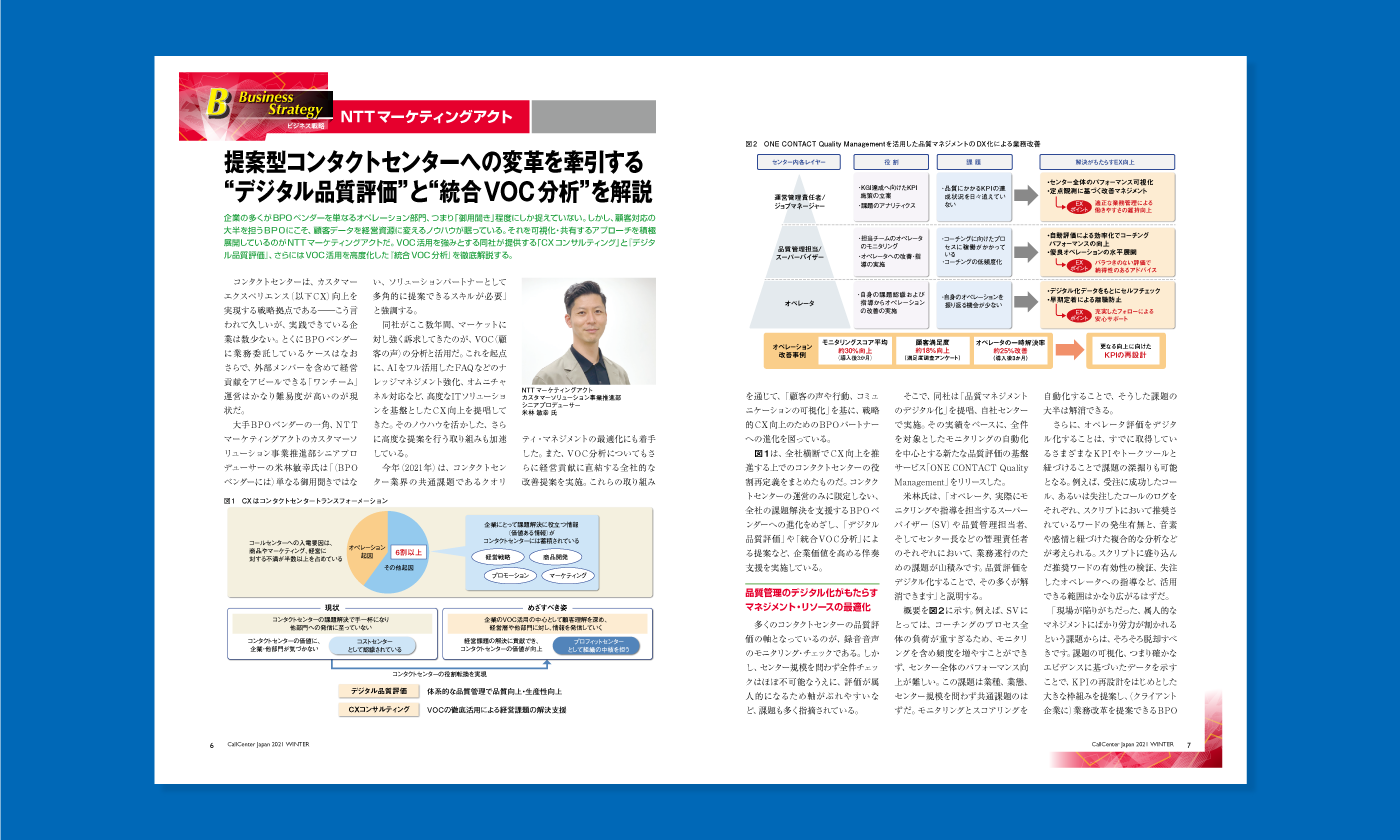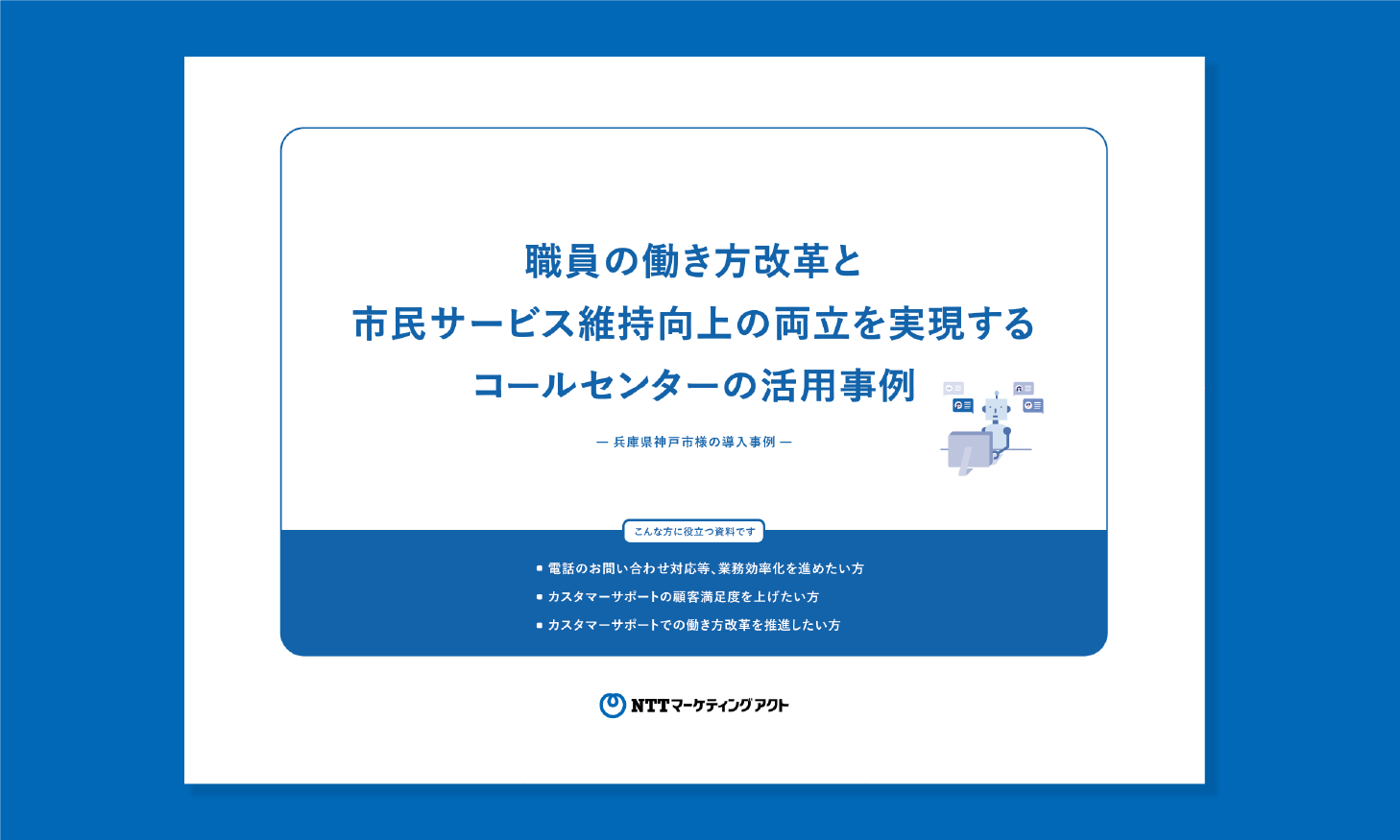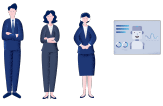コンタクトセンター
コールセンターのナレッジを武器に!ナレッジマネジメントの課題と成功のポイント
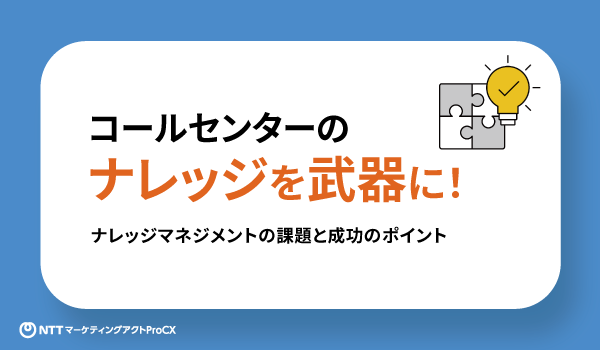
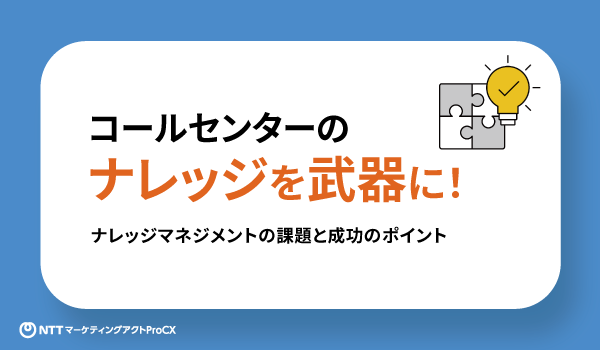

コールセンターでは日々、膨大な顧客対応を通じて多くの知見やノウハウが生まれています。しかし、それらが個人に属したままでは、同じ質問への回答がオペレーターごとに異なったり、教育コストが増えたりと非効率が発生します。
この課題を解決するのがナレッジマネジメントです。知識を組織全体で蓄積・共有することで、応対品質の均一化、教育効率化、顧客満足度(CS)や従業員満足度(ES)の向上が期待できます。
本記事では、コールセンターにおけるナレッジの定義から、ナレッジマネジメントの基礎知識、導入時のポイントまで詳しく解説します。
ナレッジとは?

まずは、ナレッジの概要やナレッジマネジメントとは何かについてご紹介します。
ナレッジ=“誰でも同じ答えに素早く届く”しくみ
ナレッジとは、組織内で得られた経験知を形式知化し、検索・再利用可能にした情報資産を指します。 顧客対応のために必要な知識を体系的に整理し、誰でも同じ答えに素早くたどり着ける仕組みを構築することが重要です。
設計は、「顧客向け(外部)」と「オペレーター向け(内部)」の二層構造で行い、FAQやヘルプページなど顧客自身がアクセスできる情報と、オペレーター専用の詳細手順をそれぞれ最適化します。
さらに、問い合わせチケットや対応履歴を起点に、都度学習・都度反映する運用が肝心です。これは「KCS(Knowledge-Centered Service)」という考え方に基づき、顧客対応のたびに知識を更新・補強していくことで、常に最新かつ実用的なナレッジを保てます。
ナレッジマネジメントの前提知識
ナレッジマネジメントを理解するには、暗黙知と形式知という2つの知識の形を押さえておく必要があります。
暗黙知:個人の経験や勘、感覚など、言語化・共有が難しい知識 形式知:マニュアルやデータベースのように、文章や図表などで共有できる知識
この2つを循環的に変換する理論として有名なのがSECIモデルです。SECIモデルとは、以下の4つの言葉の頭文字で構成されている概念です。
【SECIモデルとは】
- Socialization(共同化):暗黙知を共有する
- Externalization(表出化):暗黙知を形式知に変換する
- Combination(連結化):形式知を組み合わせて体系化する
- Internalization(内面化):形式知を再び個人の暗黙知として習得する
これらの4段階を繰り返し行うのが、SECIモデルの基本です。コールセンターでナレッジマネジメントを成功させるには、このSECIサイクルを意識しながら、現場の知識を迅速かつ正確に形式知へ落とし込み、再利用できる形にすることが不可欠です。
ナレッジが担う役割(品質・生産性・ES/CS向上)
ナレッジはコールセンターの運営効率と品質を支える「組織の資産」です。具体的な効果は以下の通りです。
・AHT(平均処理時間)の短縮 オペレーターが必要な情報にすぐアクセスできるため、回答までの時間を大幅に短縮します。
・FCR(一次解決率)の向上 顧客の質問にその場で正確に答えられるため、折り返し対応を減らし顧客満足度を高めます。
・教育期間の短縮と応対品質の平準化 新人オペレーターもナレッジを参照することで即戦力化し、ベテランと同等レベルの対応が可能になります。
・ES(従業員満足度)の向上 必要な情報を探すストレスが減り、オペレーターの離職率低下につながります。
・多チャネル対応の一貫性 電話・メール・チャット・ボイスボットなど、チャネルをまたいでも統一された回答を提供でき、企業の信頼性が向上します。
KCS(Knowledge-Centered Service)とは?
KCSは、ナレッジマネジメントを実践するための国際的なフレームワークです。
顧客対応業務を通じて得られた知識や経験をナレッジとして収集・構造化・共有・再利用し、組織全体で活用します。KCSでは、問い合わせ対応そのものを学習の機会と捉え、「問題を解決する=ナレッジを更新する」という考え方を採用します。
これにより、現場が自律的にナレッジを改善・拡充し続けるサイクルが生まれ、常に最新の情報を顧客やオペレーターに提供できるようになります。
KCSを導入すれば、ナレッジは単なるデータベースではなく、顧客体験向上と業務効率化を同時に実現する戦略的資産となります。
コールセンターのナレッジマネジメントでよくある課題

ナレッジマネジメントはコールセンターの生産性と品質を高める重要な取り組みですが、実際の運用では多くの課題に直面します。ここでは、現場でよく見られる4つの代表的な課題を整理します。
探すのに時間がかかる/最新情報がどこにあるか不明
ナレッジの一番の役割は「必要な情報にすぐアクセスできること」ですが、実際には以下のような問題が起こりがちです。
・複数の媒体(Excel、Word、社内Wiki、チャット履歴など)が乱立し、検索性が低い ・タグ付けや分類が未整備で、検索ワードを入れても期待した情報が出てこない ・更新履歴が不明瞭なため、古い手順や記述を参照してしまうリスクがある ・個人の「属人メモ」に依存しており、知識がナレッジとして共有・体系化されていない
結果として、オペレーターは顧客対応中に探す時間がかかり、AHT(平均処理時間)が長引く原因となります。
品質ばらつき・トーンの不統一
ナレッジ記事の品質が均一でないことも大きな課題です。
・記事ごとに書式や用語、敬語表現がバラバラで、顧客への説明トーンに不統一が出る ・担当者によって回答の粒度や根拠の示し方が異なり、応対品質に差が生まれる ・レビュー体制が整っていないため、誤記や情報の重複がそのまま放置されてしまう
この状態ではナレッジを参照しても安心できず、オペレーターが独自判断で応対する傾向が強まり、CS(顧客満足度)の低下につながります。
更新が回らない“ナレッジの墓場化”
ナレッジは最新でなければ価値を持ちません。
しかし、更新が回らず「ナレッジの墓場」と化してしまうケースは少なくありません。それによって、以下のような課題が生じやすくなります。
・現場で改善された対応内容が記事に反映されず、年次改定や事後更新で止まってしまう ・誰が更新責任者か不明確で、ワークフローも整備されていない ・記事更新に必要な工数が見積もられず、日常業務に押されて後回しになる ・効果測定がないため、ナレッジ活用による投資対効果(ROI)が見えず、優先度が下がる
こうした状況では、ナレッジシステムそのものが形骸化し、オペレーターに活用されなくなってしまいます。
ツールが現場フローに馴染まない
どれだけ高機能なナレッジツールでも、現場オペレーターが使いにくければ定着しません。ツールのマニュアルや利用方法を共有できていないケースでは、以下のような課題が起こりやすくなります。
・別画面や別システムで参照する必要があり、通話中に「探す手間」がかかる ・権限制御や監査ログ、版管理が弱いため、セキュリティや運用面に不安がある ・検索機能が弱く、AI検索やレコメンド機能が備わっていないため、ヒット率が低い
その結果、現場で「結局使えない」と判断され、ナレッジの利用が進まないのです。
コールセンターのナレッジマネジメントでは、検索性の低さ、品質のばらつき、更新停滞、ツールの非定着といった課題が繰り返し指摘されています。これらを解決するには、記事の標準化や更新責任の明確化、現場フローに合ったツール選定、AI活用による検索精度向上など、戦略的な運用改善が不可欠です。
コールセンターのナレッジが重要な理由は?

コールセンターは顧客対応の最前線であり、オペレーターが顧客満足度(CS)に直結する役割を担っています。そこで重要になるのがナレッジマネジメントです。
組織の知識を体系化し、誰でもすぐに活用できるようにすることで、オペレーターの負担軽減から研修効率化、顧客対応品質の向上まで、さまざまな効果をもたらします。
オペレーターをコミュニケーション能力重視で評価可能
近年、コールセンターではオペレーターに求めるスキルが専門知識からコミュニケーション能力重視へとシフトしています。
ナレッジに顧客対応の手順や解決策が集約されていれば、オペレーターは専門知識を丸暗記する必要がなく、顧客との対話力や傾聴力を評価の中心に据えることが可能です。
これにより「顧客満足度向上につながる接客スキル」を持つ人材を採用・育成しやすくなり、採用戦略の柔軟化にも貢献します。オペレーターはコミュニケーションに集中でき、現場全体のサービス品質向上につながります。
顧客向けFAQとしても活用できる
ナレッジはセンター内部で活用するだけでなく、顧客向けFAQやチャットボットのコンテンツとしても役立ちます。
問い合わせ対応のノウハウをそのまま企業サイトの「よくある質問」やチャットボットに展開すれば、顧客が自分で課題を解決できる仕組みを構築可能です。
これにより顧客の自己解決率が上がり、電話やメールの問い合わせ件数を削減できるため、オペレーターの負荷軽減やAHT(平均処理時間)の短縮にも効果があります。
顧客体験の向上と運営コストの削減を同時に実現できる点は、ナレッジ活用の大きな魅力です。
離職率を抑える効果も
コールセンター業界ではオペレーターの離職率の高さが慢性的な課題です。
離職理由のひとつとして、顧客からのクレーム対応に強いストレスを感じるケースが挙げられます。ナレッジとしてよくあるクレームやその対応策を整理・共有しておけば、新人オペレーターでも安心して対応でき、心理的負担が軽減されます。
結果として職場定着率が高まり、採用・研修にかかるコスト削減にもつながります。
研修コストや期間を抑えられる
新人教育には、ベテランオペレーターが長年培ったノウハウやコツを伝える必要がありますが、これには時間と費用がかかります。
ナレッジマネジメントで手順や事例、トークスクリプトなどをデータベース化して共有しておけば、誰でもすぐに必要な知識を習得可能です。
研修期間が短縮されることで、早期の即戦力化が実現し、教育コストも削減されます。 ・教育内容が標準化されることで、個々のトレーナーに依存しない安定した研修が可能になります。
コールセンターと技術部門のナレッジギャップの解消
コールセンターでは、複雑な製品やサービスの問い合わせに対応する際、技術部門との連携が必要になる場面があります。
このとき、オペレーターと技術者の間で知識レベルに差があると、情報伝達に時間がかかり、顧客対応が遅れる原因となります。
ナレッジとして技術的なFAQや手順、過去の対応履歴を蓄積しておけば、オペレーターが一定レベルの技術知識を即座に参照でき、ギャップを最小限に抑えられます。
結果として、顧客への一次解決率(FCR)向上や、部門間連携の効率化につながります。
コールセンターにおけるナレッジは、顧客対応品質を高め、オペレーターの負担軽減や教育効率化、離職率低減まで多方面に効果を発揮する重要資産です。ナレッジを活用することで、オペレーターはコミュニケーションに集中でき、顧客は自己解決しやすくなり、組織全体のパフォーマンスが向上します。
コールセンターにおけるナレッジマネジメントを成功させるポイントは?

コールセンターのナレッジマネジメントは、単なる情報共有ではなく、品質向上・業務効率化・顧客満足度アップを実現するための重要な仕組みです。
しかし、現場に浸透させて成果を出すには、目的の明確化からツール選定まで、段階的かつ計画的な取り組みが必要です。以下の4つのポイントを意識すると、持続可能で活用度の高いナレッジマネジメントを実現できます。
目的を明確に設定する
ナレッジマネジメントは、何のために行うのかを全員が理解していることが成功の第一歩です。
「応対品質の均一化」「新人教育の効率化」「顧客自己解決率の向上」など、具体的な目的を明確に設定し、チーム全体で共有しましょう。チームで共通認識を持つことで、長期的に業務負荷を軽減でき、ナレッジの定着もスムーズになります。
また、失敗事例を共有するときにメンバーが委縮しないよう、管理者はポジティブかつ建設的なフィードバックを心がけ、安心して情報共有できる環境を作ることが大切です。
ナレッジ共有・活用のルールを設定する
ナレッジを集めても、ルールがなければ混乱を招きます。
どのように作成し、誰が承認し、どのカテゴリに格納するかなど、共有と活用のルールを明文化しましょう。「カテゴリごとの分類」「タグ付け」「ナレッジワーカー(責任者)の設置」など、検索・更新がしやすい運用ルールを策定することで、最適なナレッジがすぐに見つかります。
このルールは一度決めたら終わりではなく、実運用を踏まえて定期的に改善することが重要です。
情報のアップデートを定期的に行う
ナレッジは常に最新であることが信頼性の鍵です。コールセンター業務では受電・架電を問わず多様な問い合わせが発生するため、古い情報が残ると誤った対応につながるリスクがあります。
ナレッジが更新されないと現場メンバーが参照しなくなり、マニュアルは「放置された資料」となってしまいます。
定期的なレビューや自動リマインド機能を活用し、最新情報をいつでもチェックできる体制を維持しましょう。現場からのフィードバックを積極的に取り込み、チケット起点で随時アップデートする運用が理想です。
適切なナレッジ管理ツールを使用する
大量の情報を効率的に扱うには、専用のナレッジ管理ツールの導入が不可欠です。
膨大なデータベースから迅速に必要情報を検索できる機能が求められ、紙やExcelなどのアナログ管理では限界があります。
検索精度の高いツールやAIレコメンド機能付きのシステムを選べば、オペレーターは通話中でも即座に答えを見つけられます。権限管理、監査ログ、バージョン管理などのセキュリティ機能も重視し、現場フローに合ったツールを選定してみましょう。
コールセンターのナレッジマネジメントに適したツールの選び方

ナレッジマネジメントを成功させるには、現場の業務フローに合ったツール選定が欠かせません。 導入後に「欲しい機能がない」「運用が煩雑」といった問題を防ぐため、以下のポイントを事前に確認しておきましょう。
必要な機能が搭載されているか
まず注目すべきは、自社のナレッジ運用に適した機能を備えているかです。
AI検索は必須機能のひとつで、表記ゆれや口語表現にも対応し、長文からの要約検索ができれば、オペレーターが短時間で最適解にたどり着けます。
過去の対応履歴から関連情報を提示するレコメンド機能や、類似チケットを学習してナレッジ化を促進する仕組みも重要です。顧客が自分で解決できるセルフサービス(ヘルプセンターやFAQ)機能と、オペレーター向けのエージェント支援機能が両立しているかもチェックしましょう。
これらの機能が揃っていれば、顧客と現場双方の利便性が向上し、ナレッジ活用効果を最大化できます。
コールセンターとの連携機能
次に確認すべきは、CRMやCTIとの連携性です。
CRM連携により、顧客データとナレッジをシームレスに統合でき、問い合わせ内容に即した最適な回答を提案できます。通話録音の自動文字起こしからナレッジ候補を抽出し、ドラフト記事を自動生成する機能があれば、更新作業の工数を大幅に削減できます。
ボット、IVR、音声認識システムと連携して、顧客の自己解決率を最大化できるかどうかも重要なポイントです。 これらの連携機能は、オペレーターの負荷軽減と顧客体験の向上を同時に実現します。
運用コストと拡張性
導入後のコストと拡張性も、長期的な活用において重要な判断基準です。
導入や日常運用が複雑すぎると、現場で使いこなせず効率化どころか逆効果になる恐れがあります。費用が高すぎればROI(投資対効果)が低下し、継続利用が難しくなるため、初期費用・月額料金・保守費用を総合的に比較しましょう。
グローバル展開を視野に入れる場合は、多言語対応や高度なAI機能を備えたモデルを選ぶことで、将来的な拡張にも柔軟に対応できます。
合わせて、利用規模が増えても安定して稼働できるか、契約プランのアップグレードが容易かどうかも確認しておきましょう。
まとめ
業務を通じて集まったナレッジは、業務効率化や顧客満足度の向上に欠かせない要素です。
コールセンターの全スタッフが共通して利用できるナレッジを構築するためには、ナレッジマネジメントのポイントやフロー、必要なツールを理解し、体系化のために日々少しずつ作り上げていく必要があります。
コールセンターのナレッジ構築にお悩みの方は、ぜひ今回ご紹介した内容を参考にしてみてください。

ProCX編集部
NTTマーケティングアクトProCX