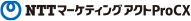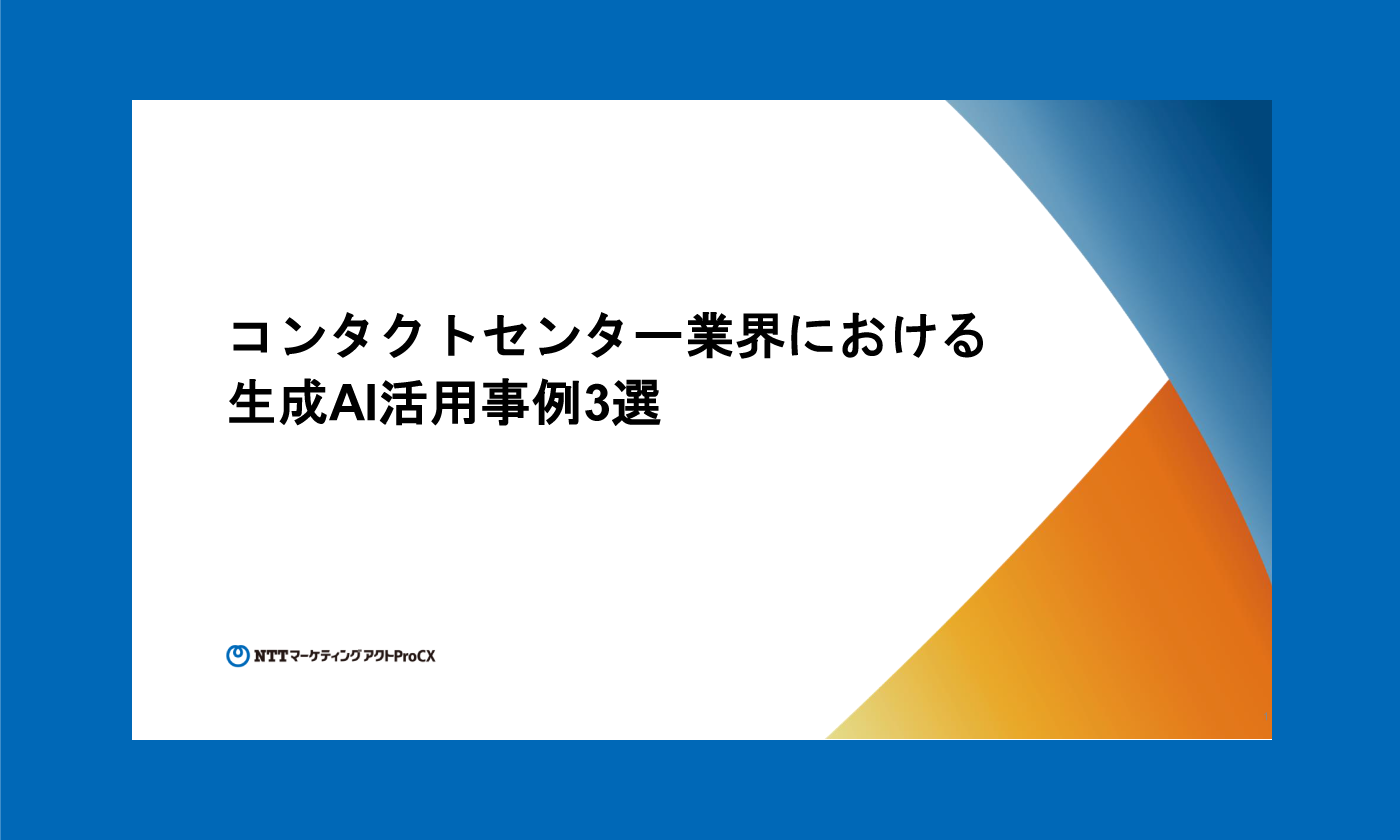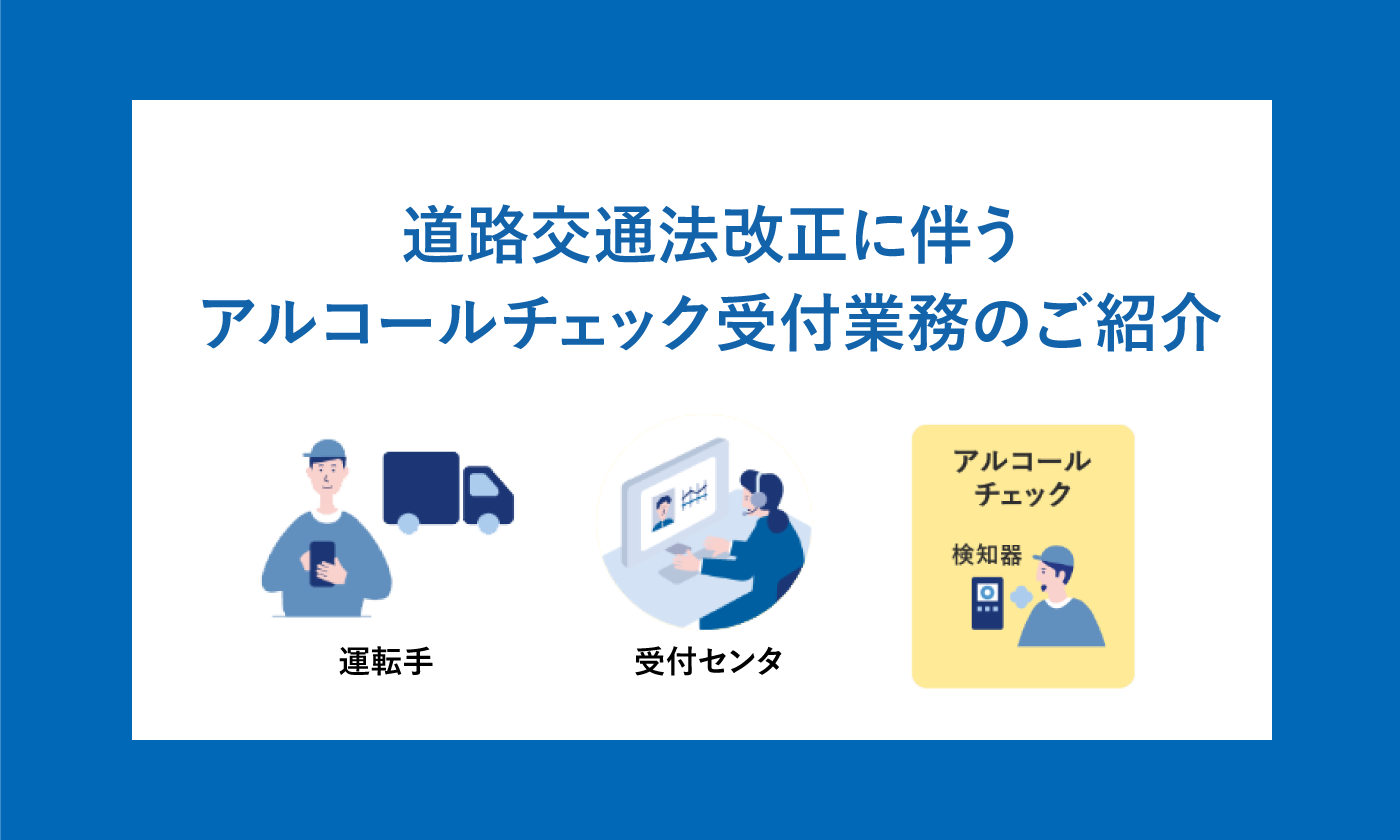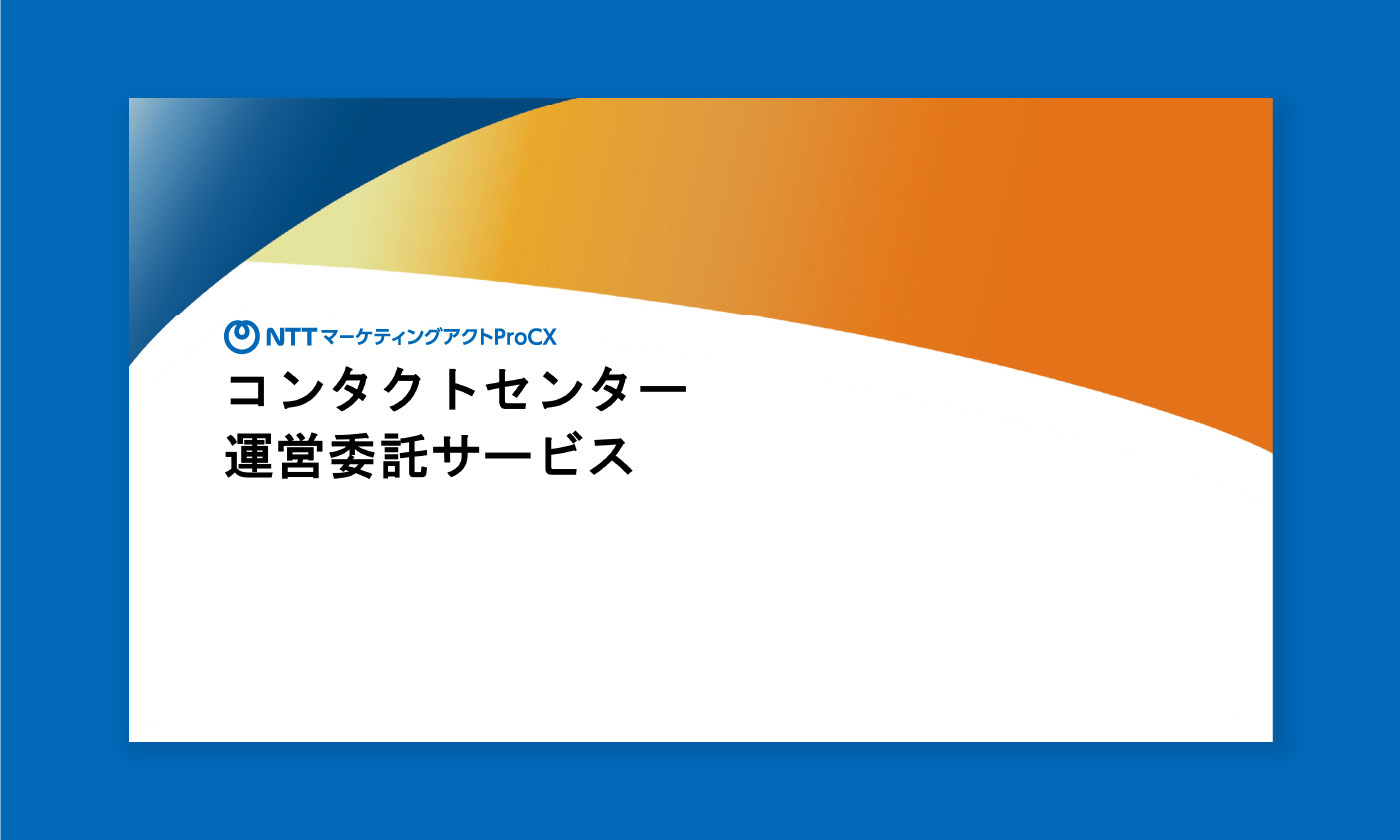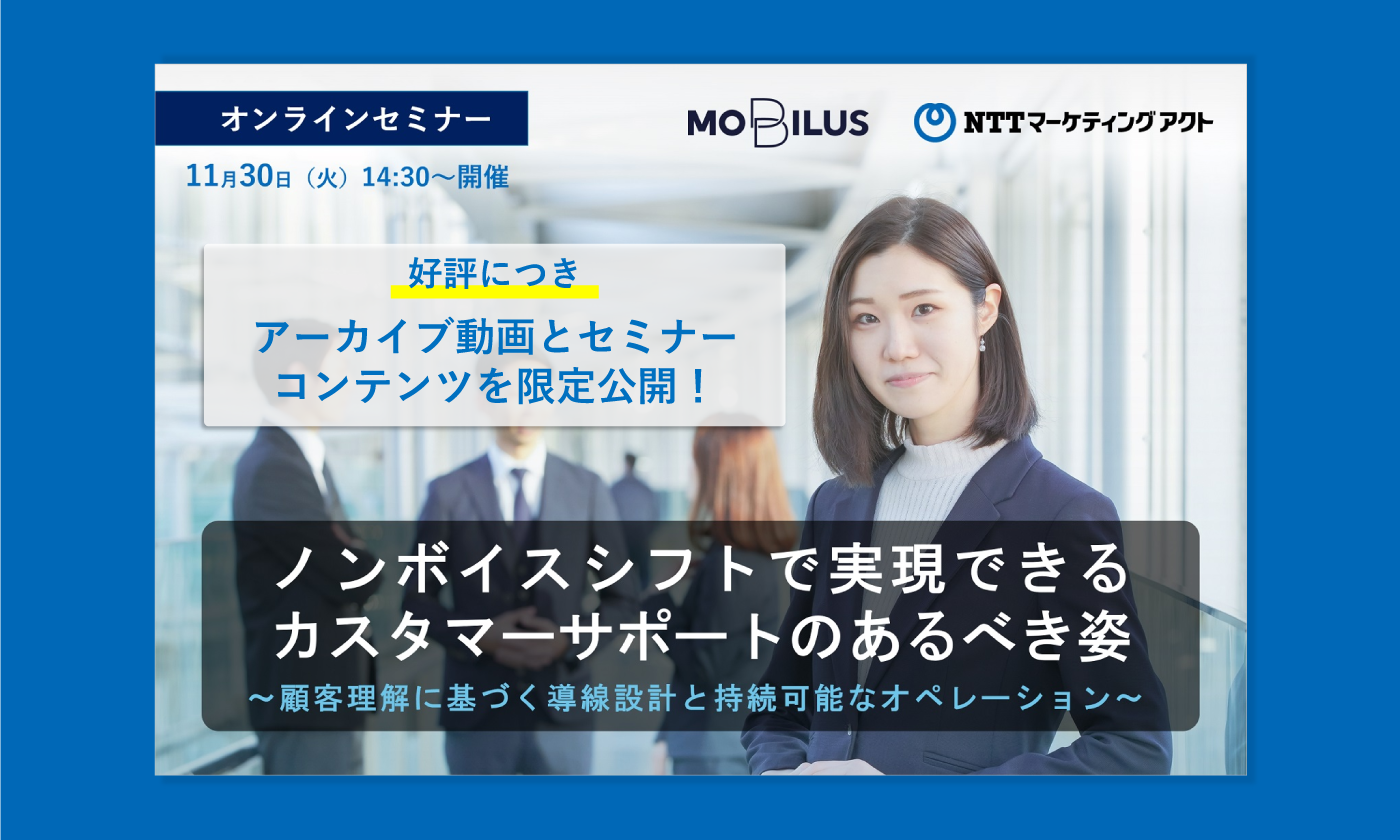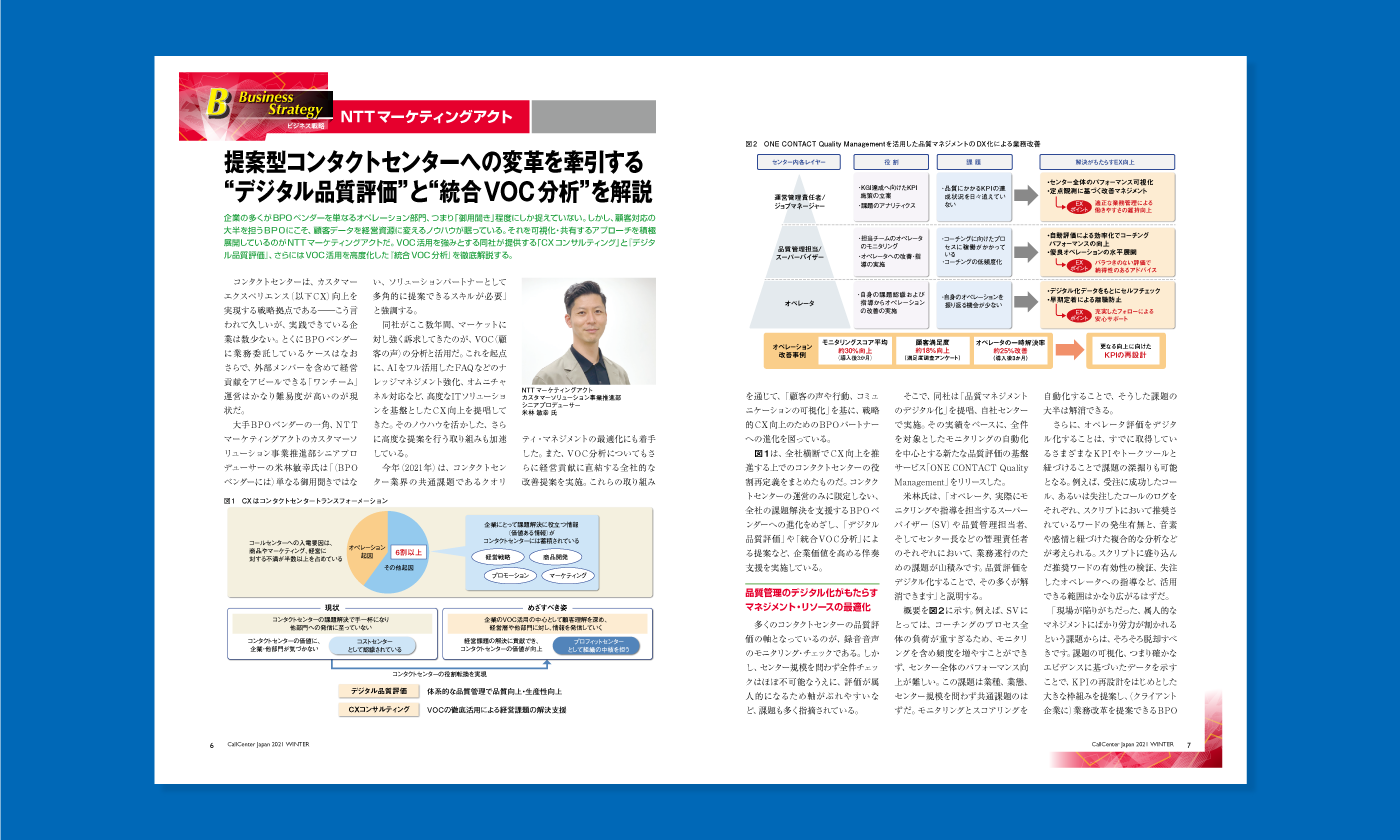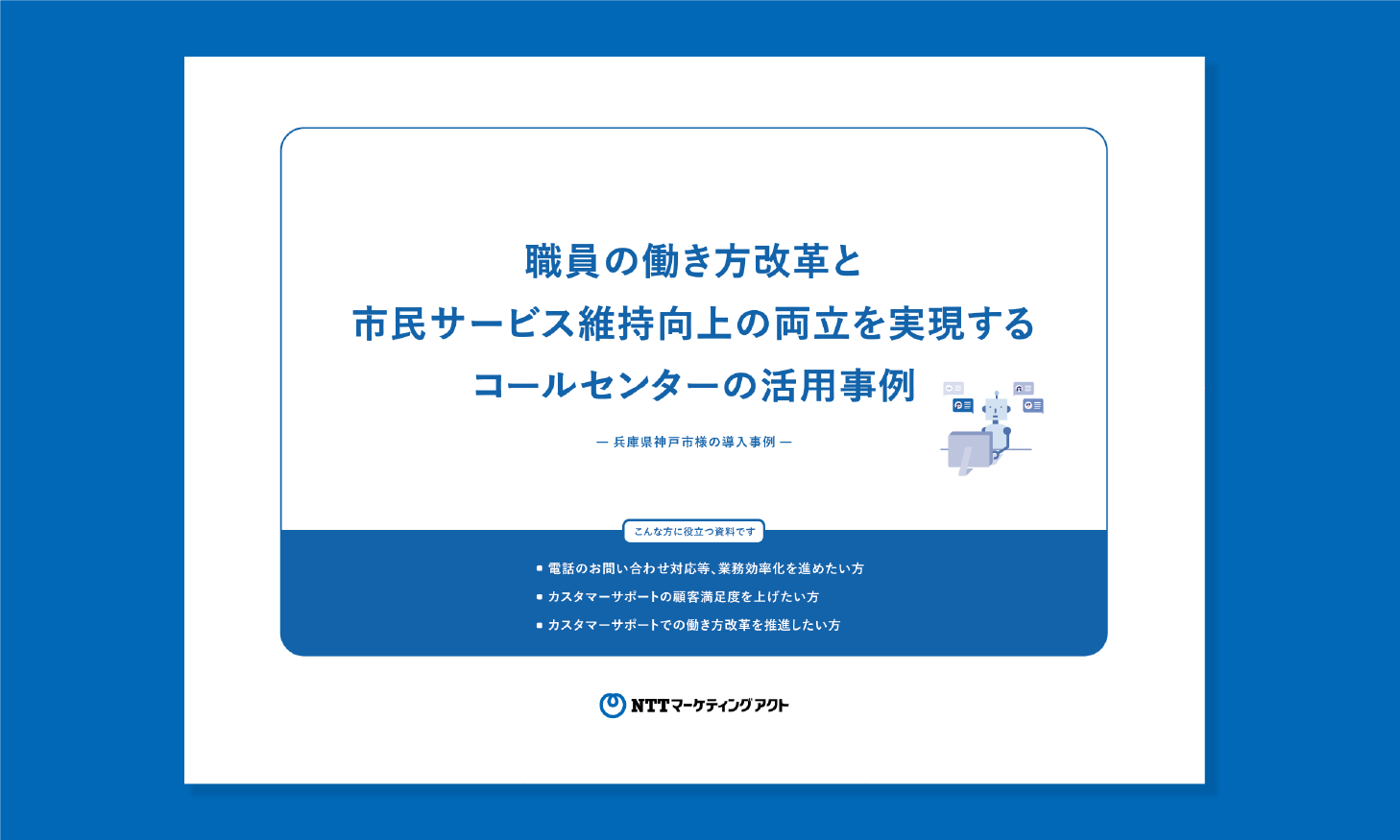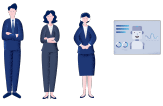コンタクトセンター
電話業務を効率化する方法は?課題・デメリット・改善策・おすすめツールを紹介
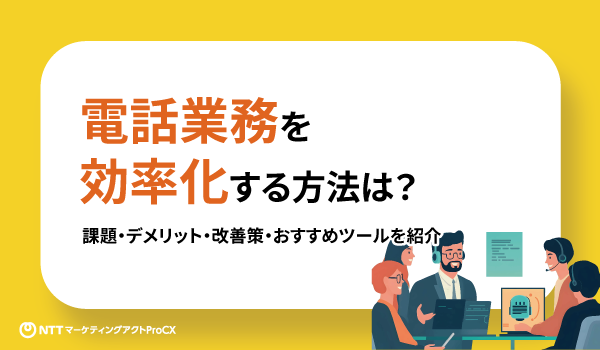
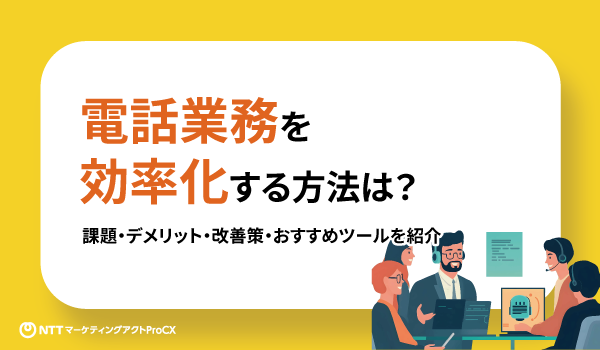

電話対応は企業にとって欠かせないコミュニケーション手段ですが、生産性低下や人件費増加の原因にもなり得ます。
特に中小企業やオフィス業務では、「電話対応に追われて本来の業務が進まない」「取り次ぎや記録ミスが多い」といった悩みが多く見られます。
この記事では、電話業務が非効率になる主な原因とその課題、そして効率化を実現するための実践的な方法・おすすめツールまでをわかりやすく解説します。
電話対応を見直したい担当者や、業務改善を進めたいマネージャーの方はぜひ参考にしてください。
電話業務を効率化するべき理由

電話業務の非効率さは、単に「時間が取られる」という問題にとどまりません。企業全体の生産性・コスト・従業員満足度にまで影響するため、早期の見直しが重要です。
電話対応に追われて他業務が滞る
問い合わせや取引先からの電話対応が多いと、営業・事務・開発など本来の業務が中断されやすくなります。特に一部社員に電話対応が集中すると、作業効率が著しく低下し、ミスや納期遅延を引き起こすこともあります。
聞き間違いや伝達ミスが発生しやすい
電話は口頭でのやり取りであるため、記録漏れ・言い間違い・聞き間違いが発生しやすく、トラブルの原因になります。担当者がメモを取れなかった場合や、伝言が正確に共有されなかった場合、顧客満足度の低下やクレームにつながることもあります。
受電漏れによる信用・機会損失
「電話に出られない」「不在中に重要な連絡を逃す」といった受電漏れは、取引機会の損失や企業の信頼低下を招きます。特に初回問い合わせを逃すと、顧客が競合他社へ流れてしまうケースも少なくありません。
人件費・残業コストの増加
電話対応に多くの人員を割く必要がある場合、非効率な人件費の増加が発生します。また、定時後の電話や緊急対応が多い環境では、残業時間が増え、コスト面だけでなく従業員のワークライフバランスにも悪影響を及ぼします。
従業員のストレス・モチベーション低下
頻繁な着信や突発的な対応は、集中力を削ぎ、精神的なストレスを増大させます。特に「自分の業務が中断される」「電話に追われて終わらない」という感覚は、モチベーションの低下や離職意向の上昇につながります。
電話業務を効率化するための基本ポイントと6つの方法

電話対応を効率化するには、ルール設計・マニュアル整備・システム活用の3つを組み合わせて実行することが重要です。
電話業務を効率化する基本ポイント
電話業務を効率化する際の基本的なポイントを紹介します。
担当制・時間割を設ける
時間ごとに電話担当をローテーションすることで、他の社員が集中して作業できる時間を確保します。「午前中はAチーム、午後はBチーム」といった運用を行うと、電話負担を均等に分散できます。
マニュアル・教育体制の整備
対応品質を標準化するため、電話応対マニュアルやFAQ集を整備し、全社員が同じ品質で対応できる体制を構築します。 新人教育時の基礎研修に加え、定期的なロールプレイやモニタリング評価も有効です。
電話の優先順位をつける
すべての電話に即時対応する必要はありません。 緊急度・重要度を判断基準にして優先順位を設定し、 緊急案件 → 直通対応 ・一般問い合わせ → コールバックまたはメール対応 など、チャネルを分けて処理することで効率化できます。
不要な電話を削減する
社内連絡や確認事項を電話で行う代わりに、チャットツールや社内ポータルに移行します。 「Slack」「Microsoft Teams」「Chatwork」などを活用することで、電話発生率を大幅に削減できます。
電話業務を効率化する6つの方法
上記の基本的なポイントをふまえて、効率化に効果的な6つの方法を紹介します。
1. 電話対応マニュアル・教育を徹底する
マニュアルに基づく対応ルールを整備することで、オペレーターや事務担当者が誰でも一定品質で応対できるようになります。 特に新人・パート社員の教育コストを削減し、引き継ぎ時の混乱を防ぐ効果もあります。
2.電話の取り次ぎをスムーズにする
代表電話の取り次ぎや社内転送を自動化することで、伝言ロスや対応遅延を防止します。 クラウドPBXを活用し、在宅・外出先からでも内線転送を実現。 ・自動音声ガイダンス(IVR)で、部署や担当者への振り分けを効率化。
3. 非効率な業務フローを見直す
入電の多い時間帯・問い合わせ内容・担当部署を分析し、 「どの業務が電話を発生させているのか」を明確化します。 分析結果に基づき、FAQ強化・手続きのオンライン化など、電話の根本原因を減らす仕組みを導入します。
4. 効率化システムを導入する
電話対応を自動化・効率化するためには、クラウドサービスやツールの導入が不可欠です。
・コミュニケーションプラットフォーム:社内外の通話・チャット・履歴を一元化するツール ・IVR(自動音声応答):問い合わせ内容に応じて自動で担当部署へ振り分けるツール ・クラウドPBX:外出先・在宅でも代表番号で着信・発信が可能になるツール ・アウトソーシング・BPO:一次受付を外部委託して、自社社員の稼働を軽減
これらを組み合わせることで、「人が対応すべき電話」だけを絞り込む運用が実現します。
5. 電話以外の連絡手段を増やす
顧客が自分で情報を確認できるように、FAQサイト・チャットボット・問い合わせフォームを整備します。 これにより、「簡単な質問の電話」が減り、オペレーターは付加価値の高い対応に集中できます。
6. 問い合わせ削減ツールを導入する
FAQシステム ・チャットボット ・DAP(デジタルアダプションプラットフォーム)といったツール・システムを連携させることで、よくある質問や手続き案内を自動化し、入電数を削減します。特にチャットボットは24時間稼働できるため、営業時間外対応の補完にも有効です。
電話業務効率化に役立つ主要ツール

電話対応を効率化するには、テクノロジーの導入が不可欠です。ここでは、電話業務の生産性向上や属人化の防止に役立つ主要ツールを紹介します。それぞれの特徴や活用シーンを理解し、自社の課題に合わせて組み合わせることがポイントです。
クラウドPBX
クラウドPBXとは、従来オフィス内に設置していた電話交換機(PBX)の機能をクラウド上で提供するシステムです。インターネット環境さえあれば、社内・在宅・外出先からでも同じ代表番号で着信・発信が可能になります。
・通話履歴・録音データ・内線番号などをクラウドで一元管理できる ・社員のスマートフォンやPCを内線化できるため、外出時の折り返し対応が不要 ・録音データを共有することで、伝達・共有ミスの防止やクレーム対応の精度向上が期待できる
テレワークや多拠点オフィスにも対応できるため、中小企業から大規模コールセンターまで幅広く導入が進んでいます。
IVR(自動音声応答システム)
IVR(Interactive Voice Response)は、顧客が音声ガイダンスに従って番号を入力し、問い合わせ内容に応じて最適な担当者・部署へ自動的に振り分ける仕組みです。
「製品に関する問い合わせ」「請求・契約に関する問い合わせ」といった分岐設定が可能になり、入電の集中を分散し、オペレーターの対応効率が向上します。FAQ対応や自動音声案内を組み合わせれば、一次対応の自動化も可能です。 問い合わせ件数が多い企業・コールセンターでは、待ち時間短縮と応答率改善に大きく貢献します。
チャットツール
社内外のコミュニケーションを電話中心からチャットへ移行することで、確認や共有のスピードが飛躍的に向上します。
そのほか、「社内の簡単な確認・報告をチャット化し、電話の回数を削減」「ファイル共有・タスク連携なども一元管理できる」「メッセージ履歴が残るため、情報の漏れ・重複を防止」などの効果も期待できます。
代表的なツールとしては、「Microsoft Teams」「Slack」「Chatwork」などがあります。これらを導入することで、電話発生率を3〜5割削減できるケースもあります。
FAQシステム
FAQシステムは、顧客から寄せられる問い合わせ内容をWeb上に整理し、自己解決を促すためのナレッジベースです。
「営業時間」「返品方法」「ログインできない」などの質問を掲載・更新でき、社内の問い合わせ対応時間を削減し、顧客満足度も向上期待できます。検索機能・カテゴリ分類を強化することで、必要な情報にすぐアクセスすることも可能です。
さらに、チャットボットやCRMと連携することで、問い合わせ履歴を蓄積・分析し、FAQの精度向上にもつなげられます。
チャットボット
AIを活用したチャットボットは、WebサイトやLINE公式アカウントなどで、顧客の質問に自動応答するシステムです。
チャットボットを導入することで、24時間365日稼働し、営業時間外の問い合わせにも対応可能になります。定型質問(例:料金・納期・操作方法)をチャットボットによる自動処理にすることで、人的対応を削減することが可能です。
また、FAQ・CRMと連携することで、顧客情報をもとにパーソナライズされた回答を提供することもできます。チャットボットを導入することで、一次対応を自動化し、オペレーターは複雑な案件やクレーム対応に集中できるようになります。
電話代行サービス(アウトソーシング・BPO)
電話代行サービスは、繁忙期や小規模オフィスにおける受電業務を外部委託するサービスです。専門のオペレーターが一次受付を行い、内容をメールやチャットで報告してくれます。このようなアウトソーシング・BPOサービスを利用するメリットとしては以下があります。
・営業時間外・休日の対応も柔軟に可能 ・小規模企業や個人事業主でも導入しやすい低コストプランが多い ・顧客対応を外部委託することで、社員はコア業務に集中できる
また、コールセンター代行業者の中には、CRM連携やスクリプト対応、リード獲得支援まで行うBPOサービスもあります。社内の電話対応負担を大幅に削減したい企業に最適です。
電話対応効率化の具体策と成功事例

電話業務の効率化は、単なる「人員削減」ではなく、生産性と顧客満足度を両立させるための仕組みづくりです。ここでは、具体的な改善策と実際の成功事例を紹介します。
電話対応の効率化の具体例
企業の電話対応が非効率になる原因は、伝達・対応・情報共有の3点に集約されます。それぞれの課題に対して、以下のような具体的な改善策が有効です。
伝言に時間がかかる場合
クラウドPBX/スマホ内線PBXを導入し、外出先でも会社番号で受発信可能にします。在宅勤務や営業外出中でも代表番号で通話でき、折り返し対応の遅延を防止します。
また、チャットツールでリアルタイムに伝達し、伝言ミスを防ぐ方法も考えられます。SlackやTeamsなどの社内チャットを使い、通話内容・要点を即時共有。紙メモや口頭伝達による「聞き間違い」「連絡漏れ」を防げます。
問い合わせ管理システムで履歴を可視化し、対応漏れを防止するのも効果的です。通話内容や対応履歴をCRMに自動記録することで、引き継ぎやフォロー対応もスムーズになります。
入電数が多く、電話対応時間が膨大な場合
入電が多すぎる場合は、FAQシステムを設置し、よくある質問でセルフ解決を促しましょう。「営業時間」「料金」「手続き方法」などの定型質問をWebで公開することで、電話件数が削減できます。
また、チャットボットを導入して、24時間自動応答を実現する方法もあります。営業時間外の問い合わせを自動対応にすることで、翌日の受電負担を軽減できます。
IVR(音声ガイダンス)で部署振り分けを自動化し、顧客の待機時間を短縮する方法もあります。「1:契約関連」「2:修理・サポート」などと自動分岐することで、オペレーターが適切な案件に集中できます。
これらを組み合わせることで、「電話を減らす」「つながるまでを短くする」「対応を早く終える」という3方向の効率化が実現します。
電話業務効率化の成功事例
最後に電話業務効率化の成功事例を紹介します。
事例1:医療機関・クリニックのケース
地域密着型のクリニックでは、診療予約やキャンセル、診療時間の確認などの電話が集中し、1日あたりの受電件数が膨大になっていました。特に、午前診療前後や休診日前には回線がパンク状態となり、 「電話がつながらない」「折り返しが遅い」といったクレームが発生。受付スタッフは常に電話対応に追われ、窓口対応や電子カルテ入力、レセプト処理などの本来業務が滞るという課題を抱えていました。
【対応】 FAQシステムとIVR(自動音声応答)を組み合わせて導入。FAQには「診療時間」「予約方法」「休診日」「予防接種の受付状況」など、問い合わせの多い内容をあらかじめWebサイトに掲載しました。 また、電話では「1:予約」「2:診療内容」「3:その他」といった音声ガイダンスで自動分岐し、必要に応じてスタッフへの転送も最適化しました。
【結果】 電話応対時間を約50%削減。受付スタッフが手を止めずにカルテ入力や窓口対応を行えるようになり、 業務効率と患者対応の質が両立しました。また、FAQ利用率が高まり、営業時間外の問い合わせも減少。患者からは「電話がつながりやすくなった」「対応がスムーズ」といったポジティブな声が増え、満足度向上とクレーム減少の双方を実現しました。
事例2:自動車販売店・カーディーラーのケース
営業担当者が顧客訪問や試乗対応などで外出している時間が長く、代表電話に問い合わせが入っても即時に対応できない状況が頻発していました。その結果、「営業担当からの折り返しが遅い」「商談のタイミングを逃した」といった声が増加。顧客満足度や成約率の低下、商談機会の損失が深刻な課題となっていました。
【対応】 クラウドPBXを導入し、代表番号をスマートフォン内線化。外出中の営業担当も会社番号で着信・発信できるようにしました。加えて、通話録音機能や着信履歴の共有により、誰がどの顧客からの電話を受けたかを可視化。必要に応じてチャットツールと連携し、即座に情報共有できる体制を整備しました。
【結果】 社外からでも代表番号で対応できるようになり、顧客へのレスポンスが平均30分→5分に短縮。不在時の機会損失が激減し、月間受注率が15%アップ。また、録音・履歴共有により、上司の同行支援や教育フィードバックも容易になり、営業組織全体の対応品質が底上げされました。
事例3:IT企業(SaaS事業者)のケース
自社提供のSaaSサービスに関する問い合わせの約7割が「初期設定」「ログイン方法」「操作手順」といった定型的な内容でした。このため、サポートチームが同様の質問対応に追われ、本来注力すべきシステム障害対応やアップセル提案にリソースを割けない状況に。結果として、顧客対応の遅れやCS(顧客満足度)低下が課題となっていました。
【対応】 チャットボットとテックタッチ(DAP:デジタルアダプションプラットフォーム)を組み合わせて導入。チャットボットがFAQと連動し、基本的な操作質問に自動回答。さらに、DAPを活用して、アプリ画面上にガイドを表示し、ユーザー自身がステップごとに設定作業を進められるようにしました。また、問い合わせデータをCRMと連携し、よくある質問を定期的にアップデート。
【結果】 問い合わせ対応時間を約80%短縮。サポート担当者が高度なトラブルシューティングや顧客分析に集中できるようになりました。また、ユーザーが自力で問題を解決できるようになったことで、「サポート依存度の低下」と「顧客満足度の向上」を同時に実現。利用継続率(リテンション)が向上し、顧客1社あたりの年間契約更新率が90%を突破しました。
まとめ
電話業務の効率化は、単なる「自動化」ではなく、顧客満足と従業員負荷のバランスを最適化する仕組みづくりです。
クラウドPBXやIVRなどの導入による入電制御、FAQやチャットボットによる自己解決支援を組み合わせることで、企業規模を問わず大きな効果が期待できます。
特に近年では、「電話を減らすこと=悪」ではなく、「電話を最小限にして最適な接点を作ること=価値」へと変化しています。自社の課題と顧客動線を分析し、段階的にデジタルツールを導入することが、持続的な業務改善の第一歩です。

ProCX編集部
NTTマーケティングアクトProCX