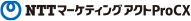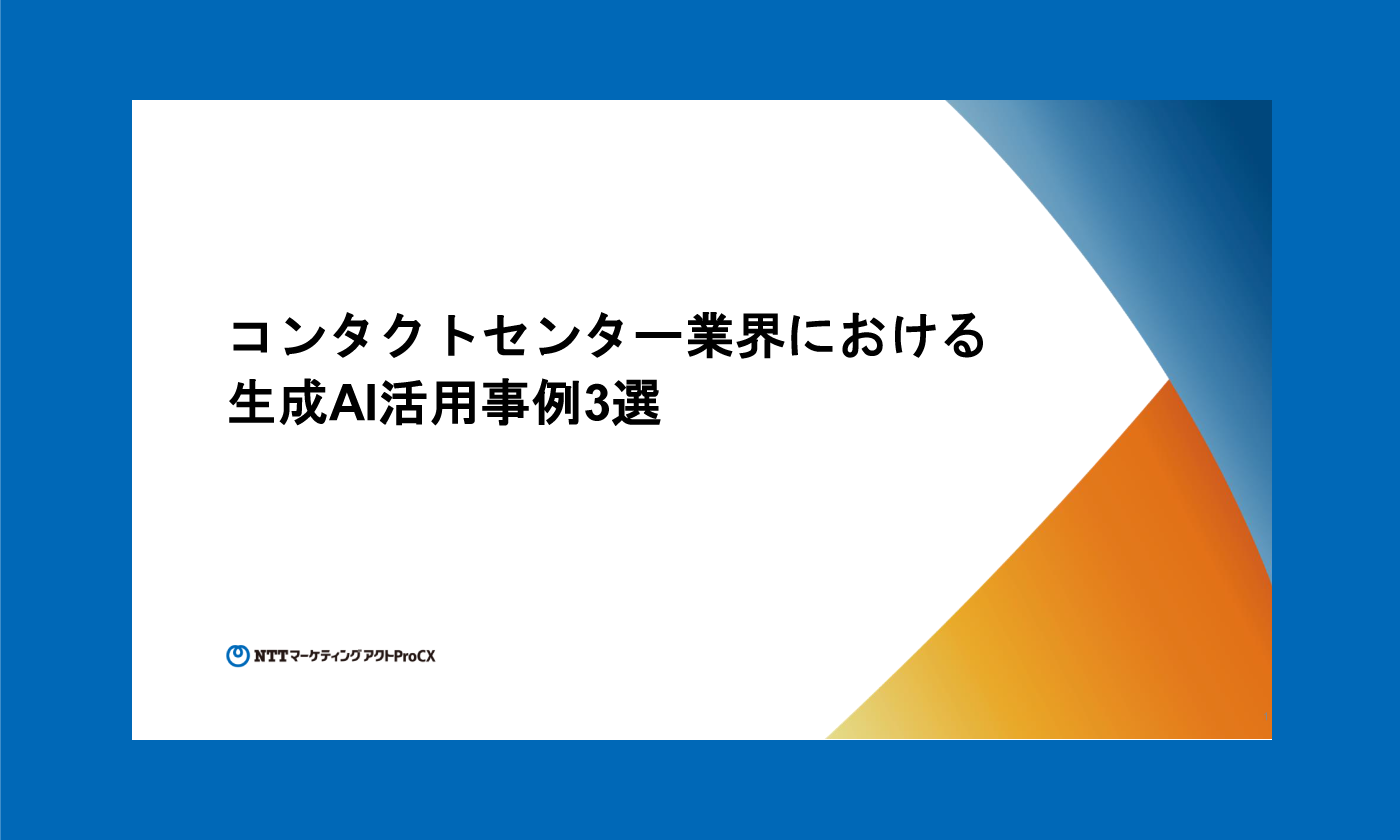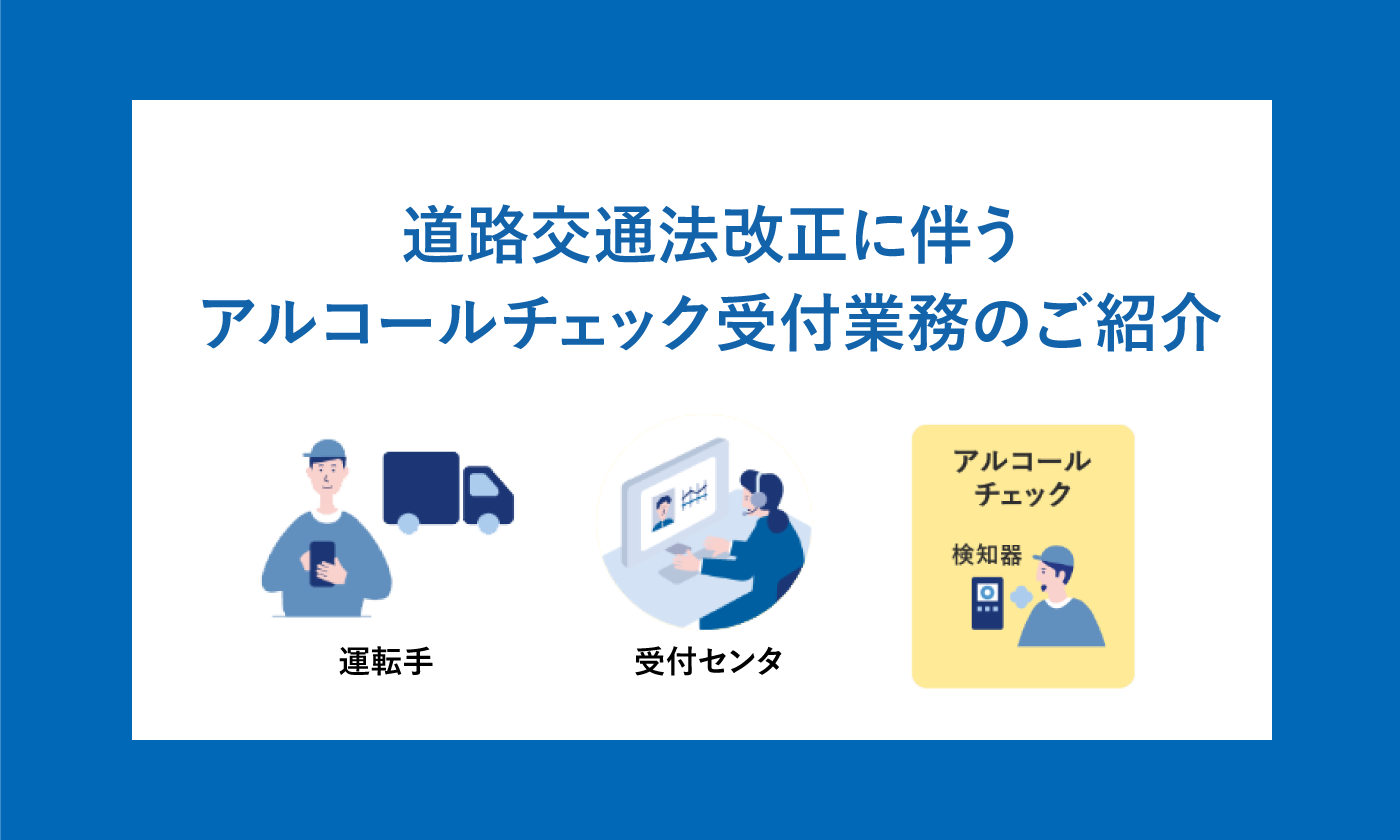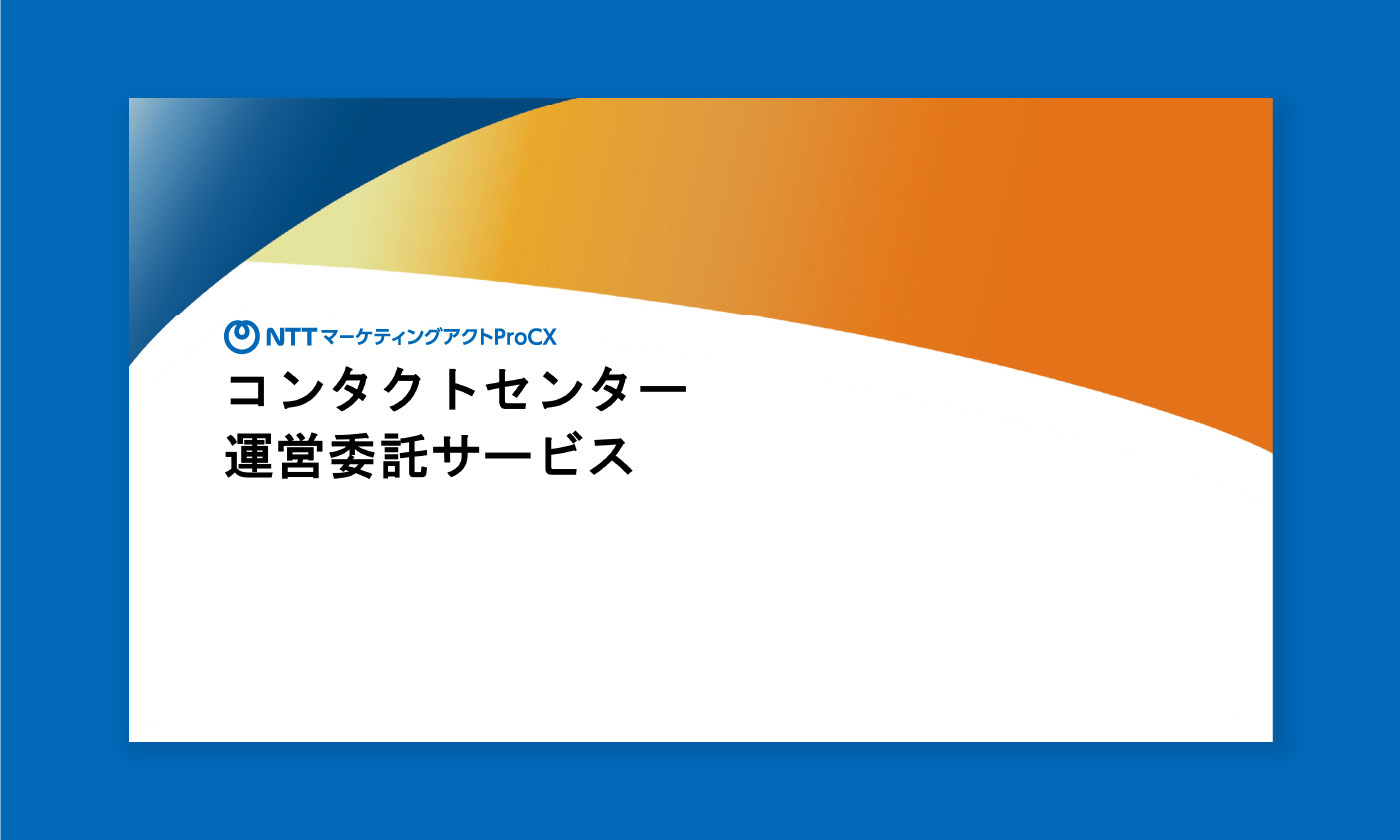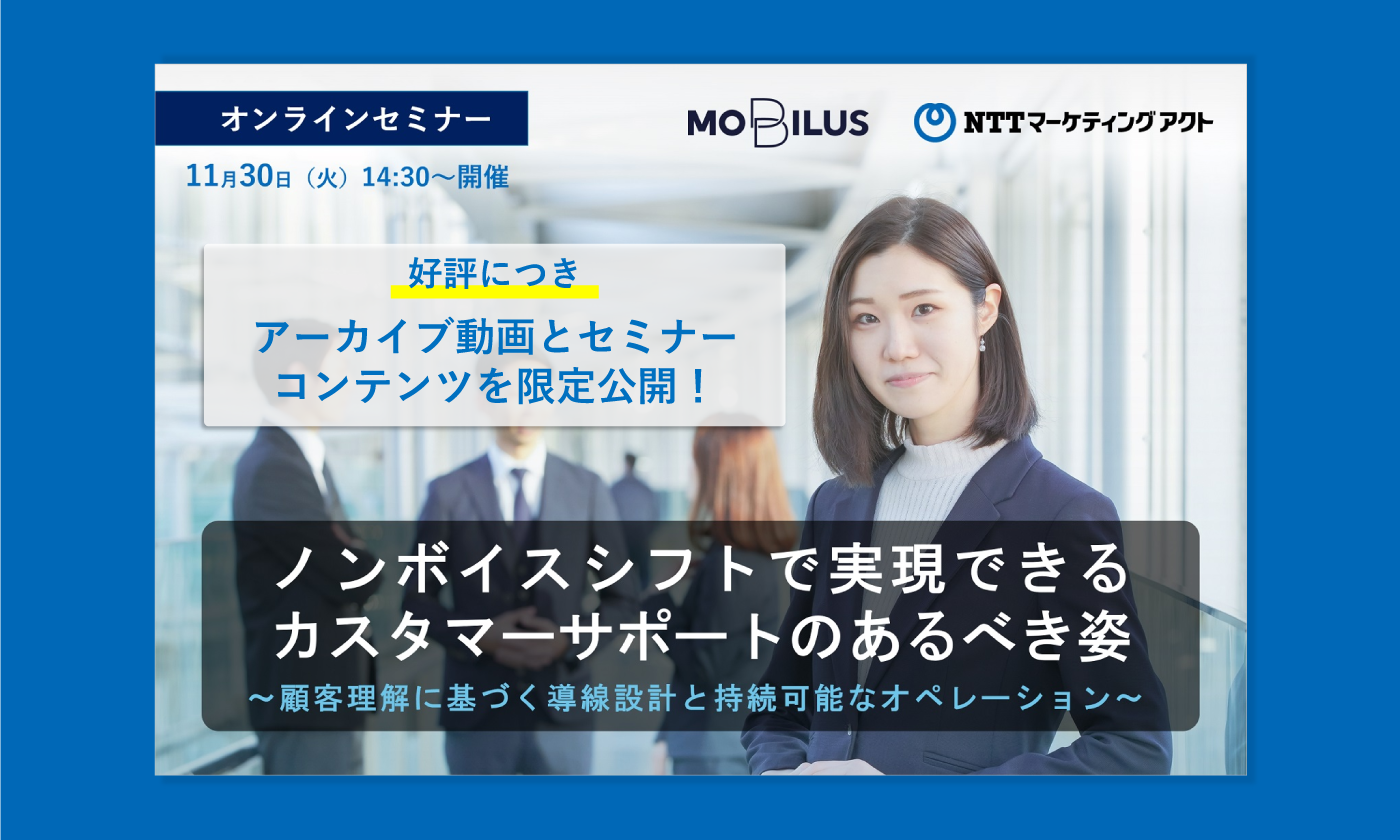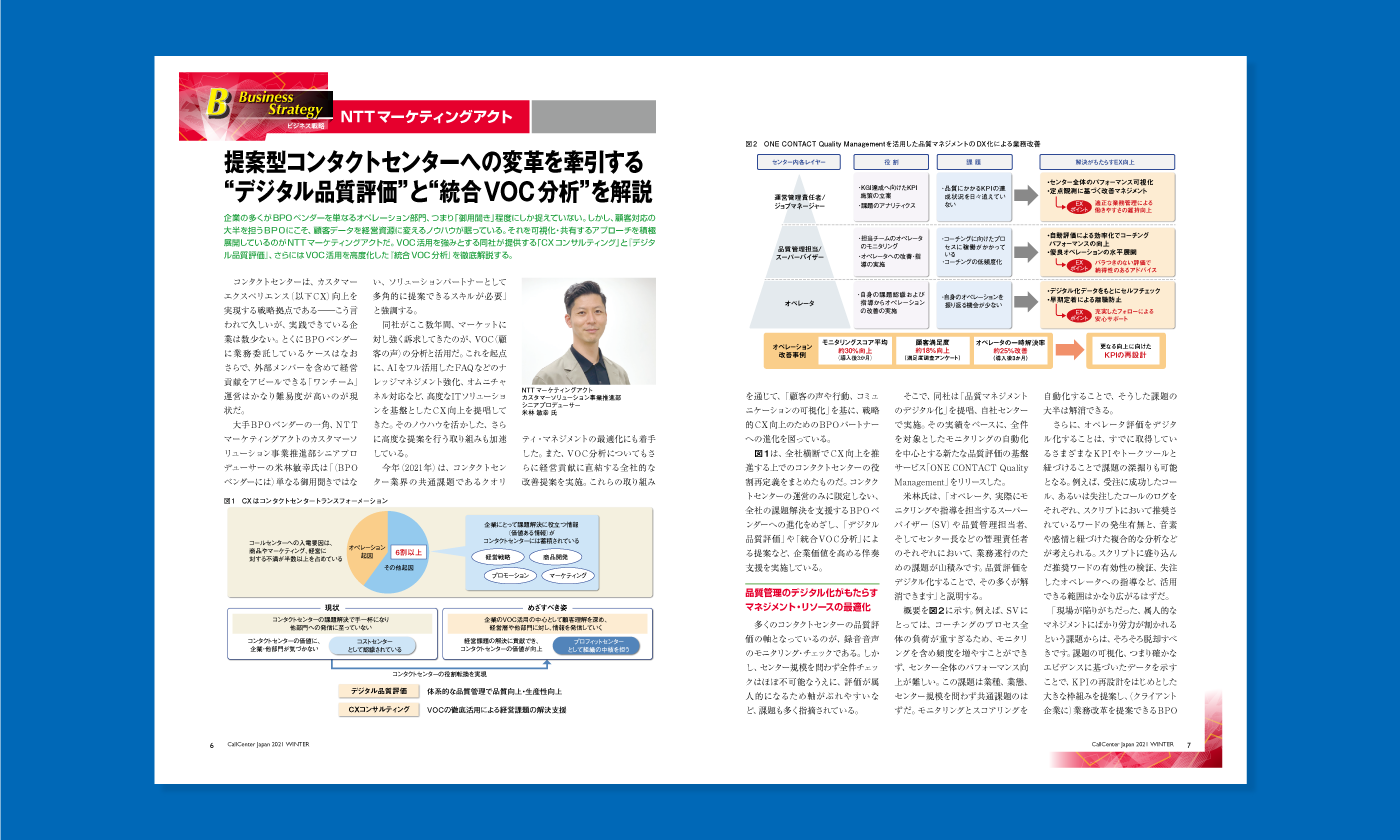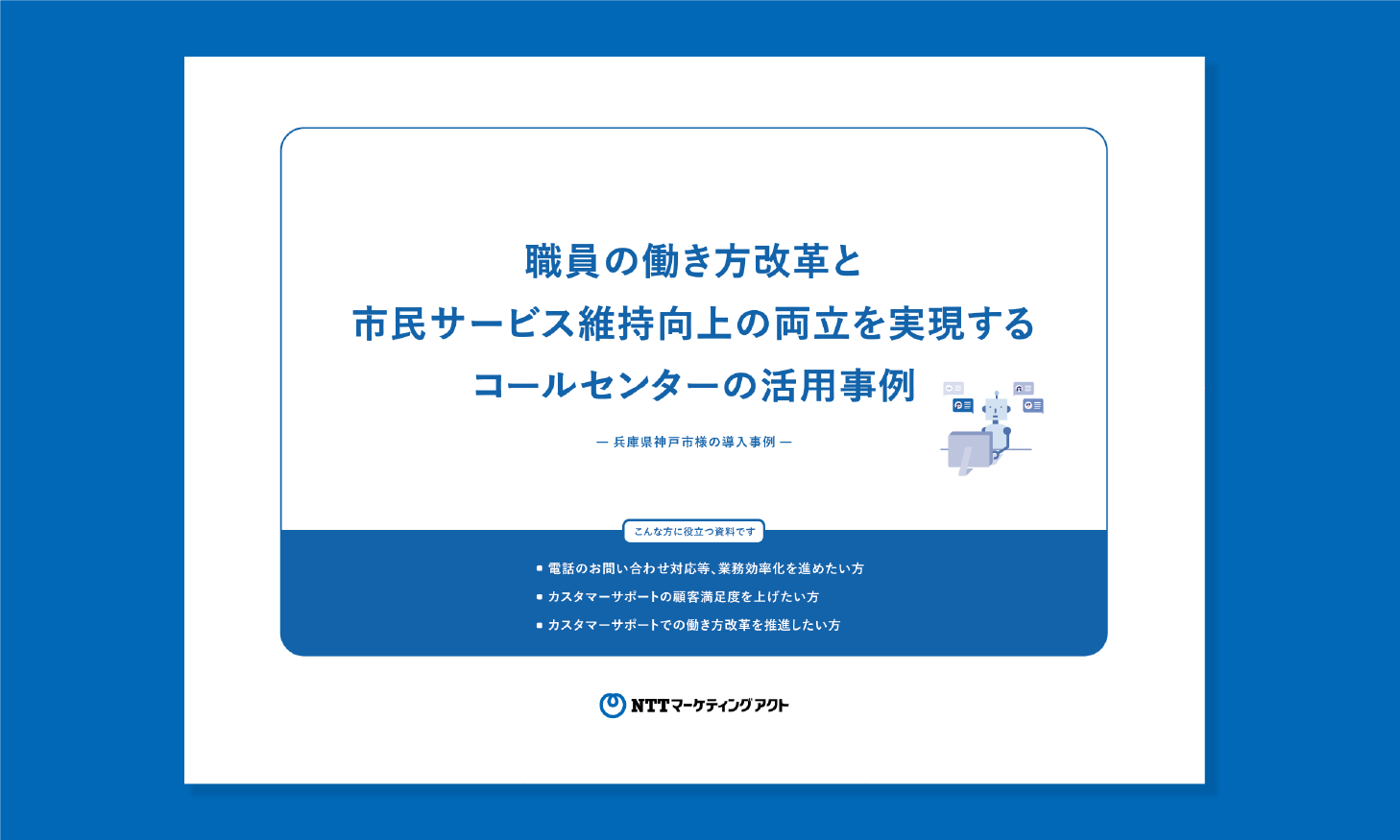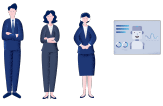コンタクトセンター
コールセンターの音声認識とは?機能や効果、導入のステップを解説
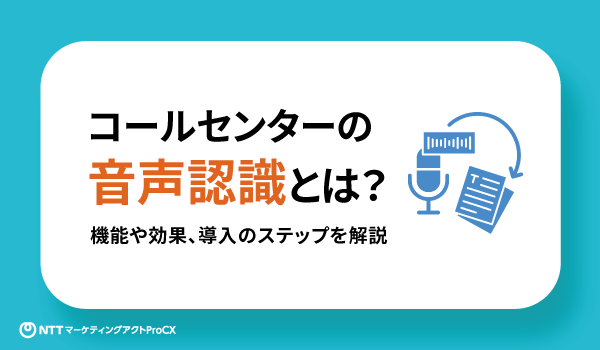
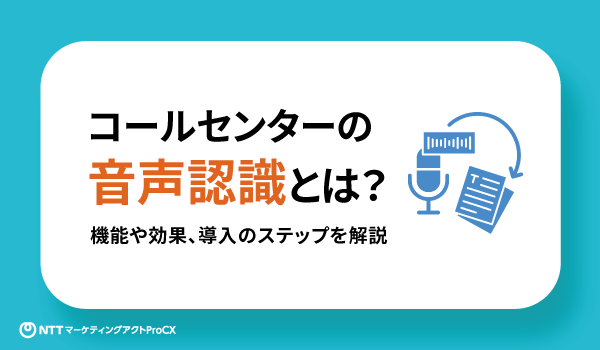

コールセンターでは日々膨大な通話が行われており、その内容を正確に記録・分析することは顧客満足度や業務品質を高める上で欠かせません。
従来はオペレーターが手作業で通話内容を記録していましたが、音声認識技術を活用すれば自動で文字起こしや要約が可能です。
リアルタイムで会話を解析し、品質管理やナレッジ活用を支援することで、業務効率と顧客対応の質を同時に向上させることができます。この記事では、コールセンターにおける音声認識の仕組みと導入メリットを詳しくご紹介します。
音声認識とは?導入のメリットも解説

まずは、コールセンターにおける音声認識の概要やメリットについてご紹介します。
コールセンターでの音声認識とは
コールセンター向けの音声認識は、通話音声を自動でテキスト化・解析する技術を指します。「自動文字起こし・自動要約」「キーワード抽出・NGワード検知・感情推定」「FAQ/ナレッジ連携」などの機能を活用することで、オペレーターは通話対応に集中しつつ、正確な記録と品質管理を自動的に実現できます。
音声認識の導入メリットは?
音声認識の導入メリットとしては以下があります。
1. ACW(After Call Work)短縮と後処理自動化 通話後に行う対応履歴の記録や要約作業を自動化できるため、後処理時間を大幅に削減できます。 オペレーターは次の通話対応へスムーズに移行でき、運用コストや現場の負荷も低減します。
2. 会話の“可視化”による属人化解消 音声認識で全通話をテキスト化すると、すべての会話を可視化して共有可能になります。特定のオペレーターだけが持つ対応ノウハウに頼らず、誰でも同じ情報を活用できるため、品質の底上げと教育効率化が期待できます。
3. 記録の完全保存でコンプライアンス強化 通話を全録音しテキスト化しておけば、言った言わないのトラブル防止や、法令・社内規程の遵守強化にも有効です。監査や品質評価にも活用でき、金融・保険・医療など規制が厳しい業界でも安心して運用できます。
コールセンターに音声認識を導入すれば、記録作成の効率化、品質向上、コンプライアンス強化といった多くのメリットが得られます。次のステップとしては、自社業務に合った音声認識ツールを選定し、CRMやナレッジシステムと連携させることが、導入効果を最大化するポイントです。
音声認識の主な機能とは?

コールセンターにおける音声認識は、単なる文字起こしにとどまらず、顧客対応の品質向上や業務効率化を支える多彩な機能を備えています。ここでは、代表的な4つの機能を詳しく紹介します。
文字起こし・要約・キーワード抽出
音声認識の基本であり最も活用される機能です。 ・会話をリアルタイムにテキスト化し、通話後の記録作成を自動化します。
人名や商品名など固有名詞を事前に登録でき、誤変換を減らして読みやすさをアップ。 「結論」「約束事項」などの要点を自動で抽出・要約することで、重要情報の見落としを防ぎます。
さらに、頻出するキーワードを分析すれば、よくある相談内容の把握やFAQ・案内文の改善にも役立ちます。
気持ちの変化やNG発言の検知
音声認識は単なる文字化だけでなく、顧客の感情分析やリスク検知も可能です。
声の調子(早口・かぶせ・長い沈黙など)を解析し、顧客が不満や不安を抱えているサインをリアルタイムに検知します。オペレーターが言ってはいけない言い回しや禁止ワードを発した場合、自動でアラートを出し、トラブルを未然に防ぐことも可能です。
挨拶・復唱・締めくくりなどの評価観点を自動チェックでき、応対品質の改善や教育にも活用できます。
話者分離と雑音への強さ
コールセンターの環境は必ずしも静かとは限りません。
音声認識は「お客様」と「オペレーター」の話者を自動で識別して分離し、誰が話したかが一目で分かるテキストを生成します。 周囲の雑音や回線ノイズがあっても、できるだけ正確に聞き取る耐性を持つため、忙しい現場でも安心です。
専門用語や略語は事前に辞書登録しておくことで、認識精度をさらに高めることも可能です。
システムとの連携機能
音声認識は、他の業務システムと連携することで真価を発揮します。
電話システムと接続すれば、通話内容やメタ情報が自動的に記録されます。CRM(顧客管理システム)へ自動保存されるため、検索や共有の手間を削減できます。
さらに、表やグラフを作成するBI(ビジネスインテリジェンス)ツールにデータを流し込めば、定例会のレポートや分析資料の作成も効率化できます。
音声認識の具体的な活用方法は?

音声認識は、単なる文字起こしツールにとどまらず、業務効率化・品質管理・ナレッジ活用を包括的にサポートする仕組みです。ここでは、コールセンターで実際に効果を発揮する活用シーンと、最新の技術動向を紹介します。
後処理(ACW)の自動化で、まず“時間のムダ”を減らす
通話後のACW(After Call Work)は、メモ作成や要点整理、CRMへの記録入力など、オペレーターにとって大きな負担となる作業です。
音声認識を活用すれば、会話内容を自動で要約・タグ付けし、CRMに自動反映できるため、手作業を大幅に削減できます。記録の質が均一化され、検索性・再利用性が高まることで、後からの分析やレポート作成もスムーズになります。
結果として、オペレーターは次の通話へスピーディーに移行でき、運用コスト削減と応対効率向上を同時に実現します。
全ての通話を同じ基準で見て、教育やルール整備に活用
従来はサンプリングした通話だけを監査していましたが、音声認識を導入すれば全通話を同じ基準で自動評価できます。
すべての会話が可視化されることで、属人化を減らし、教育や評価を客観的データに基づいて実施可能です。
品質指標や改善点を数値化すれば、マニュアル改定やルール整備の根拠としても活用できます。これにより、オペレーター教育の効率化や応対品質の平準化が進み、CSAT(顧客満足度)の向上につながります。
要約やタグを元に、FAQやマニュアルを定期的に更新
音声認識で自動生成される要約やタグ情報は、FAQやマニュアル改善の貴重な材料になります。
問い合わせが多いテーマや新たなトラブル傾向を素早く把握し、現場で“いま困っていること”をFAQへ迅速に反映できます。
定期的なナレッジ更新により、顧客が自己解決できる範囲も広がり、問い合わせ件数削減にもつながります。
音声認識の最近の傾向は?(生成AIの相乗効果)
近年は音声認識と生成AIを組み合わせた高度な活用が進んでいます。
会話の流れから最適な回答候補を即時提案し、その場でオペレーターを支援。会話全体を自動チェックし、改善すべきトーク内容や不足箇所をフィードバックしてくれます。さらに、通話内容をもとにメールやチャットの返信テンプレートを自動生成でき、オペレーターは微調整だけで済みます。
これらの技術は、業務効率を飛躍的に高めるだけでなく、応対品質の均一化と顧客体験の向上を同時に実現します。
コールセンター向け音声認識機能の選び方は?

音声認識システムは各社さまざまな製品があります。以下のポイントを押さえて選定すれば、導入後に「思った機能がない」「コストが合わない」といったトラブルを防げます。
聞き取りの正しさ・速さ・読みやすさ
まず重視すべきは、文字変換の正確さとスピード、そして表示の見やすさです。
単純に「どれくらい正しく文字になるか」だけでなく、句読点や話者分離の精度も確認しましょう。リアルタイム文字起こしは、1〜2秒以内に画面に反映されるかが目安です。顧客対応中にタイムラグがあると活用しづらくなります。
専門用語や商品名を登録しておく「単語登録機能」や、辞書の更新が簡単に行えるかも事前にチェックすると、導入後のメンテナンス負荷を軽減できます。
セキュリティ面
顧客の個人情報を扱うコールセンターでは、通信・保存の安全性が最優先です。
データ通信や保存時に暗号化が施されているか、アクセス権限の細かい設定や保存期間の指定ができるかを確認しましょう。
録音データの取り扱いルール、誰がどの範囲まで閲覧できるのか、保存期限はどれくらいかなども事前に取り決めておくと安心です。
つながりやすさ・使い心地・サポート
音声認識は他システムと連携してこそ効果を発揮します。
電話システム、CRM、レポート作成ツールなどと標準機能で連携できるかを確認しましょう。オペレーターが使いやすい直感的な画面設計(ハイライト表示、検索機能、教育用メモなど)も重要です。
導入後も一緒に改善をサポートしてくれるベンダーの体制や対応スピードも、長期運用では大きな安心材料になります。
自社に合ったプランかどうか
最後に、料金体系が自社の利用スタイルに合っているかを確認します。
「従量課金(使った分だけ課金)」か「人数ごとの固定課金」かなど、料金の仕組みを理解しておきましょう。
お試しプランの有無や最低利用期間、利用を増やしたときの価格変動も把握しておくと安心です。
問い合わせ窓口やサポート対応時間、日本語でのサポート可否も、現場でトラブルが起きた際の重要な判断材料になります。
コールセンターに音声認識を導入する方法

音声認識をコールセンターに導入することで、記録業務の効率化や品質管理の高度化など多くの効果が期待できます。ただし、システムを入れるだけでは成果は出ません。以下のステップを参考に、自社に最適な導入プロセスを描きましょう。
1. 目的と対象を決める
まずは導入の目的と対象業務を明確に設定します。「ACW(後処理)を平均○分短縮」「顧客満足度を○点向上」など、数値目標を具体的に掲げることで効果測定がしやすくなります。
2. スモールスタートからはじめる
いきなり全社展開するのではなく、小規模テストで段階的に導入しましょう。1~2か月のテスト運用で、精度や使い勝手を現場目線で確認します。テストで得られた成功パターンをテンプレート化し、他の班や拠点に横展開することで、全体への定着を無理なく進められます。
3. 運用のコツ
導入後は、継続的な改善とメンテナンスが欠かせません。
毎月、誤変換が多い単語を洗い出し、辞書を少しずつブラッシュアップして精度を維持します。自動評価のスコアだけでなく、人の目によるチェックを併用することで、記録の品質と正確さを担保できるでしょう。
また、生成された要約や優れた通話事例を教育用教材として活用すれば、新人オペレーターの成長も早くなります。
4. 費用対効果の確認
最後に、投資がどの程度効果を生んでいるか定量的に評価します。「短縮できた時間 × 処理件数 × 人件費」で削減した工数を金額換算し、時間的メリットを可視化します。
また、クレーム減少や満足度向上は、再購入率や解約防止率の数値として補助的に評価します。システム利用料や教育コストなども含め、黒字化の見込み時期を明確化することで、経営層への説明や次の投資判断がしやすくなります。
音声認識導入は、「目的設定 → 小規模テスト → 運用改善 → 費用対効果の測定」という4段階のプロセスが成功の鍵です。
段階的な導入と継続的なチューニングを行えば、後処理の効率化だけでなく、品質向上や教育コスト削減など多方面の成果を着実に得られます。
まとめ
コールセンターに音声認識を導入すると、通話の自動文字起こしや要約、キーワード抽出、感情分析などが可能になり、記録作成や品質管理を効率化できます。音声認識の導入を検討している方は、ぜひ今回ご紹介した内容を参考にしてみてください。
また、リソースや工数などの関係で導入が難しいと感じる場合は、アウトソーシング・BPOを有効活用する方法もあります。音声認識のノウハウを含めたコールセンターのプロに業務を委託できます。さまざまな方法から音声認識の導入を検討しましょう。

ProCX編集部
NTTマーケティングアクトProCX