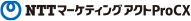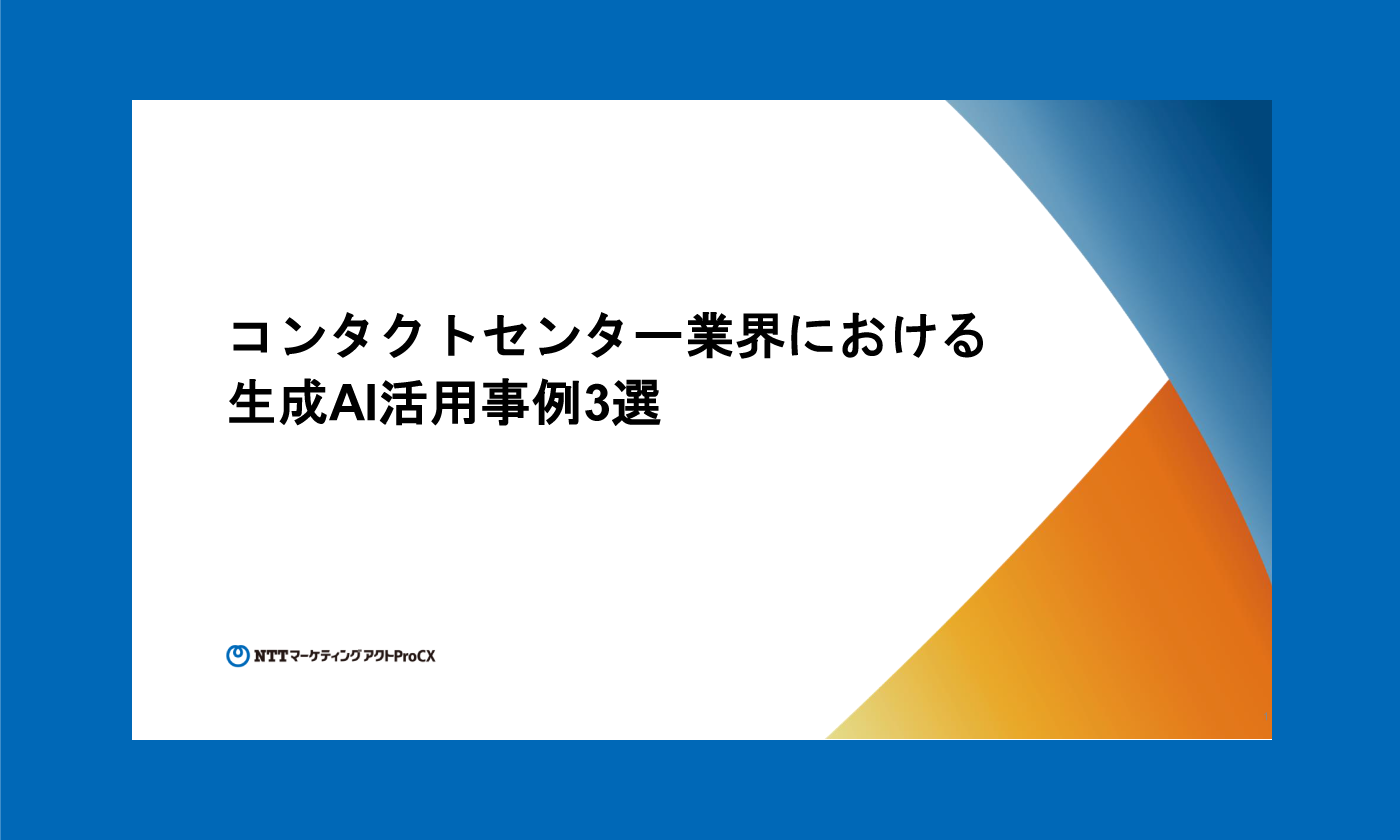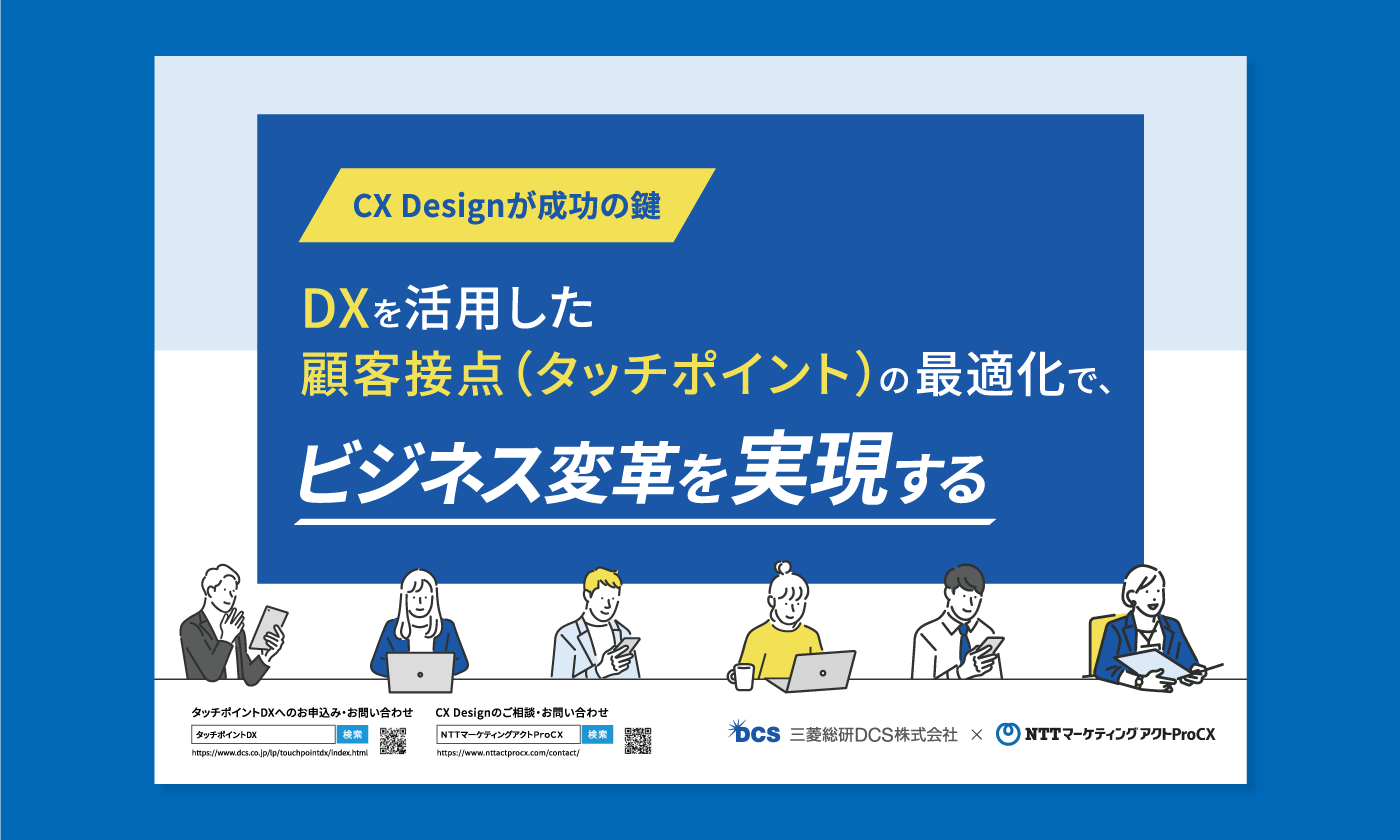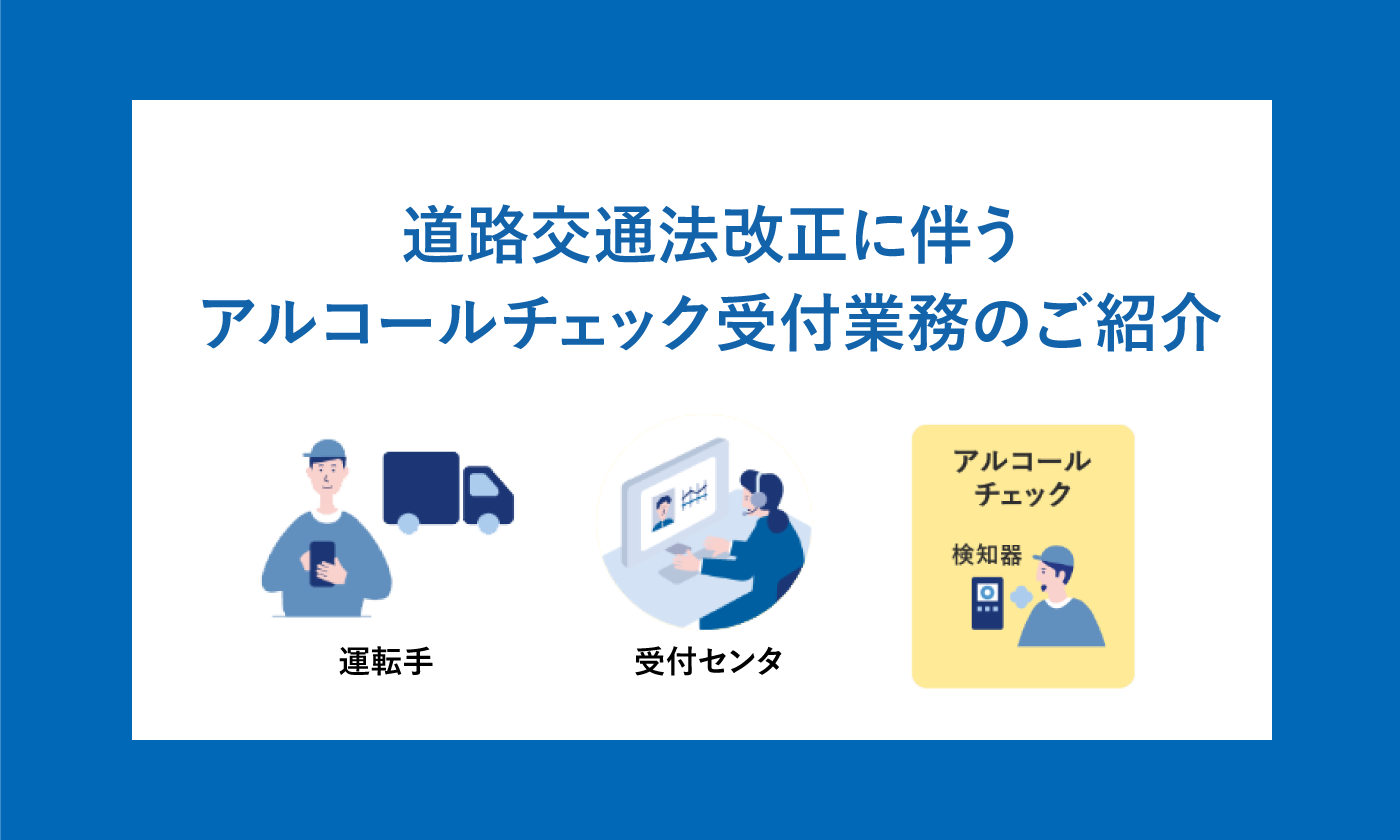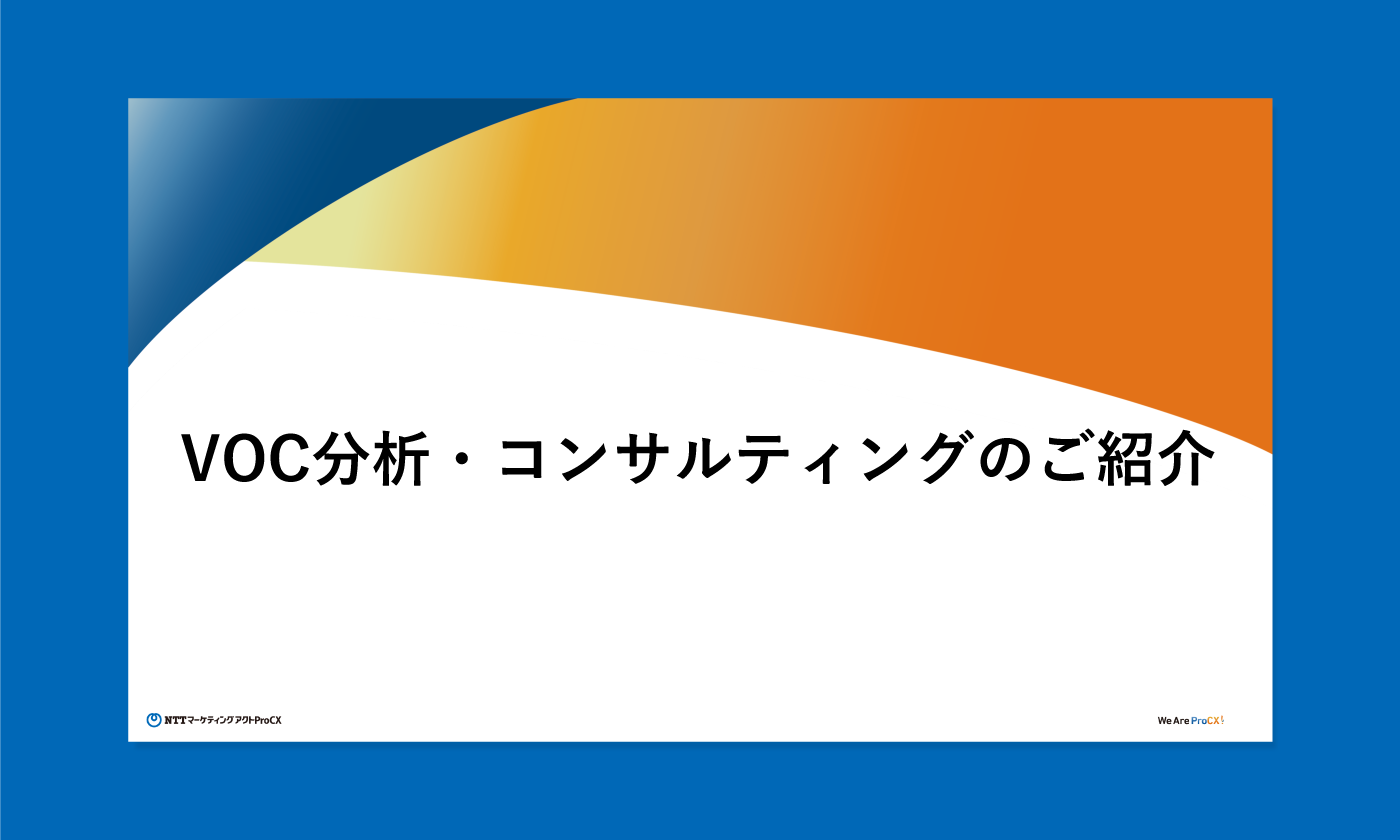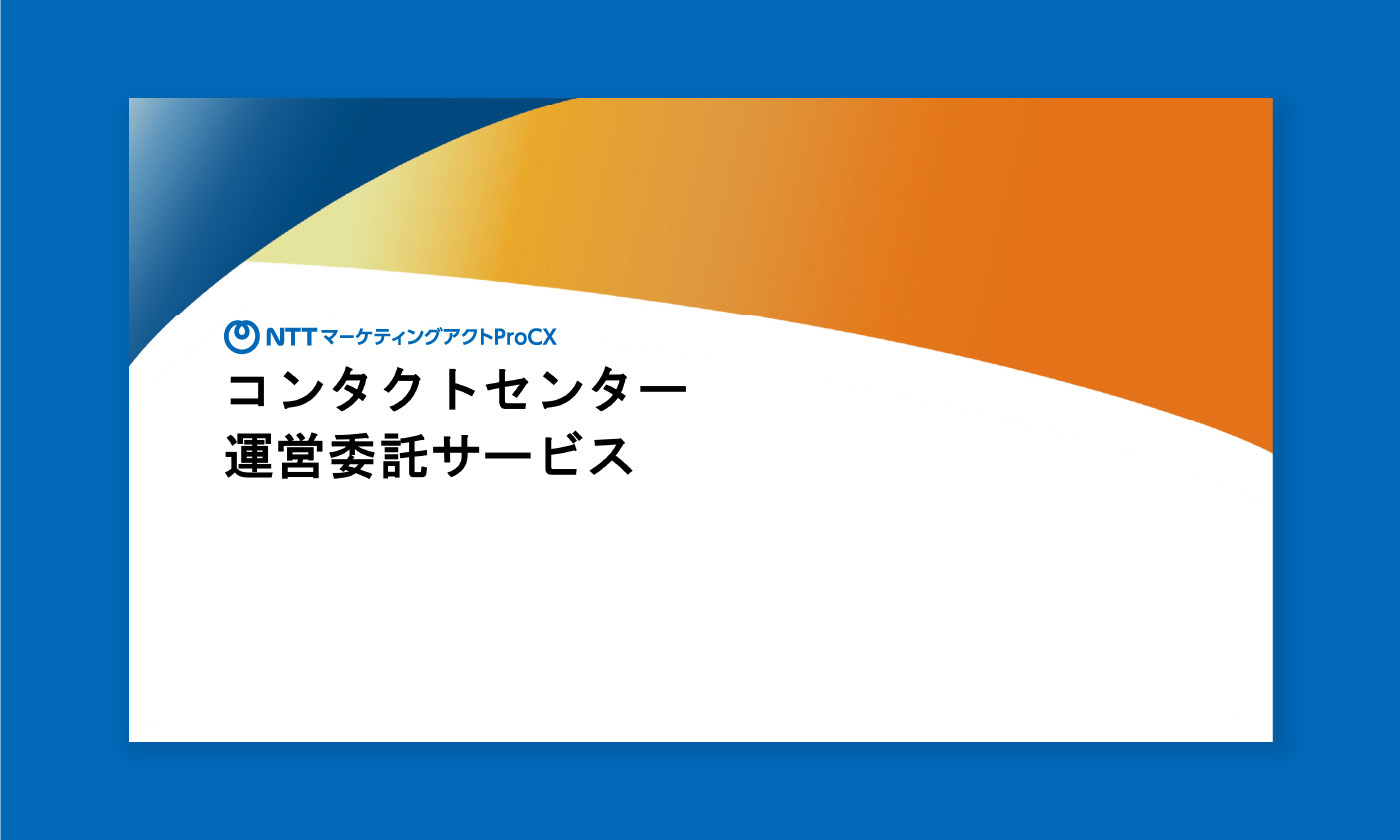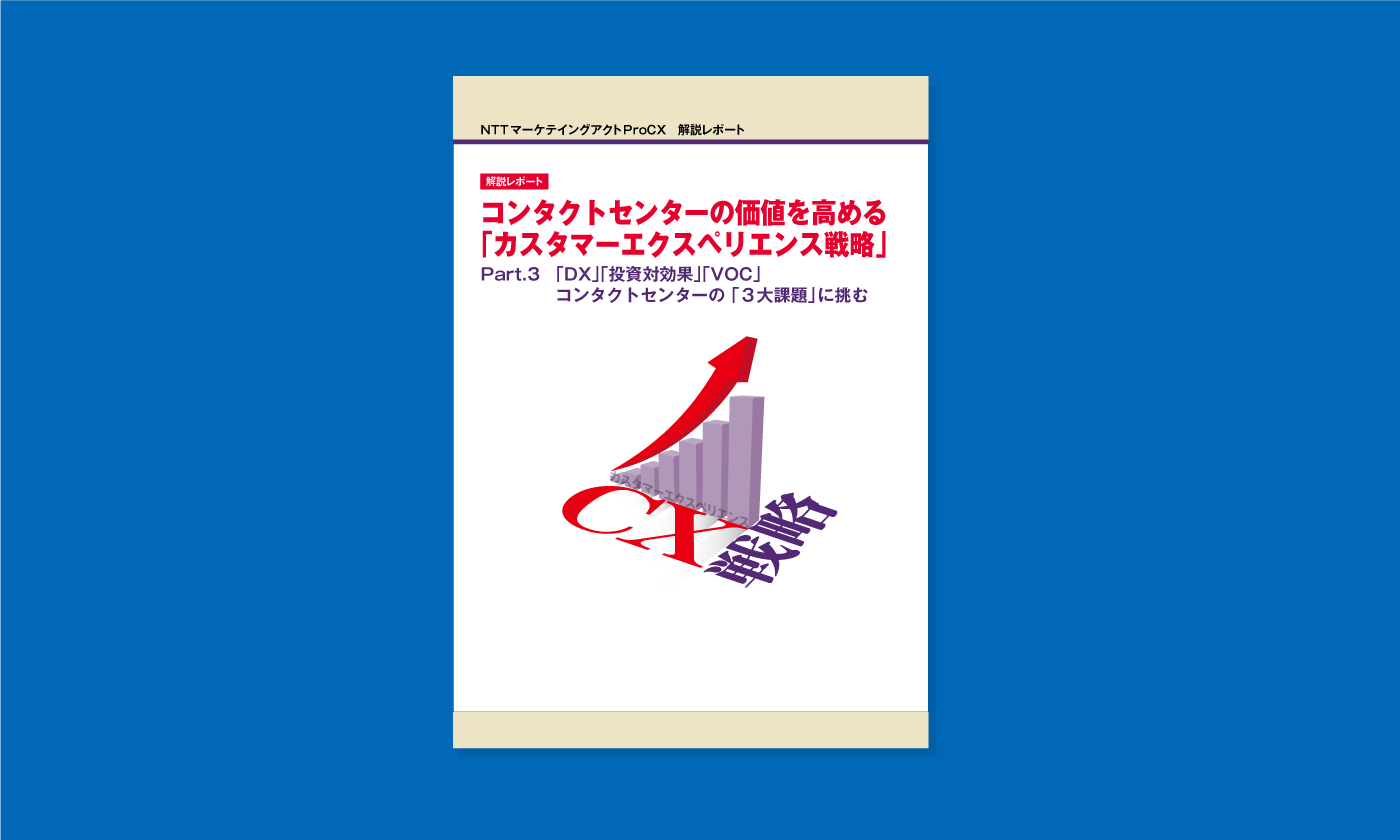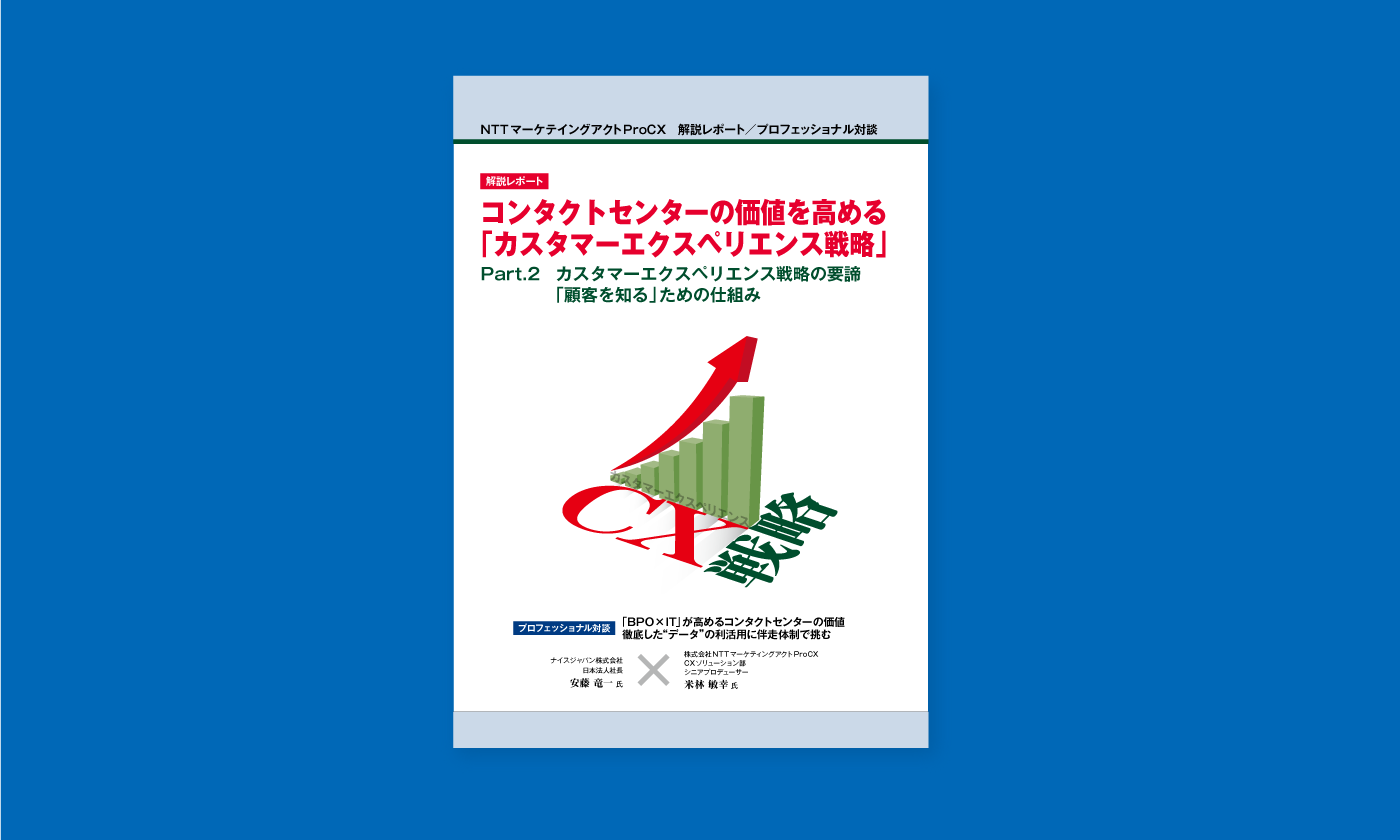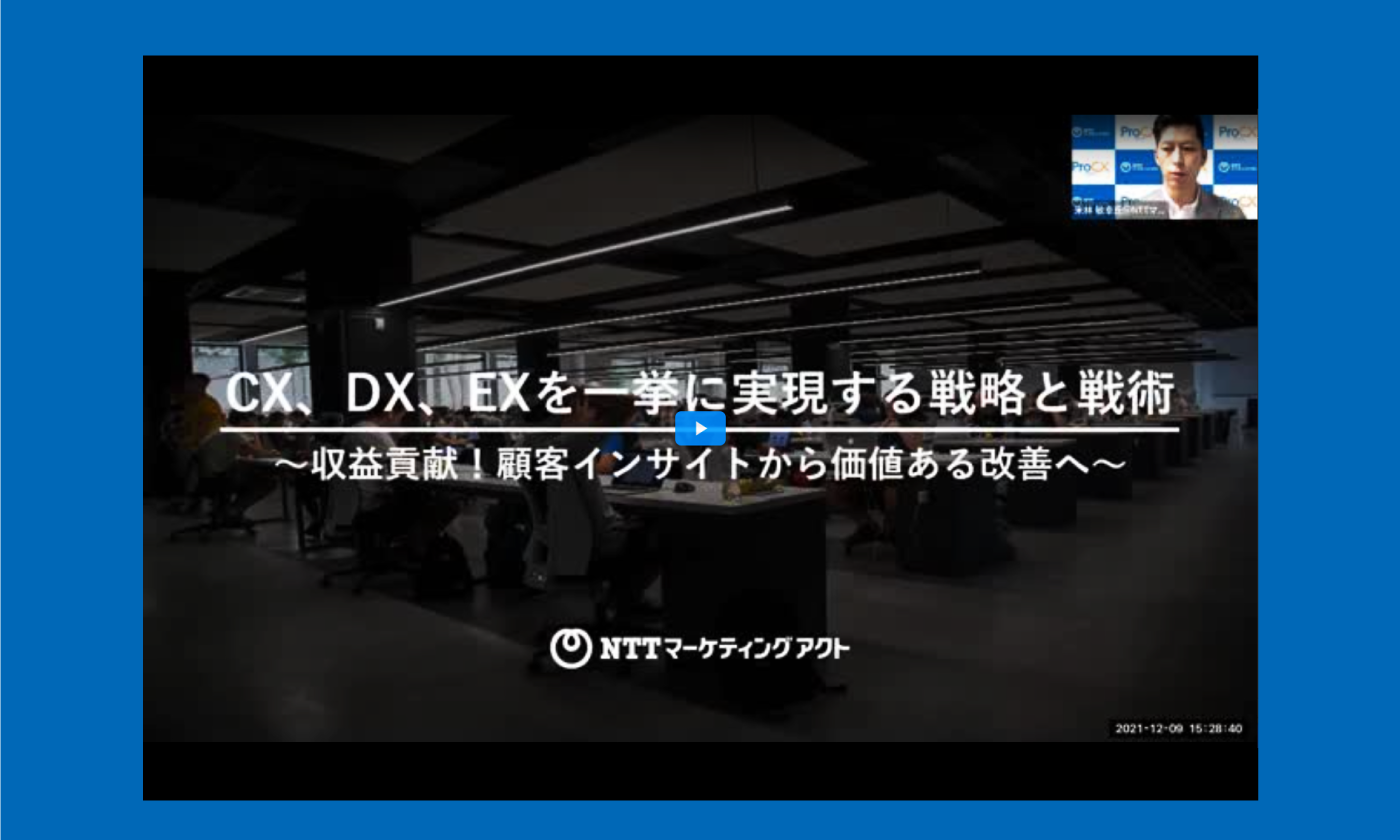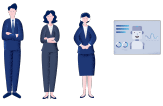コンタクトセンター
コールセンターのクレーム対応のポイントは?原因と対処方法を解説!
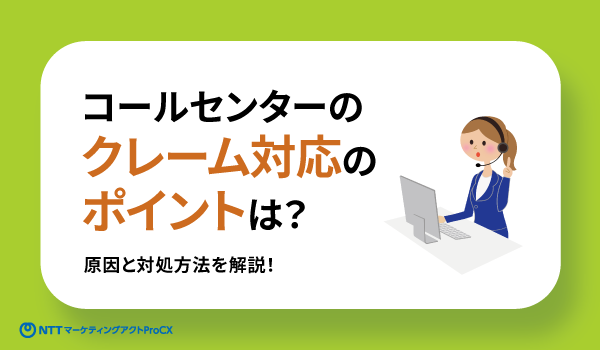
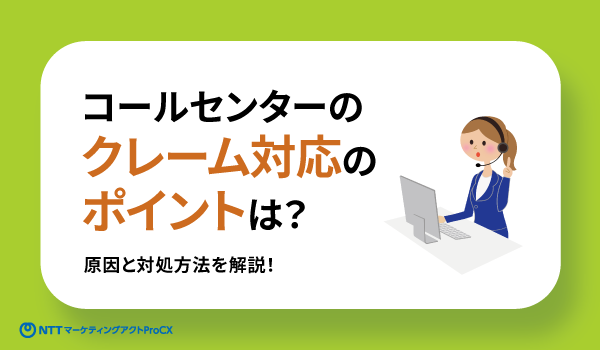

コールセンターのオペレーターは、精神的な負担が大きな仕事のひとつとされていますが、その原因のひとつは「クレーム対応」です。
怒りや不満を持った顧客への対応はストレスや緊張感を伴う業務で、これが原因で離職してしまうオペレーターも少なくありません。
そこで今回は、クレーム対応の原因や対処方法について解説します。
クレーム対応とは?クレームの例は?

まずは、クレーム対応とは何を指すのか?代表的な例にはどのようなものがあるのかなど、クレーム対応の基本についておさらいしておきましょう。
クレーム対応とは?
「クレーム」とは、もともと英語の 「claim(主張・要求・請求)」から派生した和製英語です。英語では必ずしもネガティブな意味ではなく、「保険の請求」や「権利の主張」といった中立的な文脈でも使用されます。
しかし日本においては、「クレーム」という言葉は一般的に商品やサービスに対する不満・怒りを伴った苦情や申し立てを指し、それに対して企業側に何らかの対応(返金・謝罪・改善など)を求める行為として認識されています。
クレームと苦情の違いは?
「クレーム」と「苦情」は似たような意味で使われることが多いですが、厳密には違いがあります。 それぞれの違いとしては以下があります。
・クレーム 商品やサービスの不備により顧客が不利益を被ったと認識し、それに対して返金や交換、謝罪などの具体的な要求(請求)を行う行為です。
・苦情 顧客の不満や怒りの表明が中心で、必ずしも請求行為を伴わない点が特徴です。感情的な訴えや不満表明にとどまるケースもあります。
つまり、「請求行為」があるかどうかが、クレームと苦情を分ける大きなポイントといえるでしょう。
クレームの例は?
クレームにはさまざまなタイプがあり、企業はその性質に応じて適切な対応をとる必要があります。以下に代表的なクレームの例を紹介します。
・間違いの指摘 商品の破損、注文ミス、説明との相違など、事実に基づくミスを指摘されるケースです。
・感情的なクレーム サービスの質や接客態度に対して、強い怒りや不満をぶつけるケースです。
・顧客の勘違いによるもの 商品説明や契約内容を誤解していたことによるクレームです。事実確認と丁寧な説明が必要です。
・謝礼品や補償を求めるクレーム 不満に対して、返金・謝礼品・割引などを要求するケースです。企業の対応方針が問われます。
・暴言や威圧を伴うクレーム 担当者を萎縮させるような暴言・脅迫を含むクレームです。適切な線引きと対応マニュアルが不可欠です。
・クレーマーによる理不尽な要求 過剰な補償や企業の過失ではない内容への執拗な要求など、悪質なクレームです。毅然とした対応が求められます。
このようにクレームには多様なパターンがあり、それぞれに応じた冷静かつ丁寧な対応が、顧客との関係修復と企業の信頼維持につながります。
クレーム対応が発生する原因は?

クレームが発生する原因はさまざまですが、多くの場合、顧客の期待と実際の提供内容とのギャップによって引き起こされます。ここでは代表的な原因を4つの視点から解説します。
接客やオペレーターへの不満
店舗や窓口での接客態度や言葉遣いに対する不満は、クレーム発生の大きな要因となります。
特に、従業員の態度が冷たい、説明が不十分、敬語が使えていないなどの問題があると、顧客は企業全体への不信感を抱きやすくなります。
また、コールセンターでも同様に、対応が雑だったり言葉遣いに配慮がなかったりすると、不満がエスカレートして深刻なクレームに発展することがあります。
対面・非対面を問わず、顧客接点では常に丁寧で誠実な対応が求められます。
商品やサービスへの不満
商品やサービスの品質や内容が期待に達していない場合にも、クレームが発生します。
たとえば「すぐに壊れた」「写真と実物がまったく違う」「予約内容が違っていた」など、不具合・欠陥・手配ミスが原因となるケースは多く見られます。
顧客は代金に見合う価値を求めており、期待を裏切られたと感じた瞬間に不満が高まるため、事前の品質管理や案内ミス防止が重要です。
顧客の勘違い
案内内容を誤って理解してしまった顧客によるクレームも少なくありません。
たとえば「キャンペーンの条件を勘違いしていた」「説明を読み違えていた」など、事実と異なる認識から苦情が寄せられるケースです。
このような場合でも、すぐに否定的な対応を取ると逆効果です。 まずは顧客の話をしっかり聞いて受け止め、徐々に誤解を解くアプローチが有効です。冷静な対応を心がけることで、状況の鎮静化につながります。
悪質なクレーム
まれに、事実に基づかないクレームや過剰な要求を繰り返す、いわゆる「悪質クレーマー」が存在します。
「全額返金しろ」「ただで新しいものを寄こせ」など、正当性のない不当な請求や脅迫的な発言が含まれるケースです。
このような場合、その場しのぎで安易に要求に応じると、さらなる要求や悪評リスクにつながる恐れがあるため、冷静かつ慎重に対応する必要があります。
場合によっては、法的機関や警察への相談も視野に入れ、毅然とした姿勢で対処することが求められます。
このように、クレームは原因ごとに適切な対応方法が異なるため、原因を見極めたうえで冷静かつ丁寧に対応する姿勢が重要です。
コールセンターでのクレーム対応のポイント

コールセンターでは、クレーム対応が業務の一部として避けられない場面も多くあります。顧客との関係を悪化させず、信頼を保つためには、感情に寄り添いながら冷静かつ的確に対応する姿勢が重要です。以下では、対応時に意識すべきポイントを紹介します。
クレーム対応の基本は?
まず大切なのは、お客様の気持ちに寄り添う姿勢を持つことです。
要求をすべて受け入れる必要はありませんが、「気持ちを理解しようとする姿勢」を見せるだけでも、相手の感情が和らぐことがあります。
クレーム対応の目的は「論破」ではなく、お互いに納得できる着地点を探ることです。冷静に対応し、顧客との対話から解決の糸口を見つけましょう。
スピードを意識する
クレーム対応では、迅速さも大きなポイントになります。電話がつながるまでに時間がかかった場合は、接続後にすぐ対応し、一言のお詫びを添えるだけでも印象が大きく変わります。以下のような、待たせたことに配慮する一言が、信頼回復の第一歩になります。
【例】 ・たいへんお待たせしてしまい申し訳ございません ・お時間を頂戴し申し訳ございません
顧客に共感し理解を示す
顧客の話は遮らずに傾聴し、内容を要約することで理解していることを示します。 共感や理解の言葉を挟むことで、顧客は「自分の言いたいことが伝わっている」と感じ、心を開いてくれるようになります。
【例】 ・○○のときに××の不具合が起きるのですね ・現在、▢▢になっているということですね
クレーム内容をしっかり把握する
怒りや不満の背景には、顧客の真の要望が隠れていることもあります。まずは焦らず、話の中から本質を聞き取りましょう。以下のように、問題の本質や目的を明確化することが、スムーズな解決につながります。
【例】 ・冷蔵庫の温度が下がらないので、修理をご希望ですね ・商品の返品をご希望されているということですね
クッション言葉やあいづちで安心感を与える
話を聞いている姿勢を示すためには、適度なあいづちやクッション言葉を挟むことが効果的です。 過度にならないよう注意しながら、安心感を与えましょう。相手に「理解してくれている」という印象を与えることで、怒りが和らぐこともあります。
【例】 ・おっしゃる通りでございます ・誠に申し訳ございません
顧客の要望にできるだけ応える
クレームに対しては、顧客の本当の要望をくみ取り、適切かつ迅速に対応することが重要です。
同じ内容のクレームでも、顧客の期待する対応は異なる場合があります。一律対応ではなく、会話を通じて個別に最適な対応を見つけるようにしましょう。
対応に困る場合は上長に相談する
想定外のクレームや、顧客の怒りが収まらないケースでは、早めに上長に相談することが重要です。経験の浅いオペレーターがマニュアル外の対応を独断で行うと、さらなるトラブルにつながることもあります。「迷ったらすぐに相談する」という姿勢を徹底することで、リスクを最小限に抑えることができます。
ストレスを解消するマネジメントを行う
クレーム対応は精神的負担が大きく、オペレーターが自分を責めてしまうケースも少なくありません。 しかし顧客はあくまで製品やサービスに対して不満を感じているのであり、個人を責めているわけではないことを理解することが大切です。
冷静に「何に対して怒っているのか」を分析し、感情的にならずに対応するよう心がけましょう。また、件数の制限や対応後の休憩時間の確保など、職場としてストレスをためない環境づくりも重要です。
コールセンターにおけるクレーム対応では、スピード・共感・正確な理解・冷静な判断が求められます。オペレーター一人ひとりが顧客対応の質を意識することで、信頼の維持・回復につながります。
クレーム対応時のNGワードは?

クレーム対応時には、事態を悪化させてしまうようなNGワードに注意することが大切です。クレーム対応時に使ってはいけないNGワードについて詳しく解説します。
否定ワード
お客様の言葉を否定するような表現は、たとえ事実であっても避けるべきです。
「話を聞いてもらえない」「自分の主張が軽視された」と感じさせてしまうと、顧客の怒りや不満が一気に高まります。
【言い回し例】 ・お言葉ですが ・そのようなことはないと思うのですが ・何度も申し上げているとおり
これらの言い方は、相手の話を一蹴する印象を与えるため、共感的な聞き方や柔らかい表現への置き換えが求められます。
ネガティブなワード
逆接・反論を含む言葉は、クレーム対応の場面では相手に不快感を与える原因になります。 たとえマニュアルに沿った説明であっても、相手の気持ちを否定するように受け取られがちです。
【言い回し例】 ・でも ・だって ・ですから
まずは顧客の主張を受け止め、「一度共感してから説明する」という順序を意識することが大切です。
「絶対」「普通」などのワード
断定的・一般論的な言葉は、相手を強く否定したり、見下しているように聞こえたりするため避けましょう。
【言い回し例】 ・絶対にしていません ・絶対にできません ・普通はそのような○○はしません ・普通であれば~ ・普通の人は~
こうした言葉は、顧客に「自分の意見を否定された」「異常扱いされた」と感じさせ、信頼関係を壊してしまう可能性があります。
代わりに、「通常はこのような対応ですが」「確認の上、柔軟に対応いたします」といった表現を使うことで、柔らかく伝えることができます。
クレーム対応では、事実以上に「感じのよさ」や「共感」が大切です。 NGワードを避け、誠実で冷静な言葉遣いを心がけることで、顧客との信頼回復につながります。
コールセンターのクレームを減らすためのポイントは?

コールセンターにおけるクレームは、顧客対応の質や企業イメージに大きな影響を与えます。クレームが発生してから対応するだけでなく、日頃から予防・対策を講じることが重要です。
以下では、クレームを減らすための具体的なポイントを解説します。
クレームの分析
クレームを減らす第一歩は、過去のクレームを分析し、原因を明確化することです。 オペレーターが顧客の話に十分耳を傾けていたか、誤解を招く言動はなかったかなど、対応の質を振り返り、改善点を洗い出します。
対応後のフィードバックを蓄積・共有することで、再発防止や対応スキルの底上げにもつながります。
トークスクリプトを精査する
クレーム発生時の対応品質を安定させるためには、トークスクリプトの整備が不可欠です。 特に、クレーム対応用のスクリプトでは、「NGワード」や「ネガティブな言い回し」を避けた表現を心がける必要があります。
あらかじめ想定される質問や反応に応じた対応フローを作成しておくことで、オペレーターは迷わず落ち着いて対応でき、顧客に安心感を与えることができます。
やりとりの録音
クレーム防止には、通話内容の録音も効果的です。録音には以下の2つのメリットがあります。
・抑止効果 あらかじめ「通話は録音されています」と伝えることで、過度なクレームや暴言を防ぐ効果が期待できます。
・記録・証拠の活用 通話内容を後から確認できるため、事実関係の検証や、第三者への説明材料としても活用可能です。
録音はオペレーターの研修素材としても活かすことができ、対応の質を継続的に高めるツールとして有効です。
スタッフやオペレーターの教育
クレームを減らすには、現場スタッフの教育・トレーニングが不可欠です。 マニュアルの整備だけでなく、定期的な研修によって「いざというときに慌てない対応力」を身につけさせる意識を持ちましょう。
特に有効なのが、ロールプレイング形式の研修です。クレームを言う役と受ける役に分かれ、リアルな対応の練習を行うことで、対応力といざというときに慌てない・委縮しないメンタルの強化が期待できます。
クレームはゼロにはできなくても、分析・予防・教育の体制を整えることで最小限に抑えることは可能です。日頃からの準備と意識づけが、顧客満足度向上とトラブル防止の鍵となります。
まとめ
コールセンターにおけるクレーム対応は、オペレーター大きなストレスとなり、離職率が上がってしまう原因にもなります。
今回ご紹介した内容をもとに、クレーム対応時のマニュアルをまとめ、オペレーターの教育にも活かしてみてください。
原因を正しく理解し、実践的な対策を講じることで、現場の負担軽減と顧客満足の両立が行えるようになるでしょう。

ProCX編集部
NTTマーケティングアクトProCX