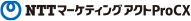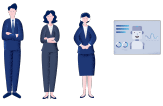コールセンター・コンタクトセンターの関連記事一覧です。
立ち上げから運用まで、コールセンター・コンタクトセンターに関する悩みをお持ちの方はぜひ参考にしてください。
-
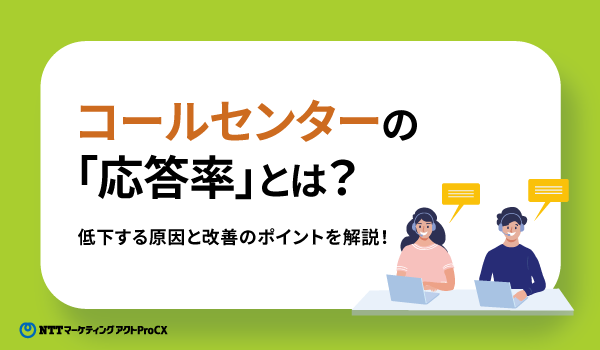
コンタクトセンター
コールセンターの「応答率」とは?低下する原因と改善のポイントを解説!
-

コンタクトセンター
コールセンターの応対品質とは?評価方法や改善のためのポイントを解説!
-

コンタクトセンター
コールセンターとは?導入の効果やメリット・デメリットと判断基準を解説
-

コンタクトセンター
コールセンターの指標「稼働率」の重要性とは?チェックポイントや適切な管理方法
-

コンタクトセンター
コールセンターのインバウンドとは?アウトバウンドとの違いや効率化のポイント
-

コンタクトセンター
コールセンターの指標「CPH」とは?重要性と改善のポイントを解説!
-

コンタクトセンター
コールセンターのATTとは?長くなってしまう原因と短縮のポイントを解説!
-

コンタクトセンター
コールセンターのアウトソーシングとは?メリット・デメリットと業者選びのポイント!
-

コンタクトセンター
コールセンターの運用費用は?内製と外注の違いと費用を抑える方法
-

コンタクトセンター
コールセンターのBPOとは?アウトソーシングとの違いやメリット・デメリットを解説!
-
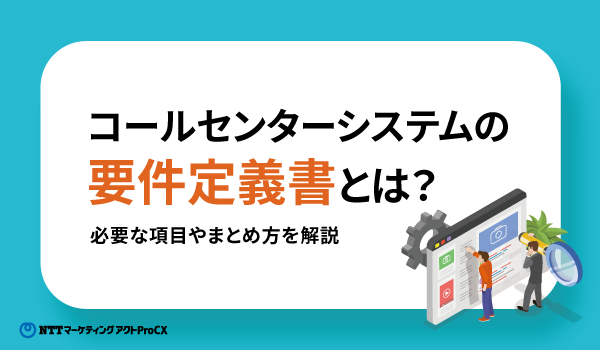
コンタクトセンター
コールセンターシステムの要件定義書とは?必要な項目やまとめ方を解説
-
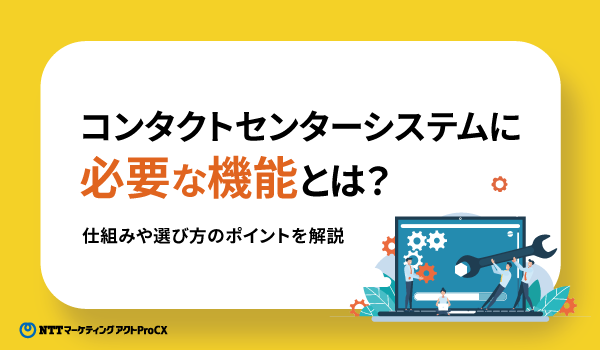
コンタクトセンター
コンタクトセンターシステムに必要な機能とは?仕組みや選び方のポイントを解説